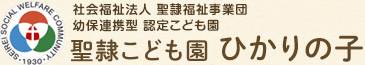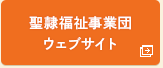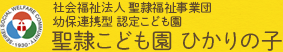4月 「光の子として歩みなさい」 エフェソの信徒への手紙 第5章8節
「聖隷こども園ひかりの子」の歴史は、1976年(昭和51年)、初代園長の平野健二氏と平野鈴子氏夫妻が私財をなげうって創設した「ひかりの子保育園」から始まります。2004年(平成16年)の資料『ひかりの子保育園の創設』で、平野鈴子氏がこう語っています。
「ひかりの子保育園は、私たちを始め、皆様の祈りを聞き入れて下さった主イエス・キリストの恵みの計らいによって建てられました。『幼い子たちを持つ若い父親、母親、そしてあらゆる可能性をもつ乳幼児と共に、キリストの愛によって生きる』ことをしていこう、これがひかりの子保育園の創立の原点、初心です」。
「あなたがたは、以前には暗闇でしたが、今は主〔イエス様〕に結ばれて、光となっています。光の子として歩みなさい」(エフェソ5・8)。聖書は救い主イエス様を「光」と言います。「光」であるイエス様が、いつも一緒にいてくれる。私たちの心が辛い「暗闇」に落ち込んでしまう時、私たちを光で照らし、新しく生きる力を与えてくれる。私たちを支えてくれる愛の力です。「ひかりの子」につながる私たちは、皆、このイエス様の光、愛をいただきます。そしてイエス様の光と愛をいただいた私たちは、今度は自分が、辛い思いの中にいる他の誰かを助け、その人の光の道しるべになる、愛をもって隣人と一緒に生きる者となる、その力を得ます。「ひかりの子」の創立の原点、初心は、この聖書の言葉によって言い表されています。
遠州教会 牧師 石井佑二
「ひかりの子保育園は、私たちを始め、皆様の祈りを聞き入れて下さった主イエス・キリストの恵みの計らいによって建てられました。『幼い子たちを持つ若い父親、母親、そしてあらゆる可能性をもつ乳幼児と共に、キリストの愛によって生きる』ことをしていこう、これがひかりの子保育園の創立の原点、初心です」。
「あなたがたは、以前には暗闇でしたが、今は主〔イエス様〕に結ばれて、光となっています。光の子として歩みなさい」(エフェソ5・8)。聖書は救い主イエス様を「光」と言います。「光」であるイエス様が、いつも一緒にいてくれる。私たちの心が辛い「暗闇」に落ち込んでしまう時、私たちを光で照らし、新しく生きる力を与えてくれる。私たちを支えてくれる愛の力です。「ひかりの子」につながる私たちは、皆、このイエス様の光、愛をいただきます。そしてイエス様の光と愛をいただいた私たちは、今度は自分が、辛い思いの中にいる他の誰かを助け、その人の光の道しるべになる、愛をもって隣人と一緒に生きる者となる、その力を得ます。「ひかりの子」の創立の原点、初心は、この聖書の言葉によって言い表されています。
遠州教会 牧師 石井佑二
5月 「沖に漕ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい」 ルカによる福音書 第5章4節
漁師であるシモンはこの時、一晩中働いたけれども、一匹の魚も捕れませんでした。徹夜をして働いたのに、何の実りもなかった。無駄だった。その空しさの中、沖に上がって網を洗っています。やらなければならない作業に没頭して、その空しい思いを打ち消してしまいたい。そんな思いにシモンは捕われていました。そのシモンに、イエス様が近づき、言葉を掛けられます。「沖に漕ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい」。もう一度漁をしよう。沖へ行って網を降ろしなさい。これは人間の目から見たら愚かな、無駄に無駄を重ねることです。夜、最も魚が捕れる時に働いた。でも駄目だった。シモンは「もう疲れて果てています、またの機会にしましょう」と言うこともできました。しかしシモンは、続く聖書の言葉において、「しかし、お言葉ですから」と言って、沖に漕ぎ出しました。「イエス様、あなたが語った言葉に賭けます」。その思いだけがシモンの漕ぎ出しの動機でした。大切なことは、この時のシモンの心、漁の失敗、空しさに捕われ、その空しさを自分で解決しなければと思っていた、その心が新しくなる、イエス様の御言葉が与えられた、ということです。「私はこのイエス様が示される御言葉に乗っかれば良い」。これが、聖書が語る「信じる」ということです。私たちの、行き詰まってしまった心が、もう一度前に進める様になる、その秘訣です。
遠州教会 牧師 石井佑二
遠州教会 牧師 石井佑二
6月 「見よ、それは極めて良かった」 創世記 第1章31節
聖書の最初に、神様が愛と慈しみを持って、この世界を造ってくださった、と書いてあります。そして神様は、ご自分が造られた世界の隅から隅まで見回して言いました。「見よ、それは極めて良かった」。この世界、色々なことがあり、どうしてこんなことが起こるのかと思ってしまう時もあります。しかしそれでも、神様がこの世界を、私たちを、愛と慈しみの眼差しを持って、「極めて良い」ものとして導いてくださっている、と言うのです。
カトリック教会のシスターである渡辺和子さんという方が『置かれた場所で咲きなさい』という本を書いています。自分の生きている環境で、辛いことが沢山あった時、ある宣教師から手紙をもらったそうです。「置かれた場所で咲きなさい。咲くということは、仕方がないと諦めるのではなく、自分が笑顔で幸せに生き、周囲の人々も幸せるにすることによって、神様があなたをここにお植えになったのは間違いではなかったと、証明することなのです」。その言葉で、渡辺シスターは「現在」というかけがえのない時間を精一杯生きようと思い、自分の生き方を変えることが出来た、と言います。
神様はこの世界、私たちを見てくださり「極めて良かった」と言ってくださっています。この神様の愛と慈しみの眼差しの支えがあると知る時、私たちも、生きているそのところで、新しい花を咲かせるような生き方ができる。その力をいただけます。
遠州教会 牧師 石井佑二
カトリック教会のシスターである渡辺和子さんという方が『置かれた場所で咲きなさい』という本を書いています。自分の生きている環境で、辛いことが沢山あった時、ある宣教師から手紙をもらったそうです。「置かれた場所で咲きなさい。咲くということは、仕方がないと諦めるのではなく、自分が笑顔で幸せに生き、周囲の人々も幸せるにすることによって、神様があなたをここにお植えになったのは間違いではなかったと、証明することなのです」。その言葉で、渡辺シスターは「現在」というかけがえのない時間を精一杯生きようと思い、自分の生き方を変えることが出来た、と言います。
神様はこの世界、私たちを見てくださり「極めて良かった」と言ってくださっています。この神様の愛と慈しみの眼差しの支えがあると知る時、私たちも、生きているそのところで、新しい花を咲かせるような生き方ができる。その力をいただけます。
遠州教会 牧師 石井佑二
7月 「隣人を自分のように愛しなさい」 マルコによる福音書 第12章31節
今月の聖句を、もう少し広く見てみましょう。イエス様に一人の律法学者が問います。「あらゆる掟のうちで、どれが第一でしょうか」。イエス様は答えます。「第一の掟は、これである。『……心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい』。第二の掟は、これである。『隣人を自分のように愛しなさい。』この二つにまさる掟はほかにない」。つまり「神様を愛すること」と「隣人を愛すること」、これらをきちんと繋げて捉える愛の教え、これが最も大切な聖書の教えだ、と言うのです。その中で「隣人を愛する」ために、隣人を「自分のように愛しなさい」と言います。それは言い換えると「自分で自分を愛することを忘れてはいけない。そうであってこそ、あなたは隣人を愛することができる」ということです。自分で自分を愛する思いを捨てれば、人に愛を与えられる、などということはないのです。イエス様は言われます。「あなたは神様との愛の絆の中にある自分であることを知って欲しい。あなたは神様から愛されている、大切な存在である。その者として、自分を愛し、自分を大切にして欲しい。そのことに生きる時に、あなたは本当に、自分の側にいる人、隣人を愛し、大切にすることができる」。神を愛し、隣人を愛し、自分を愛する。この愛のつながりに生きて欲しい。そうイエス様は、私たちに言っておられるのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
遠州教会 牧師 石井佑二
「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」 マタイによる福音書 第7章12節
私たちはいつも、「あれが足りない」「これがない」という、自分の欠けた部分を思って、嘆いてしまいます。「人にしてもらいたいと思う」というのは、そんな自分の貧しさを悲しみ、要求ばかりに生きてしまう、その私たちの心を言います。そんな思いの中にある私たちを、イエス様は、愛と慈しみの眼差しを持って、良く見てくださります。そしてその様な私たちが、自分の貧しさに嘆くのとは違う、本当の意味で満たされた人生を歩むにはどうすれば良いのか。そのことを語るのです。
イエス様は、私たちの人生の欠け、貧しさを嘆く悲しみの心、それを良く知っていてくださる。その私たちに言われるのです。「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」。イエス様は、要求ではなく、人に与える事を勧めます。なぜそう言われるのでしょう。それは、自分の欠けた部分を思い、自分の貧しさを悲しみ嘆くあなた。そのあなただからこそ、周りにいる人の、自分の欠けや貧しさに苦しむ、その人の痛みを良く理解できる。そのものとして、その人の悲しみに寄り添い、必要な慰めを与える事に生きて欲しい。イエス様が、救い主としてあなたの苦しみに寄り添い、支えたように、悲しみを知るあなたは、周りの人の苦しみ、悲しみに寄り添って生きられる。そこにあなたの、自分の欠けや貧しさを嘆くことを超えた、本当に満たされた人生がある。そう言われるのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
イエス様は、私たちの人生の欠け、貧しさを嘆く悲しみの心、それを良く知っていてくださる。その私たちに言われるのです。「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」。イエス様は、要求ではなく、人に与える事を勧めます。なぜそう言われるのでしょう。それは、自分の欠けた部分を思い、自分の貧しさを悲しみ嘆くあなた。そのあなただからこそ、周りにいる人の、自分の欠けや貧しさに苦しむ、その人の痛みを良く理解できる。そのものとして、その人の悲しみに寄り添い、必要な慰めを与える事に生きて欲しい。イエス様が、救い主としてあなたの苦しみに寄り添い、支えたように、悲しみを知るあなたは、周りの人の苦しみ、悲しみに寄り添って生きられる。そこにあなたの、自分の欠けや貧しさを嘆くことを超えた、本当に満たされた人生がある。そう言われるのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
9月「主において常に喜びなさい。」フィリピの信徒への手紙 第 4 章 4 節
この言葉を書き送ったパウロは、今、牢獄に捉えられ、明日に
も処刑されるかもしれません。その所にありながら、仲間たちに
「常に喜びなさい」と言うのです。苦しみの中で悲しむばかりで
あろうという状況の中で「喜び」を見出し、人を励ますことができ
る。その秘密は何でしょう。パウロは「主において」喜びなさい、
と言います。それは「救い主イエス・キリストの恵みに包まれてい
る中で」という意味です。イエス様は私たちの罪の裁きを身代り
に負って、十字架に架かってくださりました。そうして私たちのど
んな苦しみをも共にし、心に憶えてくださる。どんな時でも私を
心に憶えてくれているイエス様がいる。そのことが苦しみの中で
生きる力となるのです。
第二次世界大戦の時、ユダヤ人の精神科医で、『夜と霧』を
記したフランクルは、その著書の中で言います。収容所の絶望
の中、多くの人が自暴自棄となり、死んで行った。しかしその中
で、「私を心に憶えてくれている人がいる。一人の友、一人の家
族、そして神が、私たちを見てくれている」ということを知る人
は、絶望の中にあっても生きる力を得ていた。そう言うのです。
どんな苦しみ、絶望も、「私を憶えてくれている人がいる」と知る
ことが命の力となります。その力に支えられて、また私たち自身
も、誰かのことを心に憶えることで、その命を支えられる。その励
ましが、この御言葉で語られています。
も処刑されるかもしれません。その所にありながら、仲間たちに
「常に喜びなさい」と言うのです。苦しみの中で悲しむばかりで
あろうという状況の中で「喜び」を見出し、人を励ますことができ
る。その秘密は何でしょう。パウロは「主において」喜びなさい、
と言います。それは「救い主イエス・キリストの恵みに包まれてい
る中で」という意味です。イエス様は私たちの罪の裁きを身代り
に負って、十字架に架かってくださりました。そうして私たちのど
んな苦しみをも共にし、心に憶えてくださる。どんな時でも私を
心に憶えてくれているイエス様がいる。そのことが苦しみの中で
生きる力となるのです。
第二次世界大戦の時、ユダヤ人の精神科医で、『夜と霧』を
記したフランクルは、その著書の中で言います。収容所の絶望
の中、多くの人が自暴自棄となり、死んで行った。しかしその中
で、「私を心に憶えてくれている人がいる。一人の友、一人の家
族、そして神が、私たちを見てくれている」ということを知る人
は、絶望の中にあっても生きる力を得ていた。そう言うのです。
どんな苦しみ、絶望も、「私を憶えてくれている人がいる」と知る
ことが命の力となります。その力に支えられて、また私たち自身
も、誰かのことを心に憶えることで、その命を支えられる。その励
ましが、この御言葉で語られています。
10月 「ひとりよりもふたりが良い。」 コヘレトの言葉 第 4 章 9 節
コヘレト(「呼び集める者」という意味)と呼ばれる人物が記し
た、旧約聖書「コヘレトの言葉」。その第 4 章で、彼が生きている
社会を憂いて、強い嘆きの言葉を語ります。「見よ、虐げられる人
の涙を。彼らを慰める者はない」(1 節)。コヘレトが生きた時代、
社会に大きな経済格差がありました。金持ちはどんどん富を得、
貧しい者はもっと貧しくなって行く。社会的弱者が切り捨てられて
しまうのです。そして言います。「ひとりの男があった。友も息子も
兄弟もない。際限もなく労苦し、彼の目は富に飽くことがない」(8
節)。そこに生きる人は、富を得ることだけを関心事とし、際限な
く、終りなく働き続け、もっと多くの富を得る、そのことしか考えら
れず、友人も家族も眼中になくなってしまう。そう生きざるを得な
い、孤独な人間ばかりが存在する社会となってしまっている状況
なのです。
しかしその中で、コヘレトは言います。「ひとりよりもふたりが良
い。共に労苦すれば、その報いは良い」(9 節)。人間が、側にい
る者同士、共に生きることの素晴らしさがある。涙を流さないでは
いられない、苦しさを味わうこの社会で、心を閉ざして孤独を嘆く
のではなく、共に生きる共同体を皆で造ろう。そこにおいてこそ、
本当の生きる力が与えられる。コヘレトはそのことを必死に呼び
掛けています。そこに聖書の語る、人間が共同体として共に生き
る、その喜びが示されています。
遠州教会 牧師 石井佑二
た、旧約聖書「コヘレトの言葉」。その第 4 章で、彼が生きている
社会を憂いて、強い嘆きの言葉を語ります。「見よ、虐げられる人
の涙を。彼らを慰める者はない」(1 節)。コヘレトが生きた時代、
社会に大きな経済格差がありました。金持ちはどんどん富を得、
貧しい者はもっと貧しくなって行く。社会的弱者が切り捨てられて
しまうのです。そして言います。「ひとりの男があった。友も息子も
兄弟もない。際限もなく労苦し、彼の目は富に飽くことがない」(8
節)。そこに生きる人は、富を得ることだけを関心事とし、際限な
く、終りなく働き続け、もっと多くの富を得る、そのことしか考えら
れず、友人も家族も眼中になくなってしまう。そう生きざるを得な
い、孤独な人間ばかりが存在する社会となってしまっている状況
なのです。
しかしその中で、コヘレトは言います。「ひとりよりもふたりが良
い。共に労苦すれば、その報いは良い」(9 節)。人間が、側にい
る者同士、共に生きることの素晴らしさがある。涙を流さないでは
いられない、苦しさを味わうこの社会で、心を閉ざして孤独を嘆く
のではなく、共に生きる共同体を皆で造ろう。そこにおいてこそ、
本当の生きる力が与えられる。コヘレトはそのことを必死に呼び
掛けています。そこに聖書の語る、人間が共同体として共に生き
る、その喜びが示されています。
遠州教会 牧師 石井佑二
11月 「成長させてくださったのは神です。」 コリントの信徒への手紙一 第3章6節
イエス様の弟子パウロが、コリントの教会の人々に「本当に成熟した人とはどういう人か」と示します。この時、コリント教会にはいくつかの派閥、グループが出来てしまい、互いに言い争う状態でした。「パウロが最初にこの教会を作ったのだから、私はパウロ派になろう」。「いや、その後の教会を守り続けた中心人物はアポロだから、私はアポロ派だ」。そんなことを言い合って「では、どっちが偉いか」と、いつも言い争っているのです。そんな教会の様子を聞いて、パウロは言います。「そうではないでしょう。教会にいる誰もが、神様に守られて、一緒に協力して生きる。それが求められているでしょう」。そう言ってパウロは、「成長させてくださったのは神です」。そのことを良く捉えて欲しい、と言うのです。
この言葉は、一つの仲間として集められている皆が、共通して見つめるべき事、それはどこにあるのか、ということに気付きを与えます。皆、神様の御心を表すために集められた。一番大切なことは神様。そのことを皆で見つめられれば、お互いの派閥、グループ、それぞれの考え方の違いを超えて、一緒に協力して、素晴らしいものを作り出すために生きて行ける。本当に成熟した人の姿がそこにある。神様は、私たちを一つの仲間として集めてくださり、他者と共に生きることを喜べる者へと「成長」する、その力を私たちに与えてくださっています。
遠州教会 牧師 石井佑二
この言葉は、一つの仲間として集められている皆が、共通して見つめるべき事、それはどこにあるのか、ということに気付きを与えます。皆、神様の御心を表すために集められた。一番大切なことは神様。そのことを皆で見つめられれば、お互いの派閥、グループ、それぞれの考え方の違いを超えて、一緒に協力して、素晴らしいものを作り出すために生きて行ける。本当に成熟した人の姿がそこにある。神様は、私たちを一つの仲間として集めてくださり、他者と共に生きることを喜べる者へと「成長」する、その力を私たちに与えてくださっています。
遠州教会 牧師 石井佑二
12月「あなたがたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。」 ルカによる福音書 第2章12節
クリスマスの夜。天使が「飼い葉桶に寝ている乳飲み子」、「これがあなたがたへのしるしである」と言います。それは「神様があなたを愛している証拠だ」という意味です。どうして赤ちゃんが神様の愛の証拠、となるのでしょう。赤ちゃんを見ると、心が和みます。それは、その赤ちゃんが誰かに守られ、愛され、赤ちゃんを通して、愛が語られるからです。赤ちゃんは最も弱い存在です。そのものとして、神の御子イエス様が生まれてくださりました。そのことについて私たちはどう思うでしょう。有り得ない、と思うでしょうか。
私たちは、この世の価値観によって、誰かに守られて生きるよりも、一人で、強く生きなければならない、と思うところがあるかもしれません。しかしその価値観が、この世界の多くの人を、独りぼっちの寂しさに追い込み、愛されて生きる事、また他者を愛して生きる喜びを、分からなくさせていると思うのです。
この時に、クリスマスのイエス様と出会いたい。神の御子イエス様は、神の守りと愛によって生きる小さな赤ちゃんとして生まれてくださりました。それが「神の愛の証拠」。あなたにも、この赤ちゃんイエス様と同じように、神の愛によって守られ、愛によって生きる、その恵みが与えられている。あなたは神の愛の中にある。決して独りぼっちではないと知って欲しい。イエス様を通してこの神の愛を知るクリスマスの時を、共に過ごしましょう。
遠州教会 牧師 石井佑二
私たちは、この世の価値観によって、誰かに守られて生きるよりも、一人で、強く生きなければならない、と思うところがあるかもしれません。しかしその価値観が、この世界の多くの人を、独りぼっちの寂しさに追い込み、愛されて生きる事、また他者を愛して生きる喜びを、分からなくさせていると思うのです。
この時に、クリスマスのイエス様と出会いたい。神の御子イエス様は、神の守りと愛によって生きる小さな赤ちゃんとして生まれてくださりました。それが「神の愛の証拠」。あなたにも、この赤ちゃんイエス様と同じように、神の愛によって守られ、愛によって生きる、その恵みが与えられている。あなたは神の愛の中にある。決して独りぼっちではないと知って欲しい。イエス様を通してこの神の愛を知るクリスマスの時を、共に過ごしましょう。
遠州教会 牧師 石井佑二
1月「受けるよりは与える方が幸いである。」 使徒言行録 第20章35節
イエス様は「受けるよりは与える方が幸いである」と言われます。その意味は分かります。受けるばかりではなく、人に親切にし、助けてあげる。そうしてこそ、ひとかどの人間になれる気がする。しかし何の見返りもなく、その様にするというのは大変難しい。何かをしても、人から感謝をされないなら、私たちは途端に嫌になってしまいます。
ところがイエス様ご自身は、何の見返りもなく、徹底的にご自分を与え尽くされました。クリスマスの時、神のご身分を捨てて、人間の赤ちゃんとして生まれ、十字架の死に至るまで、ご自身を人間のために与え尽くし、全ての人間の罪、その裁きを全部引き受けて、死んでくださりました。そして全ての人間が、その罪を赦される恵みをいただいたのです。
‘Pay it forward’という言葉があります。自分が受けた善意、恵みを他の誰かに渡すことで、善意、恵みをその先につないで行く。そうして善意、恵みが広がって行く、という考えです。それに従うならば、私たちは皆、このイエス様の恵みをいただき、それを他の誰かに渡す、その者として今を生きている、と分かります。いただいた恵みを次の人に渡す。そうすることで私たちの「与える」幸いは、真実となります。私たちは、既に沢山の恵みを与えられています。イエス様から、また繋がる多くの人たちから。この恵みに心を向け、感謝をする。そのことが、私たちが人生を幸いに生きる、最初の一歩です。
遠州教会 牧師 石井佑二
ところがイエス様ご自身は、何の見返りもなく、徹底的にご自分を与え尽くされました。クリスマスの時、神のご身分を捨てて、人間の赤ちゃんとして生まれ、十字架の死に至るまで、ご自身を人間のために与え尽くし、全ての人間の罪、その裁きを全部引き受けて、死んでくださりました。そして全ての人間が、その罪を赦される恵みをいただいたのです。
‘Pay it forward’という言葉があります。自分が受けた善意、恵みを他の誰かに渡すことで、善意、恵みをその先につないで行く。そうして善意、恵みが広がって行く、という考えです。それに従うならば、私たちは皆、このイエス様の恵みをいただき、それを他の誰かに渡す、その者として今を生きている、と分かります。いただいた恵みを次の人に渡す。そうすることで私たちの「与える」幸いは、真実となります。私たちは、既に沢山の恵みを与えられています。イエス様から、また繋がる多くの人たちから。この恵みに心を向け、感謝をする。そのことが、私たちが人生を幸いに生きる、最初の一歩です。
遠州教会 牧師 石井佑二
2月「わたしは弱いときにこそ強いからです」コリントの信徒への手紙二 第12章10節
パウロは、「弱さ」を持っていたようです。身体的な弱さか、心の病気か。とにかく大変苦しい重荷を負っていました。しかしそこで言うのです。「キリストの力がわたしの内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。……わたしは弱いときにこそ強いからです」(コリント二12・9~10)。「弱さを誇りましょう」とは、自分の弱さそのものを誇る、ということではなくて、「弱さの中で、誇りを持って生きていこう」ということです。私たちは、自分の「弱さ」に直面する時、弱い自分のことで頭が一杯になってしまいます。弱さや苦しさを思う時、私たちは「自分」に拘ってしまう。弱い「自分」。苦しい「自分」。心が「自分」「自分」で一杯になってしまう。しかしパウロは言うのです。そんな心を解き放つ生き方がある。それが「キリストの力がわたしの内に宿る」、それを信じることだ。弱くて良い。弱い自分をそのままに愛し、支えてくれるお方がいる。そこで生きれば良い。そう思える時、「わたしは弱いときにこそ強い」と言える。弱い時にこそ、私を支える、強い救い主が一緒にいてくれると気付ける。そこで、誇らしく、自分を生きて行ける。
私たちは、みんな弱い。でも弱いからこそ、その自分を支えてくれる自分以外の人が、助けてくれる人が、側にいてくれていることに気付ける。そのことに新しい感謝をして生きられるなら、その人は強いのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
私たちは、みんな弱い。でも弱いからこそ、その自分を支えてくれる自分以外の人が、助けてくれる人が、側にいてくれていることに気付ける。そのことに新しい感謝をして生きられるなら、その人は強いのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
3月 「光の子として歩みなさい」 エフェソの信徒への手紙 第5章8節
「光」というものに皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。私は最近まで、闇に打ち勝つ、とても力強いもの。それが聖書が語る「光」だ、と思っていました。しかし最近、実はそうではないのではないか、とも思うようになってきました。この世の「光」として、クリスマスの時に生まれた神の子、救い主イエス様。しかしそのイエス様は、実は沢山、逃げ回っています。生まれてすぐ、自分を殺そうとする領主ヘロデから逃げる。大人になって、神様の救いを宣べ伝え始めてからも、自分を迫害する者たちからずっと逃げ回っています。
聖書の中にこういう言葉があります。「光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった」(ヨハネ1・5 口語訳)。光が闇に「勝った」とは言わない。闇は光に「勝たなかった」と言うだけです。消えそうで消えない光。しぶとい光。でも遂に闇の方が音を上げた。そんなイメージです。
聖書が語る、私たちの救いの光。希望としてのイエス様を信じる、この心の光。それも実はこういうものなのではないでしょうか。それはとても小さい。けれどもその光は、消えさえしなければ良い。どんなに小さい光でも、弱々しくても、光は光として、闇に輝く。闇は勝てない。そして最後の時には、必ず光が闇を吹き飛ばす。その時が来ることを信じて、私たち「ひかりの子」は、いつも聖書の言葉を聴き、歩みます。「光の子として歩みなさい」。
遠州教会 牧師 石井佑二
聖書の中にこういう言葉があります。「光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった」(ヨハネ1・5 口語訳)。光が闇に「勝った」とは言わない。闇は光に「勝たなかった」と言うだけです。消えそうで消えない光。しぶとい光。でも遂に闇の方が音を上げた。そんなイメージです。
聖書が語る、私たちの救いの光。希望としてのイエス様を信じる、この心の光。それも実はこういうものなのではないでしょうか。それはとても小さい。けれどもその光は、消えさえしなければ良い。どんなに小さい光でも、弱々しくても、光は光として、闇に輝く。闇は勝てない。そして最後の時には、必ず光が闇を吹き飛ばす。その時が来ることを信じて、私たち「ひかりの子」は、いつも聖書の言葉を聴き、歩みます。「光の子として歩みなさい」。
遠州教会 牧師 石井佑二