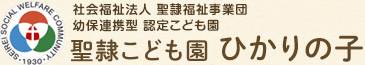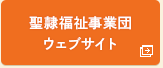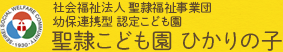4月 「光の子として歩みなさい」 エフェソの信徒への手紙 第5章8節
あなたがたは、以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて、光となっています。光の子として歩みなさい」(エフェソ5・8)。これは私たち聖隷こども園ひかりの子が、一番大切にしている聖書の言葉です。
神様の言葉である聖書は、何度も「光」について語ります。光は、人に勇気を与えます。光は、疲れて倒れてしまった人にもう一度立ち上がる力を与えます。光は、暗さの中に落ち込んでしまった人の心に喜ばしい明るさを取り戻させます。そうして聖書は「光」を、人間の救い、救いの道しるべである、と語るのです。
その聖書が、私たちに言うのです。「あなたがたは、……光となっています」。それは「光り輝く者になれ」とか、「努力をしてあなたの光を輝かしなさい」と言っているのではないのです。「あなたは光だ」と言っているのです。神様が私たちを見て、私たちの存在そのものが、誰かにとっての光である。暗さがあるこの世にあって、「あなたは、全ての人間にとっての光、生きる道しるべだ」と、言っているのです。
聖書の神様は、私たちを無条件に肯定し、私たち自身では思いもしなかった、自分という存在の深い意味を教えてくれます。「光の子として歩みなさい」。この言葉は、神様が私たちを、徹底的に愛し抜いてくださっているところで語られる言葉です。私たちひかりの子は、このように私たちを愛してくださる神様に支えられて、皆で一緒に歩んで行きます。
遠州教会 牧師 石井佑二
神様の言葉である聖書は、何度も「光」について語ります。光は、人に勇気を与えます。光は、疲れて倒れてしまった人にもう一度立ち上がる力を与えます。光は、暗さの中に落ち込んでしまった人の心に喜ばしい明るさを取り戻させます。そうして聖書は「光」を、人間の救い、救いの道しるべである、と語るのです。
その聖書が、私たちに言うのです。「あなたがたは、……光となっています」。それは「光り輝く者になれ」とか、「努力をしてあなたの光を輝かしなさい」と言っているのではないのです。「あなたは光だ」と言っているのです。神様が私たちを見て、私たちの存在そのものが、誰かにとっての光である。暗さがあるこの世にあって、「あなたは、全ての人間にとっての光、生きる道しるべだ」と、言っているのです。
聖書の神様は、私たちを無条件に肯定し、私たち自身では思いもしなかった、自分という存在の深い意味を教えてくれます。「光の子として歩みなさい」。この言葉は、神様が私たちを、徹底的に愛し抜いてくださっているところで語られる言葉です。私たちひかりの子は、このように私たちを愛してくださる神様に支えられて、皆で一緒に歩んで行きます。
遠州教会 牧師 石井佑二
5月 「野の花がどのように育つのか、注意して見なさい」 マタイによる福音書 第6章28節
イエス様が「野の花がどのように育つのか、注意して見なさい」という、この御言葉を語るその前後で、何度も「思い悩むな」と言われます。私たちは、色々なことで思い悩みを抱えてしまいます。人間関係の困難さ、生活の悩み、勉強や仕事の悩み、将来ヘの不安……。そういったことに上手く対応できない。そんな自分の小ささを思うと、思い悩みで心がいっぱいになってしまいます。しかしその私たちに、イエス様は言われるのです。「この『野の花』を見て見なさい」。ここで言う「野の花」、それは誰も気に留めないような、本当に小さな小さな存在です。こんなに小さいものなのに、でも美しく花を咲かせている。それは「神はこのように装ってくださる」からだ。そして重ねて言います。「まして、あなたがたにはなおさらのことではないか」(30節)。どうか忘れないで欲しい。神様は、あなたが幸せに生きるのに必要なものが何であるのか、良くご存じていてくださる。そして小さな小さな野の花に、必要なものを喜んで与えてくださる神様は、愛するあなたが幸せに、今日を、明日を生きるために、本当に必要なものを「みな加えて与え」てくださる(33節)。「野の花」を通して、この神様を一緒に見上げよう。そうしたらもう、不安に生きることはない。思い悩むことなく、喜んで、一緒に生きてこう。そう仰ってくださるイエス様が、あなたと共にいてくださります。
遠州教会 牧師 石井佑二
遠州教会 牧師 石井佑二
6月「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。 そうすれば、見つかる。」マタイによる福音書 第7章7節
イエス様は「父なる神様に、いつも『求めて』生きる者でありなさい」と言います。しかし、いったい何を「求めて」生きろ、と言われるのでしょうか。私たち自身、人間として「何を求めて生きるのか」と考える。それはとても大切なことです。その場限りの、欲望を満たす「求め」などではなくて、本当に、自分の人生に幸いをもたらすものを、求めて生きられたら、これ以上素晴らしいことはないでしょう。それをイエス様は率直に教えてくれています。それは「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」(12節)ということです。他者への愛に生き、自分を他者に献げること。ここに人間として本当の幸いな人生の道がある。そこに生きることを求めなさい、と言うのです。私たちは「そんな生き方は出来ない」と思ってしまうかもしれません。しかしイエス様は、あなたが「他者への愛」に生きることを求める時、必ず、その愛に生きられる力が「与えられる」と言うのです。なぜなら、このイエス様ご自身が、罪人である私たちを愛し、私たちの罪の赦しのために、十字架で命を献げてくれたからです。このイエス様の愛を知る時、私たちは自分の欲望を満たす「求め」に生きるのではない。イエス様の愛に応え、他者を愛し、他者のために自分を献げて生きる。その幸いを「求めて」生きる者に、必ずなれる。
そうイエス様は教えてくれているのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
そうイエス様は教えてくれているのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。」テサロニケの信徒への手紙一 第5章16~18節
私たちの生活は、いつも喜んでばかりいられるものではありません。また感謝すべきことも色々あるかもしれませんが、そうでないことの方がずっと多いです。その苦しさに心奪われるとき、私たちの祈りもまた絶えてしまいます。そのような私たちに、今月の聖句が与えられているのです。この御言葉は、私たちに、「いつも喜んで生きていて欲しい。沢山の感謝の心を持って生きていて欲しい。だから神さまへの祈りに生きていて欲しい」と望み、願っておられるお方の心を表している御言葉です。それは、この直後、同じ18節に「これこそ、キリスト・イエスにおいて、神があなたがたに望んでおられることです」と記されているのですが、救い主イエス様が、私たちが幸いに生きることを望んでくださっている、そのことに支えられている御言葉なのです。
「喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさい」。それは自分で自分に言い聞かせることが出来る事柄ではありません。ひたすらに、救い主である神の子、イエス様が、目には見えなくても私たちと一緒にいてくださり、そのお方が、私たちに与えてくださるものです。ここに、私たちが喜びと感謝に生きられる支え、慰めがあります。聖書が語り示す慰めとは、苦しみを一人で乗り越えるなどというものではありません。慰めは、いつも一緒にいてくれる存在に、心を向けることでこそ示されます。祈る時、その慰めの存在に気付けます。
遠州教会 牧師 石井佑二
「喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさい」。それは自分で自分に言い聞かせることが出来る事柄ではありません。ひたすらに、救い主である神の子、イエス様が、目には見えなくても私たちと一緒にいてくださり、そのお方が、私たちに与えてくださるものです。ここに、私たちが喜びと感謝に生きられる支え、慰めがあります。聖書が語り示す慰めとは、苦しみを一人で乗り越えるなどというものではありません。慰めは、いつも一緒にいてくれる存在に、心を向けることでこそ示されます。祈る時、その慰めの存在に気付けます。
遠州教会 牧師 石井佑二
8月「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである。」マタイによる福音書 第18章20節
「二人または三人が」集まる。これは何を言っているのでしょう。それは「一人ぼっちではない」ということです。救い主イエス様の求めること、聖書の神様の勧めは、人が孤独に生きるのではなく「共同体」を作ること、「他者と共に生きる」ことを求める、ということです。「個人」が自立して生きることが尊重される現代です。聖書の「他者と共に生きる」勧めは、個人の尊重を軽んじることではありません。むしろ本当の意味での「個人」の自立と尊重、そのあり方を教えてくれます。ある人が言いました。「本当の意味で自立した『個人』とは、『他者』に、喜んで仕えることの出来る人のことだ」。他者と共に、喜んで生きる。そのところにこそ、成熟した「個人」の姿がある。このことは、今日の社会においても大切なことを語り示します。他者と共に人が生きる時、そこに愛の繋がり、互いに仕え合うことのできる喜びの交わりが生まれます。そこにこそ、神の愛そのものであるイエス様のお姿が言い表されるのです。何より、そのイエス様は、あなたとあなたの側にいる人が、互いに相手を裁いてしまう、そんな罪の心を赦し合い、愛し合って生きられるようになるために、あなたの罪の裁きの身代りとして十字架に架かってくださりました。イエス様の愛のご支配において、「他者と共に生きる」関係、「共同体」の関係。この恵みの導きの中に、今、私たちは生かされているのです。
9月「主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。」 詩編 第23編1節
この詩人は言います。「わたしには何も欠けることがない」。「私は貧しくない」「乏しくない」と言うのです。ではこの詩人の生活は、いつも満たされ、苦しみや乏しさは何もなかったのでしょうか。そんなことはありません。聖書の民イスラエルの人々は、天候の厳しい土地に生き、そこで家畜を養うため、いつも移動を続けなければなりません。その生活は安定せず、日々、乏しさの中にあったのです。それなのに「乏しくない」と言えるのはなぜでしょう。詩人は言います。「主は羊飼い」。主なる神様は、羊飼いが羊を守るように、いつも私を守り、導いてくださる、と言うのです。羊は弱い生き物です。戦うための角も牙もなく、敵の狼が来たらすぐ食べられてしまう。一度転んだら自分では起き上がれず、すぐ迷子になります。しかしその側に、必ず羊飼いがいてくれる。狼と戦い、転んだ羊を助け、迷子の羊を見つけ出し、正しく導く。その弱い羊のように苦しさと乏しさを味わう私を、力強い羊飼いのような主なる神様が、いつも私を助けてくださる。その信頼を、詩人は言い表すのです。本当に頼れる、信頼できる存在が側にいてくれる。それを知る人は、もう乏しくない。その人は、自分の乏しさ、足りないものを数え上げる人生ではなく、「こんなに多くの助けを私はいただいている」という、今、自分に与えられている恵みと祝福を、新しく数え、感謝に生きる人生を歩めます。
10月 「あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているのです」ペトロの手紙一 第4章10節
私たちは誰も、自分の才能や能力、自分の状況、それらを「自分の力で得た」とは言えません。それらは、親や周りの人たち、人生で出会った人たちから「与えられた」もの。贈り物として与えられた「賜物」です。聖書はその様な賜物を、神様が私たちに与えてくださった、と理解するのです。しかし私たちは自分の能力や状況を見つめる時、思い通りにできない弱さや、状況の悪さ、不幸を嘆きます。「よくも神様、こんな弱さを、不幸を与えてくれましたね」と考えてしまう。しかしそう思うところで、今月の聖句を見たい。この「賜物を授かっている」という言葉を、「あなたがたはそれぞれ」という言葉に続いて語っています。この言葉は、あなた一人ではなく、あなたと、あなたと共にいる周りの人たちに語られているのです。神様は、あなたと、周りにいる皆が、「それぞれ」に与えられた「賜物」を、共に用いて、互いに支え合って、一緒に生きることを求めているのです。神様は、あなたの弱いところ、あなたの抱える苦しさを知っている。だから、あなたの側に、あなたとは違う「賜物」を持った人がいて、共に支え合って生きるようにと導かれるのです。自分の弱さが、人の弱さをいたわる心を生み、自分の苦しみが、人の苦しみを助けたいと思う優しさを育みます。神様の導きを思う時、皆「それぞれ」に与えられた「賜物」の素晴らしさに気付かされ、喜んで、人生を歩めます。
11月 「神は愛です。」 ヨハネの手紙一 第4章16節
私たちは、愛の美徳、自分以外の誰かを愛して生きる、ということの素晴らしさを知っています。しかし同時に、そこに生きることの難しさをも思い知らされています。なぜなら、愛に生きる時、私たちは、自分のしたいこと、自分の思いを優先させて生きることを捨てなければならないからです。愛とは思想ではありません。愛する者のために自分を献げる行為です。聖書は言います。「神は愛です」。それは何より、神様があなたのために、自分の最も大切な独り子である御子イエス様の命を与えてくださった。その行為のことを言っています。同じ聖書の箇所で言います。神様は「わたしたちの罪を償ういけにえとして、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります」(10節)。神様は「あなたが救われるためならば、大切な独り子の命を、十字架に架けるために差し出そう」。その愛の決断をしてくださりました。そして言うのです。「神は愛です。愛にとどまる人は、神の内にとどまり、神もその人の内にとどまってくださいます」。愛に生きることの難しさに困惑する私たちに、神様は言われる。「私はあなたを愛している。そのことを知るあなたも愛に生きられる。私があなたの内にとどまって、他者を愛する力を与えよう」。そう言ってくださるのです。「神は愛です」と言う時、あなたは神の愛の中に生き、誰かを愛することができる者として生きている。その真実を語るのです。
遠州教会 牧師 石井佑二
遠州教会 牧師 石井佑二
12月 「そして急いで行って、マリアとヨセフ、また飼い葉桶に寝かせてある乳飲み子を探し当てた。」 (ルカによる福音書 第2章16節)
救い主イエス様のお生まれを天使から知らされた羊飼いたちは、「急いで行って」、馬小屋の飼い葉桶に寝かせてある赤ちゃんイエス様に会いました。また聖書の民ではない異邦人の占星術の学者たちも、同じ思いでイエス様のもとに集いました。クリスマスは皆がイエス様のもとに集う時です。なぜなら、イエス様が「私たちのために生まれてくださった」と知らされるからです。天使は「あなたがたのために救い主がお生まれになった」(11節)と伝えています。これを知らされた羊飼いは、人々から忌み嫌われ、孤独な中にありました。占星術の学者たちも、異邦人として聖書の民からさげすまされています。しかしそのような人たちに、イエス様の救いは真っ先に知らされるのです。イエス様はこの世の救い主なのに、立派な王宮のベッドではなく、馬小屋の飼い葉桶という惨めな場所に生まれてくださりました。なぜでしょう。それは、神様の救いが、この世で、力のない者、小さくされている者にこそ先に示され、そうして神様の愛が示されるためです。それは、この世に生きる中で、惨めさや孤独を思う私たちに示される神様の愛です。あなたは独りぼっちではない。その神様の声を聞いて、私たちは喜び、「急いで行って」、イエス様のもとに皆で集う。そこにはもう何の寂しさも、疑いの心もない。そこには神様に愛されている私たちとしての、喜びのクリスマスの集いがあるのです。
1月 「イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。」 (ルカによる福音書 第2章52節)
ルカ2・41以下に、イエス様が12歳の時のお話しが記されています。聖書のユダヤの民は12歳になると、一人前の者として、都エルサレムにある神様の神殿に詣でることになっていました。そこで、イエス様が親を困らせてしまう、親と向かい合う出来事が起こります。それは、私たちの誰もが、一人の人間として親から独り立ちをする、その道筋が示されている、と言えると思います。このイエス様の、親に対峙する「一人前」の姿は、イエス様が神殿に詣で、父なる神様の前に立った、神の祝福の中に立った、そのことによって表わされました。人間は、やがて親から自立します。親から離れ、親とはっきり向かい合う時が来ます。その人間の健全な成長は、その子が神の祝福の中に、一人の人間として真剣に立つ時にこそ与えられる。そう聖書は言うのです。そして聖書が言うのは、その様にして一人の人間としてしっかり立つ者こそが、改めて親を、本当に愛することができる、ということです。「イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された」と記される。このイエス様に続いて、私たちが見守っている子どもたちも成長し、神様の祝福の中で自立し、人を、親を愛する者となれる。子どもの自立は、子どもが親から離れる時。親にとっても一つの試練の時です。しかしそれもまた、神の祝福の道、神の愛の道です。もう少し先にある将来の時に、私たちは祈りつつ、向かって行きます。
2月 「わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。」 (ヨハネによる福音書 第15章12節)
この御言葉は、主イエスが十字架に架けられる直前、弟子たちと食卓を囲むところで主イエスが弟子たちと語り合う、その言葉の一つです。「わたしがあなたがたを愛したように」。主イエスが弟子たちを、私たち全ての者を愛している、と言います。その愛とはどのようなものであるのか。御自身のお姿を持って表します。この語り合いの最初の第13章で、主イエスはひざまずいて、弟子たちの足を洗い「相手に仕える」、そのお姿を示されます。そしてこの第15章で、強調して「友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない」(15・13)と語られます。誰かの友であること、その人に仕えること、そして愛すること。それらは互いにその言葉の意味の深みを表します。主イエスご自身が、私たちの掛け替えのない友であってくださり、私たちの全ての苦しみ、悲しみを負って、共に生き、私たちに仕え、愛し、支えてくださっている。主イエスは私たちに、その喜びを憶えて「互いに愛し合いなさい」と言われる。あなたも隣人に対して真実の友となり、互いに仕え合い、愛し合う者であって欲しい、と言われます。それは難しいことではない。むしろそこにこそ、人間が人間として生きるのに自然な、喜びの姿があります。主イエスが、全ての者に与えてくださっている愛そのものが、私たちが互いに愛し合う喜びの道に生きられる、その確かな導きとなっているのです。