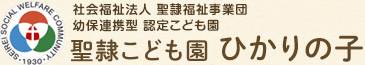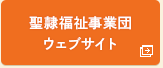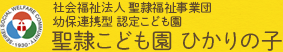4月
入園進級おめでとうございます
園庭のプランターのチューリップも咲き誇り、陽も長くなって季節が変わっていくことを感じます。新しい年度がスタートしましたね。今年は28名の新入園児を迎えました。どうぞよろしくお願いいたします。また、3月には40名の子どもたちが巣立っていきました。それぞれの小学校で新しい生活のスタートです。一人ひとりの子どもたちが自分らしく輝けることをずっと願っていきたいと思います。
さて、先月は年度末特別保育期間のご協力をありがとうございました。全国の聖隷のこども園・保育園の職員がオンラインでつながり、「聖隷の理念と歴史」について学び、さらに自園では、職員一同が改めてこのひかりの子で大事にしていきたい保育は何か、今まで何が大事にされてきたのか等を話し合うことができました。「困っている人がいたら、自分ができることをしよう」。これが聖隷の理念にもつながりますが、昭和51年にひかりの子保育園が創設されたのもこの思いからでした。時代の変化とともに変わっていくこともありますが、変わらない大切なこともあります。子どもたちはいつも「今」を生きています。大人は良かれと思って「今」を通り越し、先を見ながら「〇〇ができないと困る」「〇〇をさせた方がいいのでは」と目に見えることに囚われすぎてしまうことがあるかもしれません。芽を出したばかりの双葉を「早く大きくなって」とばかりに手で引っ張れば折れてしまうかもしれません。花を咲かせることもできないでしょう。適切な栄養を与え、見守り、時に「きれいな花が咲くといいね」「楽しみだね」と優しく声をかけながら待つのではないでしょうか。無理やり引っ張ったら折れてしまうのは子どもたちも同じです。早く早くと急がせるのではなく、その時々の興味や関心はどこにあるのか、今何をしようとしているのかを知り、一緒に楽しんだり、ゆったりと待つことが必要です。この待ってもらえる時間に、子どもは人生の基盤になるしっかりとした根っこを張っていくのだと思います。礼拝の中で牧師先生がおっしゃっていました。相手を信じているから「待つ」ことができるのだと。そして待った分だけ子どもは育つと。とても考えさせられました。「信じて待つ」ことをとても大事だと私も思っています。実際には待てないことも多々あるのですが、それでも「信じて待つ」ことを忘れないでいたいと思うのです。そしてありのままの姿を受け止められて、このひかりの子で大きくなってほしいと思います。
ありのままを受け止めてもらえる環境は、子どもだけでなく大人にとっても必要であると思っています。新生活が始まって落ち着かないのは子どもだけでなく、保護者の皆様もきっと同じですね。不安なこと、心配なことがありましたらいつでも職員に声をかけてください。ひかりの子で過ごすすべての人が愛に包まれて安心して過ごすことができたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
園庭のプランターのチューリップも咲き誇り、陽も長くなって季節が変わっていくことを感じます。新しい年度がスタートしましたね。今年は28名の新入園児を迎えました。どうぞよろしくお願いいたします。また、3月には40名の子どもたちが巣立っていきました。それぞれの小学校で新しい生活のスタートです。一人ひとりの子どもたちが自分らしく輝けることをずっと願っていきたいと思います。
さて、先月は年度末特別保育期間のご協力をありがとうございました。全国の聖隷のこども園・保育園の職員がオンラインでつながり、「聖隷の理念と歴史」について学び、さらに自園では、職員一同が改めてこのひかりの子で大事にしていきたい保育は何か、今まで何が大事にされてきたのか等を話し合うことができました。「困っている人がいたら、自分ができることをしよう」。これが聖隷の理念にもつながりますが、昭和51年にひかりの子保育園が創設されたのもこの思いからでした。時代の変化とともに変わっていくこともありますが、変わらない大切なこともあります。子どもたちはいつも「今」を生きています。大人は良かれと思って「今」を通り越し、先を見ながら「〇〇ができないと困る」「〇〇をさせた方がいいのでは」と目に見えることに囚われすぎてしまうことがあるかもしれません。芽を出したばかりの双葉を「早く大きくなって」とばかりに手で引っ張れば折れてしまうかもしれません。花を咲かせることもできないでしょう。適切な栄養を与え、見守り、時に「きれいな花が咲くといいね」「楽しみだね」と優しく声をかけながら待つのではないでしょうか。無理やり引っ張ったら折れてしまうのは子どもたちも同じです。早く早くと急がせるのではなく、その時々の興味や関心はどこにあるのか、今何をしようとしているのかを知り、一緒に楽しんだり、ゆったりと待つことが必要です。この待ってもらえる時間に、子どもは人生の基盤になるしっかりとした根っこを張っていくのだと思います。礼拝の中で牧師先生がおっしゃっていました。相手を信じているから「待つ」ことができるのだと。そして待った分だけ子どもは育つと。とても考えさせられました。「信じて待つ」ことをとても大事だと私も思っています。実際には待てないことも多々あるのですが、それでも「信じて待つ」ことを忘れないでいたいと思うのです。そしてありのままの姿を受け止められて、このひかりの子で大きくなってほしいと思います。
ありのままを受け止めてもらえる環境は、子どもだけでなく大人にとっても必要であると思っています。新生活が始まって落ち着かないのは子どもだけでなく、保護者の皆様もきっと同じですね。不安なこと、心配なことがありましたらいつでも職員に声をかけてください。ひかりの子で過ごすすべての人が愛に包まれて安心して過ごすことができたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
5月
「 そうだ、いいこと考えた! 」
新年度が始まり一か月がたちました。先日は大変お忙しい中、各クラスの懇談会にご参加いただきありがとうございました。保護者の皆様もお互いのお顔を見て安心できた部分もあるのではないでしょうか。今後もよろしくお願いいたします。
さて、泣き声よりも笑い声が増えて、新入園児にも笑顔が見られるようになりました。本当に子どもの柔軟な心に感心させられます。そして、初めて関わる私たちにも心を開き、笑顔を見せてくれることに喜びと幸せを感じています。子どもたちから与えられる幸せに感謝して過ごしたいと思います。
先日、2歳児クラスの子どもたちが園庭でダンゴムシを見つけてきた時のことです。砂場用のお皿やカップにとてもたくさんダンゴムシを入れて見せてくれたり、自分の手や腕に乗せて見せてくれたりしました。昨日まで自分では触れなかった子も、今日は触れるようになった!ということを一生懸命アピールしてくれたりもしました。子どもたちの集中力はすごくて、ダンゴムシへの熱意は数日続いていたようでした。この、熱中してじっくり関わることが「学び」そのものだと思います。ひっくりかえってしまったダンゴムシを見て「いっぱい」とつぶやいた子がいました。足がたくさんあるんですよね。「本当だ、足がいっぱいあるね。」と同じものを見て、同じことを感じてくれる大人の関わりが大事になります。幼児クラスの子は、担任と一緒に足を数えてみたそうです。動いてしまうので数えられなかったと残念そうでしたが、とても微笑ましく、そして、興味を広げる出来事だと感じました。2歳児のAちゃんは自分の手にダンゴムシを乗せて、じっくり観察。腕を登ってくるダンゴムシでしたが、ぽとっとテラスの隙間に落ちてしまいました。はっとした表情で、私の顔を見たので「落ちちゃったね、どうしようか」と聞くと、テラスに腹ばいになり、隙間を見つめて「どうしようかな~」と。しばらくして、ダンゴムシが戻らない(見えない)と分かると、起き上がり「そうだ、いいこと考えた!」と言って、園庭の真ん中の方に走っていきます。どうするんだろう、細長いスコップでも持ってくるのかな?と見ていた私ですが、なんと、別のダンゴムシを捕まえてきました。そして満面の笑みで「ほら見て!」と言ってまた腕を這わせていました。なんとも2歳児らしいなとほっこりしました。
子どものこの「そうだ、いいこと考えた!」の発想を大事にしたいなと思うのです。自分で考えて行動してみる。それが生きる力につながるのではないでしょうか。大人が先回りして準備万端にするのではなく、困ったときにはどうしたらいいだろう?ということを子どもと一緒に考えてあげたいですね。つい最近、長靴をはいて帰ろうとしたお子さんをお母さんが玄関で抱き上げたらその子が怒りました。私は「長靴を自分ではきたかったのかな?」と思ったのですが、違いました。長靴をはいたから抱っこではなくて自分で歩きたかったのです。そのことにお母さんはすぐ気づき、「ごめんごめん」とおろしてくれました。子どもの気持ちに敏感でありたいと改めて感じた一場面でした。
新年度が始まり一か月がたちました。先日は大変お忙しい中、各クラスの懇談会にご参加いただきありがとうございました。保護者の皆様もお互いのお顔を見て安心できた部分もあるのではないでしょうか。今後もよろしくお願いいたします。
さて、泣き声よりも笑い声が増えて、新入園児にも笑顔が見られるようになりました。本当に子どもの柔軟な心に感心させられます。そして、初めて関わる私たちにも心を開き、笑顔を見せてくれることに喜びと幸せを感じています。子どもたちから与えられる幸せに感謝して過ごしたいと思います。
先日、2歳児クラスの子どもたちが園庭でダンゴムシを見つけてきた時のことです。砂場用のお皿やカップにとてもたくさんダンゴムシを入れて見せてくれたり、自分の手や腕に乗せて見せてくれたりしました。昨日まで自分では触れなかった子も、今日は触れるようになった!ということを一生懸命アピールしてくれたりもしました。子どもたちの集中力はすごくて、ダンゴムシへの熱意は数日続いていたようでした。この、熱中してじっくり関わることが「学び」そのものだと思います。ひっくりかえってしまったダンゴムシを見て「いっぱい」とつぶやいた子がいました。足がたくさんあるんですよね。「本当だ、足がいっぱいあるね。」と同じものを見て、同じことを感じてくれる大人の関わりが大事になります。幼児クラスの子は、担任と一緒に足を数えてみたそうです。動いてしまうので数えられなかったと残念そうでしたが、とても微笑ましく、そして、興味を広げる出来事だと感じました。2歳児のAちゃんは自分の手にダンゴムシを乗せて、じっくり観察。腕を登ってくるダンゴムシでしたが、ぽとっとテラスの隙間に落ちてしまいました。はっとした表情で、私の顔を見たので「落ちちゃったね、どうしようか」と聞くと、テラスに腹ばいになり、隙間を見つめて「どうしようかな~」と。しばらくして、ダンゴムシが戻らない(見えない)と分かると、起き上がり「そうだ、いいこと考えた!」と言って、園庭の真ん中の方に走っていきます。どうするんだろう、細長いスコップでも持ってくるのかな?と見ていた私ですが、なんと、別のダンゴムシを捕まえてきました。そして満面の笑みで「ほら見て!」と言ってまた腕を這わせていました。なんとも2歳児らしいなとほっこりしました。
子どものこの「そうだ、いいこと考えた!」の発想を大事にしたいなと思うのです。自分で考えて行動してみる。それが生きる力につながるのではないでしょうか。大人が先回りして準備万端にするのではなく、困ったときにはどうしたらいいだろう?ということを子どもと一緒に考えてあげたいですね。つい最近、長靴をはいて帰ろうとしたお子さんをお母さんが玄関で抱き上げたらその子が怒りました。私は「長靴を自分ではきたかったのかな?」と思ったのですが、違いました。長靴をはいたから抱っこではなくて自分で歩きたかったのです。そのことにお母さんはすぐ気づき、「ごめんごめん」とおろしてくれました。子どもの気持ちに敏感でありたいと改めて感じた一場面でした。
6月
「 たのしみだね 」
梅雨入りの季節になりました。近年は大雨災害に悩まされることが増えていますので、一昔前のように梅雨の季節の風情を感じて楽しむことを忘れているような気がします。改めて、子どもたちと一緒に四季を感じていきたいと思います。
さて先日は、天候にも恵まれ幼児クラスの親子遠足を開催することができました。保護者の皆様のご理解とご協力をありがとうございました。少しずつ大きくなる中で、友だちとの関わりが増えたり興味のあることが変わったりしますね。園外での姿にはなりますが、少しでも保護者の方同士が顔を合わせ、子ども同士の関わりの様子を知っていただくことができて良かったです。
今、幼児の玄関に「あおむし」がいるのをご存じですか?アゲハチョウのあおむしです。卒園児のおばあさまからいただきました。昨年もこのあおむしを大事に観察していたところ、さなぎから蝶になる瞬間に出会った子どもたちがいました。あおむしからさなぎになり、姿を変えていく「命」を目の当たりにできたことは貴重な体験でした。そんな話をしていたところ、今年もあおむしをいただくことができ、今はさなぎになっていますが毎日子どもたちがケースを下におろして見ています。姿を変えていく不思議さを感じたり、去年のことを思い出して「たのしみ~」と言っている様子に大人も一緒にワクワクしています。身近な生き物に触れることは、とても大切なことですね。触り方、捕まえ方次第では大事にしたくてもその場で動かなくなってしまう経験もします。ずっと以前のことですが、研修に参加したときにこんなことを聞いたことを思い出します。私たちは「命」を大切にするということを何とか伝えようとするあまり、子どもたちから大事な経験を奪っているかもしれないということです。「そっと触らないと死んじゃうよ」と捕まえようとすること自体を躊躇させたり、先回りして、捕まえてあげてしまったりして「力加減」の学びをなくしてしまっていないか?と考えさせられたのです。命の大切さを学ぶには、やはりそれまでの経験が大事だなと感じます。悪意があってはいけませんが、子どもが純粋に興味を持ち、触ってみたい、捕まえてみたいと思って挑戦するときにはチャンスだと思って見守りたいと思います。そして、虫や小動物が死んでしまったときには、それをどう大事に扱うか。子どもたちと一緒にどうするか考えながら対応したいと思います。そのような流れのなかで、子どもたちと「命」について考えたり触れたりしたいと思います。このようなタイミングは日常の中で多々ありますので、見逃さないようにしたいですね。
さて今月は「花の日」があります。一つひとつの花が色も形も香りも違うように、子どもたちも一人ひとりが違います。どの花も、どの子も神様が大切にしてくださる存在。そんなことを改めて心に留めながら「花の日」を迎えたいと思います。そして、地域の中で見守ってくださる方々に感謝の気持ちをお届けしたいと思います。
梅雨入りの季節になりました。近年は大雨災害に悩まされることが増えていますので、一昔前のように梅雨の季節の風情を感じて楽しむことを忘れているような気がします。改めて、子どもたちと一緒に四季を感じていきたいと思います。
さて先日は、天候にも恵まれ幼児クラスの親子遠足を開催することができました。保護者の皆様のご理解とご協力をありがとうございました。少しずつ大きくなる中で、友だちとの関わりが増えたり興味のあることが変わったりしますね。園外での姿にはなりますが、少しでも保護者の方同士が顔を合わせ、子ども同士の関わりの様子を知っていただくことができて良かったです。
今、幼児の玄関に「あおむし」がいるのをご存じですか?アゲハチョウのあおむしです。卒園児のおばあさまからいただきました。昨年もこのあおむしを大事に観察していたところ、さなぎから蝶になる瞬間に出会った子どもたちがいました。あおむしからさなぎになり、姿を変えていく「命」を目の当たりにできたことは貴重な体験でした。そんな話をしていたところ、今年もあおむしをいただくことができ、今はさなぎになっていますが毎日子どもたちがケースを下におろして見ています。姿を変えていく不思議さを感じたり、去年のことを思い出して「たのしみ~」と言っている様子に大人も一緒にワクワクしています。身近な生き物に触れることは、とても大切なことですね。触り方、捕まえ方次第では大事にしたくてもその場で動かなくなってしまう経験もします。ずっと以前のことですが、研修に参加したときにこんなことを聞いたことを思い出します。私たちは「命」を大切にするということを何とか伝えようとするあまり、子どもたちから大事な経験を奪っているかもしれないということです。「そっと触らないと死んじゃうよ」と捕まえようとすること自体を躊躇させたり、先回りして、捕まえてあげてしまったりして「力加減」の学びをなくしてしまっていないか?と考えさせられたのです。命の大切さを学ぶには、やはりそれまでの経験が大事だなと感じます。悪意があってはいけませんが、子どもが純粋に興味を持ち、触ってみたい、捕まえてみたいと思って挑戦するときにはチャンスだと思って見守りたいと思います。そして、虫や小動物が死んでしまったときには、それをどう大事に扱うか。子どもたちと一緒にどうするか考えながら対応したいと思います。そのような流れのなかで、子どもたちと「命」について考えたり触れたりしたいと思います。このようなタイミングは日常の中で多々ありますので、見逃さないようにしたいですね。
さて今月は「花の日」があります。一つひとつの花が色も形も香りも違うように、子どもたちも一人ひとりが違います。どの花も、どの子も神様が大切にしてくださる存在。そんなことを改めて心に留めながら「花の日」を迎えたいと思います。そして、地域の中で見守ってくださる方々に感謝の気持ちをお届けしたいと思います。
7月
「 子ども自身で考える 」
今年の梅雨入りは遅く、すでに真夏のような暑さ。体調を崩さないようにしたいものですね。プール遊びが始まりましたが、気温や湿度にも留意しながら安全に楽しめるような環境を整えていきたいと思います。
今月はそら組の子どもたちの「お泊り保育」が予定されています。親元から離れてこども園で一泊をする子どもたち。期待と少しの不安を持ちながら子どもたちなりに心の準備をしていくと思います。そっと寄り添いながらお手伝いができたらいいなと思います。様々な経験をして、うまく言葉にならない思いを持ちながら成長していく子どもたちのことを応援していきたいですね。
さて、先日の土曜保育の時のことです。この日は玄関の修繕のために1階の保育室を使っていました。(ご協力いただきありがとうございました。)午後のおやつも終わり、風が涼しかったので、保育室だけでなくテラスにも出ながら、いつもと違う過ごし方を喜んでいるように見えました。そんな中で、一歳児クラスのAちゃんは自分の靴を持ってきて履こうとしています。園庭に行きたかったのです。「あっち」と言わんばかりに指をさしてアピールをします。まだ自分ではうまく履けません。少し様子を見ていると、私の肩につかまり、立ったまま足を入れます。私は特にお手伝いをしませんでしたが、バランスが悪そうだったので「座って履いてみたら?」と声をかけました。そして、座るためのお手伝いをしたのですが、それはきっぱり拒否。その後の様子を見ていて気付きました。座ると自分では履けないのですが、立っていると自分の体重で足を押し込むことができるのです。「なるほど」と思いました。靴のかかとはすこしつぶれていますが「はけた」と満足そうです。ただ、その時の状況からすると職員が園庭に一緒に出てあげることができないタイミングでした。Aちゃんは園庭に行きたくて靴を履いたので、一部始終を見ていた私や他の職員もどうしようかな…と。そこで、「お外に行くためには帽子も欲しいね」と声をかけると、時間をかけてようやく履いた靴をさっと脱いで室内に入り、自分の袋から帽子を持ってきました。本当に色々なことがよく分かっています。みんなで感心してしまいました。他の子たちも思い思いに室内やテラスで遊んでいましたが、Aちゃんだけは一生懸命園庭に出る準備をしていたのです。帽子をかぶった後、先ほどと同じ要領で靴を履くと一目散に走っていきました。その時は私がついていくことにしたのですが、五分もたたないうちに、テラスから二歳児のBくんが「お~い、Aちゃ~ん」と優しい声で呼ぶと、満足そうに笑顔で走って戻ってきました。そして、靴を脱いで片づけて保育室に入っていったのです。びっくりするほど短い時間でした。おそらく靴を履こうと頑張った時間の方が長かったと思います。
Aちゃんのやろうとすることを誰も否定せず見守ったことで、Aちゃんは満足できたんだということが分かりました。園庭で遊ぶ時間が長いとか短いとか、それも関係なかったのです。自分のしようとすることができた、納得できたということなのではないでしょうか。「見守る」という言葉を私たちはよく使いますが、果たして何をどこまで「見守る」ことができているのか、その状況において振り返っていかなくてはいけないと改めて思いました。「見守る」は「放っておく」ことではありません。その子のしようとしていることを理解し、適切な関わりがとても大事になるのです。そして、異年齢の関りの微笑ましさを感じられた時間でした。
今年の梅雨入りは遅く、すでに真夏のような暑さ。体調を崩さないようにしたいものですね。プール遊びが始まりましたが、気温や湿度にも留意しながら安全に楽しめるような環境を整えていきたいと思います。
今月はそら組の子どもたちの「お泊り保育」が予定されています。親元から離れてこども園で一泊をする子どもたち。期待と少しの不安を持ちながら子どもたちなりに心の準備をしていくと思います。そっと寄り添いながらお手伝いができたらいいなと思います。様々な経験をして、うまく言葉にならない思いを持ちながら成長していく子どもたちのことを応援していきたいですね。
さて、先日の土曜保育の時のことです。この日は玄関の修繕のために1階の保育室を使っていました。(ご協力いただきありがとうございました。)午後のおやつも終わり、風が涼しかったので、保育室だけでなくテラスにも出ながら、いつもと違う過ごし方を喜んでいるように見えました。そんな中で、一歳児クラスのAちゃんは自分の靴を持ってきて履こうとしています。園庭に行きたかったのです。「あっち」と言わんばかりに指をさしてアピールをします。まだ自分ではうまく履けません。少し様子を見ていると、私の肩につかまり、立ったまま足を入れます。私は特にお手伝いをしませんでしたが、バランスが悪そうだったので「座って履いてみたら?」と声をかけました。そして、座るためのお手伝いをしたのですが、それはきっぱり拒否。その後の様子を見ていて気付きました。座ると自分では履けないのですが、立っていると自分の体重で足を押し込むことができるのです。「なるほど」と思いました。靴のかかとはすこしつぶれていますが「はけた」と満足そうです。ただ、その時の状況からすると職員が園庭に一緒に出てあげることができないタイミングでした。Aちゃんは園庭に行きたくて靴を履いたので、一部始終を見ていた私や他の職員もどうしようかな…と。そこで、「お外に行くためには帽子も欲しいね」と声をかけると、時間をかけてようやく履いた靴をさっと脱いで室内に入り、自分の袋から帽子を持ってきました。本当に色々なことがよく分かっています。みんなで感心してしまいました。他の子たちも思い思いに室内やテラスで遊んでいましたが、Aちゃんだけは一生懸命園庭に出る準備をしていたのです。帽子をかぶった後、先ほどと同じ要領で靴を履くと一目散に走っていきました。その時は私がついていくことにしたのですが、五分もたたないうちに、テラスから二歳児のBくんが「お~い、Aちゃ~ん」と優しい声で呼ぶと、満足そうに笑顔で走って戻ってきました。そして、靴を脱いで片づけて保育室に入っていったのです。びっくりするほど短い時間でした。おそらく靴を履こうと頑張った時間の方が長かったと思います。
Aちゃんのやろうとすることを誰も否定せず見守ったことで、Aちゃんは満足できたんだということが分かりました。園庭で遊ぶ時間が長いとか短いとか、それも関係なかったのです。自分のしようとすることができた、納得できたということなのではないでしょうか。「見守る」という言葉を私たちはよく使いますが、果たして何をどこまで「見守る」ことができているのか、その状況において振り返っていかなくてはいけないと改めて思いました。「見守る」は「放っておく」ことではありません。その子のしようとしていることを理解し、適切な関わりがとても大事になるのです。そして、異年齢の関りの微笑ましさを感じられた時間でした。
8月
「 思いやりの気持ち 」
梅雨明けをして夏本番ですが、今年の夏は非常に暑く過ごしにくい日もありますね。夏と言えばプールや水遊びが定番のようになっていますが、近年は水遊びとは言っても戸外で過ごすことが危険な日もありますので、室内でも五感が刺激されるような夏の遊びを楽しめるように工夫していきたいと思います。
さて、先月はそら組のお泊り保育がありました。保護者の皆様のご協力をありがとうございました。そら組の子たちが出発するときには、様々なクラスの園児、そしてすれ違う保護者の方々に「いってらっしゃい」「がんばって」と声をかけてもらいました。とても誇らしげな表情をしていた子どもたちです。
初めて親元を離れてお泊りをする子が大半の中で、子どもたちは楽しみにしている気持ちと少し心配な気持ちを抱えている様子がありました。でも、ふたを開ければいつも一緒に過ごしている友だちと保育者、そしていつもの場所。自分のことを自分でするだけでなく、困っている友だちがいたら自然に手伝ってくれたりする姿もありました。夜は、大好きなご家族からもらった「秘密の手紙」を、みんな布団の下に入れて眠りにつきました。そして朝起きた時は大事そうに自分でカバンにしまったのですが、しばらくするとAさんが「手紙がない!」と。「え~それは大変!」と、周りにいた子たちが慌ただしく探し始めてくれました。「もしかすると布団をたたんだ時に一緒に入ってしまったかも…」と言えば、すぐに布団が集められている所に集まってひとつひとつを広げて確認してくれていました。結局はロッカーの中にあったのですが、こんなにもみんなが一致団結して探してくれる姿にうれしい気持ちになりました。自分が困っている時に、その気持ちに共感しながら助けてくれる友だちがいることは何よりも心強いことです。また、困っている友だちがいるときに「我関せず」ではなく「どうしたの?」と声をかけたり、その子の気持ちを推し量り、気持ちに寄り添おうとすることは言葉で教えてもなかなかできることではありません。子どもは自分がしてもらったようにするようになります。つい大人は「みんなと仲良くできるといいな」「友だちに優しくしてあげられるといいな」と思ったりします。でも大人が思うようにはならないものです。ただ、その子自身がまずは身近な人から大事にされたり、優しくされたり、気持ちに寄り添ってもらう経験を十分にしていくことで身につくことがあると思うのです。「気持ち」を言語化することは大人でも難しい時があります。ましてや幼い子どもたちには非常に難しいことなのに、「言葉で言わないと分からないよ。ちゃんと言ってごらん。」と言ってしまう自分もいます。そして反省。もちろんその子の成長発達の様子や、その子にとっての目標を理解しながら「あなたならきっと言えるよ。大丈夫、待っているから教えて。」と背中を押すことも大事です。目には見えない部分に心を向けて、相手の気持ちを想像して考えてみることは、生きていく中で必要な力になりますね。押し付けるのではなく、自分が大事にされる経験を十分にする中で育ってほしい力です。お泊り保育での子どもたちの姿を見ながら改めて感じたことでした。
今月は終戦記念日を迎えます。子どもたちと一緒に「平和」についても考える機会としたいと思います。
梅雨明けをして夏本番ですが、今年の夏は非常に暑く過ごしにくい日もありますね。夏と言えばプールや水遊びが定番のようになっていますが、近年は水遊びとは言っても戸外で過ごすことが危険な日もありますので、室内でも五感が刺激されるような夏の遊びを楽しめるように工夫していきたいと思います。
さて、先月はそら組のお泊り保育がありました。保護者の皆様のご協力をありがとうございました。そら組の子たちが出発するときには、様々なクラスの園児、そしてすれ違う保護者の方々に「いってらっしゃい」「がんばって」と声をかけてもらいました。とても誇らしげな表情をしていた子どもたちです。
初めて親元を離れてお泊りをする子が大半の中で、子どもたちは楽しみにしている気持ちと少し心配な気持ちを抱えている様子がありました。でも、ふたを開ければいつも一緒に過ごしている友だちと保育者、そしていつもの場所。自分のことを自分でするだけでなく、困っている友だちがいたら自然に手伝ってくれたりする姿もありました。夜は、大好きなご家族からもらった「秘密の手紙」を、みんな布団の下に入れて眠りにつきました。そして朝起きた時は大事そうに自分でカバンにしまったのですが、しばらくするとAさんが「手紙がない!」と。「え~それは大変!」と、周りにいた子たちが慌ただしく探し始めてくれました。「もしかすると布団をたたんだ時に一緒に入ってしまったかも…」と言えば、すぐに布団が集められている所に集まってひとつひとつを広げて確認してくれていました。結局はロッカーの中にあったのですが、こんなにもみんなが一致団結して探してくれる姿にうれしい気持ちになりました。自分が困っている時に、その気持ちに共感しながら助けてくれる友だちがいることは何よりも心強いことです。また、困っている友だちがいるときに「我関せず」ではなく「どうしたの?」と声をかけたり、その子の気持ちを推し量り、気持ちに寄り添おうとすることは言葉で教えてもなかなかできることではありません。子どもは自分がしてもらったようにするようになります。つい大人は「みんなと仲良くできるといいな」「友だちに優しくしてあげられるといいな」と思ったりします。でも大人が思うようにはならないものです。ただ、その子自身がまずは身近な人から大事にされたり、優しくされたり、気持ちに寄り添ってもらう経験を十分にしていくことで身につくことがあると思うのです。「気持ち」を言語化することは大人でも難しい時があります。ましてや幼い子どもたちには非常に難しいことなのに、「言葉で言わないと分からないよ。ちゃんと言ってごらん。」と言ってしまう自分もいます。そして反省。もちろんその子の成長発達の様子や、その子にとっての目標を理解しながら「あなたならきっと言えるよ。大丈夫、待っているから教えて。」と背中を押すことも大事です。目には見えない部分に心を向けて、相手の気持ちを想像して考えてみることは、生きていく中で必要な力になりますね。押し付けるのではなく、自分が大事にされる経験を十分にする中で育ってほしい力です。お泊り保育での子どもたちの姿を見ながら改めて感じたことでした。
今月は終戦記念日を迎えます。子どもたちと一緒に「平和」についても考える機会としたいと思います。
9月
先 月 は お 忙 し い 中 、 夏 季 特 別 保 育 の ご 協 力 を あ り が と う ご ざ い ま し た 。 猛 暑 日 が 続 い た 8 月 、 戸 外 に 出 る こ と は も ち ろ ん の こ と 、 プ ー ル 遊 び も ま ま な ら ず 室 内 で も 熱 中 症 対 策 を 講 じ な が ら 過 ご す 日 々 で し た 。 こ れ か ら の 夏 の 過 ご し 方 を 改 め て 考 え さ せ ら れ た よ う な 気 が し ま す 。 ま た 、 先 日 は 「 南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 」 や 大 雨 に よ る 避 難 指 示 が 出 さ れ 、 そ れ ぞ れ の ご 家 庭 で も 緊 急 時 の 過 ご し 方 や 、 備 蓄 等 に つ い て 見 直 し を さ れ た の で は な い か と 思 い ま す 。 園 内 で も 日 頃 か ら 訓 練 を 行 っ て い る も の の 、 今 回 改 め て 確 認 す る こ と が た く さ ん あ り ま し た 。 災 害 は い つ 起 こ る か 分 か り ま せ ん 。 常 に 自 分 事 と し て 捉 え 、 ど ん な 状 況 に お い て も 冷 静 な 判 断 が で き る よ う に 日 頃 か ら の 備 え を 確 実 に し て い き た い で す ね 。 さ て 、 先 月 は ひ か り の 子 の 「 夏 ま つ り 」 が 行 わ れ ま し た 。 保 護 者 会 役 員 の 皆 様 の ご 協 力 を は じ め 、 保 護 者 の 皆 様 に ご 理 解 ・ ご 協 力 を い た だ き 開 催 で き ま し た こ と 感 謝 い た し ま す 。 乳 児 ク ラ ス と 幼 児 ク ラ ス で 2 回 に 分 け て 開 催 し 、 そ れ ぞ れ の 時 間 も 昨 年 度 よ り 長 く と る こ と が で き ま し た 。 浴 衣 や 甚 平 等 、 思 い 思 い の 装 い で 参 加 し て く れ た 子 ど も た ち 。 小 さ い 子 た ち は い つ も と 違 う 雰 囲 気 に 緊 張 し た 表 情 で 、 お 父 さ ん や お 母 さ ん に く っ つ き な が ら 過 ご す 様 子 も 見 受 け ら れ ま し た が 、 終 わ る こ ろ に は 笑 顔 満 開 。 帰 り た く な い と 泣 い て い る 子 も い ま し た ね 。 状 況 の 違 い が 分 か る と い う こ と で 、 し っ か り 成 長 し て い る 証 拠 だ な と 思 っ て 見 て い ま し た 。 そ し て 、 何 を し よ う か 楽 し み に し な が ら 参 加 し て く れ た 幼 児 ク ラ ス の 子 ど も た ち 。 し た い こ と を 決 め て い て 、 そ の コ ー ナ ー に ま っ し ぐ ら の 子 や 、 そ の 場 を じ っ く り 見 な が ら 「 こ れ を す る 」 と 決 め て い る 子 が い ま し た 。 そ し て 、 園 内 で の 雰 囲 気 も 受 け な が ら 、 学 童 保 育 で こ の 夏 休 み を ひ か り の 子 で 過 ご し た 小 学 生 た ち が 「 学 童 ま つ り 」 を 企 画 ・ 開 催 し て く れ ま し た 。 「 わ に わ に パ ニ ッ ク 」「 空 気 砲 実 験 コ ー ナ ー 」「 ボ ー リ ン グ 」「 さ か な つ り 」 等 、 す べ て 学 童 さ ん の 手 作 り で す 。 私 も 遊 び に 行 き 、「 わ に わ に パ ニ ッ ク 」 を さ せ て も ら っ て 景 品 も い た だ き ま し た 。 わ に を 叩 い た 数 に 応 じ た 景 品 が 用 意 さ れ て い る こ と に び っ く り 。 0 歳 の 赤 ち ゃ ん た ち か ら 大 人 ま で が 楽 し め る 工 夫 が あ ち こ ち に あ り ま し た 。 乳 児 ク ラ ス の 子 が 来 て も 、 そ の 子 の ペ ー ス で わ に を 叩 け る よ う に 出 し 入 れ の ス ピ ー ド を 考 慮 し て く れ て い ま し た 。 園 児 た ち は 、 叩 け る こ と に 大 満 足 の 様 子 で 「 で き た 」「 楽 し か っ た 」「 こ っ ち も や り た い 」 と 嬉 し そ う な 声 が た く さ ん 聞 か れ ま し た 。 相 手 の 様 子 に 合 わ せ て そ の 都 度 対 応 を 変 化 さ せ る こ と は 、 容 易 な こ と で は な い で す が 、 こ れ か ら を 生 き て い く た め に と て も 大 事 で 必 要 な 力 だ と 思 い ま す 。 そ の 力 が 育 っ て き て い る 小 学 生 の 姿 を と て も 頼 も し く 感 じ ま し た 。「 自 分 で 考 え 、 判 断 す る 」 こ と の 繰 り 返 し に な り ま す が 、 仲 間 と 一 緒 に 考 え た り 、 相 談 し た り 、 自 分 の 気 持 ち を 伝 え た り … そ の よ う な 経 験 が た く さ ん で き る こ ど も 園 時 代 を 保 障 し た い と 思 い ま す 。 今 回 の 経 験 が 学 童 さ ん に と っ て も 園 児 に と っ て も 輝 い た 記 憶 に な り 、 次 に つ な が る よ う な 保 育 を し た い と 思 い ます。
10月
「安全基地」
よ う や く 秋 の 気 配 を 感 じ る よ う に な り ま し た 。今 年 の 夏 は 非 常 に 暑 く 、思 う よ う に 戸 外 に 出 る こ と は か な い ま せ ん で し た が 、 室 内 で の 夏 の 遊 び も 発 見 で き た よ う に 思 い ま す 。 園 庭 の 通 路 に は ミ ス ト も 設 置 し ま し た が 、 こ れ か ら の 時 期 に も 活 躍 し そ う で す 。 少 し ず つ 園 庭 で 遊 べ る よ う に な り 、 嬉 し そ う な 子 ど も た ち の 声 が 響 く よ う に な り ま し た 。 2 カ 月 ぶ り 程 の 戸 外 遊 び で 、 大 は し ゃ ぎ の 様 子 で す が 、 気 持 ち に 身 体 の 動 き が つ い て い か ず に 柱 に ぶ つ か っ て し ま っ た り 、 友 だ ち と 正 面 衝 突 を し た り す る こ と が 多 く 見 受 け ら れ ま す 。 外 で 体 を 動 か す た め の 「 勘 」 を 取 り 戻 す に は 少 し 時 間 が か か り そ う で す の で 、 十 分 気 を 付 け て 見 守 っ て い き た い と 思 い ま す 。 ま た 同 時 に 、 園 庭 で は 異 年 齢 が 一 緒 に 過 ご す こ と も あ り ま す の で 、 異 年 齢 の 関 わ り の 大 切 な 時 間 に も し て い き た い と 思 い ま す 。 先 日 は 能 登 半 島 の 大 雨 で 、 地 震 に 引 き 続 き 甚 大 な 被 害 に あ わ れ た 石 川 県 。 心 よ り お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す 。 大 雨 災 害 の 数 週 間 前 、石 川 県 に 地 震 後 の 復 興 状 況 の 視 察 研 修 に 参 加 さ せ て い た だ き 、七 尾 市 辺 り を 視 察 さ せ て い た だ き ま し た 。バ ス で の 移 動 中 、 家 屋 の 瓦 屋 根 は 部 分 的 に ブ ル ー シ ー ト で 覆 わ れ て い る 家 が 多 く 、 そ の 中 で 通 常 の 生 活 を 送 っ て お ら れ る こ と が 分 か り ま し た 。 ま た 、 道 路 や 駐 車 場 は 所 々 隆 起 し た ま ま 、 電 柱 は 斜 め の 状 態 。 そ れ で も 日 常 の 生 活 は 続 い て い ま す 。 道 路 沿 い に 立 ち 並 ぶ 家 に は 「 危 険 」「 注 意 」 と 貼 り 紙 が さ れ て い る 所 も あ り ま し た 。 そ し て 、 そ れ で も そ こ に 住 む し か な い 方 も い る と い う こ と を 知 り ま し た 。 私 は テ レ ビ 等 で 見 え て い る 「 一 面 」 で し か 物 事 を 見 て お ら ず 、 表 面 的 に 見 え て い る 部 分 を 切 り 取 っ て 「 知 っ た つ も り 」 に な っ て い る こ と に 改 め て 気 づ か さ れ ま し た 。 目 や 耳 か ら 入 る 情 報 の 一 面 や 側 面 だ け で 物 事 を 判 断 す る こ と や 、 自 分 の 経 験 か ら 相 手 を 分 か っ た つ も り に な っ て し ま う こ と は 多 い と 思 い ま す が 、多 角 的 に 物 事 や 相 手 の 気 持 ち を 分 か ろ う と す る こ と を 改 め て 今 後 も 意 識 的 に 大 事 に し た い と 思 い ま し た 。 さ て 、 先 週 末 に は ひ よ こ 組 と ほ し 組 の 「 お や こ で あ そ ぼ う 」 が 行 わ れ ま し た 。 お 忙 し い 中 ご 参 加 い た だ き あ り が と う ご ざ い ま し た 。 普 段 、 こ ど も 園 で ど の よ う な こ と で 楽 し ん で い る の か な ? 友 だ ち と の 関 わ り っ て ど う な の か な ? コ ド モ ン で 写 真 を 見 る 機 会 が 増 え た と は い え 、 や は り 実 際 に ご 自 分 の 目 で 見 て 、 そ の 瞬 間 を 一 緒 に 過 ご す こ と で 感 じ る こ と が あ る の で は な い で し ょ う か 。 ひ よ こ 組 で は 、 大 好 き な お 父 さ ん 、 お 母 さ ん と 一 緒 だ け れ ど な ん だ か い つ も と 違 う 雰 囲 気 に 最 初 は 緊 張 気 味 の 様 子 。 で も 、 い つ も 一 緒 に 過 ご す 友 だ ち の 顔 を 見 る と 嬉 し そ う な 笑 顔 が あ ふ れ ま し た 。 手 足 を 動 か し て 笑 顔 満 開 の 様 子 に 、 こ ん な に 小 さ く て も お 互 い の 存 在 を し っ か り 感 じ て 、安 心 す る ん だ と よ く 分 か り ま す 。ま だ ま だ 一 緒 に 遊 ぶ と い う こ と で は あ り ま せ ん 。 で も 同 じ 空 間 に い る こ と が い つ の 間 に か 当 た り 前 に な り 、 安 心 感 に つ な が っ て い く の で す ね 。 そ し て 、 い つ も と 違 う こ の 環 境 に 少 し 慣 れ て く る と 、 普 段 の よ う に 遊 び 始 め ま す 。 滑 り 台 に よ じ 登 っ た り 、 降 り て 来 た り 。 お 母 さ ん か ら 離 れ て 滑 り 台 に 登 り 、 そ し て 降 り て く る と 必 ず お 母 さ ん の 顔 を 見 ま す 。 そ し て そ こ に は 、 お 母 さ ん の 笑 顔 。 ず っ と 自 分 を 見 て い て く れ る 安 心 感 が あ る か ら 離 れ て 遊 ぶ こ と が で き 、 振 り 向 い た 時 に も 「 見 て い た よ ! す ご い ね 。」 と 笑 顔 で 応 え て く れ る 存 在 が あ る 。 ぎ ゅ っ と 抱 き し め て く れ る 人 が い る か ら ま た 離 れ て 探 索 し 始 め ま す 。 ま さ し く 「 安 全 基 地 」 で あ る お 母 さ ん 、 お 父 さ ん の 存 在 を 実 感 し ま し た 。 ち ょ っ と 冒 険 し た い け れ ど 、 安 心 で き る 「 安 全 基 地 」 が な い と 離 れ て い く こ と す ら で き ま せ ん 。 子 ど も た ち が 安 心 し て 自 分 の 周 り の 人 や 物 に 関 わ っ て い く 過 程 を 目 の 当 た り に す る こ と が で き る 日 で し た 。 そ し て ほ し 組 に な る と 、 友 だ ち と の 関 わ り も 増 え て き ま す 。 で も こ の 日 は や っ ぱ り お う ち の 人 と 一 緒 が う れ し く て 離 れ た く な か っ た 子 も い た の で は な い で し ょ う か 。 こ れ も 成 長 過 程 の 一 ペ ー ジ で す 。 一 つ ず つ そ の 時 々 に 合 っ た 関 わ り を 積 み 重 ね て い く こ と で 、 安 心 し て 成 長 し て い く こ と が で き ま す の で 、「 今 」 を 大 事 に し て い き た い も の で す ね。
よ う や く 秋 の 気 配 を 感 じ る よ う に な り ま し た 。今 年 の 夏 は 非 常 に 暑 く 、思 う よ う に 戸 外 に 出 る こ と は か な い ま せ ん で し た が 、 室 内 で の 夏 の 遊 び も 発 見 で き た よ う に 思 い ま す 。 園 庭 の 通 路 に は ミ ス ト も 設 置 し ま し た が 、 こ れ か ら の 時 期 に も 活 躍 し そ う で す 。 少 し ず つ 園 庭 で 遊 べ る よ う に な り 、 嬉 し そ う な 子 ど も た ち の 声 が 響 く よ う に な り ま し た 。 2 カ 月 ぶ り 程 の 戸 外 遊 び で 、 大 は し ゃ ぎ の 様 子 で す が 、 気 持 ち に 身 体 の 動 き が つ い て い か ず に 柱 に ぶ つ か っ て し ま っ た り 、 友 だ ち と 正 面 衝 突 を し た り す る こ と が 多 く 見 受 け ら れ ま す 。 外 で 体 を 動 か す た め の 「 勘 」 を 取 り 戻 す に は 少 し 時 間 が か か り そ う で す の で 、 十 分 気 を 付 け て 見 守 っ て い き た い と 思 い ま す 。 ま た 同 時 に 、 園 庭 で は 異 年 齢 が 一 緒 に 過 ご す こ と も あ り ま す の で 、 異 年 齢 の 関 わ り の 大 切 な 時 間 に も し て い き た い と 思 い ま す 。 先 日 は 能 登 半 島 の 大 雨 で 、 地 震 に 引 き 続 き 甚 大 な 被 害 に あ わ れ た 石 川 県 。 心 よ り お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す 。 大 雨 災 害 の 数 週 間 前 、石 川 県 に 地 震 後 の 復 興 状 況 の 視 察 研 修 に 参 加 さ せ て い た だ き 、七 尾 市 辺 り を 視 察 さ せ て い た だ き ま し た 。バ ス で の 移 動 中 、 家 屋 の 瓦 屋 根 は 部 分 的 に ブ ル ー シ ー ト で 覆 わ れ て い る 家 が 多 く 、 そ の 中 で 通 常 の 生 活 を 送 っ て お ら れ る こ と が 分 か り ま し た 。 ま た 、 道 路 や 駐 車 場 は 所 々 隆 起 し た ま ま 、 電 柱 は 斜 め の 状 態 。 そ れ で も 日 常 の 生 活 は 続 い て い ま す 。 道 路 沿 い に 立 ち 並 ぶ 家 に は 「 危 険 」「 注 意 」 と 貼 り 紙 が さ れ て い る 所 も あ り ま し た 。 そ し て 、 そ れ で も そ こ に 住 む し か な い 方 も い る と い う こ と を 知 り ま し た 。 私 は テ レ ビ 等 で 見 え て い る 「 一 面 」 で し か 物 事 を 見 て お ら ず 、 表 面 的 に 見 え て い る 部 分 を 切 り 取 っ て 「 知 っ た つ も り 」 に な っ て い る こ と に 改 め て 気 づ か さ れ ま し た 。 目 や 耳 か ら 入 る 情 報 の 一 面 や 側 面 だ け で 物 事 を 判 断 す る こ と や 、 自 分 の 経 験 か ら 相 手 を 分 か っ た つ も り に な っ て し ま う こ と は 多 い と 思 い ま す が 、多 角 的 に 物 事 や 相 手 の 気 持 ち を 分 か ろ う と す る こ と を 改 め て 今 後 も 意 識 的 に 大 事 に し た い と 思 い ま し た 。 さ て 、 先 週 末 に は ひ よ こ 組 と ほ し 組 の 「 お や こ で あ そ ぼ う 」 が 行 わ れ ま し た 。 お 忙 し い 中 ご 参 加 い た だ き あ り が と う ご ざ い ま し た 。 普 段 、 こ ど も 園 で ど の よ う な こ と で 楽 し ん で い る の か な ? 友 だ ち と の 関 わ り っ て ど う な の か な ? コ ド モ ン で 写 真 を 見 る 機 会 が 増 え た と は い え 、 や は り 実 際 に ご 自 分 の 目 で 見 て 、 そ の 瞬 間 を 一 緒 に 過 ご す こ と で 感 じ る こ と が あ る の で は な い で し ょ う か 。 ひ よ こ 組 で は 、 大 好 き な お 父 さ ん 、 お 母 さ ん と 一 緒 だ け れ ど な ん だ か い つ も と 違 う 雰 囲 気 に 最 初 は 緊 張 気 味 の 様 子 。 で も 、 い つ も 一 緒 に 過 ご す 友 だ ち の 顔 を 見 る と 嬉 し そ う な 笑 顔 が あ ふ れ ま し た 。 手 足 を 動 か し て 笑 顔 満 開 の 様 子 に 、 こ ん な に 小 さ く て も お 互 い の 存 在 を し っ か り 感 じ て 、安 心 す る ん だ と よ く 分 か り ま す 。ま だ ま だ 一 緒 に 遊 ぶ と い う こ と で は あ り ま せ ん 。 で も 同 じ 空 間 に い る こ と が い つ の 間 に か 当 た り 前 に な り 、 安 心 感 に つ な が っ て い く の で す ね 。 そ し て 、 い つ も と 違 う こ の 環 境 に 少 し 慣 れ て く る と 、 普 段 の よ う に 遊 び 始 め ま す 。 滑 り 台 に よ じ 登 っ た り 、 降 り て 来 た り 。 お 母 さ ん か ら 離 れ て 滑 り 台 に 登 り 、 そ し て 降 り て く る と 必 ず お 母 さ ん の 顔 を 見 ま す 。 そ し て そ こ に は 、 お 母 さ ん の 笑 顔 。 ず っ と 自 分 を 見 て い て く れ る 安 心 感 が あ る か ら 離 れ て 遊 ぶ こ と が で き 、 振 り 向 い た 時 に も 「 見 て い た よ ! す ご い ね 。」 と 笑 顔 で 応 え て く れ る 存 在 が あ る 。 ぎ ゅ っ と 抱 き し め て く れ る 人 が い る か ら ま た 離 れ て 探 索 し 始 め ま す 。 ま さ し く 「 安 全 基 地 」 で あ る お 母 さ ん 、 お 父 さ ん の 存 在 を 実 感 し ま し た 。 ち ょ っ と 冒 険 し た い け れ ど 、 安 心 で き る 「 安 全 基 地 」 が な い と 離 れ て い く こ と す ら で き ま せ ん 。 子 ど も た ち が 安 心 し て 自 分 の 周 り の 人 や 物 に 関 わ っ て い く 過 程 を 目 の 当 た り に す る こ と が で き る 日 で し た 。 そ し て ほ し 組 に な る と 、 友 だ ち と の 関 わ り も 増 え て き ま す 。 で も こ の 日 は や っ ぱ り お う ち の 人 と 一 緒 が う れ し く て 離 れ た く な か っ た 子 も い た の で は な い で し ょ う か 。 こ れ も 成 長 過 程 の 一 ペ ー ジ で す 。 一 つ ず つ そ の 時 々 に 合 っ た 関 わ り を 積 み 重 ね て い く こ と で 、 安 心 し て 成 長 し て い く こ と が で き ま す の で 、「 今 」 を 大 事 に し て い き た い も の で す ね。
11月
「 子どもの安全基地になる 」
朝夕がやっと涼しくなり、陽が落ちる時間が早くなりました。田んぼの稲刈りもおわり、ようやく秋の気配を感じます。先月は幼児クラスの秋の遠足があり、子どもたちは大型バスに乗って近くの公園に秋を見つける探検に出かけることができました。保護者の皆様にはご協力いただきありがとうございました。にじ・そら組の遠足の日は朝まで小雨が降り、行先をギリギリまで検討していましたが、天気予報を信じて都田総合公園へ。雨に降られずたっぷりと遊んでくることができました。公園の中では色々な人たちと出会いました。すれ違う時に「こんにちは」と自分から声をかけるのは少し勇気が必要ですが、何度か繰り返しているうちに自ら声が出せるようになっていく子もいました。相手の方もにっこり笑って「こんにちは」「いいね~楽しそうだね」と声をかけてくださいました。そんなふうに笑顔を見せてくださるとうれしいものですね。先日の不審者対応訓練では『知らない人に声をかけられてもついていかない』と教えてもらいましたが、やはり普段からあいさつは大事。私たち大人が率先してすれ違う人たちに挨拶をすることを大切にしたいと感じた一場面でした。
ひかりの子では、年間の中で必ず一度は保護者の皆様と担任が顔を合わせて個人面談をさせていただいています。その中で、年長児についてはこの時期に園長も交えた三者で「卒園面談」をさせていただいています。短時間ではありますが、一人ひとりの「その子」のことに思いを巡らせ考える時間は、その子に関わる私たちにとっても非常に貴重な時間になっています。年長児ともなると、「このくらい自分でできて当たり前」といつの間にか思ってしまうことがいかに多いか。保護者の方も「下の子は、トイレで排泄できるだけで褒められているのに…いつの間にか上の子は色々できて当たり前と思ってしまっていました。」と気づかれていました。「褒める」「認める」ポイントも年齢相応でなくてはいけませんが、普段から「できていること」もたくさんあるはずなのです。できていないことに意識がいき、つい「また〇〇してない」「いつも言っているでしょ」と言いがちですが、きっとできている時もあるはずなのです。その「できている時」はなぜか気づいていないことが多いのです。もしくは、できていて当然と思ってしまっていると、褒めることができないのかもしれません。でも、できている時にすかさず褒めていきたいですね。「〇〇できてるね。さすがだね。」等々、注意されるばかりでなく、ちゃんとできている時も見ていてくれる、褒めてくれることが子どもたちに伝わるといいなと思います。「注意される=注目される」ことになるので、子どもたちの意識もそちらに向くのだと思います。してほしい行動に注目して、具体的に言葉で伝えてあげるといいですね。こども園でも同じように関わっていきたいと思っています。
面談を通して、保護者の皆様の子どもたちへの思いや、こう育ってほしいという願い、そして何よりも愛おしいと思う気持ちがとても伝わってきます。同時に、本当に大事なお子様を預からせていただいているという実感が湧いてきます。私たちも子ども自身が、自分は大事にされている、愛されてるという実感をもって大きくなっていってほしいと思って保育をさせていただいています。目には見えない部分ですが、子どもたちがつらい時、困ったことがあった時にいつでも戻れる安全な場所(家庭、主にお父さん・お母さん)があれば大丈夫。こども園もその1つになりたいと思っています。外の世界で頑張っている子どもたちですので、ゆっくりと応援してあげたいですね。
今月は収穫感謝祭があります。間近で稲刈りを見た子どもたちですので、きっと感じることがあることと思います。各ご家庭からもお気持ちで結構ですので身近な果物や野菜を持ってきていただけたらと思います。それらを囲んで収穫感謝の礼拝をおこなう予定です。そして、だんだんとクリスマスにも思いを向けて過ごしていきたいと思っています。
朝夕がやっと涼しくなり、陽が落ちる時間が早くなりました。田んぼの稲刈りもおわり、ようやく秋の気配を感じます。先月は幼児クラスの秋の遠足があり、子どもたちは大型バスに乗って近くの公園に秋を見つける探検に出かけることができました。保護者の皆様にはご協力いただきありがとうございました。にじ・そら組の遠足の日は朝まで小雨が降り、行先をギリギリまで検討していましたが、天気予報を信じて都田総合公園へ。雨に降られずたっぷりと遊んでくることができました。公園の中では色々な人たちと出会いました。すれ違う時に「こんにちは」と自分から声をかけるのは少し勇気が必要ですが、何度か繰り返しているうちに自ら声が出せるようになっていく子もいました。相手の方もにっこり笑って「こんにちは」「いいね~楽しそうだね」と声をかけてくださいました。そんなふうに笑顔を見せてくださるとうれしいものですね。先日の不審者対応訓練では『知らない人に声をかけられてもついていかない』と教えてもらいましたが、やはり普段からあいさつは大事。私たち大人が率先してすれ違う人たちに挨拶をすることを大切にしたいと感じた一場面でした。
ひかりの子では、年間の中で必ず一度は保護者の皆様と担任が顔を合わせて個人面談をさせていただいています。その中で、年長児についてはこの時期に園長も交えた三者で「卒園面談」をさせていただいています。短時間ではありますが、一人ひとりの「その子」のことに思いを巡らせ考える時間は、その子に関わる私たちにとっても非常に貴重な時間になっています。年長児ともなると、「このくらい自分でできて当たり前」といつの間にか思ってしまうことがいかに多いか。保護者の方も「下の子は、トイレで排泄できるだけで褒められているのに…いつの間にか上の子は色々できて当たり前と思ってしまっていました。」と気づかれていました。「褒める」「認める」ポイントも年齢相応でなくてはいけませんが、普段から「できていること」もたくさんあるはずなのです。できていないことに意識がいき、つい「また〇〇してない」「いつも言っているでしょ」と言いがちですが、きっとできている時もあるはずなのです。その「できている時」はなぜか気づいていないことが多いのです。もしくは、できていて当然と思ってしまっていると、褒めることができないのかもしれません。でも、できている時にすかさず褒めていきたいですね。「〇〇できてるね。さすがだね。」等々、注意されるばかりでなく、ちゃんとできている時も見ていてくれる、褒めてくれることが子どもたちに伝わるといいなと思います。「注意される=注目される」ことになるので、子どもたちの意識もそちらに向くのだと思います。してほしい行動に注目して、具体的に言葉で伝えてあげるといいですね。こども園でも同じように関わっていきたいと思っています。
面談を通して、保護者の皆様の子どもたちへの思いや、こう育ってほしいという願い、そして何よりも愛おしいと思う気持ちがとても伝わってきます。同時に、本当に大事なお子様を預からせていただいているという実感が湧いてきます。私たちも子ども自身が、自分は大事にされている、愛されてるという実感をもって大きくなっていってほしいと思って保育をさせていただいています。目には見えない部分ですが、子どもたちがつらい時、困ったことがあった時にいつでも戻れる安全な場所(家庭、主にお父さん・お母さん)があれば大丈夫。こども園もその1つになりたいと思っています。外の世界で頑張っている子どもたちですので、ゆっくりと応援してあげたいですね。
今月は収穫感謝祭があります。間近で稲刈りを見た子どもたちですので、きっと感じることがあることと思います。各ご家庭からもお気持ちで結構ですので身近な果物や野菜を持ってきていただけたらと思います。それらを囲んで収穫感謝の礼拝をおこなう予定です。そして、だんだんとクリスマスにも思いを向けて過ごしていきたいと思っています。
12月
「うれしいクリスマス 」
今年もうれしいクリスマスを迎える季節になりました。収穫感謝祭も終わり、特ににじ・そら組の子どもたちの中では早速ページェントごっこが始まっています。園内でもクリスマスにまつわる讃美歌が聞こえてくるようになりました。今年は十二月一日(日)からアドベントの期間となり、イエス様のお生まれになったうれしい日、クリスマスを心静かに喜びをもって待つ時となります。にじ・そら組の子どもたちが毎年行う生誕劇(ページェント)は、イエス様がお生まれになる時のお話です。子どもたち自身も神さまにお捧げする大切なこととして捉え、どの役もすべてが大事で、どの役(人)も欠かすことができないものということを理解していきます。昨年を含め、今までの経験の中からすでにやりたい役が明確になっている子、色々な役をやってみて、その役のことを知っていくうちに気持ちが変わる子など様々です。子どもたち一人ひとりが神さまに愛され、大切にされているのと同じように、どの役も大切で必要であることが伝わっていくといいなと思っています。どうぞ一緒に見守ってください。また、ほし組や乳児クラスの子どもたちも絵本やお話を通してクリスマスを知り、楽しみにしながら待てるようにしていきますので、保護者の皆さまにも少しずつ飾られていく園内の様子を含めて楽しみにしてくださいね。
さて、先月の育児講演会にはお忙しい中たくさんの親子に参加していただき「積み木であそぼう」を開催することができましたこと感謝申し上げます。いただいた感想は、下記でご紹介させていただきます。今回は、おもちゃコーディネーターの大隅和子さんにお越しいただき、改めて「積み木」の魅力について教えていただきました。実際に子どもたちが遊ぶ様子を見ている中での私の発見をご紹介したいと思います。二歳児のお子さんが直角二等辺三角柱と立方体を組み合わせていた時のことです。直角二等辺三角柱を二つ合わせると立方体になることに気付いた瞬間がありました。近くに立方体があるにも関わらず、あえて直角二等辺三角柱を探して組み合わせて立方体の箱にしまっていたのです。ぴったりはまっていくことの面白さにも気づいたのではないかと思います。三角を2つ組み合わせると四角になる…
図形の理解や算数につながっていくことですが、このような遊びの場面から、子どもたちがいつのまにか習得していくということがよく分かった瞬間でした。夢中になって遊ぶことが学びにつながっていくのです。こういった姿を見守る私たち大人は、子どもが何かに気付いた瞬間や、それがどのような力につながっていくのかを意識していなくてはなりませんね。そして、私自身がとても気づかされたのは、「もとに戻す」という表現でした。つい「片付けしよう」と伝えますが、この積み木の最後では「箱の中に戻してね」「もとに戻そうね」という表現をされていました。「片付け」はその場をきれいにする、というイメージですが、「もとに戻す」はその物も大切にされているような印象でした。それは些細なことかもしれませんが、私たち大人の言葉がけも子どもたちにとっての大切な環境であることを改めて感じました。
子どもたちが自分で考えてやってみようとする力は、これからを生きていくために必要な力です。どのような関わりがその力を育むことにつながるのか、私たちも日々学びながら子どもたちと過ごしていきたいと思います。
今年もうれしいクリスマスを迎える季節になりました。収穫感謝祭も終わり、特ににじ・そら組の子どもたちの中では早速ページェントごっこが始まっています。園内でもクリスマスにまつわる讃美歌が聞こえてくるようになりました。今年は十二月一日(日)からアドベントの期間となり、イエス様のお生まれになったうれしい日、クリスマスを心静かに喜びをもって待つ時となります。にじ・そら組の子どもたちが毎年行う生誕劇(ページェント)は、イエス様がお生まれになる時のお話です。子どもたち自身も神さまにお捧げする大切なこととして捉え、どの役もすべてが大事で、どの役(人)も欠かすことができないものということを理解していきます。昨年を含め、今までの経験の中からすでにやりたい役が明確になっている子、色々な役をやってみて、その役のことを知っていくうちに気持ちが変わる子など様々です。子どもたち一人ひとりが神さまに愛され、大切にされているのと同じように、どの役も大切で必要であることが伝わっていくといいなと思っています。どうぞ一緒に見守ってください。また、ほし組や乳児クラスの子どもたちも絵本やお話を通してクリスマスを知り、楽しみにしながら待てるようにしていきますので、保護者の皆さまにも少しずつ飾られていく園内の様子を含めて楽しみにしてくださいね。
さて、先月の育児講演会にはお忙しい中たくさんの親子に参加していただき「積み木であそぼう」を開催することができましたこと感謝申し上げます。いただいた感想は、下記でご紹介させていただきます。今回は、おもちゃコーディネーターの大隅和子さんにお越しいただき、改めて「積み木」の魅力について教えていただきました。実際に子どもたちが遊ぶ様子を見ている中での私の発見をご紹介したいと思います。二歳児のお子さんが直角二等辺三角柱と立方体を組み合わせていた時のことです。直角二等辺三角柱を二つ合わせると立方体になることに気付いた瞬間がありました。近くに立方体があるにも関わらず、あえて直角二等辺三角柱を探して組み合わせて立方体の箱にしまっていたのです。ぴったりはまっていくことの面白さにも気づいたのではないかと思います。三角を2つ組み合わせると四角になる…
図形の理解や算数につながっていくことですが、このような遊びの場面から、子どもたちがいつのまにか習得していくということがよく分かった瞬間でした。夢中になって遊ぶことが学びにつながっていくのです。こういった姿を見守る私たち大人は、子どもが何かに気付いた瞬間や、それがどのような力につながっていくのかを意識していなくてはなりませんね。そして、私自身がとても気づかされたのは、「もとに戻す」という表現でした。つい「片付けしよう」と伝えますが、この積み木の最後では「箱の中に戻してね」「もとに戻そうね」という表現をされていました。「片付け」はその場をきれいにする、というイメージですが、「もとに戻す」はその物も大切にされているような印象でした。それは些細なことかもしれませんが、私たち大人の言葉がけも子どもたちにとっての大切な環境であることを改めて感じました。
子どもたちが自分で考えてやってみようとする力は、これからを生きていくために必要な力です。どのような関わりがその力を育むことにつながるのか、私たちも日々学びながら子どもたちと過ごしていきたいと思います。
1月
「新年あけましておめでとうございます 」
新年あけましておめでとうございます。新しい年の幕開けですね。本年もよろしくお願いいたします。
さて、先月は幼児クラス、乳児クラスそれぞれにクリスマスをお祝いいたしました。保護者の皆さまには色々とご理解、ご協力をいただきありがとうございました。年中児と年長児のクラスではページェント(生誕劇)を通して保護者の皆さまにもクリスマスの出来事をお伝えしました。年少児クラスは親子で礼拝に参加していただき、職員による人形劇でクリスマスの出来事をお伝えしました。その中で歌われるたくさんの歌。それは年中・年長児の子どもたちが行うページェントの中で歌うものと同じです。子どもたちもよく分かっていて、身体を揺らしながら一緒に歌ってくれていました。こうやって次の年につながっていくんだなと改めて嬉しい気持ちになりました。また、乳児クラスでもアドベント期間からクリスマス当日までそれぞれに年齢に合わせて礼拝を守ってきました。讃美歌はみんな大好きで手を振ったり身体を揺らして歌い、心地よい雰囲気がありました。ろうそくの灯りをじっと見て「ついた」とそっとつぶやく子もいましたよ。子どもたちの年齢によってお祝いの仕方は違いますが、私たちが大切にしたい思いは同じです。子どもたちと保護者の皆さまと一緒にクリスマスをお祝いすることができたことを感謝したいと思います。
そして、年中・年長児のページェントを作り上げていく過程の中では今年も様々なことがありました。どの役も大切であることを子どもたちはしっかり分かっていますが、一人ひとりの中にはやりたい役があります。できるだけ子どもたちが話し合いの中で、自分の気持ちを伝え、友だちの気持ちを聴きながら決められるように見守ってきました。色々な思いがありながらもそれぞれに納得し、次の段階に進んでいってくれた様子がありました。それまでも色々な役をやって楽しんできた子どもたちですので、今度はおうちの人たちにクリスマスの話を伝える、そして神さまにお捧げするという目標に向かって楽しそうに(時には緊張感もありましたが…)日々を過ごす様子がとても頼もしく感じました。祝会当日の週は体調不良でお休みする子が出てきて、全員がそろわない日が続きました。それでも、子どもたちはお休みの子のせりふをカバーし合い、時には周りの複数の子が同時に立ち上がりお休みの子のせりふを言ってくれ、事前に特にお願いしていなかった職員もびっくりするやら感動するやら。全員で作り上げるページェントであり、ただ自分だけのことを考えていたり理解しているだけでは絶対にできないということを子どもたちが教えてくれました。緊張もあってせりふが飛んでしまったりするときも、周りの子が必ずそっとささやいて教えてくれました。大人が「やらせる」ものではなく、子どもたちが自分で考えて行ってくれたことにとても嬉しさがありました。
子どもたちは、日々それぞれに経験したことを自分なりに学び、そのスキルを活かす場を探しているのだと思います。私たちが教えることはできないことが多々あります。特に目には見えない「気持ち」は、とても難しいです。「私」の気持ちと「相手」の気持ちが一致するとは限りませんし、一致したように感じても実は違うことを思っていたりもします。確認し合うことも大事ですが非常に難しいです。私たちは、子どもの気持ちを代弁したり、ただ寄り添うことしかできないこともありますが、代弁する時に「これは私の思い込みなのでは?」と思う時もあります。うまく表現できないもどかしい気持ちもありのまま受けとり、そっと本人の気持ちを見守ることも大事にしたいと思います。
子ども自身が自分自身を信頼し、そして周りの人たちを信頼できることが生きる力につながっていきます。そんな心の根っこがこれからも強く太く育つように、一人ひとりを大切に関わらせていただきたいと思います。今年度も残りわずかとなりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
新年あけましておめでとうございます。新しい年の幕開けですね。本年もよろしくお願いいたします。
さて、先月は幼児クラス、乳児クラスそれぞれにクリスマスをお祝いいたしました。保護者の皆さまには色々とご理解、ご協力をいただきありがとうございました。年中児と年長児のクラスではページェント(生誕劇)を通して保護者の皆さまにもクリスマスの出来事をお伝えしました。年少児クラスは親子で礼拝に参加していただき、職員による人形劇でクリスマスの出来事をお伝えしました。その中で歌われるたくさんの歌。それは年中・年長児の子どもたちが行うページェントの中で歌うものと同じです。子どもたちもよく分かっていて、身体を揺らしながら一緒に歌ってくれていました。こうやって次の年につながっていくんだなと改めて嬉しい気持ちになりました。また、乳児クラスでもアドベント期間からクリスマス当日までそれぞれに年齢に合わせて礼拝を守ってきました。讃美歌はみんな大好きで手を振ったり身体を揺らして歌い、心地よい雰囲気がありました。ろうそくの灯りをじっと見て「ついた」とそっとつぶやく子もいましたよ。子どもたちの年齢によってお祝いの仕方は違いますが、私たちが大切にしたい思いは同じです。子どもたちと保護者の皆さまと一緒にクリスマスをお祝いすることができたことを感謝したいと思います。
そして、年中・年長児のページェントを作り上げていく過程の中では今年も様々なことがありました。どの役も大切であることを子どもたちはしっかり分かっていますが、一人ひとりの中にはやりたい役があります。できるだけ子どもたちが話し合いの中で、自分の気持ちを伝え、友だちの気持ちを聴きながら決められるように見守ってきました。色々な思いがありながらもそれぞれに納得し、次の段階に進んでいってくれた様子がありました。それまでも色々な役をやって楽しんできた子どもたちですので、今度はおうちの人たちにクリスマスの話を伝える、そして神さまにお捧げするという目標に向かって楽しそうに(時には緊張感もありましたが…)日々を過ごす様子がとても頼もしく感じました。祝会当日の週は体調不良でお休みする子が出てきて、全員がそろわない日が続きました。それでも、子どもたちはお休みの子のせりふをカバーし合い、時には周りの複数の子が同時に立ち上がりお休みの子のせりふを言ってくれ、事前に特にお願いしていなかった職員もびっくりするやら感動するやら。全員で作り上げるページェントであり、ただ自分だけのことを考えていたり理解しているだけでは絶対にできないということを子どもたちが教えてくれました。緊張もあってせりふが飛んでしまったりするときも、周りの子が必ずそっとささやいて教えてくれました。大人が「やらせる」ものではなく、子どもたちが自分で考えて行ってくれたことにとても嬉しさがありました。
子どもたちは、日々それぞれに経験したことを自分なりに学び、そのスキルを活かす場を探しているのだと思います。私たちが教えることはできないことが多々あります。特に目には見えない「気持ち」は、とても難しいです。「私」の気持ちと「相手」の気持ちが一致するとは限りませんし、一致したように感じても実は違うことを思っていたりもします。確認し合うことも大事ですが非常に難しいです。私たちは、子どもの気持ちを代弁したり、ただ寄り添うことしかできないこともありますが、代弁する時に「これは私の思い込みなのでは?」と思う時もあります。うまく表現できないもどかしい気持ちもありのまま受けとり、そっと本人の気持ちを見守ることも大事にしたいと思います。
子ども自身が自分自身を信頼し、そして周りの人たちを信頼できることが生きる力につながっていきます。そんな心の根っこがこれからも強く太く育つように、一人ひとりを大切に関わらせていただきたいと思います。今年度も残りわずかとなりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
2月
「 きれいな花を楽しみに待つ 」
早いものでもう二月。今年度も残すところ二カ月となりました。寒いと感じる日も多いですが、幼児クラスの子どもたちを中心に、毎朝体操をした後マラソンを楽しんでいます。走ることが得意な子、好きな子、苦手な子…様々ですが、子どもたちの気持ちは大きくなるにつれて複雑です。『走りたいけれど、一番になれないかもしれないから走りたくない』『とにかく一番になりたい』等強い思いがあったり、みんなに応援されながらニコニコと自分のペースで走ったりといろいろです。自分だけでなく、周りが見えてきて、自分と友だちを比べてみたりすることもあります。私たちは、誰かと比べたりせずにその子の頑張りや、その過程を認めたいと思いますが、目に見えない部分を認めたり励ましていくのは本当に難しいものですね。しかし、一人ひとりの思いを理解しようとしながら、具体的な姿を認めていきたいと思います。子どもたちはその時に一緒にやらなくても、周りの様子をその子なりによく見ています。そして、『大丈夫かもしれない』『やれるかもしれない』と考えて自分でタイミングを計っているようです。
年始明け、羽根つきやこま回し、縄跳びに夢中になっている子の姿が多くありました。職員たちも一緒に楽しみましたが、幼少期にそれらの遊びの経験があって「得意だった」「好きだった」と肯定的な思い出がある職員は今でも夢中になり、うまくいかなくても何度もやっていました。私自身は幼少期にこま回しが得意だった記憶はあるのですが、保育士になってから「できない」経験を重ねてきました。しかしこの冬、得意な職員に改めて教えてもらってコツをつかむことができたら、子どもたちと一緒で楽しくて何度も何度もやりたくなりました。子どもたちにもこういう達成感や喜びを感じてもらいたいと思うのですが、誘うタイミングは難しいですね。【わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。】という聖句があります。いま、園庭のプランターに植えたチューリップが少しずつ芽を出し始めました。すぐにきれいな花が見たいからと言って「早く大きくな~れ!」と球根や小さな芽をひっぱってもきれいな花は咲きません。それどころかぽきっと折れてしまいます。子どもたちにもそれと同じことがいえると私は思っています。一人ひとりの成長には個人差があると分かっているつもりでも、「そろそろ〇〇ができる頃なのでは?」「まだ△△ができないけど大丈夫かな?」と気になることもあるかもしれません。でも、成長・発達の順序をとばすことなく一歩ずつ確実に積み重ねることが力になり、最終的には【きれいな花】を咲かすことになるのです。きれいな花は、「その子らしさ」だと思うのです。その子が自分らしく自分を発揮して、そして自分のことを好きでいてほしいと思います。私たち大人が、先を見すぎて子どもたちを引っ張りすぎることのないように、目の前の子どもたちにしっかり思いと意識を向けたいものです。その子の興味のあること、好きなこと、得意なことを通して成功体験をたくさんしてほしいですね。また、そのアシストをしてあげられるように、その子をよく知ることを改めて大事にしたいと思います。
引っ張って伸ばすよりも、その時に必要な栄養をたっぷりと与えながら、その子がその子らしく花開く時を信じて待つ。きっと土の中でしっかりと根が張り巡らされ、ちょっとやそっとの風では折れないしなやかな幹や枝にきれいな花が咲き、豊かな実がなると思います。
この時期、改めて子どもたちの姿をよく見て、大人が手をかけすぎていることはないか?今一度しっかり手や目をかけていくべきところはどこかを確認しながら過ごしています。就学や進級を控えていますが、安心して次の年度を迎えることができるように日々の生活を丁寧に送りたいと思います。
早いものでもう二月。今年度も残すところ二カ月となりました。寒いと感じる日も多いですが、幼児クラスの子どもたちを中心に、毎朝体操をした後マラソンを楽しんでいます。走ることが得意な子、好きな子、苦手な子…様々ですが、子どもたちの気持ちは大きくなるにつれて複雑です。『走りたいけれど、一番になれないかもしれないから走りたくない』『とにかく一番になりたい』等強い思いがあったり、みんなに応援されながらニコニコと自分のペースで走ったりといろいろです。自分だけでなく、周りが見えてきて、自分と友だちを比べてみたりすることもあります。私たちは、誰かと比べたりせずにその子の頑張りや、その過程を認めたいと思いますが、目に見えない部分を認めたり励ましていくのは本当に難しいものですね。しかし、一人ひとりの思いを理解しようとしながら、具体的な姿を認めていきたいと思います。子どもたちはその時に一緒にやらなくても、周りの様子をその子なりによく見ています。そして、『大丈夫かもしれない』『やれるかもしれない』と考えて自分でタイミングを計っているようです。
年始明け、羽根つきやこま回し、縄跳びに夢中になっている子の姿が多くありました。職員たちも一緒に楽しみましたが、幼少期にそれらの遊びの経験があって「得意だった」「好きだった」と肯定的な思い出がある職員は今でも夢中になり、うまくいかなくても何度もやっていました。私自身は幼少期にこま回しが得意だった記憶はあるのですが、保育士になってから「できない」経験を重ねてきました。しかしこの冬、得意な職員に改めて教えてもらってコツをつかむことができたら、子どもたちと一緒で楽しくて何度も何度もやりたくなりました。子どもたちにもこういう達成感や喜びを感じてもらいたいと思うのですが、誘うタイミングは難しいですね。【わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。】という聖句があります。いま、園庭のプランターに植えたチューリップが少しずつ芽を出し始めました。すぐにきれいな花が見たいからと言って「早く大きくな~れ!」と球根や小さな芽をひっぱってもきれいな花は咲きません。それどころかぽきっと折れてしまいます。子どもたちにもそれと同じことがいえると私は思っています。一人ひとりの成長には個人差があると分かっているつもりでも、「そろそろ〇〇ができる頃なのでは?」「まだ△△ができないけど大丈夫かな?」と気になることもあるかもしれません。でも、成長・発達の順序をとばすことなく一歩ずつ確実に積み重ねることが力になり、最終的には【きれいな花】を咲かすことになるのです。きれいな花は、「その子らしさ」だと思うのです。その子が自分らしく自分を発揮して、そして自分のことを好きでいてほしいと思います。私たち大人が、先を見すぎて子どもたちを引っ張りすぎることのないように、目の前の子どもたちにしっかり思いと意識を向けたいものです。その子の興味のあること、好きなこと、得意なことを通して成功体験をたくさんしてほしいですね。また、そのアシストをしてあげられるように、その子をよく知ることを改めて大事にしたいと思います。
引っ張って伸ばすよりも、その時に必要な栄養をたっぷりと与えながら、その子がその子らしく花開く時を信じて待つ。きっと土の中でしっかりと根が張り巡らされ、ちょっとやそっとの風では折れないしなやかな幹や枝にきれいな花が咲き、豊かな実がなると思います。
この時期、改めて子どもたちの姿をよく見て、大人が手をかけすぎていることはないか?今一度しっかり手や目をかけていくべきところはどこかを確認しながら過ごしています。就学や進級を控えていますが、安心して次の年度を迎えることができるように日々の生活を丁寧に送りたいと思います。
3月
「心の成長」
今年度も最後の月となりました。先月は大寒波の襲来で、寒さに慣れていない私たちにとっては「おはよう」のあいさつの前に「今日も寒いね」が続いたのではないでしょうか。ようやく春らしい日差しを実感しています。また園庭の河津さくらも少しずつ咲き始めていて、ほっとした気持ちになります。今月は、改めて子どもたち一人ひとりの成長に目を向けながら、共に喜びを噛みしめて過ごす時としたいと思います。4月からの入学や進級を控え、もしかすると「このままで大丈夫かな?」と心配になったり、不安を感じることがある方もいるかもしれませんが、そんな時だからこそ今は、子どもたちの頑張っている所や大きくなったなと感じることに目を向けていきたいですね。それぞれのペースでしっかりと目には見えない大切な根っこの部分を張り巡らせながら、目に見える部分も成長してきていることが分かると思います。
先月末に、今年も年長児のお別れ遠足に一緒に行かせてもらいました。日頃子どもたちとじっくりとずっと一緒に過ごすことがない私にとっては、今年も大変うれしい日となり、バスの中で子どもたち同士の他愛もない会話を聞いているだけでも楽しいものでした。「あ、私小さい時にここに来たことあると思う」「ぼくも‼」「え?どこ?」そんな会話も飛び交っていました。私たちから見ればまだまだ小さい子どもたちですが、就学を間近に控えた年長児は確かに立派に大きく成長しているのです。大人は勝手なもので「まだ小さい」と思ったり、「もう大きい」と思ったりするんだな、と改めて感じました。子どもたちの「小さい時に」の表現を聞きながら、この「お別れ遠足」は年長さんしか行けない、特別なものだということをよく分かっているし、大きくなった自分を誇らしく感じていることも伝わってきました。「ここ行ったことある!」「え?どこ?」の視線の先がたまねぎ畑だった時には「え?ここ?」とみんなでちょっと笑ってしまいました。
のんほいパークでは、一つひとつの場所で子どもたちはじっくり動物を観察。鳥の目は上から閉じるのではなく下から閉じることに気付いたり(事前に図鑑で見てきて知っていた子もいました)、サルがくっついて過ごしているのを見て「おしくらまんじゅうみたい」と笑ったり。出会う人には挨拶ができたりと本当に頼もしいなと感じました。年長児としての自覚のようなものが確かに子どもたちの中にあり、「自分たちしか行けないお別れ遠足」が喜びになっていたようでした。一方で、きっとこの反対の感情もどこかで生まれることもあると思います。これから卒園に向けての具体的な準備が始まっていくと、寂しさや不安を感じる子も出てくることでしょう。その時は、その気持ちに共感しながらそっと寄り添えたらいいなと思います。大丈夫、と励ますだけでなく「そうだよね、寂しいよね」と私たちも同じ気持ちを感じていることや、「今」を大事に過ごしたいことが通じ合えたらいいなと思うのです。『ありのままのあなたで大丈夫』というメッセージが伝わるように関わりを持っていきたいと思います。
昨年の4月、不安な中でひかりの子の玄関を入ってきてくださったのは保護者の皆さまも同じですね。きっと今振り返るとあっという間の一年だったのではないでしょうか。子どもたちも成長していきますが、私たち大人も同じように成長させてもらっているのだと思います。様々な人に出会い、知らなかったことを知り、毎年毎年同じではないなと思います。先日、ある職員と話している時にこんなことを言っていました。「保護者の方と子どもの話ができることがうれしいんです」と。私たちは、ただお子さんをお預かりしているのではなく、保護者の皆さまから大切なお子さんをお預かりし、一緒に成長を見守り、喜んだり、笑ったり、時には泣いたりくやしがったりする大きな家族のような存在でありたいと思っています。3月に卒園する園児たちは私たちにとっても大切な宝物の一人ひとりです。その一人ひとりが神さまから愛され、いつも応援してもらっている存在であることを胸に覚えながら、自分らしく歩んでいってくれることを祈っています。そして、ひかりの子が大きな家族のような温かな居場所でいられるよう今後も務めてまいります。一年間ありがとうございました。
今年度も最後の月となりました。先月は大寒波の襲来で、寒さに慣れていない私たちにとっては「おはよう」のあいさつの前に「今日も寒いね」が続いたのではないでしょうか。ようやく春らしい日差しを実感しています。また園庭の河津さくらも少しずつ咲き始めていて、ほっとした気持ちになります。今月は、改めて子どもたち一人ひとりの成長に目を向けながら、共に喜びを噛みしめて過ごす時としたいと思います。4月からの入学や進級を控え、もしかすると「このままで大丈夫かな?」と心配になったり、不安を感じることがある方もいるかもしれませんが、そんな時だからこそ今は、子どもたちの頑張っている所や大きくなったなと感じることに目を向けていきたいですね。それぞれのペースでしっかりと目には見えない大切な根っこの部分を張り巡らせながら、目に見える部分も成長してきていることが分かると思います。
先月末に、今年も年長児のお別れ遠足に一緒に行かせてもらいました。日頃子どもたちとじっくりとずっと一緒に過ごすことがない私にとっては、今年も大変うれしい日となり、バスの中で子どもたち同士の他愛もない会話を聞いているだけでも楽しいものでした。「あ、私小さい時にここに来たことあると思う」「ぼくも‼」「え?どこ?」そんな会話も飛び交っていました。私たちから見ればまだまだ小さい子どもたちですが、就学を間近に控えた年長児は確かに立派に大きく成長しているのです。大人は勝手なもので「まだ小さい」と思ったり、「もう大きい」と思ったりするんだな、と改めて感じました。子どもたちの「小さい時に」の表現を聞きながら、この「お別れ遠足」は年長さんしか行けない、特別なものだということをよく分かっているし、大きくなった自分を誇らしく感じていることも伝わってきました。「ここ行ったことある!」「え?どこ?」の視線の先がたまねぎ畑だった時には「え?ここ?」とみんなでちょっと笑ってしまいました。
のんほいパークでは、一つひとつの場所で子どもたちはじっくり動物を観察。鳥の目は上から閉じるのではなく下から閉じることに気付いたり(事前に図鑑で見てきて知っていた子もいました)、サルがくっついて過ごしているのを見て「おしくらまんじゅうみたい」と笑ったり。出会う人には挨拶ができたりと本当に頼もしいなと感じました。年長児としての自覚のようなものが確かに子どもたちの中にあり、「自分たちしか行けないお別れ遠足」が喜びになっていたようでした。一方で、きっとこの反対の感情もどこかで生まれることもあると思います。これから卒園に向けての具体的な準備が始まっていくと、寂しさや不安を感じる子も出てくることでしょう。その時は、その気持ちに共感しながらそっと寄り添えたらいいなと思います。大丈夫、と励ますだけでなく「そうだよね、寂しいよね」と私たちも同じ気持ちを感じていることや、「今」を大事に過ごしたいことが通じ合えたらいいなと思うのです。『ありのままのあなたで大丈夫』というメッセージが伝わるように関わりを持っていきたいと思います。
昨年の4月、不安な中でひかりの子の玄関を入ってきてくださったのは保護者の皆さまも同じですね。きっと今振り返るとあっという間の一年だったのではないでしょうか。子どもたちも成長していきますが、私たち大人も同じように成長させてもらっているのだと思います。様々な人に出会い、知らなかったことを知り、毎年毎年同じではないなと思います。先日、ある職員と話している時にこんなことを言っていました。「保護者の方と子どもの話ができることがうれしいんです」と。私たちは、ただお子さんをお預かりしているのではなく、保護者の皆さまから大切なお子さんをお預かりし、一緒に成長を見守り、喜んだり、笑ったり、時には泣いたりくやしがったりする大きな家族のような存在でありたいと思っています。3月に卒園する園児たちは私たちにとっても大切な宝物の一人ひとりです。その一人ひとりが神さまから愛され、いつも応援してもらっている存在であることを胸に覚えながら、自分らしく歩んでいってくれることを祈っています。そして、ひかりの子が大きな家族のような温かな居場所でいられるよう今後も務めてまいります。一年間ありがとうございました。