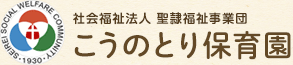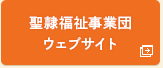色鮮やかな紫陽花の花とともに梅雨の時期がやってきました。晴れたり、雨が降ったりと自然の変化に一喜一憂する子ども達。体調を崩しやすい季節なので健康管理に気をつけていきたいと思います。
先日はお忙しい中、懇談会へご参加いただきありがとうございました。短い時間でしたが、保護者の皆様同士が顔を合わせ直接お話ができたことを嬉しく思い、感謝致します。懇談会でもお伝えさせていただいたように、子ども達は、保育園で様々な体験や経験をしています。その中でも生き物の観察は子ども達の大好きな遊びです。園庭でのダンゴムシやアリ、カエルやチョウの観察、季節によって変化する鳥類、夏野菜や稲の生長観察など、身近な生き物を通して、自然との関わりを感じ、生命の大切さを学んでいます。こうのとり保育園には毎年ツバメがやってきます。今年度は3月末の早い時期からウッドデッキに巣を作り始め、5羽のヒナがすくすく成長しています。4,5歳児クラスはA先生を中心にツバメに夢中です。本を購入し、いろいろと調べながら観察を続けています。何度も土やワラを運び、上手に重ねて巣を作っていく様子、母鳥が卵を温めている姿、ヒナが生まれ、ヒナの口に親鳥が餌を運び続ける様子、日に日に成長していくヒナの姿等、ツバメの生きる姿勢や習性、生態系の中での役割などを学んでいます。ツバメとの触れ合いを通して、子ども達は社会性、協調性、そして自然とのつながりを感じる力も身につけているのです。実はウッドデッキだけではなく、玄関、2階のテラス、2歳児のテラス(子どもの靴箱の上)にもツバメが巣を作り始めました。渡り鳥であるツバメは、風通しがよく衛生的な場所、気の流れが自然で心地よい場所、また外敵から巣を守るために人通りの多いにぎやかな場所など本能的に良いと判断した場所を選び巣を作るそうです。実際に巣を作ると、私共も管理が必要になります。一番の問題は「糞」。糞よけガードなど対策が必須になります。また、作る場所によっては園生活に支障をきたす場合があり、糞による健康被害の心配もあります。乳児クラスでは困ったあげく、撤去せざるを得ない…でもそれって本当に大丈夫?縁起物の「ツバメの巣」を壊してしまっていいのか、何よりこんなに必死に時間を掛けて作っているものを壊すだなんてと葛藤しながらも泣く泣く撤去をしました。すると作りかけていた巣が無くなってしまい、ツバメ達がパニックになり、巣があった周りをいつまでも飛び続け確認をしていました。心を痛めながらツバメの姿を見て、子ども達は何を感じていたのでしょうか。「ごめんなさい。でもね…」この気持ちを職員が子ども達にしっかり説明をし、共有をすることがとても大切なことだと思い見ていました。翌日、ツバメはまた巣を作り始めました。悩みながらも撤去。ツバメも今度は諦めたかなと思ったのですが…子どもの少ない土日に急ピッチで巣を完成させたのです。これには子ども達もビックリ!「ツバメ考えたね」「頭いいね~」と感心してしまいました。さすがに今回はツバメに譲るのかなと思いましたが、卵とヒナがいないことを確認して撤去をしました。子ども達の安全の為に決心したとの事でした。今後、ツバメと職員、子ども達の心の動きも含め、生き物達がお互いに助け合って暮らしていることを知り、自分達だけでなく、周りの人や自然環境とも対等に関わりを持てるよう見守っていきたいと思います。保育者は子どもたちがたくさんのことに触れながら、小さなことにも気付き、成長できるよう一緒に遊んだり考えたりしています。A先生のように、時には先頭に立って行動し、物事に興味を持つことも大切なことだと思います。子ども達はそんな保育者の姿を見て、成長していきます。まずはお手本となる私達大人が物事の面白さや楽しさ、美しさを感じることも大切ですね。自然からの学びは、楽しく、興味深く、記憶に残るものとなります。豊かな遊び、経験を実現するためには、子どもの気持ちをくみ取り、適切なタイミングで援助をする職員の関わりと、自由に遊びを深められる時間や空間、道具などの環境が必要です。子どもが心と頭と体をフルに働かせて、夢中で「遊び込む経験」ができるような環境を子ども達と共に創り出していきたいと思います。
園長 梶山 美里