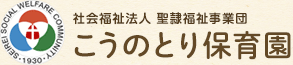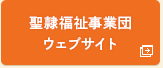雨上がりの陽射しで、園庭の人工芝や草花の葉っぱについた水滴がキラキラ輝いています。そんな自然が描く風景を日常の保育の中で、子どもたちにも感じてもらえるよう促していきたいと思います。気温・湿度共に上がり、汗ばむ季節になってきました。園では子どもたちの汗対策をはじめ、健康管理に十分気を付けていきたいと思います。
先日、日差しが眩しい青空の下、園庭では黄組(5歳児)がしっぺい音頭を踊り、3、4歳児はそれぞれ好きな遊びを楽しんでいました。曲が終わるとすぐに、4歳児のAさんが私の所に駆け寄り「園長先生、ばば抜きやろう!」と葉っぱを差し出しました。Bさんも来て、「勝った方が私とやる」と言って見守っています。私はどうやってやるのだろう?と思いながらも「やろう!」と意気込むと葉っぱを4枚貰いました。Aさんは3枚綺麗にずらして持ち「私が取る」と言うので、私も急いでトランプのように葉をずらして持ちました。Aさんが取る、次は私が取る…これは見立て遊びかな?と思っていると、「あった‼」とAさんが2枚の葉を出したのです。えぇ⁉ 私から見ると似たような葉が7枚ですが、子ども達の中には何かがあることに気付きました。そこからはわかっているかのように「あぁ…」などと言って続けながら子ども達のルールを見抜こうと必死に観察していました。ギャラリーが少し増え、ケタケタ笑いながら応援してくれます。みんなはこのルールを理解しているのだろうか?と思っていると、「あった!」とまた2枚葉を出しながらAさんが「ほら同じでしょ」と2枚を並べて見せてくれたのです。確かに他の葉と比べるとその2枚は小さ目で、ほぼ同じ大きさでした。私の心の中を見抜かれたのかしらとドキっとしましたが、優しく教えてくれたAさんに感謝です。最後に私の葉が1枚残り、残念ながら負けてしまいました。すると私の持っていた葉を見て「これ“ばば”だよね」とCさんが言いました。よくよく見てみると葉先が綺麗にすっと伸び、スマートで特別感があり“ばば”に見えたのです。観察する中で子ども達は大小、形、色の違いで法則(ルール)をつくって遊んでいることが解りました。さすが子どもは遊びの天才です。楽しかったのは勿論ですが、4歳児の概念に感心させられました。概念とは、物事を「かたまり」や「ルール」として理解していくことです。今回の遊びを見ていくと① 違いを見つける(差異化)⇒2つ以上のものを比べて違いに気づくこと。② 同じを見つける(一般化)⇒条件が当てはまれば別のものでも同じといえる。③ 同じをまとめる(類型化)⇒バラバラのものから共通するものを見つけてグループにしていくこと。をしていました。
子どもの発達でよくみられる「概念」① 大小 ② 量 ③ 時間(ここでいう「時間」とは生活における「流れ」を指しています。)④ 数字 ⑤ 形 ⑥ 色 ⑦ 空間、位置等は、いつ頃どうやってできていくのでしょうか。2歳位では、1,2,3以上は「いっぱい」と表現しますね。行動の順序が身につくのは(2~3歳)、「昨日」「今日」「明日」の連続性を理解するのは(5歳くらい)と言われています。しかし概念獲得の年齢は個人差が大きいです。そのまえに「違い」に気づくことが大切と言われています。物事をとらえるためには2つ以上のものの「違い」に気づく力が必要です。これはすべての概念の土台となる大切な力です。乳児クラスによくある「ぽっとん落とし」、缶に物を「入れる」。これだけで立派な遊びになります。大人が「物足りない」と思っても、子どもにとっては楽しい学習になります。このように一見「関係ないんじゃないかな?」と思うようなことでも、概念形成の力をつけるための大切な活動(遊び)になるのです。まずは『手を使おう』と言われています。数や文字などは機械的に覚えるよりも、他者とのやり取りを通して学んでいくことが大切です。大人がしてあげられるのは子どもがコミュニケーションで使えるようにすることなのです。
4歳児にヒントをいただき、左右の理解がまだ難しい5歳児が、より左右を意識して踊ることができるように、今年度は右手に赤、左手に白のしっぺいカラーの手袋を付けて踊りました。放映をお楽しみに。
園長 梶山 美里
先日、日差しが眩しい青空の下、園庭では黄組(5歳児)がしっぺい音頭を踊り、3、4歳児はそれぞれ好きな遊びを楽しんでいました。曲が終わるとすぐに、4歳児のAさんが私の所に駆け寄り「園長先生、ばば抜きやろう!」と葉っぱを差し出しました。Bさんも来て、「勝った方が私とやる」と言って見守っています。私はどうやってやるのだろう?と思いながらも「やろう!」と意気込むと葉っぱを4枚貰いました。Aさんは3枚綺麗にずらして持ち「私が取る」と言うので、私も急いでトランプのように葉をずらして持ちました。Aさんが取る、次は私が取る…これは見立て遊びかな?と思っていると、「あった‼」とAさんが2枚の葉を出したのです。えぇ⁉ 私から見ると似たような葉が7枚ですが、子ども達の中には何かがあることに気付きました。そこからはわかっているかのように「あぁ…」などと言って続けながら子ども達のルールを見抜こうと必死に観察していました。ギャラリーが少し増え、ケタケタ笑いながら応援してくれます。みんなはこのルールを理解しているのだろうか?と思っていると、「あった!」とまた2枚葉を出しながらAさんが「ほら同じでしょ」と2枚を並べて見せてくれたのです。確かに他の葉と比べるとその2枚は小さ目で、ほぼ同じ大きさでした。私の心の中を見抜かれたのかしらとドキっとしましたが、優しく教えてくれたAさんに感謝です。最後に私の葉が1枚残り、残念ながら負けてしまいました。すると私の持っていた葉を見て「これ“ばば”だよね」とCさんが言いました。よくよく見てみると葉先が綺麗にすっと伸び、スマートで特別感があり“ばば”に見えたのです。観察する中で子ども達は大小、形、色の違いで法則(ルール)をつくって遊んでいることが解りました。さすが子どもは遊びの天才です。楽しかったのは勿論ですが、4歳児の概念に感心させられました。概念とは、物事を「かたまり」や「ルール」として理解していくことです。今回の遊びを見ていくと① 違いを見つける(差異化)⇒2つ以上のものを比べて違いに気づくこと。② 同じを見つける(一般化)⇒条件が当てはまれば別のものでも同じといえる。③ 同じをまとめる(類型化)⇒バラバラのものから共通するものを見つけてグループにしていくこと。をしていました。
子どもの発達でよくみられる「概念」① 大小 ② 量 ③ 時間(ここでいう「時間」とは生活における「流れ」を指しています。)④ 数字 ⑤ 形 ⑥ 色 ⑦ 空間、位置等は、いつ頃どうやってできていくのでしょうか。2歳位では、1,2,3以上は「いっぱい」と表現しますね。行動の順序が身につくのは(2~3歳)、「昨日」「今日」「明日」の連続性を理解するのは(5歳くらい)と言われています。しかし概念獲得の年齢は個人差が大きいです。そのまえに「違い」に気づくことが大切と言われています。物事をとらえるためには2つ以上のものの「違い」に気づく力が必要です。これはすべての概念の土台となる大切な力です。乳児クラスによくある「ぽっとん落とし」、缶に物を「入れる」。これだけで立派な遊びになります。大人が「物足りない」と思っても、子どもにとっては楽しい学習になります。このように一見「関係ないんじゃないかな?」と思うようなことでも、概念形成の力をつけるための大切な活動(遊び)になるのです。まずは『手を使おう』と言われています。数や文字などは機械的に覚えるよりも、他者とのやり取りを通して学んでいくことが大切です。大人がしてあげられるのは子どもがコミュニケーションで使えるようにすることなのです。
4歳児にヒントをいただき、左右の理解がまだ難しい5歳児が、より左右を意識して踊ることができるように、今年度は右手に赤、左手に白のしっぺいカラーの手袋を付けて踊りました。放映をお楽しみに。
園長 梶山 美里