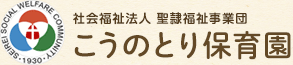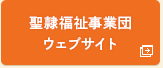今年の夏休みはどう過ごされましたか。地震や台風の影響で予定の変更をされたご家庭もあるかと思います。今回気象庁が「南海トラフ地震臨時情報」を発表したことで、今一度、真剣に防災対策について考え、話し合われたのではないでしょうか。日本各地で地震や台風、ゲリラ豪雨などが頻発していることもあり、防災意識もさらに高まっています。酷暑の中、いつ災害が起きても命を守る準備だけはしておこうと今年度の防災訓練・引き渡し訓練は、子ども・職員共に年齢発達に合わせ、経験してみる(やってみる)ことを増やしていこうと考えております。引き渡し訓練へのご理解、ご協力もよろしくお願い致します。
先日1歳児のAさんが登園するとすぐに、玄関にいる金魚を見に行きました。じっくり金魚を覗き込んでいたので、よく見えるように前向きに抱っこをして目線を合わせると、「おわよう(おはよう)!」と可愛らしく挨拶をしたのです。しっかり金魚の目を見て「おはよう」と何度か声を掛ける姿から、2匹いる金魚の1匹に気持ちを込めて声を掛け、一方的に声を掛けているだけではなく、返事を待っていることがわかりました。不思議なことに…何度か目にその金魚がこちらを向いてAさんと目を合わせ、まるで「おはよう」と言っているかのようにケース越しにパクパクと大きく口を開けているのです。Aさんはにっこり微笑んで、もう1匹にも「おはよう」と挨拶をしはじめました。するとなんと!!2匹目もケース越しにAさんに挨拶をしたのです。Aさんは満足気に「よし!」と言って私から離れ、クラスへ向かったのでした。これこそが、「言葉に耳を傾ける」姿だと感動と共に自分自身を振り返りました。
昨今、情報を発信するよりも受信する大切さが見直されています。話す事よりも聴くことを大事にしようと、「傾聴」が注目され、関連書籍が数多く出版されています。「相手の話の先回りをしない」「上手に相槌をうつ」「聴くときの表情のつくり方」など、さまざまな「聴くためのテクニック」が紹介されています。これはこれで大事なことですが、その前に聴くことがなぜ大切なのか、「聴く」とはどういうことなのかを考える必要があります。哲学者鷲田清一さんは、著書『聴くことの力』で次のように記されています。「苦しみを口にできないということ、表出できないということ。苦しみの語りは語りを求めるのではなく、語りを待つ人の、受動性の前ではじめて、漏れるようにこぼれ落ちてくる。つぶやきとして、かろうじて。/ことばが<注意>をもって聴き取られることが必要なのではない。<注意>をもって聴く耳があって、はじめてことばが生まれるのである』難しい表現ですが、要するに聴く人の姿勢が、話そうとする人の言葉を引き出し、自分では整理がつかなかったことも、聴いてくれる人に励まされて言語化できるのだということでしょう。「話を聴く」という時、私達は発語する人がいて、その人の話に耳を傾けると考えがちです。聴き手である大人が、子どもが安心して話したくなるような環境を常に整えてこそ初めて子どもは、ぼそぼそと、あるいは途切れ途切れに話し出すのです。「先生(お母さん)は、自分を問いただそうとしたり、叱ろうと思って聴いているのではないな。ただ自分に関心を持ってくれているんだ」そう思えた時に、子どもは安心して言葉を発することができる。思い込みや先入観を排し、あるがままに相手の話を聴こうとする姿勢が、言葉を引き出します。夏休みの間、中・高校生のお子さんとお互い家にいても直接に会話をせず、LINEなどでやり取りをしていると聞きました。現代の会話ツールであるLINEは、非常に便利です。LINEとは線のことですから、人と人とを結びつけることをイメージして名付けられたようです。その活用が悪い訳ではありません。ただ、本来の会話とはもっと親密で、身体性を伴うものではないでしょうか。糸電話のように、しっかりとした線で、一対一で繋がり合う。「耳を傾ける」とは相手を「受け入れ」「寄り添う」ことでもあります。子どもが何かを伝えたい時、いつでも安心して話せる環境は、急ごしらえではできません。だからこそ、普段から話しやすい親密な空気をつくっていくことが重要になることをAさんの姿から改めて学ばせていただきました。仕事をしながらの子育ては本当に大変ですが、時には家事の手を止め、お子さんと向き合い、ありのまま全てを受け入れ、耳を傾けてみましょう。
園長 梶山 美里
先日1歳児のAさんが登園するとすぐに、玄関にいる金魚を見に行きました。じっくり金魚を覗き込んでいたので、よく見えるように前向きに抱っこをして目線を合わせると、「おわよう(おはよう)!」と可愛らしく挨拶をしたのです。しっかり金魚の目を見て「おはよう」と何度か声を掛ける姿から、2匹いる金魚の1匹に気持ちを込めて声を掛け、一方的に声を掛けているだけではなく、返事を待っていることがわかりました。不思議なことに…何度か目にその金魚がこちらを向いてAさんと目を合わせ、まるで「おはよう」と言っているかのようにケース越しにパクパクと大きく口を開けているのです。Aさんはにっこり微笑んで、もう1匹にも「おはよう」と挨拶をしはじめました。するとなんと!!2匹目もケース越しにAさんに挨拶をしたのです。Aさんは満足気に「よし!」と言って私から離れ、クラスへ向かったのでした。これこそが、「言葉に耳を傾ける」姿だと感動と共に自分自身を振り返りました。
昨今、情報を発信するよりも受信する大切さが見直されています。話す事よりも聴くことを大事にしようと、「傾聴」が注目され、関連書籍が数多く出版されています。「相手の話の先回りをしない」「上手に相槌をうつ」「聴くときの表情のつくり方」など、さまざまな「聴くためのテクニック」が紹介されています。これはこれで大事なことですが、その前に聴くことがなぜ大切なのか、「聴く」とはどういうことなのかを考える必要があります。哲学者鷲田清一さんは、著書『聴くことの力』で次のように記されています。「苦しみを口にできないということ、表出できないということ。苦しみの語りは語りを求めるのではなく、語りを待つ人の、受動性の前ではじめて、漏れるようにこぼれ落ちてくる。つぶやきとして、かろうじて。/ことばが<注意>をもって聴き取られることが必要なのではない。<注意>をもって聴く耳があって、はじめてことばが生まれるのである』難しい表現ですが、要するに聴く人の姿勢が、話そうとする人の言葉を引き出し、自分では整理がつかなかったことも、聴いてくれる人に励まされて言語化できるのだということでしょう。「話を聴く」という時、私達は発語する人がいて、その人の話に耳を傾けると考えがちです。聴き手である大人が、子どもが安心して話したくなるような環境を常に整えてこそ初めて子どもは、ぼそぼそと、あるいは途切れ途切れに話し出すのです。「先生(お母さん)は、自分を問いただそうとしたり、叱ろうと思って聴いているのではないな。ただ自分に関心を持ってくれているんだ」そう思えた時に、子どもは安心して言葉を発することができる。思い込みや先入観を排し、あるがままに相手の話を聴こうとする姿勢が、言葉を引き出します。夏休みの間、中・高校生のお子さんとお互い家にいても直接に会話をせず、LINEなどでやり取りをしていると聞きました。現代の会話ツールであるLINEは、非常に便利です。LINEとは線のことですから、人と人とを結びつけることをイメージして名付けられたようです。その活用が悪い訳ではありません。ただ、本来の会話とはもっと親密で、身体性を伴うものではないでしょうか。糸電話のように、しっかりとした線で、一対一で繋がり合う。「耳を傾ける」とは相手を「受け入れ」「寄り添う」ことでもあります。子どもが何かを伝えたい時、いつでも安心して話せる環境は、急ごしらえではできません。だからこそ、普段から話しやすい親密な空気をつくっていくことが重要になることをAさんの姿から改めて学ばせていただきました。仕事をしながらの子育ては本当に大変ですが、時には家事の手を止め、お子さんと向き合い、ありのまま全てを受け入れ、耳を傾けてみましょう。
園長 梶山 美里