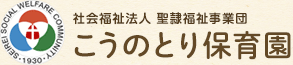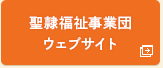青空と白い雲が、いつもより鮮明に見える10月。長かった残暑が終わり、ようやく小さな秋を見付けられるようになってきました。気持ち良い秋晴れの下、伸び伸びと身体を動かすことを楽しんでいる子どもたちです。
先日は懇談会へのご参加ありがとうございました。今回は全クラス、グループディスカッションを行う時間を持つことが出来きました。お仕事をしながら子育てをしている仲間と、子育てにおいての嬉しい事、難しさを感じている事等を共有し、安心に繋がったという声を沢山いただきました。今回4、5歳児はグループワークを行い、子ども達が日々楽しんでいる遊びをしていただきました。5歳児のグループワークは、『グループ対抗、いちばん高く積み木をつめるのはどこだ!』と題し、制限時間内にどこのグループがいちばん積み木を高く積むことができるのかを競い合いながら遊んでみました。スタートすると、頭を突き合わせて作戦会議が始まるグループ、話し合いながら積んでいくグループ、土台をしっかり作っていくグループ等色々でしたが、どのグループも時間と共に本気モードに…どうしたら頑丈に積んでいけるのか?バランスよく積み上げるにはどうしたらよいか?高さを求めるには積み木をどう使用していくのか?等々、お互いに確認し合いながら進め、様々な工夫が見られました。時間と共に集中力が増していくのが解り、後半は独創性も見られ、周りのグループの様子を確認するなど、勝敗を気にする姿も見られました。崩れそうな所に慎重に積み木を置くシーンは、グループ皆が緊張し見守る姿も。見ているこちらまで、ドキドキ、ワクワクでした。途中で崩れた場合も時間内であれば再建可能でしたので、壊れてしまっても、諦めずに再挑戦している時のパワーにも驚かされました。「久しぶりに積み木を集中してやってみて、子どもが真剣になる気持ちを改めて思い出すことができてよかったと思います。」「大人は今までの経験から、話し合う、譲り合う、助け合うができますが、子どもはこういう遊びを通じて自然に経験していくのだなと改めて感じました。」「家で遊びを中断させるとこんなにももどかしいんだ。もう少しやりたい!って思うんだな。と改めて思い出させて頂きました。」「夢中になると時間を忘れるという言葉に、ハッと気付かされ、あまり子どもに時限を強要しないようにしたいと思いました。」「子どもたちの工夫する力や想像力などは大人が思っている以上だし、何より柔軟な考えを持っているからこその発想もあり、とてもおもしろいなと思いました!」等々沢山の感想をいただきました。グループワークを通して、子ども達が遊びを通して育くんでいる力を共感していただけたことがとても嬉しく、何より私自身も大変楽しませていただきました。
大人と子どもの感覚は違いますから、子どもに共感するのは難しいですよね。今回のように子どもと同じ立場で、同じ体勢で、同じ目線で、同じことをすると、共感できることがあります。こちらが子どもに共感できるだけではなく、子どももこちらに共感するんです。「共感」読んで字のごとく、共に感じることです。言葉は無くとも、子どもと同じ立場で、同じ体勢で、同じ目線で、同じようにしてみましょう。大切なのは、わくわく(湧く湧く)と自分の内側から課題が湧き出てくること。「もっとこうしたい」「こうやってみたらどうかな」と沸き起こる感情と言われています。ですから、まずは、興味や関心を持ち、そこに関わってみること。そして子どもが見えているものを一緒に見て共感し、応答する。身近な環境の中で、とことん遊び尽くす。一見当たり前に思う遊びの中に、非認知能力の育ちは潜んでいます。是非お子さんと一緒に楽しいことを沢山見つけ、夢中になる経験をしてみて下さい。実際に見て、触って、共感して、丸ごと味わうような経験が幸せに生きていくうえでの土台となるはずです。
園長 梶山 美里
先日は懇談会へのご参加ありがとうございました。今回は全クラス、グループディスカッションを行う時間を持つことが出来きました。お仕事をしながら子育てをしている仲間と、子育てにおいての嬉しい事、難しさを感じている事等を共有し、安心に繋がったという声を沢山いただきました。今回4、5歳児はグループワークを行い、子ども達が日々楽しんでいる遊びをしていただきました。5歳児のグループワークは、『グループ対抗、いちばん高く積み木をつめるのはどこだ!』と題し、制限時間内にどこのグループがいちばん積み木を高く積むことができるのかを競い合いながら遊んでみました。スタートすると、頭を突き合わせて作戦会議が始まるグループ、話し合いながら積んでいくグループ、土台をしっかり作っていくグループ等色々でしたが、どのグループも時間と共に本気モードに…どうしたら頑丈に積んでいけるのか?バランスよく積み上げるにはどうしたらよいか?高さを求めるには積み木をどう使用していくのか?等々、お互いに確認し合いながら進め、様々な工夫が見られました。時間と共に集中力が増していくのが解り、後半は独創性も見られ、周りのグループの様子を確認するなど、勝敗を気にする姿も見られました。崩れそうな所に慎重に積み木を置くシーンは、グループ皆が緊張し見守る姿も。見ているこちらまで、ドキドキ、ワクワクでした。途中で崩れた場合も時間内であれば再建可能でしたので、壊れてしまっても、諦めずに再挑戦している時のパワーにも驚かされました。「久しぶりに積み木を集中してやってみて、子どもが真剣になる気持ちを改めて思い出すことができてよかったと思います。」「大人は今までの経験から、話し合う、譲り合う、助け合うができますが、子どもはこういう遊びを通じて自然に経験していくのだなと改めて感じました。」「家で遊びを中断させるとこんなにももどかしいんだ。もう少しやりたい!って思うんだな。と改めて思い出させて頂きました。」「夢中になると時間を忘れるという言葉に、ハッと気付かされ、あまり子どもに時限を強要しないようにしたいと思いました。」「子どもたちの工夫する力や想像力などは大人が思っている以上だし、何より柔軟な考えを持っているからこその発想もあり、とてもおもしろいなと思いました!」等々沢山の感想をいただきました。グループワークを通して、子ども達が遊びを通して育くんでいる力を共感していただけたことがとても嬉しく、何より私自身も大変楽しませていただきました。
大人と子どもの感覚は違いますから、子どもに共感するのは難しいですよね。今回のように子どもと同じ立場で、同じ体勢で、同じ目線で、同じことをすると、共感できることがあります。こちらが子どもに共感できるだけではなく、子どももこちらに共感するんです。「共感」読んで字のごとく、共に感じることです。言葉は無くとも、子どもと同じ立場で、同じ体勢で、同じ目線で、同じようにしてみましょう。大切なのは、わくわく(湧く湧く)と自分の内側から課題が湧き出てくること。「もっとこうしたい」「こうやってみたらどうかな」と沸き起こる感情と言われています。ですから、まずは、興味や関心を持ち、そこに関わってみること。そして子どもが見えているものを一緒に見て共感し、応答する。身近な環境の中で、とことん遊び尽くす。一見当たり前に思う遊びの中に、非認知能力の育ちは潜んでいます。是非お子さんと一緒に楽しいことを沢山見つけ、夢中になる経験をしてみて下さい。実際に見て、触って、共感して、丸ごと味わうような経験が幸せに生きていくうえでの土台となるはずです。
園長 梶山 美里