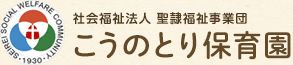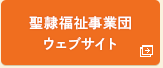白い息を吐きながら園庭で遊ぶ元気な子どもたちを見ると、なんだかこちらもポカポカしてきます。もうすぐ子どもたちが春を連れてきてくれるのではないかと楽しみな反面、このクラスで過ごす時間もあとわずか。これまで以上に一日一日を大切に、子どもたちと過ごしていきたいと思う今日この頃です。
先日はお忙しい中、乳児クラス対象の『あそびのひろば』へご参加いただきありがとうございました。日頃、園で子ども達が楽しんでいる遊びを親子で一緒に楽しんでいただくことができ、大変嬉しく思いました。各クラス共に、今夢中になって楽しんでいる様々な遊びが展開できるような工夫をし、子ども達の姿を踏まえ、発達のポイントや保育の中で大切にしていること等を掲示させていただきました。安心できるお家の方と一緒に遊ぶ中で、楽しむ・感じる・表現する・工夫する・人と関わる・気付く・見つける・考える・比べる・試す・伝え合う等々、様々な姿が見られましたね。印象的だったのは、お子さんの思いをできるだけ叶えようと対応し、お子さんの興味関心に合わせて、のびのびとやりたいことを、やりたいペースで一緒に行って下さっていたことです。0歳児のAさんはお部屋に入るとすぐに、棚に置いてある“ぽっとん落とし”を指さしました。そして「これをやるよ」と言っているかのようにお母様の顔を見て玩具を運びます。床に置いたことに気が付いた担任が「こっちでやる?」と声を掛けると、嬉しそうに机に玩具を置き座ります。そして「ここ」と目で合図をし、お母様が横に座ると嬉しそうに蓋を開け、ホースを取り出し、ぽっとん落としが始まりました。まだ指先を巧みに使うことは難しいですが、向きを変え試行錯誤しながらホースを穴に入れます。出来ると手をパチパチと叩きながらお母様を見ます。笑顔で拍手を返されると次は担任に共感を求め、共に喜び合うと次のホースに挑戦です。数回目、Aさんが共感を求めた時に担任とお母様がお話をしていたので、2人が気付きません。拍手をしながら2人に共感を求め続けている時に遠くから私が「出来たね」の気持ちを込めて拍手をしていることに気付きました。Aさんは万遍の笑みを浮かべ手を叩き、満足気に次のホースに手を伸ばしました。次からはお母様、担任、私の順番で3人と共感をし楽しみました。Aさんのように周りの物に自ら手を伸ばし、五感を通して関わっていく姿がたくさん見られましたね。お家の方達は、子どもの伴走者として、子どもの気持ちに寄り添い、共感して下さっていました。子どもは信頼できる大人に見守られ、安心して過ごす中で、力をぐんぐん伸ばしています。しかし私はその後、大失敗をしてしまいました。製作コーナーで鬼の角になる部分に模様をつけようとBさんがポンポンペンを持ちました。上手持ちで持っている為、頑張って腕を内側に捻るのですが、色はつきません。それでも何度か挑戦しているうちに少しずつペン先が画用紙に触れ、色がつき始めました。スタンプのようにポンポンと色付けを楽しめるペンなので、やりたいという気持ち(意欲)を満足させてあげたいと思い、タイミングを見てペンを持ち返させようとしました。私がペンに触れるとBさんはギュッとペンを強く握りしめ意思を示しました。「ごめんね、そうだよね」と謝りながらもBさんの指先に注目をしていました。右手で上手握り持ちでペンを持ち、左手で蓋を取ります。そのまま描くため上手持ちになってしまうことがわかりました。粘り強く、Bさんが次に色を変えるタイミングを待ち、スタンピングしやすいように蓋を取った状態で握り持ちになるようにペンを渡しました。するとBさんは、両手を使って上手持ちに持ち替え、また腕を捻って一生懸命描こうとしたのです。まさに「穴があったら入りたい」とはこういう気持ちです。Bさんがはっきりと答えを姿で教えてくれたのです。“答えはいつも相手(子ども)の中にある”を合言葉に保育を行っているにも関わらず、お恥ずかしいことにやっと2回目で気付かされました。楽しそうに遊んでいるBさんに「これはこうして遊ぶのよ」と示そうとした私の行動は、創造力や遊びに対する興味を取り上げてしまうことに繋がりかねません。あそびのひろばに参加して下さった保護者の皆さんは、まだ一人では上手に出来ないこともありますから、大変な思いをさせたくないとつい手を貸してしまったり、時間がかかるからと代わりにやってしまうようなことはなく、お子さんの思いを丁寧に汲み取り、温かく見守り、「やってみたい」「もう1回!」「やったら出来た」を繰り返し、一緒に楽しんで共感して下さっていました。子どもは、遊びを通して、体の感覚や人との心の繋がりなど、豊かで幸せに生きるための力をつけていきます。子どもが、心身共に健やかに成長できるよう、子どもを支え、共に育っていきたいと改めて振り返りをしました。子どもの姿から学ばせていただいた実りあるあそびのひろばでした。
園長 梶山 美里
先日はお忙しい中、乳児クラス対象の『あそびのひろば』へご参加いただきありがとうございました。日頃、園で子ども達が楽しんでいる遊びを親子で一緒に楽しんでいただくことができ、大変嬉しく思いました。各クラス共に、今夢中になって楽しんでいる様々な遊びが展開できるような工夫をし、子ども達の姿を踏まえ、発達のポイントや保育の中で大切にしていること等を掲示させていただきました。安心できるお家の方と一緒に遊ぶ中で、楽しむ・感じる・表現する・工夫する・人と関わる・気付く・見つける・考える・比べる・試す・伝え合う等々、様々な姿が見られましたね。印象的だったのは、お子さんの思いをできるだけ叶えようと対応し、お子さんの興味関心に合わせて、のびのびとやりたいことを、やりたいペースで一緒に行って下さっていたことです。0歳児のAさんはお部屋に入るとすぐに、棚に置いてある“ぽっとん落とし”を指さしました。そして「これをやるよ」と言っているかのようにお母様の顔を見て玩具を運びます。床に置いたことに気が付いた担任が「こっちでやる?」と声を掛けると、嬉しそうに机に玩具を置き座ります。そして「ここ」と目で合図をし、お母様が横に座ると嬉しそうに蓋を開け、ホースを取り出し、ぽっとん落としが始まりました。まだ指先を巧みに使うことは難しいですが、向きを変え試行錯誤しながらホースを穴に入れます。出来ると手をパチパチと叩きながらお母様を見ます。笑顔で拍手を返されると次は担任に共感を求め、共に喜び合うと次のホースに挑戦です。数回目、Aさんが共感を求めた時に担任とお母様がお話をしていたので、2人が気付きません。拍手をしながら2人に共感を求め続けている時に遠くから私が「出来たね」の気持ちを込めて拍手をしていることに気付きました。Aさんは万遍の笑みを浮かべ手を叩き、満足気に次のホースに手を伸ばしました。次からはお母様、担任、私の順番で3人と共感をし楽しみました。Aさんのように周りの物に自ら手を伸ばし、五感を通して関わっていく姿がたくさん見られましたね。お家の方達は、子どもの伴走者として、子どもの気持ちに寄り添い、共感して下さっていました。子どもは信頼できる大人に見守られ、安心して過ごす中で、力をぐんぐん伸ばしています。しかし私はその後、大失敗をしてしまいました。製作コーナーで鬼の角になる部分に模様をつけようとBさんがポンポンペンを持ちました。上手持ちで持っている為、頑張って腕を内側に捻るのですが、色はつきません。それでも何度か挑戦しているうちに少しずつペン先が画用紙に触れ、色がつき始めました。スタンプのようにポンポンと色付けを楽しめるペンなので、やりたいという気持ち(意欲)を満足させてあげたいと思い、タイミングを見てペンを持ち返させようとしました。私がペンに触れるとBさんはギュッとペンを強く握りしめ意思を示しました。「ごめんね、そうだよね」と謝りながらもBさんの指先に注目をしていました。右手で上手握り持ちでペンを持ち、左手で蓋を取ります。そのまま描くため上手持ちになってしまうことがわかりました。粘り強く、Bさんが次に色を変えるタイミングを待ち、スタンピングしやすいように蓋を取った状態で握り持ちになるようにペンを渡しました。するとBさんは、両手を使って上手持ちに持ち替え、また腕を捻って一生懸命描こうとしたのです。まさに「穴があったら入りたい」とはこういう気持ちです。Bさんがはっきりと答えを姿で教えてくれたのです。“答えはいつも相手(子ども)の中にある”を合言葉に保育を行っているにも関わらず、お恥ずかしいことにやっと2回目で気付かされました。楽しそうに遊んでいるBさんに「これはこうして遊ぶのよ」と示そうとした私の行動は、創造力や遊びに対する興味を取り上げてしまうことに繋がりかねません。あそびのひろばに参加して下さった保護者の皆さんは、まだ一人では上手に出来ないこともありますから、大変な思いをさせたくないとつい手を貸してしまったり、時間がかかるからと代わりにやってしまうようなことはなく、お子さんの思いを丁寧に汲み取り、温かく見守り、「やってみたい」「もう1回!」「やったら出来た」を繰り返し、一緒に楽しんで共感して下さっていました。子どもは、遊びを通して、体の感覚や人との心の繋がりなど、豊かで幸せに生きるための力をつけていきます。子どもが、心身共に健やかに成長できるよう、子どもを支え、共に育っていきたいと改めて振り返りをしました。子どもの姿から学ばせていただいた実りあるあそびのひろばでした。
園長 梶山 美里