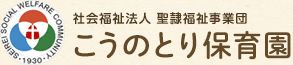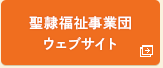朝晩の冷え込みが日に日に増し、秋の深まりを感じる季節となりました。園庭の木々も色づき始め、子ども達が落ち葉を拾い集めて遊ぶ姿が微笑ましい毎日です。色とりどりの落ち葉や様々な形のドングリなど、秋の自然は子どもたちにとって宝の山。今月は、身近な自然に触れる楽しさをより感じられる月にしたいと思っています。
先月は皆様のご理解、ご協力の中、無事に幼児クラスのあおぞらひろばを開催することができました。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。保護者の皆様の温かい見守りと拍手の中、子ども達が笑顔で楽しみ、自分らしく、ひたむきに取り組む姿は本当に輝いていましたね。今年度はヨセフの皆さんがヨセフ競技を企画して下さいました。小学生や保護者の皆様も参加していただき、大変盛り上がりました。アンケートのご協力もありがとうございました。『内容がとても新鮮でした。保育園生活の中で子ども達が何を学んで成長しているのかもこの場で再度認識できる機会であったと思います。ユーモア溢れる小道具にも感動しました。』等の感想を沢山いただきました。あおぞらひろばの遊びの中からも日々保育の中で楽しみながら育まれていることが伝わり、大変嬉しく思いました。子ども達と共に創り上げられたあおぞらひろばでしたね。3歳児は、大好きな昆虫(あり)になって遊び、4,5歳児は、現在、関心の強い食育での学びを活かした構成でした。沢山の食材は新聞紙を使用し、立体的に形作り、張り子のように一つひとつ作りました。今もお店屋さんごっこで大活躍しています。遊びを通して育まれた様々な力は、子ども達が、自分らしく、未来の社会を切り拓いていく基盤となります。子どもの遊びは成長に応じて、段階的に発展していくと言われています。2~3歳くらいの間に象徴機能が発達し、なりきる遊びや、見立て遊び、ごっこ遊び等が大好きになっていきます。あおぞらひろばでも“あり”になりきってお菓子を運ぶ姿がありましたね。このような遊びを存分に楽しんでいると共感遊びができるようになっていきます。共感遊びとは仲間と共に楽しさを体感する遊びです。友達と一緒に喜び合ったり、呼吸を合わせ、タイミングやリズムを合わせたり等をして楽しみます。3歳児の「おいしいおかしをみつけたよ」の中で、グループみんなで手を繋ぎ、タイミングを合わせて山(長縄)をジャンプして飛び越えましたね。大人の社会でも共感、協力が大切です。全て遊びを通して経験し、人生の可能性を広げているのです。その経験から協力した仲間がチームに分かれて健全な競争遊びへと発展し、4、5歳児の姿にあったように勝った、負けたを楽しめるようになっていきます。走る、転がる、飛び跳ねる、ぶら下がる、渡る、登るを盛り込んだ遊びをみんなで楽しんでいるうちに、子ども達は共感力、模倣力、観察力、発見力、判断力、対応力が身に付いていきます。仲間と一緒に楽しいと思う経験を重ねていく中で、友達が喜べば自分も嬉しい、仲間が悔しがれば自分も悔しいと思うようになります。そして友達を見て、あんなふうにかっこよくやってみたいと思い、よく見るようになります。「どうやって鉄棒を回っているのかな?」「どうやったらあの子のように…」ととてもよく観察をしています。楽しさも熱中することも、全て共感し、伝承していくのです。「わかった、こうやっているんだ!」と発見し、自分でもやってみる。しかし最初はなかなか上手くいきません。思うようにいかないこともわかりながら、出来るようになりたい憧れの思いで、挑戦し続けながら楽しんでいきます。「やっぱりこうしたらいいかな?」「ああしたらいいかも」と判断・対応していくのです。失敗してもまたチャレンジをして、やり抜く力も育っていきます。ご家庭でもお子さんが今何に興味関心を示し、何を共感し、何を見て模倣し、観察をしているのか等、そういった視点を大切にしてみて下さい。園でも引き続き、子ども達一人ひとりに合わせた声掛け、働き掛けを工夫しながら、思い思いに遊びに熱中できるような援助を行い、楽しみながら保育をしていきたいと思います。 ~参考文献『生きる力を育む遊びのつくり方』~
園長 梶山 美里