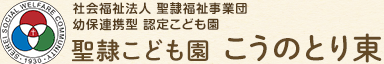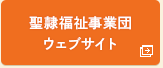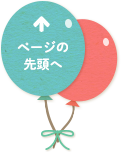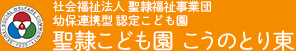園長 平野 春江
職員から興味深い話を聞きました。娘さんの小学校の運動会でのこと。種目はダンスで、とても可愛らしく楽しそうに踊る姿がみられたそうです。姿としては例年通りのダンスの様子だったようですが、今年度は当日までの練習の過程に変化があったそうです。一般的な小学校では、今までは踊る曲や振付は教員が考え、それを児童に指導して当日、披露するという流れが主流であったと思います。しかし、今年度は曲決めから振付まで得意とする児童を中心に子ども自身が考えていったそうです。平成 29 年に小学校学習指導要領が改訂・公示されました。それに伴い、学びに向かう方法等にも変化が見られてきているようです。同時期、幼保連携型認定こども園教育・保育要領も改訂・公示されました。指針の中の一説に『園児が生活を通して身近なあらゆる環境からの刺激を受け止め、自分から興味をもって環境に主体的に関わりながら、様々な活動を展開し、充実感や満足感を味わうという体験を重ねていくことが重視されなければならない。その際、園児が環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになることが大切である。』と記されています。当園でも、子ども自身が環境に働きかけ、試行錯誤しながら自ら考える機会を生活や遊びの中で沢山経験できるような保育者の関わりを大切にしています。保育者が言葉で教えるという外発的動機で子どもが行動し知識を得るのではなく、子ども自身が全身(五感を含む)を使って様々な道具や遊具等を試しながら「どうなっているんだろう」「知りたいな」等の内発的動機で行動し、知識を得ていくことを大切にしています。子育てや教育は時間をかけるべきものです。教えるのは簡単ですが、乳幼児期の子どもたちは試しながら、試行錯誤しながら学びを深めていくことが必要なのです。ここでそのことが分かるエピソードをご紹介します。5歳児の A さんは、廃材を使って想像を膨らませながら工作をするのが大好きです。担任は、遊びの環境として様々な道具を設定しています。接着剤として、糊とボンドを置いていたのですが、A さんは紙と紙を接着するのにボンドを使用していたそうです。担任としては『紙と紙なら糊のほうがいいと思うけれど…』と思い、A さんに聞いてみたそうです。「どうしてボンドでくっつけたの?」すると A さんは、作品を愛おしそうに眺めながら「だってね、絶対に取れてほしくないから。」と答えたそうです。その言葉を受けて担任は A さんの想いを大切に受け止めると共に A さん自身が製作遊びを進める中で、自ら気づきを得ていくことを待つことにしました。A さんは、製作遊びの経験の中で、ボンドの方が強いという知識は得ているようです。廃材には、紙や布、プラスチック等の様々な素材があります。きっと、これからも繰り返し遊ぶ中で、様々な道具や遊具の性質を知り、知識を深めていくことと思います。体験を通して自ら得た知識は、決して忘れることなくしっかりと根付いていくことでしょう。今後も、友達や保育者との感性豊かな応答的なやりとりを通して促される考える力に焦点にあてながら子どもたちの学びを信じて支えていきたいと思います。