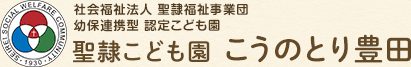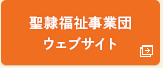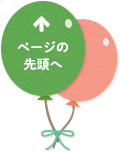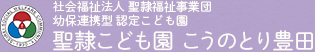園長 高木 智美
夏の音色と聞かれると、せみの鳴き声や風に揺られる風鈴の涼やかな音、花火などを思い浮かべます。皆さんはどんな音色を思い浮かべますか?まだまだ暑さ厳しい毎日ですが、水分補給をこまめに行い、体調の変化に気を付けながら今月も元気に過ごしていきたいと思います。
園内ではアゲハ蝶の幼虫やカブトムシを飼育するクラスもあり、幼虫から蛹になり、成虫になる過程を皆で見守り、幼児クラスでは図鑑を広げながら昆虫への興味関心を深めている様子がうかがえます。夏の虫だけでなく昆虫採取は4月から好きな子を中心に続いているのですが、飼育ケースに入っている虫のために、毎日のお世話を欠かさず行い、餌はどうしたらいいか、休みの間はどうしたらいいかなど、自分たちの飼育する生き物を心配する子も中にはおり、子どもたち皆で気にかけ合いながらお世話をしています。SDGsという時代において、世の中全体が自然との共存という方へ向かっています。子どものころに経験する自然体験がそんな未来を生きる子どもたちのための大切な過程であるといいなと感じます。虫を見てきれいだなとうっとり眺めたり、かっこいいとワクワクしたり、実際に触れてその手触りを体感し、虫の様々な不思議に触れ何でだろうと考えたり、目にする虫の変化から季節の移ろいを感じ取るなど、自然のもたらす恵みとそこに暮らす虫の多様さにたくさんの驚きが日々生まれ、子どもたちにとってそれはとても魅力的な世界なのだろうと想像せずにはいられません。余談ですが、昆虫好きの方から子どもたちのためにとカブトムシの幼虫を譲り受けたことがきっかけで私もカブトムシを卵から育てたことがあります。大きな声では言えませんが、当時は苦手でした。子どもの頃は平気で触れ、むしろ好きだった記憶はあるのですがいつからそうなってしまったのでしょう…。ある日、私が幼虫の土替えをしていると子どもたちが立ち寄ってくれ「こうしたらいいよ」と慣れた手つきで幼虫を持ち、お世話の方法を教えてくれました。苦手な私はそんな素振りを隠し、せっかくの子どもたちの興味、好奇心や探求心を削いでしまうことのないようにと、子どもたちと一緒に幼虫を素手で触れることをするうちいつの間にか虫への抵抗感もなくなっていった、そんな経験があります。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」の中に“自然との関わり、生命尊重”があります。(小学校入学前までに育みたい資質や能力を具体的な子どもの姿として表したものです。)自然に触れて感動する体験を通して自然の変化などを感じ取り好奇心や探求心を持って考え、言葉などで表現しながら身近な事象への関心が高まると共に、自然への愛情や畏敬の念を持つようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で生命の不思議さや尊さに気付き身近な動植物への接し方を考え命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。と、あります。(引用/保育所保育指針、こども園教育-保育要領より)子どもたちは好奇心を働かせながら、様々な経験をすることで生き物と付き合う方法を見つけて行きますが、時に大切に育てていた虫が動かなくなってしまったといった場面も少なくありません。こうした体験から“いのち”というものを知り、生き物と付き合う方法を子どもたちは実体験を通して知っていきます。自然の中で暮らす生き物の面白さ、生き物を大切に思いやる心、自然を大切にする気持ちが子どもたちの中に育まれるよう、私たち大人は目の前にいる子どもたちが今何に心動かされているのか、感じていることや考えていることに寄り添い驚きや感動を一緒に味わえるよう日々を過ごしていきたいと思います。
夏の音色と聞かれると、せみの鳴き声や風に揺られる風鈴の涼やかな音、花火などを思い浮かべます。皆さんはどんな音色を思い浮かべますか?まだまだ暑さ厳しい毎日ですが、水分補給をこまめに行い、体調の変化に気を付けながら今月も元気に過ごしていきたいと思います。
園内ではアゲハ蝶の幼虫やカブトムシを飼育するクラスもあり、幼虫から蛹になり、成虫になる過程を皆で見守り、幼児クラスでは図鑑を広げながら昆虫への興味関心を深めている様子がうかがえます。夏の虫だけでなく昆虫採取は4月から好きな子を中心に続いているのですが、飼育ケースに入っている虫のために、毎日のお世話を欠かさず行い、餌はどうしたらいいか、休みの間はどうしたらいいかなど、自分たちの飼育する生き物を心配する子も中にはおり、子どもたち皆で気にかけ合いながらお世話をしています。SDGsという時代において、世の中全体が自然との共存という方へ向かっています。子どものころに経験する自然体験がそんな未来を生きる子どもたちのための大切な過程であるといいなと感じます。虫を見てきれいだなとうっとり眺めたり、かっこいいとワクワクしたり、実際に触れてその手触りを体感し、虫の様々な不思議に触れ何でだろうと考えたり、目にする虫の変化から季節の移ろいを感じ取るなど、自然のもたらす恵みとそこに暮らす虫の多様さにたくさんの驚きが日々生まれ、子どもたちにとってそれはとても魅力的な世界なのだろうと想像せずにはいられません。余談ですが、昆虫好きの方から子どもたちのためにとカブトムシの幼虫を譲り受けたことがきっかけで私もカブトムシを卵から育てたことがあります。大きな声では言えませんが、当時は苦手でした。子どもの頃は平気で触れ、むしろ好きだった記憶はあるのですがいつからそうなってしまったのでしょう…。ある日、私が幼虫の土替えをしていると子どもたちが立ち寄ってくれ「こうしたらいいよ」と慣れた手つきで幼虫を持ち、お世話の方法を教えてくれました。苦手な私はそんな素振りを隠し、せっかくの子どもたちの興味、好奇心や探求心を削いでしまうことのないようにと、子どもたちと一緒に幼虫を素手で触れることをするうちいつの間にか虫への抵抗感もなくなっていった、そんな経験があります。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」の中に“自然との関わり、生命尊重”があります。(小学校入学前までに育みたい資質や能力を具体的な子どもの姿として表したものです。)自然に触れて感動する体験を通して自然の変化などを感じ取り好奇心や探求心を持って考え、言葉などで表現しながら身近な事象への関心が高まると共に、自然への愛情や畏敬の念を持つようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で生命の不思議さや尊さに気付き身近な動植物への接し方を考え命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。と、あります。(引用/保育所保育指針、こども園教育-保育要領より)子どもたちは好奇心を働かせながら、様々な経験をすることで生き物と付き合う方法を見つけて行きますが、時に大切に育てていた虫が動かなくなってしまったといった場面も少なくありません。こうした体験から“いのち”というものを知り、生き物と付き合う方法を子どもたちは実体験を通して知っていきます。自然の中で暮らす生き物の面白さ、生き物を大切に思いやる心、自然を大切にする気持ちが子どもたちの中に育まれるよう、私たち大人は目の前にいる子どもたちが今何に心動かされているのか、感じていることや考えていることに寄り添い驚きや感動を一緒に味わえるよう日々を過ごしていきたいと思います。