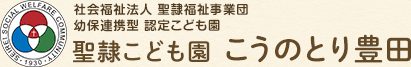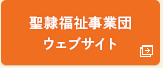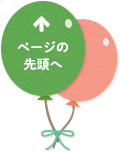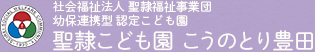園長 高木 智美
先日は夕涼みweekへの親子でのご参加、ありがとうございました。お家の方と一緒にお店を訪れる子どもたちの表情は笑顔に溢れ、和やかな時間を過ごされたことと思います。保護者会の役員の皆さまにも、お店を担当していただき、準備から当日までお忙しい中ありがとうございました。
さて、イスラエルの挨拶に「シャローム」という言葉があります。日本の言葉で表すと「こんにちは」から「さようなら」「ご機嫌いかが」と、朝、昼、夜、どんなときにも使える豊かな広がりのある言葉です。「シャローム」という言葉は、相手を思いやる言葉でもあり「平和があなたにありますように」「あなたが健やかでありますように」という意味も含んでいる言葉なのです。8月は原爆、終戦の日があり子どもたちと平和について考えるときがありました。子ども社会でも、近くにいる友だちとけんかをしてしまったり、時にひどい言葉を言ってしまったりと何かしらの問題が生じることはまれではありませんが、相手を受け入れることで状況がよい方向に向かうことができるまでには、たくさんの知恵と多くの経験が必要です。十人十色の子どもたちであり、誰として同じ人はいません。姿そのもの、考え方やその人が育って来た環境も様々であります。8月の聖句は「人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい」でした。単純に「人にしてもらいたいことを人にする」というのは、大人でも簡単なようでなかなか難しいことだと私は思うことがあります。難しいと思う理由はいくつかありますが、価値観の違いもそうですが自分がしてもらいたいと思うことと、他の人がしてもらいたいと思うことが必ずしも一致することは少ないと思うのです。例えばおもちゃの片付けに時間を要するお子さんがいて、「手伝う?」と伝えると、その子は、「自分でやるからいい」と言いました。歳児によっても違いますが、子どもの生活場面でこんな状況は、よくあるのではないでしょうか。対話したことでこの時は「自分で」という相手の気持ちがちゃんと伝わっていますが、大人の都合を優先するあまり、大人が片づけを済ませてしまい目の前の子どもたちの声を聞き逃してしまうこともあるでしょう。私たち保育者は、一人ひとりのお子さんに寄り添った関わりを心がけていますが「自分でやる」と言ったその子にとっては、自分がしていた遊びを最後まで自身でやりきることに意味がありとても重要なことだったのではないでしょうか。その人のことを思って行動に起こしたことでも、もしかしたら相手にとっては迷惑だったり、余計なお世話だったりすることもあります。しかし相手の真意は目に見えませんから、より相手の立場を正しく理解したり、相手の立場に立って考え、時に想像してみたりと、相手に寄り添うことがとても大切なことなのではないかと。相手を知ろうとしたり、傷つけないよう気を付けることはできますし、言葉を交わすことで分かり合えることもできます。そして、相手の幸せを祈ることもできます。私たちの周りにいる人は「隣人」であり、自分と同じように神から愛されている存在でありたいと思います。安心してこども園へ行くこと、友だちと過ごすこと、好きな遊びをすること、食べること、家族がいること、いつもあって当たり前のように何気なく過ごしているこうした日常も平和です。
相手の気持ちはどうかな、一方通行になってはいないかな、人に自分の価値を自分でも気づかぬうちに押し付けてはないかな、相手のことを知ることで子どもたちの大切に育みたい根っこの育ちがあってくれたらいいなと願います。私たち大人も、自分たちのことで精一杯になりがちですが言葉を交わしながら子どもたちと一緒に考える機会を持つことの大切さを感じます。子どもたちは多くの実体験を通して、生活と遊びを結びつけながら様々なことを身に付けていきます。自分で考え、自分を高めていく力を子どもは持っています。ただ、一人だけでは育ちません。やはりそこには、人とひととの関わりがあるからこそ育つものがたくさんあります。子どもたちが「自分や周りの人(隣人)を愛することができる人」になってほしいという祈りを込め、私たち保育者も子どもたちとの日々を丁寧に見つめていける保育をしていきたいと思います。~平和があなたにありますように~
先日は夕涼みweekへの親子でのご参加、ありがとうございました。お家の方と一緒にお店を訪れる子どもたちの表情は笑顔に溢れ、和やかな時間を過ごされたことと思います。保護者会の役員の皆さまにも、お店を担当していただき、準備から当日までお忙しい中ありがとうございました。
さて、イスラエルの挨拶に「シャローム」という言葉があります。日本の言葉で表すと「こんにちは」から「さようなら」「ご機嫌いかが」と、朝、昼、夜、どんなときにも使える豊かな広がりのある言葉です。「シャローム」という言葉は、相手を思いやる言葉でもあり「平和があなたにありますように」「あなたが健やかでありますように」という意味も含んでいる言葉なのです。8月は原爆、終戦の日があり子どもたちと平和について考えるときがありました。子ども社会でも、近くにいる友だちとけんかをしてしまったり、時にひどい言葉を言ってしまったりと何かしらの問題が生じることはまれではありませんが、相手を受け入れることで状況がよい方向に向かうことができるまでには、たくさんの知恵と多くの経験が必要です。十人十色の子どもたちであり、誰として同じ人はいません。姿そのもの、考え方やその人が育って来た環境も様々であります。8月の聖句は「人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい」でした。単純に「人にしてもらいたいことを人にする」というのは、大人でも簡単なようでなかなか難しいことだと私は思うことがあります。難しいと思う理由はいくつかありますが、価値観の違いもそうですが自分がしてもらいたいと思うことと、他の人がしてもらいたいと思うことが必ずしも一致することは少ないと思うのです。例えばおもちゃの片付けに時間を要するお子さんがいて、「手伝う?」と伝えると、その子は、「自分でやるからいい」と言いました。歳児によっても違いますが、子どもの生活場面でこんな状況は、よくあるのではないでしょうか。対話したことでこの時は「自分で」という相手の気持ちがちゃんと伝わっていますが、大人の都合を優先するあまり、大人が片づけを済ませてしまい目の前の子どもたちの声を聞き逃してしまうこともあるでしょう。私たち保育者は、一人ひとりのお子さんに寄り添った関わりを心がけていますが「自分でやる」と言ったその子にとっては、自分がしていた遊びを最後まで自身でやりきることに意味がありとても重要なことだったのではないでしょうか。その人のことを思って行動に起こしたことでも、もしかしたら相手にとっては迷惑だったり、余計なお世話だったりすることもあります。しかし相手の真意は目に見えませんから、より相手の立場を正しく理解したり、相手の立場に立って考え、時に想像してみたりと、相手に寄り添うことがとても大切なことなのではないかと。相手を知ろうとしたり、傷つけないよう気を付けることはできますし、言葉を交わすことで分かり合えることもできます。そして、相手の幸せを祈ることもできます。私たちの周りにいる人は「隣人」であり、自分と同じように神から愛されている存在でありたいと思います。安心してこども園へ行くこと、友だちと過ごすこと、好きな遊びをすること、食べること、家族がいること、いつもあって当たり前のように何気なく過ごしているこうした日常も平和です。
相手の気持ちはどうかな、一方通行になってはいないかな、人に自分の価値を自分でも気づかぬうちに押し付けてはないかな、相手のことを知ることで子どもたちの大切に育みたい根っこの育ちがあってくれたらいいなと願います。私たち大人も、自分たちのことで精一杯になりがちですが言葉を交わしながら子どもたちと一緒に考える機会を持つことの大切さを感じます。子どもたちは多くの実体験を通して、生活と遊びを結びつけながら様々なことを身に付けていきます。自分で考え、自分を高めていく力を子どもは持っています。ただ、一人だけでは育ちません。やはりそこには、人とひととの関わりがあるからこそ育つものがたくさんあります。子どもたちが「自分や周りの人(隣人)を愛することができる人」になってほしいという祈りを込め、私たち保育者も子どもたちとの日々を丁寧に見つめていける保育をしていきたいと思います。~平和があなたにありますように~