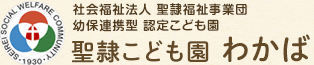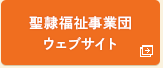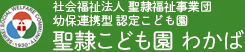園長 加藤可織
立春を迎え、これから春が少しずつ近づいてきます。寒さが和らぐ気配はまだ感じられず、体調を崩しやすい時期でもあります。1月下旬より、園内で嘔吐下痢症状・発熱等で欠席する園児が増え、保護者の皆様にはご心配をおかけしております。感染拡大を防止するために感染状況をコドモンでお知らせしたり、園内の消毒や換気等を行なったりしていますが、今後も引き続き子どもたちが安心して過ごせるよう園内の環境を整えていきますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
さて、今年の節分は立春が2月3日となるため、4年ぶりに2月2日(日)となっています。園では、本日、節分(豆まき)を子どもたちと一緒に行ないました。節分を迎えるまで、各クラスごと年齢に応じて節分の由来等を話し、日本の伝統的な行事を楽しみにしていました。子どもたちは「心の中の鬼を退治するんだよね!」「鬼は外~福は内~だよね。」等々、今まで経験した時のことを思い出しながら話をする姿がありました。その中で、1月中旬から始まった“ゆうびんやさんごっこ”でハガキを描くことを楽しんでいたき組の子どもたちが鬼宛てにハガキを描いていることを担任から教えてもらいました。子どもたちがどうして鬼にハガキを描いたのか…それは昨年、もも組の時に『かわいい鬼さんが来てください!』と鬼宛てにハガキを描いたところ、スカートを履いたかわいい鬼が来たから今年も来てもらいたいとのことでした。ハガキを描いたのは一人だけではなく、描いている友だちを見て“私も”“僕も”と数名の子どもたちが鬼宛てにハガキを描いていました。先週末にはき組保育室の天井に鬼からのハガキが貼り付けられていたようで子どもたちは大興奮!!そして、わかばでの節分の本日、鬼はやってきたのか…
各クラスでは、手作りの新聞紙を丸めて作った豆で「鬼は外!福は内!」と豆まきごっこを楽しむ姿がありました。今後も日本の伝統的な行事の由来に触れながら、子どもたちと楽しんでいきたいと思います。
子どもたちは、生活やあそびの中で様々なことを経験し学んでいきます。学ぶということは、勉強と同様の意味と使われがちですが、実際は異なります。『勉強』とは、一般的に知識や技能を習得するために行なう作業を指し、『学び』とは、好奇心や興味を持ち、自発的に探求する行為です。子どもたちにとって日々過ごしていく中で友だちの様子や身近にいる大人の姿を見て興味を持ち、やってみようとする姿が園内の色々な所で見られます。初めは上手くいかないことも繰り返し行なうことでやり方(あそび方)を獲得していきます。子どもたちの自発的な心の動きを見逃さず、私たちは見守り、時に必要な援助をしていきたいと思います。
今月はたのしいつどいが行なわれます。1年間楽しんできたことを通して子どもたちの成長を感じ、共に喜び合い、親子での楽しいひと時となるように願っています。
立春を迎え、これから春が少しずつ近づいてきます。寒さが和らぐ気配はまだ感じられず、体調を崩しやすい時期でもあります。1月下旬より、園内で嘔吐下痢症状・発熱等で欠席する園児が増え、保護者の皆様にはご心配をおかけしております。感染拡大を防止するために感染状況をコドモンでお知らせしたり、園内の消毒や換気等を行なったりしていますが、今後も引き続き子どもたちが安心して過ごせるよう園内の環境を整えていきますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
さて、今年の節分は立春が2月3日となるため、4年ぶりに2月2日(日)となっています。園では、本日、節分(豆まき)を子どもたちと一緒に行ないました。節分を迎えるまで、各クラスごと年齢に応じて節分の由来等を話し、日本の伝統的な行事を楽しみにしていました。子どもたちは「心の中の鬼を退治するんだよね!」「鬼は外~福は内~だよね。」等々、今まで経験した時のことを思い出しながら話をする姿がありました。その中で、1月中旬から始まった“ゆうびんやさんごっこ”でハガキを描くことを楽しんでいたき組の子どもたちが鬼宛てにハガキを描いていることを担任から教えてもらいました。子どもたちがどうして鬼にハガキを描いたのか…それは昨年、もも組の時に『かわいい鬼さんが来てください!』と鬼宛てにハガキを描いたところ、スカートを履いたかわいい鬼が来たから今年も来てもらいたいとのことでした。ハガキを描いたのは一人だけではなく、描いている友だちを見て“私も”“僕も”と数名の子どもたちが鬼宛てにハガキを描いていました。先週末にはき組保育室の天井に鬼からのハガキが貼り付けられていたようで子どもたちは大興奮!!そして、わかばでの節分の本日、鬼はやってきたのか…
各クラスでは、手作りの新聞紙を丸めて作った豆で「鬼は外!福は内!」と豆まきごっこを楽しむ姿がありました。今後も日本の伝統的な行事の由来に触れながら、子どもたちと楽しんでいきたいと思います。
子どもたちは、生活やあそびの中で様々なことを経験し学んでいきます。学ぶということは、勉強と同様の意味と使われがちですが、実際は異なります。『勉強』とは、一般的に知識や技能を習得するために行なう作業を指し、『学び』とは、好奇心や興味を持ち、自発的に探求する行為です。子どもたちにとって日々過ごしていく中で友だちの様子や身近にいる大人の姿を見て興味を持ち、やってみようとする姿が園内の色々な所で見られます。初めは上手くいかないことも繰り返し行なうことでやり方(あそび方)を獲得していきます。子どもたちの自発的な心の動きを見逃さず、私たちは見守り、時に必要な援助をしていきたいと思います。
今月はたのしいつどいが行なわれます。1年間楽しんできたことを通して子どもたちの成長を感じ、共に喜び合い、親子での楽しいひと時となるように願っています。