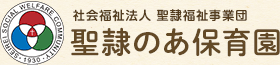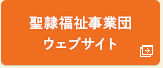『 生涯で我が子と一緒に過ごせる時間 』
1月に咲く蝋梅。厳しい寒さの中、甘く芳醇な香りとロウ細工のような透明感のある黄色い花を咲かせ、冬景色に彩りと癒しを与えてくれます。冬の冷たい空気の中で咲く力強さと、反対にうつむき加減に咲く姿が控えめで何とも奥ゆかしく、好きな花の一つです。
先日は、懇談会へのご参加をありがとうございました。子どもは一人ひとりが大切な賜物として誕生します。しかし発達の順序(課程)や成長の速度は異なります。私は親になって初めて、こんなにも全ての愛と力を注ぐ愛おしい存在がいることを知り、我が子のことであれば些細なことで不安になりました。ですから保護者の方が不安や心配事を抱える気持ちがとてもよくわかります。不安や心配事の大小はありますし受け止め方も違うとは思いますが、人と話して子育ての悩みを共有することで気持ちが軽くなったり安心したりできると思います。思いの共有と親睦を深めることを今回の懇談会のねらいとしました。全体会では「甘えとわがままの違い」「甘えと自立の関係」についてお話させていただきました。①子どもの心は「甘え(依存)」と「反抗(自立)」を行ったり来たりして育つ。②「甘えていい時に、十分に甘えた子」が自立する。③子どものペースで見守ること、大人の都合でかまい過ぎたり突き放したりしない。④「甘えさせる」と「甘やかす」の違いについて考える。⑤自立とは…と、話を深めました。その中で「愛情のコップ」についてもふれました。親は我が子にいろんな愛情を注ぎます。我が子の将来を思い良かれと思って愛情を注ぎます。しかし、子どもがして欲しいことは実は別のことかもしれない。その時の子どもの思いと合っていないとどれだけ愛情を注いでも伝わらないという話です。更に、愛情を受け取る器の大きさや何を注ぐと満たされるのかは個人差があること、満たされて溢れると、溢れた愛情は他者へ注がれるようになること、親も自分のコップが空になってしまわないよう自分自身のコップも満たすことが重要なこと、枯渇させないために定期的に愛情を注ぎ続ける必要があることをお伝えしました。全体会後、クラス懇談会へと続きました。今年度最後と言うことで一年間の成長を振り返り、我が子だけでなく一緒に大きくなった子どもたちの姿(ドキュメント)に笑顔が溢れるひと時となりました。0歳児クラスでは、よく食べよく眠り、穏やかに過ごす様子に安心された保護者の方の笑顔がありました。1歳児クラスでは、少しずつイヤイヤが増える時期ですので、お子さんとの向き合い方に試行錯誤されている様子があり…各々のご家庭からアドバイスやヒントが出てきて盛り上がりました。イヤイヤと感情を前面に出してぶつかり合う時期が、人として生きていく上で大事なものを学ぶ時(子どもも関わる大人も)です。この時期を丁寧に関わることで、大人(親や保育士)にとっても学びとなります。子どもの【今】に向き合う大切さを考えさせられました。2歳(うさぎぐみ)の子どもたちは、後2ヵ月で卒園です。小規模園から様々な園(こども園・幼稚園・保育園)への一歩は保護者の方の方がドキドキしているようでした。乳児から幼児となりクラスの人数が増えるので、大きな社会に親も子どもも驚くことがあると思いますが、大きくなったという喜びでもあります。これから沢山の人と出会いや様々な経験が益々子どもたちを豊かにしてくれると信じています。入園からの姿を懐かしく振り返りながらスクラップブッキングで思い出を形にしました。
最後に、「生涯で我が子と一緒に過ごせる時間」をお伝えしたいと思います。母親は7年6ヵ月、父親は3年4ヵ月ほどだそうです。衝撃的な数字です。乳幼児期が一緒にいる時間が長いため、小学校卒業時には上記の半分以上の時間が過ぎているとのことです。この限りある時間を知っているだけで些細な時間も「愛しい時間」と思えますね。限りある時間を大切に過ごしていきましょう。