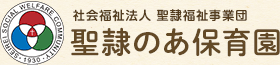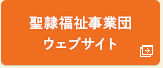『 〇〇の日 』
石川 綾乃
焼けつくような夏の日差しが少しだけ和らぎ、夕方から夜にかけて空の色や風の音が秋めいてきました。キンモクセイの匂いやコスモスの花等、季節の移ろいを探しに散歩に出かけたいと思います。
今日 9 月 1 日は防災の日です。9 月 1 日が「防災の日」と定められているのは、1923 年 9 月 1 日に発生した関東大震災を教訓に、国民の防災意識を高めるためです。この大震災では、死者・行方不明者が 10 万人を超える甚大な被害が出ました。この教訓を忘れず、台風や地震などの自然災害に対する備えを強化するために、1960 年に制定されました。地震、台風、それらによって起こる土砂災害や洪水、火事…この地球には様々な災害があります。いつ、どこで起こるかわかりません。家族が一緒にいる時に起こるとは限りません。在園のご家庭は、お子さんと離れて就労されていますので心配ですね。先日も「津波警報」が発令され緊張した 1 日を過ごしました。直ぐにメールを送信し保護者の方と共有したため、早迎えの準備や降園後の安全な過ごし方等、考える機会になったのではないかと思います。本日、園では防災訓練(東海地震・南海トラフ巨大地震注意情報および警戒宣言発令想定)を行いました。子どもの安全確保と避難、非常持ち出し袋の点検、非常食体験、引き渡し訓練等です。自園は小さいお子さんをお預かりしていますので、大人の訓練が主になりますが、子どもたちにも「どんな災害があるか。その災害が起きるとどうなってしまうか。」等、わかりやすく話をしました。園ではお子さんの安全を確保し、保護者の方に無事に受け渡すまで過ごすことになります。しかし、ライフラインが途絶えてしまうことを想定して「お迎えは誰が一番早く行けるのか。お迎え後の家族の集合場所(地域の避難場所)はどこか。」等、これを機に、ご家庭で話し合っておけるとよいと思います。また、地震の時、火事の時、台風の時、それぞれ避難の仕方が違います。どのように避難したらよいか、どうしてその避難の仕方をするのかを考え、練習しておくことも大切です。他にも、日頃から室内の安全チェック(家具の固定)、非常持ち出し袋の確認や点検等もしっかりしておけるとよいですね。
今月は「敬老の日」があります。日本の国民の祝日の一つで、毎年 9 月の第 3 月曜日に設定されています。この日は、長年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し長寿を祝う日です。(園の祖父母の皆さんは若々しく、とても高齢者とは言えませんが…。)祖父母のお宅を訪問したり、家族が集まってプレゼントを渡したり一緒に食事をすることで家族の絆を深める機会になります。園でもこの日
を大切な日ととらえ、穏やかなひと時を過ごしたいと思っています。遠方の方には「ハガキ」が届きますので楽しみにお待ちください。
それから秋の始まりを知らせる「秋分の日」もあります。秋分の日は、その年の太陽が秋分点を通過する日によって毎年日付が変わります。春分の日も同様です。(秋分の日は冬に向かって 1 日の日照時間が日に日に短くなっていき、春分の日は夏に向かって 1 日の日照時間が長くなります。)このように、天文学に基づき祝日を決定することは世界的に珍しいことなのですよ。秋分の日は「祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶ日」で、お彼岸は日本独特の風習です。仏教の世界では、先祖のいる悟りの世界を「彼岸」、今私たちが生きている世界を「此岸(しがん)」と表し、彼岸と此岸の距離が最も近い日と考えられたことが由来だそうです。いつもでしたら何となく過ごしてしまいがちですが、意味を知ることで、遠い先祖に思いをはせ、このような時代(ウクライナ紛争、地球温暖化、疫病の発生等)に、この世界に生かされていることを考えさせられます。