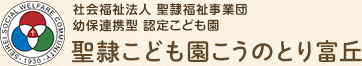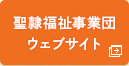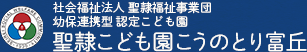新緑の若葉にすがすがしさを感じる季節になりました。新年度がスタートして1ヶ月が経ち、子どもたちの表情も緊張が和らいで、笑顔があふれています。
さて、4月に新年度を迎えるにあたってどのクラスでも「子どもたちが安心して過ごせる」ように、また、「新しい環境で『遊びたい!』と思える」ように話し合いを繰り返し、検討を重ねてスタートしました。おもちゃ棚を動かして遊びの環境を整えたり、おむつ替えや着替えの場所、食事の時間の流れや場所を考えたり…。担当するクラス(歳児)の発達を踏まえ、また子どもたちの姿を思い浮かべながら、多くの時間を費やして整えました。
こうして新年度を迎えましたが、実際に子どもたちがこの環境で過ごしてみると思い描いていた姿と異なる子どもたちの姿もあり…。新年度初日、それぞれのクラスで子どもたちの姿を踏まえて、環境や過ごし方を再度話し合いました。「環境を変えてみようと思います!」と昼の話し合い後すぐ、部屋の一部を変えているクラスもあり、子どもたちの姿を見ながら(子どもたちが戸惑わない範囲で)少しずつ環境や生活の流れ、職員の体制を変えて子どもたちの姿に合わせて過ごせるようにしています。また、4.5歳児クラスでは、異年齢グループ(りんご・ぶどう)をさらに小さい4つのグループに分けて過ごす時間もつくり、子どもたち一人一人とじっくり、丁寧に関われるよう過ごす時間も大切にしています。“進級したから(〇〇組になったから)できるようになる”ではなく、子どもたちの姿に合わせて、また子どもたちと共に環境や遊びを考えたり、計画を立てたりすることを大切にしながら日々の保育を行っています。子どもたちはとても順応性があり、新しい環境や生活にもあっという間に慣れていきます。しかし、大人が用意した環境は、もしかしたら子どもたちにとって、快適な環境ではない場合もあるかもしれません。子どもたちの「今」の姿にあった(年齢発達や興味関心にあった)保育・教育を行えるよう、職員の思いだけではなく、やりたい活動(あそび)を子どもと一緒に考えながら、大人が柔軟に対応し、保育・療育の環境をつくっていきたいと思います。
キリスト教保育冊子4月号-巻頭言-「子どもをリスペクト出来ているか」に、著者の新沢氏が子どもの頃の経験から感じた子どもの心について、「大人は、自分の経験値から、子どもの心は分かる分かると考えがちだ。-中略-「それは子どものためでしょ」と大人は言ったりするけれど、意外と「大人の都合」のためだったりする。-中略-まだ生まれて数年で、経験値の少ない未熟な子どもを、いかに同じ人間としてリスペクト出来るか。そこが大事ですよ、と幼かった頃の僕が教えてくれている(キリスト教保育冊子4月号「子どもをリスペクト出来ているか」:新沢としひこ氏)」という一文があります。もしかしたら、子どもたちがやりたいことと、大人が「やらせたい」「経験させたい」と思っていることが違うこともあるかもしれません。それでも、計画や準備から子どもたちが関わることで、一つ一つの場面(日々の生活や遊び)の主役が子どもたちになり、主体的に生きる、主体的に学ぶことへとつながってくれることと思います。どんな小さな場面でも、「こども」が真ん中であり、一人一人がどんなことを考え、感じ、学びを得ているか。私たち職員は見逃さないように、しっかりとその姿をとらえ、保護者の皆様にも共有しながら日々の成長を支えていきたいと思います。
今月はこども園4,5歳児クラスの親子遠足が予定されています。この親子遠足に向けて、ぶどうグループ・りんごグループではそれぞれ「おうちの人とどんなことをして遊びたい?」と話し合いをしながら準備を進めていきます。これから子どもたちと一緒に計画を進めていきますので、ぜひお子さんと親子遠足に向けての保育の話をしていただきながら、一緒に当日を楽しみに待っていただければと思います。
4月は、子どもも、大人も、誰もが新しい出会いの中で新しい生活がスタートしています。日々過ごす中で、共有したい子どもの姿や成長、また不安や疑問等があった方もいらっしゃると思います。保育・療育では、子どもたちと話をしたり、遊んだり、生活をしたりする中で、できるだけ丁寧にたくさん関わり、一緒の時間を過ごしていくことでまずはお互いを知るよう努めています。子どもたちにとって安心して自己発揮できる場所となるように、また保護者の皆さまにとっても安心して預けていただけるように、関心を向け、対話を大切にしながら、これからも共にお子様の成長に関わらせていただきたいと思います。
園長 二村 郁枝
さて、4月に新年度を迎えるにあたってどのクラスでも「子どもたちが安心して過ごせる」ように、また、「新しい環境で『遊びたい!』と思える」ように話し合いを繰り返し、検討を重ねてスタートしました。おもちゃ棚を動かして遊びの環境を整えたり、おむつ替えや着替えの場所、食事の時間の流れや場所を考えたり…。担当するクラス(歳児)の発達を踏まえ、また子どもたちの姿を思い浮かべながら、多くの時間を費やして整えました。
こうして新年度を迎えましたが、実際に子どもたちがこの環境で過ごしてみると思い描いていた姿と異なる子どもたちの姿もあり…。新年度初日、それぞれのクラスで子どもたちの姿を踏まえて、環境や過ごし方を再度話し合いました。「環境を変えてみようと思います!」と昼の話し合い後すぐ、部屋の一部を変えているクラスもあり、子どもたちの姿を見ながら(子どもたちが戸惑わない範囲で)少しずつ環境や生活の流れ、職員の体制を変えて子どもたちの姿に合わせて過ごせるようにしています。また、4.5歳児クラスでは、異年齢グループ(りんご・ぶどう)をさらに小さい4つのグループに分けて過ごす時間もつくり、子どもたち一人一人とじっくり、丁寧に関われるよう過ごす時間も大切にしています。“進級したから(〇〇組になったから)できるようになる”ではなく、子どもたちの姿に合わせて、また子どもたちと共に環境や遊びを考えたり、計画を立てたりすることを大切にしながら日々の保育を行っています。子どもたちはとても順応性があり、新しい環境や生活にもあっという間に慣れていきます。しかし、大人が用意した環境は、もしかしたら子どもたちにとって、快適な環境ではない場合もあるかもしれません。子どもたちの「今」の姿にあった(年齢発達や興味関心にあった)保育・教育を行えるよう、職員の思いだけではなく、やりたい活動(あそび)を子どもと一緒に考えながら、大人が柔軟に対応し、保育・療育の環境をつくっていきたいと思います。
キリスト教保育冊子4月号-巻頭言-「子どもをリスペクト出来ているか」に、著者の新沢氏が子どもの頃の経験から感じた子どもの心について、「大人は、自分の経験値から、子どもの心は分かる分かると考えがちだ。-中略-「それは子どものためでしょ」と大人は言ったりするけれど、意外と「大人の都合」のためだったりする。-中略-まだ生まれて数年で、経験値の少ない未熟な子どもを、いかに同じ人間としてリスペクト出来るか。そこが大事ですよ、と幼かった頃の僕が教えてくれている(キリスト教保育冊子4月号「子どもをリスペクト出来ているか」:新沢としひこ氏)」という一文があります。もしかしたら、子どもたちがやりたいことと、大人が「やらせたい」「経験させたい」と思っていることが違うこともあるかもしれません。それでも、計画や準備から子どもたちが関わることで、一つ一つの場面(日々の生活や遊び)の主役が子どもたちになり、主体的に生きる、主体的に学ぶことへとつながってくれることと思います。どんな小さな場面でも、「こども」が真ん中であり、一人一人がどんなことを考え、感じ、学びを得ているか。私たち職員は見逃さないように、しっかりとその姿をとらえ、保護者の皆様にも共有しながら日々の成長を支えていきたいと思います。
今月はこども園4,5歳児クラスの親子遠足が予定されています。この親子遠足に向けて、ぶどうグループ・りんごグループではそれぞれ「おうちの人とどんなことをして遊びたい?」と話し合いをしながら準備を進めていきます。これから子どもたちと一緒に計画を進めていきますので、ぜひお子さんと親子遠足に向けての保育の話をしていただきながら、一緒に当日を楽しみに待っていただければと思います。
4月は、子どもも、大人も、誰もが新しい出会いの中で新しい生活がスタートしています。日々過ごす中で、共有したい子どもの姿や成長、また不安や疑問等があった方もいらっしゃると思います。保育・療育では、子どもたちと話をしたり、遊んだり、生活をしたりする中で、できるだけ丁寧にたくさん関わり、一緒の時間を過ごしていくことでまずはお互いを知るよう努めています。子どもたちにとって安心して自己発揮できる場所となるように、また保護者の皆さまにとっても安心して預けていただけるように、関心を向け、対話を大切にしながら、これからも共にお子様の成長に関わらせていただきたいと思います。
園長 二村 郁枝