食物アレルギーは血液検査で診断できる?

近年、子どもを中心に食物アレルギーの患者数が増加しています。なぜ増えているのかという原因は、まだはっきりとはわかっていません。
以前は「卵、乳、大豆、小麦」が主なアレルゲン(アレルギーを起こす食材4選)とされていましたが、最近では「卵、乳、小麦、ナッツ類(ピーナッツ、クルミなど)」に変化してきています。
この変化に伴い、保育園(以下「園」という)や学校でもアレルギーへの配慮が非常に重要視されるようになりました。
以前は「卵、乳、大豆、小麦」が主なアレルゲン(アレルギーを起こす食材4選)とされていましたが、最近では「卵、乳、小麦、ナッツ類(ピーナッツ、クルミなど)」に変化してきています。
この変化に伴い、保育園(以下「園」という)や学校でもアレルギーへの配慮が非常に重要視されるようになりました。
診断の基本は「症状が出たかどうか」が大切!
食物アレルギーの診断は、「その食材を食べて症状が出たかどうか」。つまり、血液検査の結果だけでアレルギーの有無を判断するのではなく、実際に体が反応したかがポイントです。
実際には、血液検査で陽性(アレルギー反応があるとされる値)でも、普段その食材を問題なく食べているお子さんもたくさんいます。一方で、低月齢の赤ちゃんでは、血液検査が陰性でも実際にはアレルギー症状が出てしまうというケースもあります。
園や学校から「血液検査を受けてください」と言われ病院に来られる保護者の方もいらっしゃいます。検査結果が陽性であっても、実際に摂取できている場合には、その結果だけで食材を制限するのではなく慎重に検討する必要があります。
ただし、園や学校では食物アレルギーに対し最大限の対応が必要です。指導票などを参考に十分な話し合いをすることがとても大切になってきます。
実際には、血液検査で陽性(アレルギー反応があるとされる値)でも、普段その食材を問題なく食べているお子さんもたくさんいます。一方で、低月齢の赤ちゃんでは、血液検査が陰性でも実際にはアレルギー症状が出てしまうというケースもあります。
園や学校から「血液検査を受けてください」と言われ病院に来られる保護者の方もいらっしゃいます。検査結果が陽性であっても、実際に摂取できている場合には、その結果だけで食材を制限するのではなく慎重に検討する必要があります。
ただし、園や学校では食物アレルギーに対し最大限の対応が必要です。指導票などを参考に十分な話し合いをすることがとても大切になってきます。
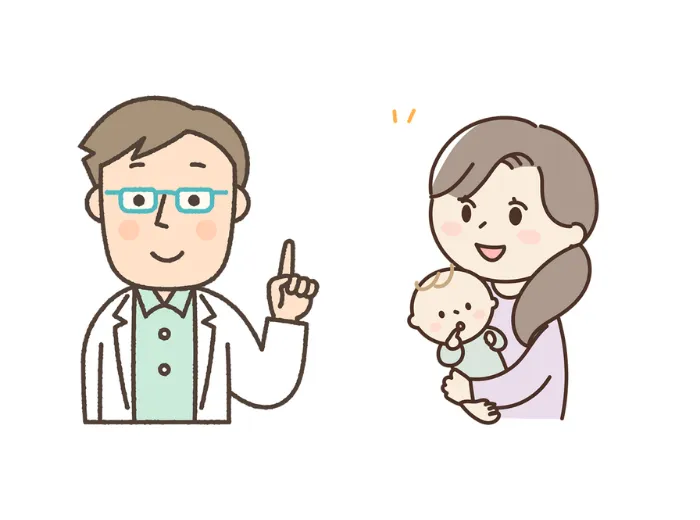
血液検査は「目安」に。実際の症状とあわせて見ていきましょう!
例えば、鶏卵を食べた際にじんま疹などのアレルギー症状が出た場合、血液検査で鶏卵に対するアレルギー反応がどのくらいの数値になっているか確認するのが一般的です。ただし、その数値が「陽性」だからといって、すぐに「これは食べられない!」というわけではありません。数値の高さやその後の変化などを見ながら、「いつから・どれくらいの量を・どのように」食べていくかを一緒に検討していきます。

(例)
・発症時のアレルギー数値が「20」で、現在も同じくらいであれば、摂取はまだ早いためもう少し様子を見ましょうと判断されることが多いです。
・一方、発症時「100以上」あった数値が「20」まで下がっている場合には、同じ「20」の数値でも、食べられる可能性が高くなります。
このように、同じ数値でも経過や背景によって判断が異なるため、医師とよく相談することが大切です。食材によっては、低アレルゲン化し食べるなど段階的に注意しながら摂取を進める必要があります。
・発症時のアレルギー数値が「20」で、現在も同じくらいであれば、摂取はまだ早いためもう少し様子を見ましょうと判断されることが多いです。
・一方、発症時「100以上」あった数値が「20」まで下がっている場合には、同じ「20」の数値でも、食べられる可能性が高くなります。
このように、同じ数値でも経過や背景によって判断が異なるため、医師とよく相談することが大切です。食材によっては、低アレルゲン化し食べるなど段階的に注意しながら摂取を進める必要があります。
気になる症状が出たら、まずは相談を!
もし、お子さんの食後にじんま疹、咳、嘔吐などの症状がみられた場合は、すぐにかかりつけの医師に相談しましょう。食物アレルギーは、必要以上に食べ物を制限してしまうことにより、栄養が偏ったり、成長に影響することもあるため、正しい診断と対応が大切です。
当院では、小児科にてアレルギー外来を行っています。心配、お困りごとなどございましたら一度相談してみませんか?
小児科 アレルギー外来について詳細はこちらをご覧ください。
当院では、小児科にてアレルギー外来を行っています。心配、お困りごとなどございましたら一度相談してみませんか?
小児科 アレルギー外来について詳細はこちらをご覧ください。
執筆者:小児科 鈴木 繁

