栄養科通信
【最新号】2026年2月号
薄味でもおいしく!旬の白菜を使った病院食のレシピをご紹介
2月は寒さが厳しく、旬の野菜や果物はあまりないと思うかもしれません。しかし2月に旬を迎える食材はたくさんあります。野菜では白菜や小松菜などの葉物野菜の他に、ブロッコリーや大根なども旬を迎え、果物ではリンゴやキウイフルーツ、魚介類ではブリや鯛が旬を迎えると言われています。
そこで今回は手軽で身近な食材である「白菜」に着目したいと思います。白菜は淡泊な味のため、栄養がなさそうな食材かと思われがちですが、様々な栄養が含まれている野菜です。白菜に含まれる代表的な栄養素は8つあります。
●ビタミンC:コラーゲンの生成に必要な栄養素で、抗酸化作用がある
●ビタミンK:血液凝固とカルシウムを骨に沈着させることで骨の形成を促す栄養素
●葉酸:赤血球の生産や胎児の正常な発育に関わりのある栄養素
●カリウム:ミネラルの一種でナトリウム(塩分)を体外に出しやすくする
●カルシウム:骨や歯を形成するのに必要なミネラルの一種
●水溶性食物繊維:食後の血糖値の上昇を抑える
●不溶性食物繊維:腸内環境を整える
●イソチオシアネート:抗酸化作用があり、老化の対策に
白菜は病院食でも多く使用される野菜です。そこで今回は実際に病院で提供している白菜を使用したレシピを紹介します。鍋で余りがちな白菜で作ってみませんか?
そこで今回は手軽で身近な食材である「白菜」に着目したいと思います。白菜は淡泊な味のため、栄養がなさそうな食材かと思われがちですが、様々な栄養が含まれている野菜です。白菜に含まれる代表的な栄養素は8つあります。
●ビタミンC:コラーゲンの生成に必要な栄養素で、抗酸化作用がある
●ビタミンK:血液凝固とカルシウムを骨に沈着させることで骨の形成を促す栄養素
●葉酸:赤血球の生産や胎児の正常な発育に関わりのある栄養素
●カリウム:ミネラルの一種でナトリウム(塩分)を体外に出しやすくする
●カルシウム:骨や歯を形成するのに必要なミネラルの一種
●水溶性食物繊維:食後の血糖値の上昇を抑える
●不溶性食物繊維:腸内環境を整える
●イソチオシアネート:抗酸化作用があり、老化の対策に
白菜は病院食でも多く使用される野菜です。そこで今回は実際に病院で提供している白菜を使用したレシピを紹介します。鍋で余りがちな白菜で作ってみませんか?
白菜香浸し(1人分)の作り方
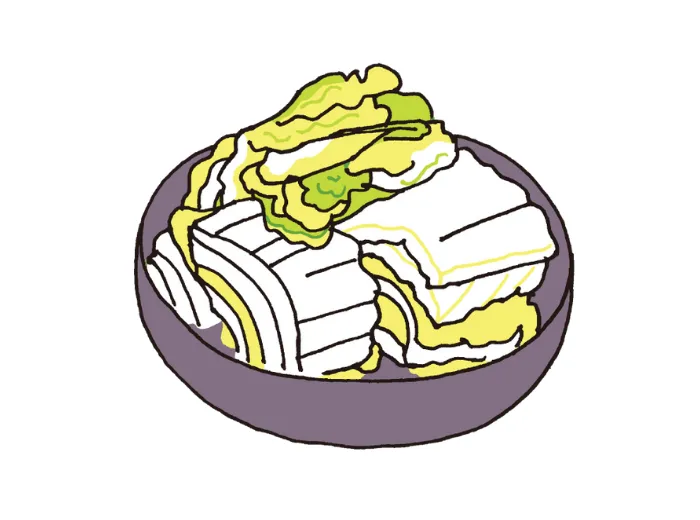
【作り方】
①白菜は2~3cm角に切り、油揚げは半分に切ってから1cm幅に切る。
②白菜は鍋で柔らかくなるまで煮て、柔らかくなったら鍋に油揚げを加え、さらに2分加熱する。
③加熱後、水にさらして水気を絞る。
④☆の調味料と和えて完成。
①白菜は2~3cm角に切り、油揚げは半分に切ってから1cm幅に切る。
②白菜は鍋で柔らかくなるまで煮て、柔らかくなったら鍋に油揚げを加え、さらに2分加熱する。
③加熱後、水にさらして水気を絞る。
④☆の調味料と和えて完成。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー:24kcal◎たんぱく質:1.6g◎脂質:1.2g◎炭水化物:1.9g◎食塩相当量:0.4g
◎エネルギー:24kcal◎たんぱく質:1.6g◎脂質:1.2g◎炭水化物:1.9g◎食塩相当量:0.4g
管理栄養士 梅原
2026年1月号
七草粥を食べて無病息災を願おう
明けましておめでとうございます。本年も栄養科通信をよろしくお願い致します。
七草粥をは、一般的には人日の節句(毎年1月7日)の朝に食べられるものを指し、七日粥ともいいます。
人日の節句は、五節句の1つで、七草の入ったお粥を食べ、無病息災を願います。
七草粥は「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の春の七草を用います。
●せり:セリ科の多年草
●なずな:アブラナ科の越年草
●ごぎょう:ははこぐさ キク科の越年草
●はこべら:はこべ ナデシコ科の越年草
●ほとけのざ:シソ科の越年草
●すずな:かぶの古い呼び名
●すずしろ:大根の古い呼び名
この七草をお粥にして1月7日に食べる七草粥の習慣は江戸時代に広まったそうです。
七草の若芽を食べて、植物がもつ生命力を取り入れ、無病息災でいられるようにという願いが込められています。七草には縁起の良い意味があり、例えばせりは「競り勝つ」、なずなは「なでて汚れをはらう」などと言われています。
今回は七草粥のレシピを紹介します。
七草粥をは、一般的には人日の節句(毎年1月7日)の朝に食べられるものを指し、七日粥ともいいます。
人日の節句は、五節句の1つで、七草の入ったお粥を食べ、無病息災を願います。
七草粥は「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の春の七草を用います。
●せり:セリ科の多年草
●なずな:アブラナ科の越年草
●ごぎょう:ははこぐさ キク科の越年草
●はこべら:はこべ ナデシコ科の越年草
●ほとけのざ:シソ科の越年草
●すずな:かぶの古い呼び名
●すずしろ:大根の古い呼び名
この七草をお粥にして1月7日に食べる七草粥の習慣は江戸時代に広まったそうです。
七草の若芽を食べて、植物がもつ生命力を取り入れ、無病息災でいられるようにという願いが込められています。七草には縁起の良い意味があり、例えばせりは「競り勝つ」、なずなは「なでて汚れをはらう」などと言われています。
今回は七草粥のレシピを紹介します。
七草粥のレシピ(4人分)の作り方(大根、大根葉、かぶ、かぶの葉で栄養計算)

【作り方】
①米飯はざるに入れ、流水でさっと洗い、粘りを取る。
②鍋に①の米飯と水を入れ、ふたをして強火にかける。
③炊いている間に別の鍋に塩を入れた湯を沸かし、七草を入れてさっとゆで、ざるにあげて水気を切ったらお好みの大きさに刻む。
④ぐつぐつと沸騰してきたら、火を弱くしてふたをずらし、30~40分煮る。
⑤炊き上がったら、刻んだ七草を入れて、塩少々で調味する。
①米飯はざるに入れ、流水でさっと洗い、粘りを取る。
②鍋に①の米飯と水を入れ、ふたをして強火にかける。
③炊いている間に別の鍋に塩を入れた湯を沸かし、七草を入れてさっとゆで、ざるにあげて水気を切ったらお好みの大きさに刻む。
④ぐつぐつと沸騰してきたら、火を弱くしてふたをずらし、30~40分煮る。
⑤炊き上がったら、刻んだ七草を入れて、塩少々で調味する。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー:122kcal◎たんぱく質:2.2g◎脂質:1.0g◎炭水化物:29.7g◎脂質:1.0g◎食塩相当量:0.3g
◎エネルギー:122kcal◎たんぱく質:2.2g◎脂質:1.0g◎炭水化物:29.7g◎脂質:1.0g◎食塩相当量:0.3g
管理栄養士 小倉
2025年12月号
身体を温めるしょうがの力とは?
調味料や香辛料として使われるしょうがは、寒くなってきた季節におすすめの食材です。
●冷え症改善
しょうがに含まれるガラノラクトンや辛み成分のジンゲロールは血管を拡張させることで、血流がよくなり、血行不良による冷え性、肩こりなどの改善が期待できます。
また、しょうがを加熱するとジンゲロールの一部がショウガオールという成分に変化し、熱をつくり出す働きをするため、冷え症の改善に効果的です。
●殺菌効果
しょうがに含まれているジンゲロン・ショウガオールには、殺菌効果があり、食中毒の予防や、風邪の原因となる細菌の殺菌効果が期待できます。
●咳や喉の痛みの緩和
しょうがに含まれるガラノラクトン、ジンゲロールは、咳や喉の痛みを緩和する効果があると言われています。生のしょうがに含まれるジンゲロールは鎮痛作用があります。
しょうがは「食べ物にも薬にもなる」と言われており薬膳にも頻繁に登場します。
薬膳には身体を温める作用のある「陽」の食材と、身体を冷やす作用のある「陰」の食材に分かれています。冬の身体が冷え込みやすい時期は「陽」の食材を上手に活用することが体調を整えるカギのひとつにもなります。しょうがは「陽」の食材と言われています。
おいしくて手軽に手に入るしょうがを用いたレシピを紹介します。
●冷え症改善
しょうがに含まれるガラノラクトンや辛み成分のジンゲロールは血管を拡張させることで、血流がよくなり、血行不良による冷え性、肩こりなどの改善が期待できます。
また、しょうがを加熱するとジンゲロールの一部がショウガオールという成分に変化し、熱をつくり出す働きをするため、冷え症の改善に効果的です。
●殺菌効果
しょうがに含まれているジンゲロン・ショウガオールには、殺菌効果があり、食中毒の予防や、風邪の原因となる細菌の殺菌効果が期待できます。
●咳や喉の痛みの緩和
しょうがに含まれるガラノラクトン、ジンゲロールは、咳や喉の痛みを緩和する効果があると言われています。生のしょうがに含まれるジンゲロールは鎮痛作用があります。
しょうがは「食べ物にも薬にもなる」と言われており薬膳にも頻繁に登場します。
薬膳には身体を温める作用のある「陽」の食材と、身体を冷やす作用のある「陰」の食材に分かれています。冬の身体が冷え込みやすい時期は「陽」の食材を上手に活用することが体調を整えるカギのひとつにもなります。しょうがは「陽」の食材と言われています。
おいしくて手軽に手に入るしょうがを用いたレシピを紹介します。
しょうがとしらすの炊き込みご飯(4人分)の作り方

【作り方】
①米は研いでざるに上げる。しょうがは千切りにする。
②炊飯器に米を入れてお好みの水加減にし、大さじ1杯分の水を取り除く。酒、醤油を加えてよく混ぜ合わせ、しょうがをまんべんなく全体にのせて炊く。
③炊き上がったら5分ほど蒸らし、混ぜ合わせる。
④茶碗に盛付け、しらすと小ネギを乗せる。
①米は研いでざるに上げる。しょうがは千切りにする。
②炊飯器に米を入れてお好みの水加減にし、大さじ1杯分の水を取り除く。酒、醤油を加えてよく混ぜ合わせ、しょうがをまんべんなく全体にのせて炊く。
③炊き上がったら5分ほど蒸らし、混ぜ合わせる。
④茶碗に盛付け、しらすと小ネギを乗せる。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー:345kcal◎たんぱく質:7.9g◎脂質:1.0g◎炭水化物:71.3g◎食塩相当量:0.9g
◎エネルギー:345kcal◎たんぱく質:7.9g◎脂質:1.0g◎炭水化物:71.3g◎食塩相当量:0.9g
管理栄養士 秦野
2025年11月号
こたつにみかん!みかんは風邪予防にもなる!?
みかんは年中スーパーなどで見かけますが、10月から4月にかけて旬を迎える果物です。みかんの品種は日本で生産されているものだけでおよそ80種類と多く、旬は品種や産地によって異なります。「温州みかん」は11月上旬から1月下旬が旬といわれています。 みかんには様々な栄養素が豊富に含まれており、多くの健康効果が期待できます。
●ビタミンC
肌の構成成分であるコラーゲン作りをサポートするだけでなく、抗酸化作用によってシミやくすみの原因となる活性酸素を取り除く効果も期待できます。
●β-クリプトキサンチン
みかんの色素成分であり、身体の酸化による老化から守る抗酸化物質として働きます。また、皮膚を健やかに保つ働きや骨の健康にも役立ちます。
●ペクチン
食物繊維であり、不溶性ペクチンと水溶性ペクチンどちらも含んでいます。これらは糖が身体に吸収されるのを遅くする働きや、腸の有害物質と結合し便として体の外に出る働きがあります。腸の有害物質が減ることによって腸内環境が良くなり、便秘の解消や吹き出物の予防ができます。
ところで皆さんはみかんの白い筋を取って食べますか?それともそのまま食べますか?
好みが分かれるこの白い筋ですが、これらにもペクチンとヘスペリジンという栄養成分が豊富に含まれています。へスペリジンは、柑橘類に含まれるポリフェノールであり、血圧を下げる効果、血管を縮める効果、毛細血管を強くする効果があります。血流を改善することで、巡りがよくなり、熱が全身のすみずみに行き届くため、冷えの改善が期待できます。これから寒くなる季節になりますが、冷えの改善だけでなく、インフルエンザや風邪予防の観点から健康のためにも「みかん」を食べてみてもいいかもしれません。
今回はみかんを使ったレシピを紹介します。
●ビタミンC
肌の構成成分であるコラーゲン作りをサポートするだけでなく、抗酸化作用によってシミやくすみの原因となる活性酸素を取り除く効果も期待できます。
●β-クリプトキサンチン
みかんの色素成分であり、身体の酸化による老化から守る抗酸化物質として働きます。また、皮膚を健やかに保つ働きや骨の健康にも役立ちます。
●ペクチン
食物繊維であり、不溶性ペクチンと水溶性ペクチンどちらも含んでいます。これらは糖が身体に吸収されるのを遅くする働きや、腸の有害物質と結合し便として体の外に出る働きがあります。腸の有害物質が減ることによって腸内環境が良くなり、便秘の解消や吹き出物の予防ができます。
ところで皆さんはみかんの白い筋を取って食べますか?それともそのまま食べますか?
好みが分かれるこの白い筋ですが、これらにもペクチンとヘスペリジンという栄養成分が豊富に含まれています。へスペリジンは、柑橘類に含まれるポリフェノールであり、血圧を下げる効果、血管を縮める効果、毛細血管を強くする効果があります。血流を改善することで、巡りがよくなり、熱が全身のすみずみに行き届くため、冷えの改善が期待できます。これから寒くなる季節になりますが、冷えの改善だけでなく、インフルエンザや風邪予防の観点から健康のためにも「みかん」を食べてみてもいいかもしれません。
今回はみかんを使ったレシピを紹介します。
みかんの牛乳寒天(4人分)の作り方

【作り方】
①牛乳を常温に戻しておく。
②鍋に水、粉寒天を入れて混ぜ、中火で加熱する。沸騰したら弱火にし、混ぜながら2〜3分加熱し、火を止める。
③砂糖を加えて混ぜて溶かし、粗熱が取れたら牛乳を加えて混ぜる。
④カップに③を等分に流し入れ、みかんを等分に入れる。冷蔵庫で30分以上冷やし固める。
①牛乳を常温に戻しておく。
②鍋に水、粉寒天を入れて混ぜ、中火で加熱する。沸騰したら弱火にし、混ぜながら2〜3分加熱し、火を止める。
③砂糖を加えて混ぜて溶かし、粗熱が取れたら牛乳を加えて混ぜる。
④カップに③を等分に流し入れ、みかんを等分に入れる。冷蔵庫で30分以上冷やし固める。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー:136kcal◎たんぱく質:3.5g◎脂質:3.8g◎炭水化物:22.8g◎食塩相当量:0.1g
◎エネルギー:136kcal◎たんぱく質:3.5g◎脂質:3.8g◎炭水化物:22.8g◎食塩相当量:0.1g
管理栄養士 梅原
2025年10月号
いわしは弱くない?栄養豊富な魚です!
10月4日は「いわしの日」です。語呂合わせで、い(1)、わ(0)、し(4)となることから、大阪府多獲性魚有効利用検討会(現・大阪おさかな健康食品協議会)が1985年に制定しました。この日は安くて美味しく栄養豊富ないわしを全国にPRし、水産資源の有効利用について理解を深めることを目的としています。いわしには生活習慣病の予防に役立つ栄養素が多く含まれています。血中の中性脂肪を減少させる働きがあり、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを低減されるとされています。また骨粗鬆症の予防や脳の活性化、美肌効果も期待できると言われています。
10月4日いわしの日は私たちにいわしの素晴らしさを再認識させてくれる絶好の機会です。日本の食文化に深く根付くいわしの驚くべき効能と多彩な調理法をぜひこの機会に楽しんでください。
いわしの種類:まいわし、うるめいわし、かたくちいわしなど
栄養:良質なたんぱく質、脂質、オメガ3脂肪酸のエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)、カルシウム、鉄、マグネシウム、リン、タウリン、ビタミンDやB群などが豊富
食べ方:煮干し、めざし、ちりめんじゃこ、田作りなど
10月4日いわしの日は私たちにいわしの素晴らしさを再認識させてくれる絶好の機会です。日本の食文化に深く根付くいわしの驚くべき効能と多彩な調理法をぜひこの機会に楽しんでください。
いわしの種類:まいわし、うるめいわし、かたくちいわしなど
栄養:良質なたんぱく質、脂質、オメガ3脂肪酸のエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)、カルシウム、鉄、マグネシウム、リン、タウリン、ビタミンDやB群などが豊富
食べ方:煮干し、めざし、ちりめんじゃこ、田作りなど
いわしのフレッシュサルサソースかけ(1人分)の作り方

【作り方】
①いわしの頭を落とし、はらわたを取る。
②小麦粉とカレー粉を混ぜたものをいわしにまぶし、サラダ油を引いたフライパンで焼き目がつくまで両面焼く。
③トマトを1センチ角に切って、オリーブ油、醤油、こしょう、パセリを混ぜ合わせて、②のいわしの上に乗せる。
①いわしの頭を落とし、はらわたを取る。
②小麦粉とカレー粉を混ぜたものをいわしにまぶし、サラダ油を引いたフライパンで焼き目がつくまで両面焼く。
③トマトを1センチ角に切って、オリーブ油、醤油、こしょう、パセリを混ぜ合わせて、②のいわしの上に乗せる。
| 材料 |
|---|
(フレッシュサルサソース)
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー:202kcal◎たんぱく質:14.5g◎脂質:14.5g◎炭水化物:13.0g◎食塩相当量:1.2g
◎エネルギー:202kcal◎たんぱく質:14.5g◎脂質:14.5g◎炭水化物:13.0g◎食塩相当量:1.2g
管理栄養士 小倉
2025年9月号
重陽(ちょうよう)の節句をご存じですか?
9月9日は「重陽の節句」と呼ばれる五節句の1つです。「9」という数字は、中国では最も縁起のよい数字(陽)とされ、その2つの数字が重なる日であるため、「重陽の節句」と呼ばれます。
重陽の節句の時期は菊の咲く季節であるため、「菊の節句」とも呼ばれます。寿命を延ばす力があるとされた菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を飲んだりして不老長寿を願います。重陽の節句には「収穫祭」の意味合いも含まれているため、栗やなすを使った料理で秋の味覚を楽しみます。
●栗
栗には、摂取した糖質をエネルギーに変える代謝をサポートするビタミンB1や肌荒れ防止に効果のあるビタミンCが含まれています。また、栗の渋皮に含まれるタンニンは抗酸化作用があり、身体の組織や血管などの老化防止効果があると言われています。
●秋なす
秋なすは健康を願う食材として昔から親しまれている食材です。なすにはナスニンと呼ばれるポリフェノールが含まれています。栗のタンニンと同じく抗酸化作用があります。また、カリウムも含まれているため、余分な塩分や水分を体外に排出する働きがあり、むくみ改善に効果的です。
●菊
長寿の象徴とされる菊は、お浸しや和え物、天ぷらや吸い物などの様々な料理に加えるなどして楽しまれています。また、菊や菊の花びらをモチーフにしたスイーツで気軽に楽しむことができます。
今回は秋なすを使ったレシピをご紹介します。秋の味覚をおいしく頂きましょう。
重陽の節句の時期は菊の咲く季節であるため、「菊の節句」とも呼ばれます。寿命を延ばす力があるとされた菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を飲んだりして不老長寿を願います。重陽の節句には「収穫祭」の意味合いも含まれているため、栗やなすを使った料理で秋の味覚を楽しみます。
●栗
栗には、摂取した糖質をエネルギーに変える代謝をサポートするビタミンB1や肌荒れ防止に効果のあるビタミンCが含まれています。また、栗の渋皮に含まれるタンニンは抗酸化作用があり、身体の組織や血管などの老化防止効果があると言われています。
●秋なす
秋なすは健康を願う食材として昔から親しまれている食材です。なすにはナスニンと呼ばれるポリフェノールが含まれています。栗のタンニンと同じく抗酸化作用があります。また、カリウムも含まれているため、余分な塩分や水分を体外に排出する働きがあり、むくみ改善に効果的です。
●菊
長寿の象徴とされる菊は、お浸しや和え物、天ぷらや吸い物などの様々な料理に加えるなどして楽しまれています。また、菊や菊の花びらをモチーフにしたスイーツで気軽に楽しむことができます。
今回は秋なすを使ったレシピをご紹介します。秋の味覚をおいしく頂きましょう。
秋なすの煮浸し(2人分)の作り方

【作り方】
①なすのへたを切る。縦半分に切り、皮側に5mm程度の間隔で斜めに切り込みをいれる。
②熱したフライパンにサラダ油を入れ、なすの皮を下にして中火で焼く。
③なすの皮が全体的に綺麗な紫色になったらひっくり返し裏側を焼く。
④☆の調味料を加え、煮立ててから5分程度煮る。
⑤④のなすを器に盛付けて、煮汁を少しかけ、いりごまを散らし完成。
①なすのへたを切る。縦半分に切り、皮側に5mm程度の間隔で斜めに切り込みをいれる。
②熱したフライパンにサラダ油を入れ、なすの皮を下にして中火で焼く。
③なすの皮が全体的に綺麗な紫色になったらひっくり返し裏側を焼く。
④☆の調味料を加え、煮立ててから5分程度煮る。
⑤④のなすを器に盛付けて、煮汁を少しかけ、いりごまを散らし完成。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー:110kcal◎たんぱく質:2.2g◎脂質:7.2g◎炭水化物:8.8g◎食塩相当量:1.2g
◎エネルギー:110kcal◎たんぱく質:2.2g◎脂質:7.2g◎炭水化物:8.8g◎食塩相当量:1.2g
管理栄養士 秦野
2025年8月号
夏バテに負けない身体は食事から
今年の夏も中盤にさしかかっていますが、いまだ気温の高い日々が続いています。気温の高い夏には身体に様々な不調が見られることがあり、そのような症状をまとめて「夏バテ」といいます。夏バテの症状として食欲不振や倦怠感、全身の疲労感そして吐き気などが代表的です。免疫力が低下している身体状況が続くと他の感染症にもかかりやすくなってしまいます。年々厳しさを増す猛暑に負けないためにも、今回は夏バテ対策に効果のある栄養素とおすすめの食材について紹介します。
●たんぱく質:肉・魚・卵・豆腐などの大豆製品・乳製品など
→筋肉の疲労回復や基礎代謝向上の効果。不足すると体力低下や疲労感を感じやすくなる。
●ビタミンB群:B1 豚肉・大豆・玄米など/B2 サバ、イワシ等の青魚・レバー・牛乳・卵など
→炭水化物をエネルギーに変換するため、疲労回復の効果。不足すると倦怠感や疲労感を感じやすい。
●ビタミンC:野菜(ブロッコリー・ピーマンなど)・果物(アセロラ・柑橘類など)・さつまいも
→ストレス耐性の向上や疲労回復の効果。暑さや紫外線の刺激により、不足しがちな栄養素である。
●ミネラル:野菜・キノコ類・海藻類・豆類など
→発汗とともに失われ、不足しやすい栄養素。不足すると倦怠感や疲労感を感じやすい。
次に夏バテ対策に効果のある食材を使用したレシピを紹介します。
●たんぱく質:肉・魚・卵・豆腐などの大豆製品・乳製品など
→筋肉の疲労回復や基礎代謝向上の効果。不足すると体力低下や疲労感を感じやすくなる。
●ビタミンB群:B1 豚肉・大豆・玄米など/B2 サバ、イワシ等の青魚・レバー・牛乳・卵など
→炭水化物をエネルギーに変換するため、疲労回復の効果。不足すると倦怠感や疲労感を感じやすい。
●ビタミンC:野菜(ブロッコリー・ピーマンなど)・果物(アセロラ・柑橘類など)・さつまいも
→ストレス耐性の向上や疲労回復の効果。暑さや紫外線の刺激により、不足しがちな栄養素である。
●ミネラル:野菜・キノコ類・海藻類・豆類など
→発汗とともに失われ、不足しやすい栄養素。不足すると倦怠感や疲労感を感じやすい。
次に夏バテ対策に効果のある食材を使用したレシピを紹介します。
夏野菜のドライカレー(3人分)の作り方

【作り方】
①材料の玉ねぎ、なす、じゃがいも、にんじん、しめじをみじん切りする。
②熱したフライパンにサラダ油をひき、おろし生姜を加えて炒め、香りが出たら豚挽肉に塩こしょうを振り炒める。
③①でみじん切りした材料を加え、中火で3〜5分具材に火が通るまで炒める。
④☆の調味料を加え、汁気がなくなるまで炒める。
⑤皿に盛り付けたら完成。
①材料の玉ねぎ、なす、じゃがいも、にんじん、しめじをみじん切りする。
②熱したフライパンにサラダ油をひき、おろし生姜を加えて炒め、香りが出たら豚挽肉に塩こしょうを振り炒める。
③①でみじん切りした材料を加え、中火で3〜5分具材に火が通るまで炒める。
④☆の調味料を加え、汁気がなくなるまで炒める。
⑤皿に盛り付けたら完成。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー:346kcal◎たんぱく質:18.3g◎脂質:20.5g◎炭水化物:19.4g◎食塩相当量:1.4g
◎エネルギー:346kcal◎たんぱく質:18.3g◎脂質:20.5g◎炭水化物:19.4g◎食塩相当量:1.4g
管理栄養士 梅原
2025年7月号
土用の丑の日
2025年の土用の丑の日は、7月19日(土)と7月31日(木)で、7月19日を一の丑、7月31日を二の丑と呼びます。
土用は立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前一八日のことで、土用の丑の日は、その中の丑に当たる日です。特に夏の土用の丑の日にはうなぎを食べる習慣が定着しています。うなぎを食べる理由は江戸時代に平賀源内がうなぎを食べることで、夏バテを防ぐという提案をしたことがきっかけで、うなぎを食べる習慣が広まりました。
うなぎ以外にも、うどんや梅干し、瓜科の野菜、牛肉など「う」のつく食べ物や、黒い食べ物、土用餅、土用しじみなども食べられていました。
◎うなぎ
現在最もポピュラーで、栄養価が高く夏バテ対策に効果的であるとされています。
◎うどん
暑い日でも食べやすく、体調を整えるのに役立つ食材として食べられています。
◎梅干し
消化を助け、腸内環境を整える働きがあるため、夏場に特に食べられる習慣があります。
◎瓜(ウリ)
きゅうり、すいか、カボチャなど夏が旬の瓜類はビタミンも豊富で、体のほてりや熱をとる効果があります。
◎黒い食べ物
しじみ、どじょう、なす、黒豆、黒ごまなども、土用の丑の日に食べられる風習があります。
土用は季節の変わり目であるため、体調を崩しやすい時期です。そのため、土用の期間中は、滋養のあるものを食べる、早寝早起きを心がけるなど、健康に気をつけるようにしましょう。
土用は立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前一八日のことで、土用の丑の日は、その中の丑に当たる日です。特に夏の土用の丑の日にはうなぎを食べる習慣が定着しています。うなぎを食べる理由は江戸時代に平賀源内がうなぎを食べることで、夏バテを防ぐという提案をしたことがきっかけで、うなぎを食べる習慣が広まりました。
うなぎ以外にも、うどんや梅干し、瓜科の野菜、牛肉など「う」のつく食べ物や、黒い食べ物、土用餅、土用しじみなども食べられていました。
◎うなぎ
現在最もポピュラーで、栄養価が高く夏バテ対策に効果的であるとされています。
◎うどん
暑い日でも食べやすく、体調を整えるのに役立つ食材として食べられています。
◎梅干し
消化を助け、腸内環境を整える働きがあるため、夏場に特に食べられる習慣があります。
◎瓜(ウリ)
きゅうり、すいか、カボチャなど夏が旬の瓜類はビタミンも豊富で、体のほてりや熱をとる効果があります。
◎黒い食べ物
しじみ、どじょう、なす、黒豆、黒ごまなども、土用の丑の日に食べられる風習があります。
土用は季節の変わり目であるため、体調を崩しやすい時期です。そのため、土用の期間中は、滋養のあるものを食べる、早寝早起きを心がけるなど、健康に気をつけるようにしましょう。
うなぎときゅうりの酢の物(2人分)の作り方

【作り方】
① きゅうりは千切りにして、塩で軽くもむ。
②うなぎは1センチ幅に切る。
③☆の調味料を混ぜて、①と②と和える。
④器に盛り付け、山椒を少々上から振りかけて完成。
① きゅうりは千切りにして、塩で軽くもむ。
②うなぎは1センチ幅に切る。
③☆の調味料を混ぜて、①と②と和える。
④器に盛り付け、山椒を少々上から振りかけて完成。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分 (1人分あたり)】
◎エネルギー:142kcal◎たんぱく質:8.5g◎脂質:7.8g◎炭水化物:8.7g◎塩分:2.4g
◎エネルギー:142kcal◎たんぱく質:8.5g◎脂質:7.8g◎炭水化物:8.7g◎塩分:2.4g
管理栄養士 小倉
2025年6月号
梅雨に負けない3つの食事ポイント
梅雨の季節は雨や曇りが続き、湿気が多く、変わりやすい天候は身体にとってストレスとなります。体調を崩しやすいこの季節に注意してほしいポイントをご紹介します。
【1日3食食べて必要な栄養補給を】1回の食事で食べられる量には限りがあり、欠食してしまうと栄養が不足してしまいます。体調を崩し食欲がなくなると更に栄養が不足してしまうため、3食食べて必要な栄養を摂取しましょう。
【主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食事を】主食は身体のエネルギー源になり、主菜は身体を作るもとになり、副菜は身体の調子を整えるものになります。この3つをそろえたバランスのよい食事を心がけましょう。
【疲労回復効果のある食材を】梅雨は自律神経が乱れて疲れやすくなるため、疲労回復効果のある食材を意識して摂取するとよいとされています。
◎ビタミンB群:ビタミンB群は食べたものをエネルギーに変える「代謝」を行う際に役立つ栄養素です。不足すると代謝が上手くいかず、エネルギーが十分作られない状態になり、疲れやすくなります。ビタミンB群は豚肉や鶏肉、マグロやカツオなどの赤身の魚、大豆やゴマなどに多く含まれています。
◎クエン酸:クエン酸には疲れの原因である「乳酸」を身体の外へ排出したり、身体の疲労物質を分解したりする働きがあります。クエン酸はみかんやレモンなどの柑橘類や梅干しなどに含まれています。
疲労回復効果のある和え物を紹介します。いつものメニューに追加してみてください。
【1日3食食べて必要な栄養補給を】1回の食事で食べられる量には限りがあり、欠食してしまうと栄養が不足してしまいます。体調を崩し食欲がなくなると更に栄養が不足してしまうため、3食食べて必要な栄養を摂取しましょう。
【主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食事を】主食は身体のエネルギー源になり、主菜は身体を作るもとになり、副菜は身体の調子を整えるものになります。この3つをそろえたバランスのよい食事を心がけましょう。
【疲労回復効果のある食材を】梅雨は自律神経が乱れて疲れやすくなるため、疲労回復効果のある食材を意識して摂取するとよいとされています。
◎ビタミンB群:ビタミンB群は食べたものをエネルギーに変える「代謝」を行う際に役立つ栄養素です。不足すると代謝が上手くいかず、エネルギーが十分作られない状態になり、疲れやすくなります。ビタミンB群は豚肉や鶏肉、マグロやカツオなどの赤身の魚、大豆やゴマなどに多く含まれています。
◎クエン酸:クエン酸には疲れの原因である「乳酸」を身体の外へ排出したり、身体の疲労物質を分解したりする働きがあります。クエン酸はみかんやレモンなどの柑橘類や梅干しなどに含まれています。
疲労回復効果のある和え物を紹介します。いつものメニューに追加してみてください。
もやしのさっぱり和え(2人分)の作り方
【作り方】
① もやしをゆで、ざるにあげ、水気を絞る。ミョウガは芯を除き千切りにする。
② ①にAの調味料を混ぜ合わせ、盛り付ける。
① もやしをゆで、ざるにあげ、水気を絞る。ミョウガは芯を除き千切りにする。
② ①にAの調味料を混ぜ合わせ、盛り付ける。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分 (1人分あたり)】
◎エネルギー : 63kcal ◎たんぱく質: 3.7g ◎脂質: 3.9g ◎炭水化物: 4.8g ◎食塩相当量: 0.9g
◎エネルギー : 63kcal ◎たんぱく質: 3.7g ◎脂質: 3.9g ◎炭水化物: 4.8g ◎食塩相当量: 0.9g
管理栄養士 秦野
2025年5月号
こどもの日の行事食 ちまき
5月5日は子どもの日です。今回は子どもの日に食べられる行事食、ちまきについてご紹介します。ちまきはこどもの健やかな成長を願って食べられる食べ物で、笹の葉で米や餅を蒸して作られます。関東地方ではおこわとして具材を入れて食べられることが多く、関西地域では白くて甘い餅をちまきと言います。もち米はうるち米に比べてエネルギー、タンパク質が豊富に含まれており、しっかり栄養を摂取できることが特徴です。うるち米には劣りますが食物繊維も多く含まれており、栄養価の高い食品と言えます。今回はちまき風おこわのレシピをご紹介します。炊き込みご飯で野菜も摂取することで不足しがちな食物繊維を補うことができます。
ちまき風おこわ(3人分)の作り方

【作り方】
① もち米を水で洗って水気をきる。
② 干し椎茸を水で戻す。
③ たけのこ水煮、にんじんは皮をむき、干し椎茸は軸を取り、全て1cm角に切る。
④ 豚バラ肉を1cm角に切る。
⑤ ボウルに調味料の材料と干し椎茸の戻し汁を混ぜ合わせる。
⑥ 炊飯器にもち米を入れて⑤を注ぎ規定量の水を入れ混ぜる。
⑦ ⑥に切った具材を入れ、炊飯器で炊く。
⑧ 炊き上がったら器に盛って完成。
① もち米を水で洗って水気をきる。
② 干し椎茸を水で戻す。
③ たけのこ水煮、にんじんは皮をむき、干し椎茸は軸を取り、全て1cm角に切る。
④ 豚バラ肉を1cm角に切る。
⑤ ボウルに調味料の材料と干し椎茸の戻し汁を混ぜ合わせる。
⑥ 炊飯器にもち米を入れて⑤を注ぎ規定量の水を入れ混ぜる。
⑦ ⑥に切った具材を入れ、炊飯器で炊く。
⑧ 炊き上がったら器に盛って完成。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分 (1人分あたり)】
◎エネルギー : 534kcal ◎たんぱく質: 13.7g ◎脂質: 16.2g ◎炭水化物: 86.6g ◎食塩相当量: 1.4g
◎エネルギー : 534kcal ◎たんぱく質: 13.7g ◎脂質: 16.2g ◎炭水化物: 86.6g ◎食塩相当量: 1.4g
管理栄養士 石田
2025年3月号
菜の花を食べて免疫力アップ
3月は菜の花が旬の季節です。菜の花には免疫力を高める栄養素が多く含まれていることが特徴です。今回は菜の花の栄養素についてご紹介します。
【ビタミンC】菜の花は同量のレモンよりビタミンCが多く含まれており野菜の中でもトップクラスです。酸化防止作用があり、ダメージから細胞を守るのを助けます。また、体の治癒に必要なコラーゲンを生成するためにも必要な栄養素であり、傷や炎症の治りを助ける役割を果たします。水溶性のビタミンのため、調理の際に茹ですぎない、水にさらしすぎないことがポイントです。
【ビタミンE】ビタミンCと同様に、強い抗酸化作用があり、ダメージから細胞を守るのを助けます。免疫力を高め、体内に侵入してくる細菌やウイルスを撃退するためにも必要な栄養素です。また、血行拡張を促し、血管内で血液が凝固するのを防ぐ働きもあります。
【βカロテン】βカロテンは体内でビタミンAへ変換される性質を持ちます。ビタミンAとして、目の機能や免疫システムの維持、臓器が適切に機能することを助けます。また、ビタミンAに変換されず残ったβカロテンは抗酸化物質として効果を発揮します。
【ビタミンC】菜の花は同量のレモンよりビタミンCが多く含まれており野菜の中でもトップクラスです。酸化防止作用があり、ダメージから細胞を守るのを助けます。また、体の治癒に必要なコラーゲンを生成するためにも必要な栄養素であり、傷や炎症の治りを助ける役割を果たします。水溶性のビタミンのため、調理の際に茹ですぎない、水にさらしすぎないことがポイントです。
【ビタミンE】ビタミンCと同様に、強い抗酸化作用があり、ダメージから細胞を守るのを助けます。免疫力を高め、体内に侵入してくる細菌やウイルスを撃退するためにも必要な栄養素です。また、血行拡張を促し、血管内で血液が凝固するのを防ぐ働きもあります。
【βカロテン】βカロテンは体内でビタミンAへ変換される性質を持ちます。ビタミンAとして、目の機能や免疫システムの維持、臓器が適切に機能することを助けます。また、ビタミンAに変換されず残ったβカロテンは抗酸化物質として効果を発揮します。
菜の花の白和え(2人分)の作り方
【作り方】
① 菜の花を塩小さじ1を入れたお湯で茹でる。
② ①を冷水にとり、ぎゅっと絞って水気を切って、食べやすい大きさに切る。(和え衣)
③ 豆腐をなめらかになるまで混ぜ、醤油、砂糖、すりごまを加えて混ぜる。
④ ②の菜の花を③の和え衣と和える。
⑤ ④を盛り付けた上に茹で卵の卵黄を細かく潰し、黄色い花のように盛り付けて完成。
① 菜の花を塩小さじ1を入れたお湯で茹でる。
② ①を冷水にとり、ぎゅっと絞って水気を切って、食べやすい大きさに切る。(和え衣)
③ 豆腐をなめらかになるまで混ぜ、醤油、砂糖、すりごまを加えて混ぜる。
④ ②の菜の花を③の和え衣と和える。
⑤ ④を盛り付けた上に茹で卵の卵黄を細かく潰し、黄色い花のように盛り付けて完成。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー: 56kcal ◎たんぱく質: 5.1g ◎脂質: 2.3g ◎炭水化物: 5.3g ◎食塩相当量: 0.5g
◎エネルギー: 56kcal ◎たんぱく質: 5.1g ◎脂質: 2.3g ◎炭水化物: 5.3g ◎食塩相当量: 0.5g
管理栄養士 石田
2025年2月号
知られざる大豆の健康効果
今年の節分は2月2日です。邪を払い福と春を呼び込む行事として古くから行われてきました。節分といえば福豆。年の数の炒り大豆を食べることで、無病息災になるといわれています。今回は大豆の代表的な栄養素と健康効果についてご紹介します。
【大豆の代表的な栄養素】
◎たんぱく質体を作るもととなるたんぱく質。大豆には、肉や魚と同じくらい良質なたんぱく質が豊富に含まれており、昔から「畑の肉」とも言われています。
【健康効果】
◎脂肪燃焼効果大豆に含まれるたんぱく質には、コレステロールを減らす、脂質の代謝を促進するなどの働きがあります。また、大豆たんぱく質の主要成分である「β-コングリシニン」は、肝臓での脂肪酸の合成を抑制して脂肪の燃焼を促進させてくれます。◎腸内環境を整える大豆には、腸内環境を整える大豆オリゴ糖が含まれています。ビフィズス菌や乳酸菌などの餌となって、善玉菌を増やす効果が期待できるため、便秘の改善に役立ちます。
今回は、蒸し大豆を使って手軽にできる、ご飯のお供レシピをご紹介します。
【大豆の代表的な栄養素】
◎たんぱく質体を作るもととなるたんぱく質。大豆には、肉や魚と同じくらい良質なたんぱく質が豊富に含まれており、昔から「畑の肉」とも言われています。
【健康効果】
◎脂肪燃焼効果大豆に含まれるたんぱく質には、コレステロールを減らす、脂質の代謝を促進するなどの働きがあります。また、大豆たんぱく質の主要成分である「β-コングリシニン」は、肝臓での脂肪酸の合成を抑制して脂肪の燃焼を促進させてくれます。◎腸内環境を整える大豆には、腸内環境を整える大豆オリゴ糖が含まれています。ビフィズス菌や乳酸菌などの餌となって、善玉菌を増やす効果が期待できるため、便秘の改善に役立ちます。
今回は、蒸し大豆を使って手軽にできる、ご飯のお供レシピをご紹介します。
大豆の甘辛炒め(4人分)の作り方
【作り方】
① 大豆に片栗粉をまぶし、上からサラダ油を絡める。
② フライパンに①を入れ、蓋をして1~2分蒸し焼きにする。
③ 全体に焼き色がつき、もっちりして豆同士がくっつくようになってきたら弱火にして、砂糖、みりん、醤油を加えて絡める。
④ 最後に、白ごまを振って完成。
① 大豆に片栗粉をまぶし、上からサラダ油を絡める。
② フライパンに①を入れ、蓋をして1~2分蒸し焼きにする。
③ 全体に焼き色がつき、もっちりして豆同士がくっつくようになってきたら弱火にして、砂糖、みりん、醤油を加えて絡める。
④ 最後に、白ごまを振って完成。
| 材料 |
|---|
|
【栄養成分(1人分あたり)】
◎エネルギー: 107kcal ◎たんぱく質: 4.55g ◎脂質: 5.1g ◎炭水化物: 9.8g ◎食塩相当量: .6g
◎エネルギー: 107kcal ◎たんぱく質: 4.55g ◎脂質: 5.1g ◎炭水化物: 9.8g ◎食塩相当量: .6g
管理栄養士 土屋
2025年1月号
お雑煮
お雑煮は、お正月に食べる伝統的な日本料理です。お雑煮の歴史は古く、平安時代から食べられていました。当時、お餅は農耕民族である日本人にとって、「ハレの日」に食べるおめでたい食べ物でした。里芋やお餅、にんじん、大根などを、その年の最初に井戸や川から汲んだ若水と、新年初めての火で時間をかけて煮込み、 元日に食べたことが始まりだと言われています。お雑煮の中には、お餅の他に里芋やにんじん、大根などの具材が入っています。具材それぞれに意味があることを知っていますか。
●里芋...子芋をたくさんつけるため、子孫繁栄。
●大根...角が立たないように丸く切って家庭円満。
●にんじん...赤色であるため魔除けの効果
また、地域によって味付けの特徴が異なります。関西地方のお雑煮は白味噌仕立てが多く、一方で、近畿地方を除く西日本と関東地方では、すまし汁で仕立てることが多いようです。能登半島や出雲地方では小豆の入ったお雑煮が食べられています。
●里芋...子芋をたくさんつけるため、子孫繁栄。
●大根...角が立たないように丸く切って家庭円満。
●にんじん...赤色であるため魔除けの効果
また、地域によって味付けの特徴が異なります。関西地方のお雑煮は白味噌仕立てが多く、一方で、近畿地方を除く西日本と関東地方では、すまし汁で仕立てることが多いようです。能登半島や出雲地方では小豆の入ったお雑煮が食べられています。
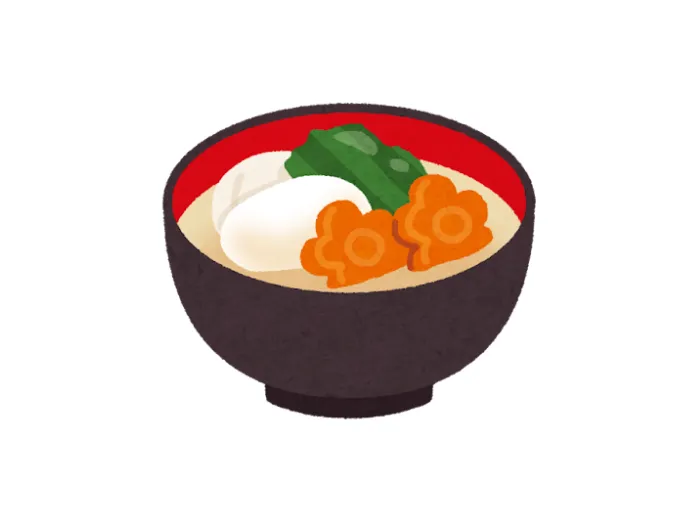
お餅の豆知識
白米のうるち米と餅の原材料のもち米では、でんぷんのアミロースとアミロペクチンの割合が異なります。お餅は消化しやすく腹持ちが良いです。さらに、よく噛むことで満腹中枢が刺激されるため早く満腹になりやすいです。しかし、消化しやすい分血糖値も上がりやすいので、食物繊維の多い野菜やキノコ類、海藻類、たんぱく質などを組み合わせたお雑煮にするとさらに腹持ちが良くなります。冷めた状態のお餅は消化不良の原因となるため、温かいうちにいただきましょう。今年のお正月は、いつもと違ったお雑煮を食べてみるのも良いかもしれませんね。
管理栄養士 杉田

