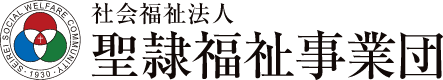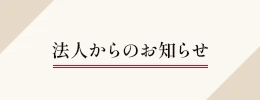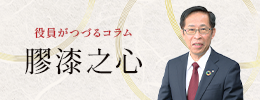聖隷カーネーションホーム 聖隷在宅介護支援センター淡路 「コロナ禍での認知症サポーター養成講座の普及活動」
「コロナ禍での認知症サポーター養成講座の普及活動」の取り組み

淡路市では、全国平均より高い水準で少子高齢化が進んでおり「認知症、みんなで支える、やさしいまち」を市のスローガンとして、まち全体で認知症サポーター講座に取り組んでいる。当事業所は、2013年から町内会や学校などを中心に「地域で支えあおう」をテーマに認知症サポーター養成講座を開始し、①認知症の理解 ②認知症の方への関わり方 ③グループワーク(みんなで考える)を実践することで、地域住民の意識や支えあいに成果をもたらしている。 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催回数や場所、感染予防策に考慮しながら取り組んだ。
SDGsの関連性
「コロナ禍での認知症サポーター養成講座の普及活動」と関連するSDGsの目標は・・・

3.すべての人に健康と福祉を
11.住み続けられるまちづくりを
17.パートナーシップで目標を達成しよう
新箭 幸平 (あたらしや こうへい)

聖隷カーネーションホーム
聖隷在宅介護支援センター淡路 所長
コロナ禍での認知症サポーター養成講座の普及啓発に取り組んでいる。
聖隷在宅介護支援センター淡路 所長
コロナ禍での認知症サポーター養成講座の普及啓発に取り組んでいる。
河部 義一 (かわべ よしかず)

聖隷カーネーションホーム
聖隷在宅介護支援センター淡路 主任マネジャー
ケアマネジャーとして、認知症の正しい理解を広めている。
聖隷在宅介護支援センター淡路 主任マネジャー
ケアマネジャーとして、認知症の正しい理解を広めている。
インタビュー
①この取り組みを行うきっかけを教えてください。

地域包括ケアシステムの話し合いの場では地域での困りごとを共有。
新箭
買い物の会計時に支払い手順がわからなくなってしまったり、道に迷って家に戻れなくなったりする認知症の方にどう対応したらいいだろうか、という声が地域から寄せられたことです。地域包括ケアシステム※1の話し合いの場で、民生委員の方が地域の困りごととして共有してくださいました。そこで認知症の正しい理解を広めるべく、認知症サポーター養成講座(以下、講座)を開催することになりました。淡路市は、全国に比べて高齢化が加速していますが、地域住民の方達は認知症への知識がさほど多くありませんでした。
河部
以前は、「認知症って風邪みたいにうつるの?」と聞かれたこともありました。私は高校生の頃からボランティアをしていましたが、仕事として関わり始めたのは、1994年頃からです。当時に比べれば、認知症が知られるようになって、理解は深まっているように感じていますが、まずは「認知症とはこういうものだ」と理解していただくことが課題だと思います。その上で、早期から私たち専門職が関わっていくなど今後の展開をしていくことが必要だと考えています。
買い物の会計時に支払い手順がわからなくなってしまったり、道に迷って家に戻れなくなったりする認知症の方にどう対応したらいいだろうか、という声が地域から寄せられたことです。地域包括ケアシステム※1の話し合いの場で、民生委員の方が地域の困りごととして共有してくださいました。そこで認知症の正しい理解を広めるべく、認知症サポーター養成講座(以下、講座)を開催することになりました。淡路市は、全国に比べて高齢化が加速していますが、地域住民の方達は認知症への知識がさほど多くありませんでした。
河部
以前は、「認知症って風邪みたいにうつるの?」と聞かれたこともありました。私は高校生の頃からボランティアをしていましたが、仕事として関わり始めたのは、1994年頃からです。当時に比べれば、認知症が知られるようになって、理解は深まっているように感じていますが、まずは「認知症とはこういうものだ」と理解していただくことが課題だと思います。その上で、早期から私たち専門職が関わっていくなど今後の展開をしていくことが必要だと考えています。
②認知症サポーター養成講座の内容を詳しく教えてください。

講座では寸劇など交えて関心を持ってもらえるよう工夫しています。
※コロナ禍以前の講座のため、マスクを着用していません。
新箭
私たちの地域は年5回講座を開催するという目標を掲げていて、要請があれば行政から私たちの事業所に声がかかります。講座は90分、講義やビデオ上映、寸劇や日常エピソードも交え、聴講層の関心にあわせて構成を考えています。講座は小中学校、地域の町内会やサロンなどが中心ですが、先日は企業の新人職員向けにも開催しました。内容は、認知症はどういった症状や行動があるかなど、認知症への正しい理解を促すものにしています。
誰しも認知症になる可能性があります。受講者にお伝えしたいのは、「認知症になったらダメ」ではなく、世代を超えて、皆で温かい目で見守ることが大切だということです。それにより認知症になっても地域で暮らせる可能性が広がるからです。いつか私たちも歳をとって周りの援助が必要な場面がくるかもしれません。受講者には、困っている高齢者がいたら、「一言『大丈夫ですか?』と声をかけてみよう」という気づきを得てくれた人もいます。
河部
例えば、認知症の方の家族が受講していなくても、地域で正しい理解が広がれば、認知症の方は地域で自分らしく暮らし続けられます。ケアマネジャーという立場から見ると、この講座は、認知症の正しい理解を広めるという点で意義があると思います。理解が広がり、周りに相談できる人や応援者がたくさんいる雰囲気ができれば、認知症の方がいるご家族も問題を抱え込まず、相談しやすくなると思います。以前に比べればオープンになってきていますが、まだ「認知症を知られたくない、周りに迷惑をかけたくない」という雰囲気は残っているように感じますので、これからも講座を続けていく必要があると思います。
私たちの地域は年5回講座を開催するという目標を掲げていて、要請があれば行政から私たちの事業所に声がかかります。講座は90分、講義やビデオ上映、寸劇や日常エピソードも交え、聴講層の関心にあわせて構成を考えています。講座は小中学校、地域の町内会やサロンなどが中心ですが、先日は企業の新人職員向けにも開催しました。内容は、認知症はどういった症状や行動があるかなど、認知症への正しい理解を促すものにしています。
誰しも認知症になる可能性があります。受講者にお伝えしたいのは、「認知症になったらダメ」ではなく、世代を超えて、皆で温かい目で見守ることが大切だということです。それにより認知症になっても地域で暮らせる可能性が広がるからです。いつか私たちも歳をとって周りの援助が必要な場面がくるかもしれません。受講者には、困っている高齢者がいたら、「一言『大丈夫ですか?』と声をかけてみよう」という気づきを得てくれた人もいます。
河部
例えば、認知症の方の家族が受講していなくても、地域で正しい理解が広がれば、認知症の方は地域で自分らしく暮らし続けられます。ケアマネジャーという立場から見ると、この講座は、認知症の正しい理解を広めるという点で意義があると思います。理解が広がり、周りに相談できる人や応援者がたくさんいる雰囲気ができれば、認知症の方がいるご家族も問題を抱え込まず、相談しやすくなると思います。以前に比べればオープンになってきていますが、まだ「認知症を知られたくない、周りに迷惑をかけたくない」という雰囲気は残っているように感じますので、これからも講座を続けていく必要があると思います。
③講座を受講した方々の受講動機や反応を詳しく教えてください。
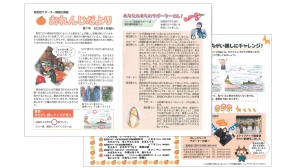
認知症サポーター情報広報誌「おれんじだより」も発行し、認知症の方に優しい地域づくりを促進。
新箭
小学校は、福祉の授業を定期開催する学校が増えてきています。人と人との違いを学び、育む機会を養うためとのことです。生徒たちは感受性が豊かで、「スーパーでお金を払う時に困っていたら声をかけようかな」という着眼点を得てくれた生徒が多くいました。
町内会やサロンでは、認知症に自分がなったらどうするか、同居の家族が認知症でどう接したらいいかを知りたいと開催希望があり、70~80歳代の方々に講座を行っています。実は、町内会やサロンの参加者の中には「同じことを何回もお話しているけど大丈夫かな…」と認知症の心配がある人もいますが、認知症について正しい理解をすることで、「その人の発言や想いを受け止めて守ることが大事なんだ」と気付いてくれた受講者もいました。
私は異動してまだ1年半なので、講座の担当数は多くありませんが、毎回参加するごとに違う反応があるので、自分自身、いい刺激を受けています。
小学校は、福祉の授業を定期開催する学校が増えてきています。人と人との違いを学び、育む機会を養うためとのことです。生徒たちは感受性が豊かで、「スーパーでお金を払う時に困っていたら声をかけようかな」という着眼点を得てくれた生徒が多くいました。
町内会やサロンでは、認知症に自分がなったらどうするか、同居の家族が認知症でどう接したらいいかを知りたいと開催希望があり、70~80歳代の方々に講座を行っています。実は、町内会やサロンの参加者の中には「同じことを何回もお話しているけど大丈夫かな…」と認知症の心配がある人もいますが、認知症について正しい理解をすることで、「その人の発言や想いを受け止めて守ることが大事なんだ」と気付いてくれた受講者もいました。
私は異動してまだ1年半なので、講座の担当数は多くありませんが、毎回参加するごとに違う反応があるので、自分自身、いい刺激を受けています。
④講座を開催するうえで工夫されていることはありますか?
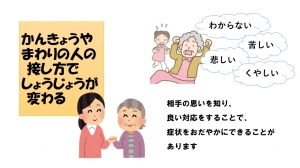
小学生にも理解してもらえるよう、分かりやすく構成しています。
新箭
淡路市では3ヶ所の在宅介護支援センターに委託して、地域包括支援センターブランチ※2を運営しており、各在宅介護支援センターが地区ごとに講座を担当しています。他法人とは定期的に連絡会で情報共有しています。
また行政、他法人とは常に連携しており、困ったことなどがあれば相談しています。講座の経験は行政や他法人のほうが長いので、色々とアドバイスをもらっています。
講座を受ける年齢層によっては認知症に関心がない場合があります。過去に高校生向けに講座をした時に、眠たそうな学生もおり、どうやって関心を持ってもらうか苦労しました。そういった時は担任の先生を巻き込んで寸劇をし、淡路市はバスで通学する人が多いので、バスでのシチュエーションを設定し、乗り方がわからない、どこに行ったらよいかわからないという方に会ったらどうするか、というような構成にして工夫をしました。
淡路市では3ヶ所の在宅介護支援センターに委託して、地域包括支援センターブランチ※2を運営しており、各在宅介護支援センターが地区ごとに講座を担当しています。他法人とは定期的に連絡会で情報共有しています。
また行政、他法人とは常に連携しており、困ったことなどがあれば相談しています。講座の経験は行政や他法人のほうが長いので、色々とアドバイスをもらっています。
講座を受ける年齢層によっては認知症に関心がない場合があります。過去に高校生向けに講座をした時に、眠たそうな学生もおり、どうやって関心を持ってもらうか苦労しました。そういった時は担任の先生を巻き込んで寸劇をし、淡路市はバスで通学する人が多いので、バスでのシチュエーションを設定し、乗り方がわからない、どこに行ったらよいかわからないという方に会ったらどうするか、というような構成にして工夫をしました。
⑤コロナ禍での開催で苦労したこと、気を付けたことを教えてください。
新箭
感染状況によりどのタイミングで開催するか判断するのに苦労しました。開催予定の小学校でクラスターが発生し、学級閉鎖になってしまったこともあり、2021年度は5回開催予定でしたが4回の開催となりました。また参加者もマスクをしているので表情が読み取りづらく、こちらが伝えたいことがしっかり伝わっているのか不安に思うこともあります。これまでより参加者の様子を気に掛けての講座開催でした。
一度、行政の方がWebで開催されましたが、臨場感が伝わりにくかったようです。特に寸劇などは事前に撮影しておくなどの工夫が必要なようでした。世の中の動向もWeb講座が浸透しているので今後検討していきたいと思っています。
感染対策は徹底し、本来なら90分の開催時間を行政と相談し時間を縮小したり、広い会場を準備し密にならないようにしたり配慮しました。コロナ禍ですが参加人数の減少はなく、例年通り40名ほどが参加してくれました。講座を受講したい人は多いという印象でした。
感染状況によりどのタイミングで開催するか判断するのに苦労しました。開催予定の小学校でクラスターが発生し、学級閉鎖になってしまったこともあり、2021年度は5回開催予定でしたが4回の開催となりました。また参加者もマスクをしているので表情が読み取りづらく、こちらが伝えたいことがしっかり伝わっているのか不安に思うこともあります。これまでより参加者の様子を気に掛けての講座開催でした。
一度、行政の方がWebで開催されましたが、臨場感が伝わりにくかったようです。特に寸劇などは事前に撮影しておくなどの工夫が必要なようでした。世の中の動向もWeb講座が浸透しているので今後検討していきたいと思っています。
感染対策は徹底し、本来なら90分の開催時間を行政と相談し時間を縮小したり、広い会場を準備し密にならないようにしたり配慮しました。コロナ禍ですが参加人数の減少はなく、例年通り40名ほどが参加してくれました。講座を受講したい人は多いという印象でした。
⑥取り組みを行って得られた効果や課題を教えてください。

受講者に交付しているオレンジリングは、認知症サポーターの証。
新箭
これまでの講座の成果として、淡路市では認知症の理解も年々深まっていると感じますし、受講された皆さんはそれぞれのやり方で、温かく見守ってくれています。
例えば別の社会福祉法人と認知症の集まりを推進するようになった町内会の自治会長や民生委員の方がいたり、認知症カフェへの参加も増えていたりしています。また些細な行動かもしれませんが、買い物の際に、発言や行動に少し違和感を覚えたり、道に迷っていたりしたら、行政や私たちの施設に連絡をくれるようになった店舗店主の方もいて、そのおかげで私たちのような在宅介護支援センターの専門職が早く介入することができています。早期に介入することで交通事故やトラブルに遭うのを回避できたり、病院を受診し適切な薬の処方で症状によっては進行を遅らせられたり等、大きな混乱なく生活を送ることができます。場合によっては介護保険サービスにもつなぎます。もし介入が遅くなると認知症の本人と家族が戸惑いながら生活を送ることが長くなり、家族も介護が大変になり仕事にも行けない、本人も偏見をもたれる等、日常生活が崩壊してしまうこともあります。
このようなことからも講座を受講してくれる方が一人でも多くなり、認知症への理解が広がってほしいと思います。
河部
専門職だけでは地域の福祉を支えきれないと思っています。その為には認知症サポーターの力が必要不可欠です。認知症は少しずつ症状が現れてきます。家族も急に不安になるわけではなく、だんだんと「認知症なのかな?」と自覚していくことが多いです。ケアマネジャーとして介入する際は、なるべく住み慣れた地域で過ごしてはどうかと提案しますが、逆にそれが家族を追い詰めることになるケースもあるので、そこは慎重に対応しています。
認知症の方が施設に入所されるのか、在宅で介護となるのか、どちらにしても認知症を理解し、認知症の方や家族を見守る認知症サポーターが多くいればいるほど、安心して地域で暮らすことができると思っています。そのためにも講座に参加しやすい雰囲気づくりや認知症についてわかりやすく伝えるなど、啓発活動に貪欲に取り組みたいと思います。
これまでの講座の成果として、淡路市では認知症の理解も年々深まっていると感じますし、受講された皆さんはそれぞれのやり方で、温かく見守ってくれています。
例えば別の社会福祉法人と認知症の集まりを推進するようになった町内会の自治会長や民生委員の方がいたり、認知症カフェへの参加も増えていたりしています。また些細な行動かもしれませんが、買い物の際に、発言や行動に少し違和感を覚えたり、道に迷っていたりしたら、行政や私たちの施設に連絡をくれるようになった店舗店主の方もいて、そのおかげで私たちのような在宅介護支援センターの専門職が早く介入することができています。早期に介入することで交通事故やトラブルに遭うのを回避できたり、病院を受診し適切な薬の処方で症状によっては進行を遅らせられたり等、大きな混乱なく生活を送ることができます。場合によっては介護保険サービスにもつなぎます。もし介入が遅くなると認知症の本人と家族が戸惑いながら生活を送ることが長くなり、家族も介護が大変になり仕事にも行けない、本人も偏見をもたれる等、日常生活が崩壊してしまうこともあります。
このようなことからも講座を受講してくれる方が一人でも多くなり、認知症への理解が広がってほしいと思います。
河部
専門職だけでは地域の福祉を支えきれないと思っています。その為には認知症サポーターの力が必要不可欠です。認知症は少しずつ症状が現れてきます。家族も急に不安になるわけではなく、だんだんと「認知症なのかな?」と自覚していくことが多いです。ケアマネジャーとして介入する際は、なるべく住み慣れた地域で過ごしてはどうかと提案しますが、逆にそれが家族を追い詰めることになるケースもあるので、そこは慎重に対応しています。
認知症の方が施設に入所されるのか、在宅で介護となるのか、どちらにしても認知症を理解し、認知症の方や家族を見守る認知症サポーターが多くいればいるほど、安心して地域で暮らすことができると思っています。そのためにも講座に参加しやすい雰囲気づくりや認知症についてわかりやすく伝えるなど、啓発活動に貪欲に取り組みたいと思います。
⑦利用者・職員にとってさらに良い施設・サービスにしていくために、今後どう発展させていきたいですか?

地域の方々が抱えている生活上のご不安やご心配事などのご相談をお受けします。(聖隷在宅介護支援センター淡路の職員)
新箭
今後は講座を多くの方にまず知っていただき、受講していただくことで、認知症への理解が深まってほしいと思います。そして受講した方には、開催を企画しているステップアップ研修を受けてもらい、もう一歩踏み込んだ活動ができるようになってほしいと思います。その為には啓発活動が大切だと考えていて、ケアマネジャーなどの専門職よりも町内会や民生委員から発信のほうが地域には広がりやすいと思っています。活動を通して地域貢献しつつ、認知症以外の福祉、医療の課題にも行政や他法人と連携し、住み慣れた地域で暮らせるよう取り組んでいきたいと思っています。淡路市の未来に向けて地域の福祉の力を上げていきたいと思っています。
河部
今後ケアマネジャーとしても講座の啓発活動に力を入れていきたいです。同時に私たちのような専門職が身近にいるということを知っていただき、ぜひ頼っていただきたいと思います。相談窓口に来られた方で「こういった相談窓口があることをもっと早く知っていたらよかった」とおっしゃられる方もおられます。専門職が介入することで早期に解決できる問題も多々あるので、ぜひ地域の相談窓口として利用していただきたいと思います。相談事も多岐にわたるので色々な相談事に対応できる施設にしていきたいと思います。
今後は講座を多くの方にまず知っていただき、受講していただくことで、認知症への理解が深まってほしいと思います。そして受講した方には、開催を企画しているステップアップ研修を受けてもらい、もう一歩踏み込んだ活動ができるようになってほしいと思います。その為には啓発活動が大切だと考えていて、ケアマネジャーなどの専門職よりも町内会や民生委員から発信のほうが地域には広がりやすいと思っています。活動を通して地域貢献しつつ、認知症以外の福祉、医療の課題にも行政や他法人と連携し、住み慣れた地域で暮らせるよう取り組んでいきたいと思っています。淡路市の未来に向けて地域の福祉の力を上げていきたいと思っています。
河部
今後ケアマネジャーとしても講座の啓発活動に力を入れていきたいです。同時に私たちのような専門職が身近にいるということを知っていただき、ぜひ頼っていただきたいと思います。相談窓口に来られた方で「こういった相談窓口があることをもっと早く知っていたらよかった」とおっしゃられる方もおられます。専門職が介入することで早期に解決できる問題も多々あるので、ぜひ地域の相談窓口として利用していただきたいと思います。相談事も多岐にわたるので色々な相談事に対応できる施設にしていきたいと思います。
| ※1 地域包括ケアシステム:要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のこと。 ※2 地域包括支援センターブランチ:高齢者の方が可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活できるように、介護・福祉・健康・医療などに関する相談に応じるため設けられた地域の総合相談窓口のこと。 |