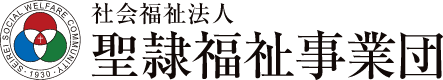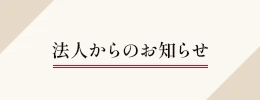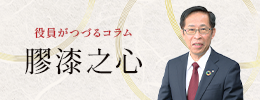地域包括支援センター和合 「地域でつながるケアマネネットワーク ~圏域内における居宅介護支援事業所間の相互支援体制を構築~」
取り組み概要

地域包括支援センター和合の職員の皆さん
地域包括支援センター和合では、地域の課題に取り組み、「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」を行っている。そのため特に法人内外問わず圏域内の居宅介護支援事業所とは勉強会や事例検討会などを定期的に開催し、ケアマネジメント力の向上に繋げている。定期的に居宅介護支援事業所との関わりを持っているため、お互いに顔の見える関係ができている。その中でコロナ禍において小規模な居宅介護支援事業所では事業継続に対して不安の声が度々聞かれるようになった。新型コロナウイルス感染症等による居宅介護支援事業所休業時に利用者の不利益を最小限にするため、圏域内の居宅介護支援事業所で助け合える体制を確立した。
SDGsの関連性
「地域でつながるケアマネネットワーク」と関連するSDGsの目標は・・・

3.すべての人に健康と福祉を
11.住み続けられるまちづくりを
17.パートナーシップで目標を達成しよう
駒月 笑美子 (こまづき えみこ)

地域包括支援センター和合
主任介護支援専門員
ケアマネネットワーク構築にあたり、圏域内の居宅介護支援事業所との調整や行政への確認などを担い、体制の確立に尽力した。
主任介護支援専門員
ケアマネネットワーク構築にあたり、圏域内の居宅介護支援事業所との調整や行政への確認などを担い、体制の確立に尽力した。
松山 美津代 (まつやま みつよ)

地域包括支援センター和合 所長
看護師/主任介護支援専門員
ケアマネネットワーク構築にあたり、圏域内の居宅介護支援事業所と協議するなど全体的なマネジメントを担った。
看護師/主任介護支援専門員
ケアマネネットワーク構築にあたり、圏域内の居宅介護支援事業所と協議するなど全体的なマネジメントを担った。
インタビュー
①この取り組みを行うきっかけとなった決定的なエピソードを教えてください。

圏域内の居宅介護支援事業所との勉強会は定期的に開催しています。
駒月
2018年から地域包括支援センター和合圏域内の5つの居宅介護支援事業所と勉強会や事例検討会を定期的に行っていましたが、コロナ禍になり、小規模の居宅介護支援事業所から「自施設がコロナ感染で休業になると法人内で助けてもらえるところがなく困っている」という話が出ました。浜松市では、居宅介護支援事業所が閉鎖や休業となる場合には、介護保険課に相談することになっていましたが、「自分が担当する大切な利用者を、顔がわかり信頼できる介護支援専門員(以下ケアマネジャー)に頼みたい」という声があり、法人が違っても近くのケアマネジャー同士で助け合えるネットワークを作ろうという話が持ち上がりました。
松山
2020年4月から検討を進めていくうち、月刊誌「コミュニティケア2020年8月号」に、土砂災害が続いていた広島県で、現地の訪問看護の事業所が事前にネットワークを組んで有事に備えるというBCP※1の記事を読み、これを応用できないかと思い、参考にしました。
2018年から地域包括支援センター和合圏域内の5つの居宅介護支援事業所と勉強会や事例検討会を定期的に行っていましたが、コロナ禍になり、小規模の居宅介護支援事業所から「自施設がコロナ感染で休業になると法人内で助けてもらえるところがなく困っている」という話が出ました。浜松市では、居宅介護支援事業所が閉鎖や休業となる場合には、介護保険課に相談することになっていましたが、「自分が担当する大切な利用者を、顔がわかり信頼できる介護支援専門員(以下ケアマネジャー)に頼みたい」という声があり、法人が違っても近くのケアマネジャー同士で助け合えるネットワークを作ろうという話が持ち上がりました。
松山
2020年4月から検討を進めていくうち、月刊誌「コミュニティケア2020年8月号」に、土砂災害が続いていた広島県で、現地の訪問看護の事業所が事前にネットワークを組んで有事に備えるというBCP※1の記事を読み、これを応用できないかと思い、参考にしました。
②この取り組みの内容を詳しく教えてください。

ネットワーク構築までには、各居宅介護支援事業所とは何度も打合せをしました。
駒月
このネットワークは、ケアマネジャーの調整が不可欠な利用者を助け合うというものです。必要性が高い利用者には、有事の際に受け入れてくれる居宅介護支援事業所が主治医などと連携できるように、ネットワーク内で個人情報を提供できる同意書を事前に取りました。それ以外の利用者は、事が起きてから、同意を得る流れにしました。
松山
居宅介護支援事業所とネットワーク構築の契約を結ぶ際、これが介護保険法に合致するかを行政にも相談し、お墨付きをいただきました。当初は当和合圏域だけでしたが、聖隷の浜松市内にある5つの地域包括支援センターのうち、高丘、細江もそれぞれの圏域の居宅介護支援事業所と話し合いをし、契約を結び同様にネットワークを構築していきました。
駒月
まだこのネットワークが稼働したことはありませんが、2020年12月にネットワーク構築の契約を結んで以降、2回ほど訓練をしました。1回目は、ある居宅介護支援事業所で職員がコロナに感染し、一時休業になる場合、事前にトリアージした利用者を各居宅介護支援事業所が何人担当可能かというリストを出していただくところまでの訓練でした。中心の役割を果たす私たち地域包括支援センターに休業の居宅介護支援事業所から連絡が入り、私たちから一斉にネットワーク参加の居宅介護支援事業所に、事前にトリアージした利用者を担当できるか連絡票を送り、それぞれの担当可能人数の回答をとりまとめ、調整を行いました。
松山
一緒にネットワークを組み立てた主任介護支援専門員(以下主任ケアマネジャー)のみではなく、実際に多くの利用者を担当しているケアマネジャーに体験してもらうことで、「できたこと、できなかったこと」が見えたのが一番大きかったです。
駒月
情報共有用メールを活用するなど、事務所外での対応もできるよう連絡網も整えました。訓練をしてみて、利用者の日々の様子を知っている訪問看護師や訪問介護員の方からケアマネジャーに連絡する手段もあるといいという話もでるなど、新たな問題点を考えるよいきっかけになっています。
このネットワークは、ケアマネジャーの調整が不可欠な利用者を助け合うというものです。必要性が高い利用者には、有事の際に受け入れてくれる居宅介護支援事業所が主治医などと連携できるように、ネットワーク内で個人情報を提供できる同意書を事前に取りました。それ以外の利用者は、事が起きてから、同意を得る流れにしました。
松山
居宅介護支援事業所とネットワーク構築の契約を結ぶ際、これが介護保険法に合致するかを行政にも相談し、お墨付きをいただきました。当初は当和合圏域だけでしたが、聖隷の浜松市内にある5つの地域包括支援センターのうち、高丘、細江もそれぞれの圏域の居宅介護支援事業所と話し合いをし、契約を結び同様にネットワークを構築していきました。
駒月
まだこのネットワークが稼働したことはありませんが、2020年12月にネットワーク構築の契約を結んで以降、2回ほど訓練をしました。1回目は、ある居宅介護支援事業所で職員がコロナに感染し、一時休業になる場合、事前にトリアージした利用者を各居宅介護支援事業所が何人担当可能かというリストを出していただくところまでの訓練でした。中心の役割を果たす私たち地域包括支援センターに休業の居宅介護支援事業所から連絡が入り、私たちから一斉にネットワーク参加の居宅介護支援事業所に、事前にトリアージした利用者を担当できるか連絡票を送り、それぞれの担当可能人数の回答をとりまとめ、調整を行いました。
松山
一緒にネットワークを組み立てた主任介護支援専門員(以下主任ケアマネジャー)のみではなく、実際に多くの利用者を担当しているケアマネジャーに体験してもらうことで、「できたこと、できなかったこと」が見えたのが一番大きかったです。
駒月
情報共有用メールを活用するなど、事務所外での対応もできるよう連絡網も整えました。訓練をしてみて、利用者の日々の様子を知っている訪問看護師や訪問介護員の方からケアマネジャーに連絡する手段もあるといいという話もでるなど、新たな問題点を考えるよいきっかけになっています。
③取り組みの際に工夫したことや苦労したことを教えてください。

有事の際にネットワークを効果的に稼働できるよう、普段から各居宅介護事業所とは密に連携をとっています。
松山
聖隷の他の地域包括支援センターでもネットワークの構築を試みていますが、地域によっては圏域内の居宅介護支援事業所の規模等に差があるため、なかなか話が進まないということも聞いています。
当圏域では、対象とする利用者をどう選定するかを主任ケアマネジャーとかなり時間をかけて検討しました。例えば、訪問介護サービスを毎日利用している認知症の方は、訪問介護員からコロナ感染で事業所が休業しているものの対応が可能な担当以外のケアマネジャーに連絡し、相談いただいてもいいかもしれません。電話が難しい難聴の利用者や普段通りの生活が送れないことで不安になる精神疾患の利用者はどうするか、神経難病やがん末期の利用者を担当している居宅介護支援事業所はどうするか、など選定の基準を検討しました。
このネットワークを知った圏域内の他のサービス提供事業所から、「自分たちも何かできるのでは」と協力を申し出てくださるところも出てきました。地域づくりにおいて、サービス提供事業所が連携しやすい顔が見える関係性づくりが、いま次の段階に進んでいるところです。今後も見直しを図りながらこの体制を維持していきたいと考えています。
聖隷の他の地域包括支援センターでもネットワークの構築を試みていますが、地域によっては圏域内の居宅介護支援事業所の規模等に差があるため、なかなか話が進まないということも聞いています。
当圏域では、対象とする利用者をどう選定するかを主任ケアマネジャーとかなり時間をかけて検討しました。例えば、訪問介護サービスを毎日利用している認知症の方は、訪問介護員からコロナ感染で事業所が休業しているものの対応が可能な担当以外のケアマネジャーに連絡し、相談いただいてもいいかもしれません。電話が難しい難聴の利用者や普段通りの生活が送れないことで不安になる精神疾患の利用者はどうするか、神経難病やがん末期の利用者を担当している居宅介護支援事業所はどうするか、など選定の基準を検討しました。
このネットワークを知った圏域内の他のサービス提供事業所から、「自分たちも何かできるのでは」と協力を申し出てくださるところも出てきました。地域づくりにおいて、サービス提供事業所が連携しやすい顔が見える関係性づくりが、いま次の段階に進んでいるところです。今後も見直しを図りながらこの体制を維持していきたいと考えています。
④取り組みを行って得られた効果や課題を詳しく教えてください。

事業団内での静岡エリア介護保険サービス学会で最優秀賞を受賞しました。
駒月
ある居宅介護支援事業所では、有事が起きた際にネットワークを利用したほうがいい利用者を事前にチェックし、同意書にサインいただいたということを聞いています。ネットワーク構築に携わったことで、各居宅介護支援事業所では危機管理意識が高まったのだと思います。その他にもBCP作成・検討にも繋がっているようです。
松山
またある居宅介護支援事業所では、同意書を取るにあたり、訪問介護や訪問看護の事業所にも意見をもらい判断しており、利用者を取り囲む事業所との繋がりが以前より強くなったと聞いています。
駒月
以前から、ケアマネジャーが突然休んだり退職してしまった際、担当していた利用者を一体誰が担当するかという問題が、どこの居宅介護支援事業所にもありました。このネットワークを構築するにあたり、そういった時にも役立てたいという意見があったので、コロナ禍以外の理由で人員が不足した際にも対応できる仕組みになっています。
松山
今回この取り組みを主に担当したのが私と駒月のため、私たちが異動などでいなくなった途端に、担当者がいなくなったからネットワークが稼働できないという状況は避けなくてはいけないと考えております。今後このネットワークをどのように継続性・発展性を持たせていくのかは、検討していかなければならない課題だと考えています。
ある居宅介護支援事業所では、有事が起きた際にネットワークを利用したほうがいい利用者を事前にチェックし、同意書にサインいただいたということを聞いています。ネットワーク構築に携わったことで、各居宅介護支援事業所では危機管理意識が高まったのだと思います。その他にもBCP作成・検討にも繋がっているようです。
松山
またある居宅介護支援事業所では、同意書を取るにあたり、訪問介護や訪問看護の事業所にも意見をもらい判断しており、利用者を取り囲む事業所との繋がりが以前より強くなったと聞いています。
駒月
以前から、ケアマネジャーが突然休んだり退職してしまった際、担当していた利用者を一体誰が担当するかという問題が、どこの居宅介護支援事業所にもありました。このネットワークを構築するにあたり、そういった時にも役立てたいという意見があったので、コロナ禍以外の理由で人員が不足した際にも対応できる仕組みになっています。
松山
今回この取り組みを主に担当したのが私と駒月のため、私たちが異動などでいなくなった途端に、担当者がいなくなったからネットワークが稼働できないという状況は避けなくてはいけないと考えております。今後このネットワークをどのように継続性・発展性を持たせていくのかは、検討していかなければならない課題だと考えています。
⑤利用者・職員にとってさらに良い施設・サービスにしていくために、今後どう発展させていきたいですか。

今後も一丸となってネットワークの発展・継続に力を入れていきます。
駒月
担当圏域外のケアマネジャーともこのようなネットワークが構築できると、圏域内で対応ができないとなった場合でも、圏域外の事業所に助けを要請することができます。
松山
例えば地震で避難をする際、利用者は必ずしも担当圏域内の避難所に避難されるとは限りません。そういった時にも圏域を超えたネットワークのつながりがあれば、迅速かつ柔軟に対応ができるのではと考えています。今後は圏域を越えたネットワークの構築も考えていけたらと思っています。
駒月
また今回の居宅介護支援事業所のネットワーク構築が第一歩として、高齢者施設や障がい者施設なども交えたネットワークに発展していけたらと思います。
松山
様々なサービス提供事業所等との横のつながりを広げ、気軽に相談し助け合える関係性をつくり、最終的には地域住民の皆さんに還元できる仕組みに発展させていきたいです。
担当圏域外のケアマネジャーともこのようなネットワークが構築できると、圏域内で対応ができないとなった場合でも、圏域外の事業所に助けを要請することができます。
松山
例えば地震で避難をする際、利用者は必ずしも担当圏域内の避難所に避難されるとは限りません。そういった時にも圏域を超えたネットワークのつながりがあれば、迅速かつ柔軟に対応ができるのではと考えています。今後は圏域を越えたネットワークの構築も考えていけたらと思っています。
駒月
また今回の居宅介護支援事業所のネットワーク構築が第一歩として、高齢者施設や障がい者施設なども交えたネットワークに発展していけたらと思います。
松山
様々なサービス提供事業所等との横のつながりを広げ、気軽に相談し助け合える関係性をつくり、最終的には地域住民の皆さんに還元できる仕組みに発展させていきたいです。
| BCP※1…事業継続計画(Business Continuity Plan)。企業が、災害やシステム障害など危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、事業の継続や復旧を図るための計画。 |