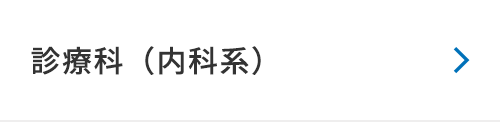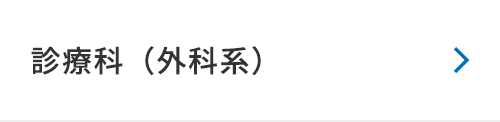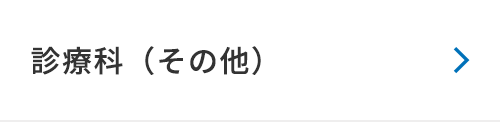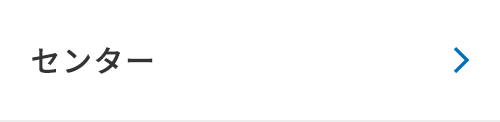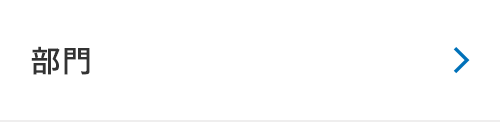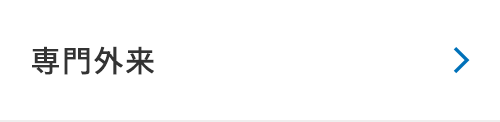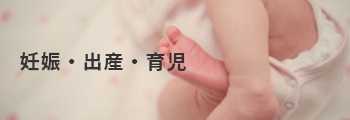どのようなときに病院へ行ったほうがよいか?
頭部CTは、頭蓋骨の骨折、脳の損傷や出血を評価するために必要な検査です。しかし、小さなこどもの場合は、頭部CTによる放射線被ばくも考慮する必要があります(大人の場合、頭部CTを1回撮影することで放射線被ばくの影響は少ないです)。
したがって、こどもの頭部外傷において、以下のいずれかの症状がある場合は、頭部CTを撮影する必要があるかもしれません。
したがって、こどもの頭部外傷において、以下のいずれかの症状がある場合は、頭部CTを撮影する必要があるかもしれません。
| どの年齢にも共通 | ・意識清明ではない 意識がない、呼びかけに反応しない(反応が鈍い)、視線があわない、放っておくとすぐに寝てしまう、起こしても起きない、など ・意識消失があった けがをした前後の記憶があいまい、一瞬でも記憶がとんでいる、少ししたら意識がもどってきた、など ・皮膚が深くきれており、長時間押さえても血が止まらない ・頭蓋骨が凹んでいる(頭蓋骨骨折) ・血液をサラサラにする薬を飲んでいる |
| 2歳未満のとき | ・おでこ以外の部分にたんこぶがある ・頭蓋骨骨折が触知される ・交通事故や0.9m以上の高さからの転落などの危険な受傷機転 ・親からみて普段と違う |
| 2歳以上の場合 | ・激しい頭痛、嘔吐 ・交通事故や1.5m以上の高さからの転落などの危険な受傷機転 ・眼や耳の周りが黒くなっている ・耳や鼻から血や透明な液体が出て止まらない |
頭部CT撮影する基準(こどもの場合)
頭部CTは、骨折やあたまの中での出血を確認するために必要な検査ですが、子供の場合は、放射線被ばくを伴います。放射線被ばくを受けると発がんリスクが高くなることが報告されていますので、頭部CTの必要性と被ばくリスクを考えて、担当医師が頭部CTの必要性は判断します(小児頭部外傷時のCT撮像基準の提言・指針を参考にしています)。
頭部外傷後の経過について
あたまをぶつけたすべての方は、頭部外傷後24時間は体調に変化がないか観察してください。特に最初の3~6時間は、意識の悪化や手足の麻痺などないか観察してください。
こどもの場合、数時間で元気になるこどもから数週間かかって元気になるこどもまで様々ですので、体調にあわせて生活してください。
大人の場合、2週間~2ヶ月くらい経過しながら、ゆっくりと頭蓋骨と脳の間に血液が貯まってくる慢性硬膜下血腫を認めることがあります。慢性硬膜下血腫の症状は、頭痛、意識障害、手足の麻痺や物忘れ(認知症に似た症状)、尿失禁など様々です。慢性硬膜下血腫となった場合は、貯まった血液を頭蓋骨の外に排液するための手術が必要となることがあります。
こどもの場合、数時間で元気になるこどもから数週間かかって元気になるこどもまで様々ですので、体調にあわせて生活してください。
大人の場合、2週間~2ヶ月くらい経過しながら、ゆっくりと頭蓋骨と脳の間に血液が貯まってくる慢性硬膜下血腫を認めることがあります。慢性硬膜下血腫の症状は、頭痛、意識障害、手足の麻痺や物忘れ(認知症に似た症状)、尿失禁など様々です。慢性硬膜下血腫となった場合は、貯まった血液を頭蓋骨の外に排液するための手術が必要となることがあります。
セカンドインパクト症候群について
けがをして、すぐにもう1度同様のけがをした場合、2回目のけがは重篤となることがあります。これをセカンドインパクト症候群と呼びます。そのため、スポーツ(特にサッカーやラグビー、ボクシングなどのコンタクトスポーツ)の場合、競技復帰まで1~2週間かけて徐々に復帰することが勧められています。このような場合は、診察した医師に必ず確認をしてから競技復帰してください。
あたまをぶつけた程度の軽傷頭部外傷の方へ
聖隷浜松病院脳神経外科・小児脳神経外科では、高度かつ専門的な外科治療(手術)を中心に行っています。平日の日中などは、機能分担の観点からも、まずはお近くの脳神経外科クリニックやこどもの場合は、かかりつけの小児科の受診をおすすめします。夜間休日は、救急外来での対応となりますのでご了承ください。