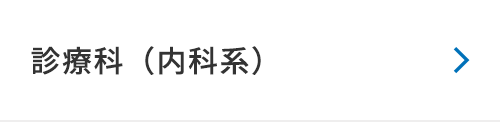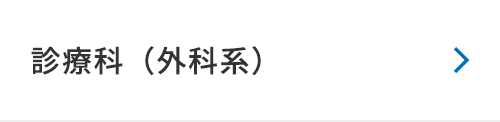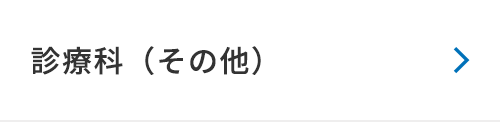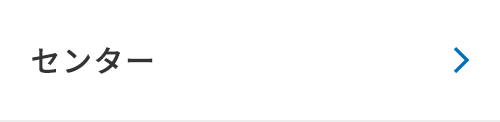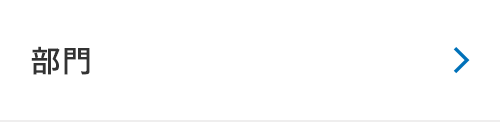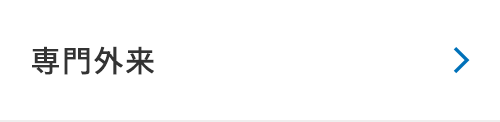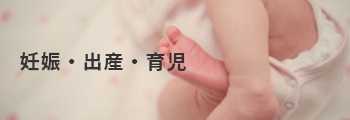小児脳神経外科

小児脳神経外科は、静岡県西部で唯一の小児を専門とする脳神経外科です。
部長:中戸川 裕一
小児脳神経外科では、こどもの脳や脊髄の病気・けがを治療(主に手術)する科です。また、脳神経外科治療をうけたこどもたちが成人してからも移行期医療として診療を行っています。
我々小児脳神経外科が扱うこどもの脳や脊髄の病気・けがは、頻度が高いわけではありませんが、患児ご本人、ご家族の不安は甚大と思います。病気・けがに対して一緒に闘うには、病状について理解いただくことが重要と考え十分な説明を行うよう心掛けています。他職種も含め、患児に関わるスタッフは、患児やご家族に寄り添う医療を行えるように努めています。
さらに、治療を受けた患児の成長を一緒に見守り、大人になったとき社会で活躍することを期待し、患児やそのご家族が将来に亘り「治療してよかった」と思っていただける診療を目指しています。
また、小児脳神経外科医は本邦では非常に少ないことから、日本国内の小児脳神経外科医が協力をして小児脳神経外科における医学の発展に努める必要があります。聖隷浜松病院だけでなく、全国の大学や病院と連携して臨床研究も行っています。
静岡県内でこどもの脳や脊髄の手術を専門に行っている脳神経外科医は非常に少ないのが現状です。したがって、基本的に小児科や脳神経外科などからの紹介予約制です。
我々小児脳神経外科が扱うこどもの脳や脊髄の病気・けがは、頻度が高いわけではありませんが、患児ご本人、ご家族の不安は甚大と思います。病気・けがに対して一緒に闘うには、病状について理解いただくことが重要と考え十分な説明を行うよう心掛けています。他職種も含め、患児に関わるスタッフは、患児やご家族に寄り添う医療を行えるように努めています。
さらに、治療を受けた患児の成長を一緒に見守り、大人になったとき社会で活躍することを期待し、患児やそのご家族が将来に亘り「治療してよかった」と思っていただける診療を目指しています。
また、小児脳神経外科医は本邦では非常に少ないことから、日本国内の小児脳神経外科医が協力をして小児脳神経外科における医学の発展に努める必要があります。聖隷浜松病院だけでなく、全国の大学や病院と連携して臨床研究も行っています。
静岡県内でこどもの脳や脊髄の手術を専門に行っている脳神経外科医は非常に少ないのが現状です。したがって、基本的に小児科や脳神経外科などからの紹介予約制です。
特色ある診療
小児脳神経外科の特徴
成人と異なり小児の脳は成長していくため、小児の特性にあった個々のオーダーメイドの治療が必要で、小児科、新生児科、小児外科、眼形成眼窩外科、腫瘍放射線科などと協力して診療を行うこともあります。当院では、総合周産期母子医療センターであり、小児診療における各科の連携が良いのも特徴です。
移行期医療
複数回の手術が必要な場合や成人期まで治療を継続する必要がある場合も、こども病院などで必要とされる移行期の転院は必要なく、治療を継続できる体制が整っています。
手術の特徴
4K神経内視鏡手術システム
小児脳神経外科では「神経内視鏡」を使用した手術を積極的に行っています。対象疾患は小児の脳腫瘍、水頭症、頭蓋骨縫合早期癒合症などです。従来の手術方法にくらべて皮膚や脳を切開する範囲が減少するとともに、脳のより深い部位の病変に対する治療が可能になります。また内視鏡も常に進化しており、現在使用している内視鏡は4Kシステムです。高精細な画像のため、血管や神経の判別がしやすく、より安全で精緻な内視鏡手術が可能となっています。
4K-3D外視鏡手術システム

2023年3月に外視鏡(ORBEYE)が導入されました。外視鏡は、フルハイビジョンで4Kの大型モニターに術野を映して手術を行う道具です。以前は顕微鏡を用いて手術を行っていましたが、顕微鏡は術者と助手の2人が接眼レンズを覗いて手術を行っているため、手術室にいる術者と助手以外は、3Dでモニターを観察することができませんでした。一方、外視鏡はモニターを見ながら手術を行うため、手術室にいる全員が術者と同じ画面を共有できるという特徴があります。医師や看護師を含めた手術室のスタッフ教育にも役に立っています。患者さんにとっては、無理な体勢での手術が不要となる場合があり、術後の疼痛が軽減される可能性があります。また、外視鏡は、カメラが小さいため自由度が高くなり、顕微鏡よりも皮膚切開する範囲が小さくなる可能性もあり、低侵襲な手術が期待できます。さらに、内視鏡との併用がスムーズという利点があり、より患者さんの負担が軽くなる器械です。
術中ナビゲーション・術中CTシステム
2003年から脳神経外科の手術支援装置である「術中ナビゲーションシステム」を導入しています。手術前に作成した各患者さんの画像をもとに、手術中に脳のどこを手術しているのか、病変はどこまであるのかなどを細かい範囲かつリアルタイムに把握するものです。これにより脳の切開を必要最小限に抑え、脳の重要な機能部位を温存するのに役立ててきました。また、脳の手術中に、脳を保護している脳脊髄液が減少したり、病変を取り除くことで脳は容易に変形します。このため手術前の画像との「ずれ」を補正する必要がでてきます。2017年に更新したナビゲーションシステムでは、術中CTを撮影することで、手術の進行に伴い変化した脳の撮影データを再取り込みし、自動で患部の位置と画像の位置を合わせる、自動レジストレーション機能が搭載されています。手術中の位置情報の把握が飛躍的に向上し、一層の安全性と正確性が確保されています。
脳神経モニタリング
脳疾患の手術は病変を取り除くことと同時に、脳の正常な機能をいかに温存させるかが重要です。特に運動(手足の動き)、視覚、聴覚、言語、排泄(膀胱や直腸機能)など生活に直結する機能を温存するために手術中には手術に関わる各神経を刺激し機能が維持できているかリアルタイムにモニタリングを行っています。小児の手術で一番多いのは、脊髄係留解除術を行うときに、下肢や排泄の機能をモニタリングします。また、脳腫瘍やてんかんなどで言語機能に関わる部位に病変がある場合には「覚醒下手術」を行うことで機能維持を図ります。
手術室内CT
2015年に現在の手術室が完成し、隣接する2つの手術室で同時並行して使用が可能な移動式CTを導入しました。開頭術をはじめとした頭部に関わる手術を行った際は、集中治療室へ帰る前にほぼ全例に手術室内で頭部CTを撮影しています。これは手術が終了した時点で、予想外の出血などの合併症が生じていないか、また手術の目的が達成できているかを迅速に評価し、治療の安全性を維持するためです。
こどもの場合は、放射線被ばくについて気になりますが、撮影の目的にあわせて線量を調節し、放射線被ばく軽減に努めています。
こどもの場合は、放射線被ばくについて気になりますが、撮影の目的にあわせて線量を調節し、放射線被ばく軽減に努めています。
手術室について
主な対象疾患
腫瘍
脳や脊髄に正常と異なる細胞が増殖してできる塊を脳腫瘍・脊髄腫瘍といいます。腫瘍の種類によって、良性から悪性までさまざまです。
治療は手術、化学療法、放射線療法を組み合わせて行います。小児科、腫瘍放射線科と連携し治療を行います。
脳腫瘍は、100種類以上の種類があることから、まずは診断をつけることが大切です。MRIの画像診断である程度の診断は予想されますが、実際に腫瘍を手術で摘出することが推奨されます。
治療は手術、化学療法、放射線療法を組み合わせて行います。小児科、腫瘍放射線科と連携し治療を行います。
脳腫瘍は、100種類以上の種類があることから、まずは診断をつけることが大切です。MRIの画像診断である程度の診断は予想されますが、実際に腫瘍を手術で摘出することが推奨されます。
神経膠腫(グリオーマ)
当院は、地域がん診療連携拠点病院と認定されており、脳腫瘍の診療にも力を入れています。2021年に脳腫瘍の診断基準が改訂されました。2021年以前は、摘出した脳腫瘍を顕微鏡で観察して詳しい診断(病理診断)を行っていましたが、2021年からは脳腫瘍の遺伝子を解析することを追加して神経膠腫の詳しい診断を行うのが国際基準となりました。当院では、一般的な病理診断では解析が困難な分子遺伝学的特徴の解析を行うことを目的として、「関西中枢神経腫瘍分子診断ネットワーク」の多施設共同研究に参加しています。そこで各腫瘍の遺伝子診断を実施して、各腫瘍のより詳しい特性解析に努めています。さらに、分子標的薬を治療に用いる可能性があることから、がん遺伝子パネル検査を行う場合があります。
≫ がんゲノム医療・がん遺伝子パネル検査のページはこちら
≫ がんゲノム医療・がん遺伝子パネル検査のページはこちら
胚細胞腫瘍
小児に多い腫瘍の一つです。胚細胞腫瘍の中にいくつか種類が存在しており、ジャーミノーマという腫瘍の割合が高いです。ジャーミノーマの場合は、神経内視鏡手術によって腫瘍を生検(少しだけ摘出)し、診断をつけて、化学療法を行うことで治療していき、放射線治療を行います。同時に水頭症を合併していることがあるため、神経内視鏡手術で第3脳室底開窓術を行うことが多いです。
先天奇形
頭蓋骨縫合早期癒合症、脊髄髄膜瘤、脊髄脂肪腫、脊髄係留症候群、キアリ奇形などの疾患を治療します。
頭蓋骨縫合早期癒合症
一般的に2500~3500人に1人くらいの割合で発症します。頭蓋が変形し、頭蓋骨に脳が圧迫され、脳の成長発達を妨げる病気です。手術を行い頭蓋を拡大させることで、脳の圧迫を減らし、成長発達を促す必要があります。生後6ヶ月以内の場合、内視鏡下縫合切除術という内視鏡を用いた低侵襲な手術が可能です。また、生後6ヶ月以降の場合は、従来法もしくは骨延長法のどちらかの方法を用いて治療を行います。当院では、内視鏡下縫合切除術、従来法、骨延長法の3つの種類の手術が行えます。
脊髄髄膜瘤
近年では、母親の妊婦健診によるエコー検査で脊髄髄膜瘤が疑われ、妊娠中に胎児MRIを撮像することで診断されることもあります。出生後早期に、産科や新生児科と連携し修復術を行い、神経形成を行います。必要であれば、水頭症に対する脳室腹腔短絡術(VPシャント)を行う必要があります。
脊髄脂肪腫(潜在性二分脊椎)
脊髄脂肪腫は、出生後すぐに殿部の膨らみで発見されることもありますが、殿裂の凹みや左右差によって精査することで発見されることもあります。年齢も0歳から成人までまちまちです。脊髄脂肪腫は、脊髄が尾側(足側)に引っ張られることで膀胱やおしりへの指令が弱くなり、おしっこが出しにくい、ひどい便秘などの症状がでることがあります。このような症状が出現している場合は、手術をおすすめしています。
脊髄係留症候群
脊髄髄膜瘤や脊髄脂肪腫などの手術をうけたかたで、成長とともに脊髄がひっぱられてしまい、足が動かしにくい、足首が硬い、おしっこの回数が少ない(もしくは多い)、尿意がない、ひどい便秘、せぼねが曲がる(側弯)などの症状を呈すことがあり、手術で脊髄がひっぱられない状態にもどす脊髄係留解除術を行います。
キアリ奇形
キアリ奇形は、いくつか種類がありますが、主に脊髄髄膜瘤に合併しているキアリ奇形Ⅱ型や脊髄髄膜瘤の合併がないキアリ奇形Ⅰ型があります。キアリ奇形は、Ⅰ型でもⅡ型でも神経症状を確認して、手術の必要性、手術方法を判断します。
脳脊髄液関連疾患
水頭症
水頭症は、様々な原因の結果として、脳脊髄液が脳に比べて多くなってしまい、脳を圧迫する病気です。頭とお腹をチューブでつなぐシャント術(脳室腹腔短絡術・VPシャント)が主な治療法ですが、近年神経内視鏡が普及してきており、神経内視鏡下第三脳室底開窓術も多く行われています。
くも膜嚢胞
くも膜は、脳を包んでいる膜の一つです。名前の通り「膜」なので、1枚のシート状になって脳を包んでいるのですが、「袋」の状態のままのものをくも膜嚢胞と言います。発生頻度は1~3%程度とされています。こどもの時期には、大きくなったり縮んだりすることが報告されています。くも膜嚢胞は、大きさや神経症状などによって、外科的な治療(手術)を行う場合があります。部位や大きさによって異なりますが、まずは身体への負担が少ない神経内視鏡手術ができるか検討し、なるべく傷も小さくできるよう配慮しています。
頭部外傷
こどもがあたまを打つことを頭部外傷と言います。小児の頭部外傷は、年齢によって受傷機転が異なります。交通事故や転落が多いのですが、近年は虐待による頭部外傷も増えており、社会的に問題となっています。骨折やあたまの中で出血しているような重篤な状態であれば、手術が必要となることもあります。ただ、こどもの頭部外傷のほとんどは、経過が良い、軽症の頭部外傷です。
脳血管障害
小児でもっとも多い脳血管障害は、もやもや病です。頭の中の太い動脈が細くなり、脳梗塞や脳出血を起こす病気です。運動をしたとき、楽器を吹いたときに力が入らなかったり、痙攣を起こすこともあります。脳に栄養を送る血管を増やす(新生する)ために手術が必要となります。小児のもやもや病は、学校・幼稚園・保育園での生活の中で気をつけることなどありますので、外来受診の時に、注意点についてご説明しています。
他には、脳動静脈奇形、脳動脈瘤、 脳梗塞などの疾患も治療します。
他には、脳動静脈奇形、脳動脈瘤、 脳梗塞などの疾患も治療します。
機能的疾患
専門外来
頭のかたち外来
2019年4月に開設した赤ちゃんの頭の形についての外来です。主に生後18か月までのこどもを対象としています。