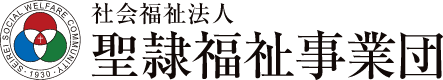2023年度功労表彰
臨床検査室の国際規格「ISO15189」を取得
聖隷三方原病院 臨床検査部

国際標準化機構が認証する「臨床検査室の国際規格である18015189認定」を聖隷検査部門として初めて取得した。この認定は検査精度の保証や医療の質などについて第三者評価を受けるもので、臨床検査部の日頃の取り組みが高く評価された。2021年にプロジェクトチームを立ち上げ、2年以上をかけて、日々の業務を手順書や記録に起こすことにより業務を標準化した。また定期的に自己評価を行ないながら業務改善に繋げることが習慣化された。その結果、認定取得により分析検査において「国際標準検査管理加算」が認められた。
高次脳機能障害に関する啓発活動
聖隷三方原病院 リハビリテーション部

聖隷三方原病院では高次脳機能障害支援拠点施設として、10年以上にわたり地域の医療福祉関連スタッフヘの啓発活動を行ってきた。また、ここ数年では公安委員会とも連携し、高次脳機能障害の支援に関する活動を推進している。啓発活動としては、相談会への参加や年1回の研修会の開催、パンフレットの資料作成などを実施している。2024年2月11日にも研修会を実施している。これらの活動から、地域の医療福祉関連スタッフの理解と意識の向上が図られ、高次脳機能障害や取り巻く人々への支援が進んでいる。今後も引き続き、地域の医療・福祉関係者との協カ・連携を重視し、高次脳機能障害の支援活動を推進していく。
外傷診療体制の整備により、重症外傷の予後を大きく改善
聖隷浜松病院 救急外来看護師・手術室看護師・臨床検査部・放射線部・臨床工学室

重症多発外傷患者は複数の臓器損傷により呼吸や血圧が保てなくなった状態であり、即座に処置や手術を行わなければ救命できない患者が多く、通常の救急診療のように救急医が診療してから各専門医をコールする体制では間に合わない。当院では救急隊から重症外傷患者の搬送要請があった場合、救急医、外科医、整形外科医、麻酔科医、手術室ナース、臨床工学技士、輸血部、放射線技師に一斉コールがなされ、患者が搬入された時には既に大量輸血や開胸開腹手術など、必要な処置・手術が即座に行える体制を確立した。この重症外傷診療体制を確立したことにより、外傷患者の予後が飛躍的に向上した。
患者からの直接予約成約率の大幅アップ
聖隷浜松病院 東海道シグマ・地域医療連絡室

開業医からの電話予約は予約待ち日数の管理や病状確認、院内他科連携などの受け入れ対応でここ数年92%以上の予約成立であった。しかし、患者からの直接予約では、2019年66%、2020年78.4%、 2021年81.3%の成約率であり、患者希望と当院の受け入れ体制とがかみ合わず、伸び悩み(患者獲得の損失)がみられた。そこで2022年途中より、東海道シグマとJUNCが連携し、電話対応内容や事前に紹介状を取り寄せる工夫等により2023年は約93%の成約率となる見込みまで改善した。地域全体での新規紹介患者が少ない中、これらの対応は病院経営にも大きく寄与した。
脳梗塞患者の入院後早期リハビリ開始
聖隷浜松病院 脳卒中科・リハビリテーション科・リハビリテーション部

脳梗塞患者の入院後早期リハビリ開始に対し、長期的な改善活動に取り組み実施率を大きく向上させた。具体的には、入院した脳梗塞患者に対して、早期リハビリを開始するため、長期に渡り改善活動を行い、10年間で実施率を大きく向上(15.5%)させた。脳卒中患者のリハビリにおけるエビデンスでは、合併症予防、機能回復のため、入院早期からの開始が推奨されており、患者にとって非常に有益な取り組みとなった。
放射線部における紙運用の一部廃止
聖隷浜松病院 放射線部

放射線部のペーパーレス化への第一歩として不要だと感じる紙運用を廃止し、業務のスリム化を図りたいと考え、CQIサークル活動として、MRI部門で当日の検査がMRI検査のみの患者の患者案内票の廃止を目指した。案内票廃止により発生する弊害への改善ポイント4つに対し、改善策として、患者本人確認の方法・ロ頭呼出に応答しない患者の確認方法の変更、他検査ありの場合の運用をマニュアル化、 検査後の患者案内を事務から技師ヘタスクシフト・マニュアル化を実施した。結果、MRIのみの患者の案内票を全て廃止することができ、従来よりも約93%の用紙削減に繋がり、目標を達成することができた。
病床稼働率の向上と迅速な紹介患者の受け入れ
袋井市立聖隷袋井市民病院 「せいれいふくろい」と地域医療を支えるんじゃー

当院は、慢性期、回復期の医療を提供する役割を担う。入院患者の約8割は近隣の急性期病院からの転院患者である。今回、転院患者を速やかに受け入れ地域のニーズに応えると共に、病床稼働率の向上を目指す取り組みを行った。病床管理シートを見直し、各病棟の入退院状況を予測的に把握し、病棟間で最も早く患者を受け入れる為の調整が可能となった。加えて各病棟課長が自職場の病床を効果的に活用する方法を検討し、看護部全体で入院業務の省力化や標準化を行った。その結果、取り組み前後で病床稼働率は79.9%から88.6%に上昇し、2024年2月の病床稼働率は94.6%と過去最高値を更新した。急性期病院から当院へ転院するまでの待機日数の平均は1.06日短縮した。新規入院患者数が増加したものの、看護業務を見直したことで、看護部の超過勤務時間は削減され、経営にも貢献する結果を得た。
日総研接遇大賞受賞~接遇の向上~
聖隷予防検診センター 顧客サービス課

顧客サービス課では、これまで課内の接遇向上に努めてきたが、利用者からの信頼をさらに高めるためには施設全体の接遇意識改革が必要と感じていた。今回、所長・事務長の全面協力のもと、事務職だけでなく、医師や看護職、コメディカルなど全職種を対象とした、施設全体の接遇意識改革に着手した。これまでに、施設全体に向けた目標設定や動画による勉強会、接遇チェックリストの活用による自己啓発等を実施することで、施設全体の接遇意識や課員のモチベーションの向上、本活動の継続意欲の向上に繋がった。また外部評価(日総研接遇大賞)を得たことにより、事業部全体へ広げていきたいというさらなる目標達成への原動力となっている。
胃部X線撮影装置の故障に伴う待ち時間対策
聖隷健康診断センター 放射線課

2023年5月に7台ある胃部X線撮影装置の内1台が故障。修理が不可能の故障で装置更新が必要となったが6台体制にて検査ができる取り組みを行った。課内スタッフの配置転換、他職種、他職場の協力、受診者へ丁寧な説明をすることで1日最大16名の検査順序を変更し、待ち時間対策および読影医師への影響がない対策をとった。対策前の6月は最大25名、45分の待ち時間が発生し、13時過ぎまで検査を行う日があった。しかし、対策後の8月からは最大30分の待ち時間、13時前には検査を終了することができた。医師の読影体制に影響を及ぼすことなく、7台体制時と同様の時間内で検査を行うことができ、装置更新をせず運用ができた。
他院から過去検査画像を取り寄せることで、当院で受診歴がない受診者にもマンモグラフィ検査の比較読影を可能に
聖隷健康診断センター 放射線課

マンモグラフィ検査(以下MMG)の読影は、過去に撮影したMMG画像と比較読影をするのが望ましい。しかし、当施設において初めての検査となった場合は比較読影ができない。精密検査の可否判断をより正確なものとするため、読影で精密検査対象となった当施設初回受診で他院受診歴のある受診者については、医師に相談し他施設へ資料提供を依頼した。提供いただいた他施設画像と比較読影することで、「精密検査対象」から「精密検査不要」に判定が変更となった割合は、健診センターで51.0%、東伊場クリニックで70.0%となった。不要な精密検査を減らし、受診者の精神的不安や医療費の負担軽減につなげることができた。
「令和5年度安全安心なまちづくり関係功労者表彰(再犯防止部門・内閣総理大臣表彰)受賞」~生活困窮世帯に対する伴走支援~
浜松市生活自立相談支援センターつながり

2015年より浜松市の受託事業として生活困窮世帯に対する支援を行っているが、支援対象の内、万引き等の軽犯罪を犯して逮捕拘留されている方が釈放後に必要な支援につながらず、生活困窮状態となり再犯を繰り返す状況が社会的に散見される。この社会的な課題に対して、釈放後に安心した生活再建ができるよう釈放者の支援を実施してきたが、この度、静岡地方検察庁より推薦され『令和5年度安全安心なまちづくり関係功労者表彰(再犯防止部門・内閣総理大臣表彰)』を授与された。
送迎システム「らくぴた送迎」導入によるスムーズな送迎対応
聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター

運転員の人材確保が困難な状況と高齢パート職員による送迎の制限等があり、曜日や送迎ルートによって送迎時間が固定化できない現状があった。このことが利用者の不安につながり、施設に出発確認の電話がかかってくるケースや、事業所より遅延の連絡をする業務負担があった。そこで送迎システム「らくぴた送迎」の自動応答サービスを活用し、到着予定時刻を知らせるようにしたところ、利用者の待機時間の不安解消とお迎え時刻が予測可能となることで出発準備ができるようになった。円滑な送迎により朝の送迎時間が10分以上短縮され、利用者からの送迎に関する電話対応も減り、業務を改善できた。
サロン活動で出た廃材を活用し、近隣の放課後等デイサービスで使う備品を作成
浜名湖エデンの園 居室サービス課 機能訓練係

職員家族が通う放課後等デイサービスで、活動で使用するものをスタッフが手作りしていると聞いた。浜名湖エデンの園の生活機能低下予防プログラムの活動で出る画用紙の廃材を何かに活用したいと思っていたことや、制作に入居者が意欲的に取り組んでくださることから、入居者の提案も加えながら、放課後等デイサービスのお箸トレーニングで使う小物を作成し、寄附した。入居者にとってただの認知症予防や居場所作りに留まらず、地域貢献や生きがいを感じてもらえる楽しい活動になったと同時に、放課後等デイサービスの子供たちにも大変好評だった。継続的に簡単に制作できる物であるため、子供の「ほしい!持って帰りたい!」にも対応できた。