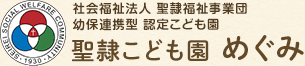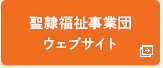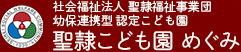園長 冨永 裕美
朝夕の風の心地良さ、聴こえてくる虫の音に秋の訪れを感じるようになりました。季節の変わり目で気温差も大きく、また夏の疲れから体調を崩しやすい時期です。生活リズムを整え、健康に過ごせるよう十分注意していきましょう。
さて、先月より園では年長クラスの保護者の皆さんを対象に「就学前面談」を行っています。園での生活も残り半年余りとなる中、園での様子をお伝えしたり、家庭での様子を伺ったりしながら子どもたちの成長の様子を確認し合い、小学校という新しい環境へとつながっていくこれからの大切な時期を出来るだけ充実して過ごしていけるよう色々なお話をする貴重な時間となっています。園と家庭とで共通している姿もあれば、家庭では見られない姿が園で見られたりと新しい発見もあるようです。また、大人が子どものことを思い心配するあまり、できないことやこうなってほしいと思うことに目が向き「学校に行ったら困っちゃうよ」などと言葉をかけがちです。反対にいつの間にかできるようになっていることは当たり前のことと感じてしまう場合が多いように思いますが、子どもの成長を具体的に言葉にして「本当に大きくなったね」などと伝えてあげることがとても大切ですねなどとお話をしています。面談の機会に色々なお話をする中で、ご家庭が子どもたちの心の安定にいかに繋がっているかを改めて感じています。保護者の皆さん、そして園では私たち職員が子どもたちとしっかりと向き合い、子どもたちが自分は大切にされている、愛されていると日々感じ、自己肯定感を育みながら成長していくことができるよう見守っていきたいと思います。心の安定は、新しい世界に一歩踏み出す力になっていきます。様々なことに挑戦できるよう働きかけながら、子どもの成長を喜びあい、自信が積み重なっていくよう今後も子どもたちそして保護者の皆さんとの関わりを大切にしていきたいと思います。ぺんぎん・いるか組でも保育参加に多数参加していただきありがとうございました。保育参加後に保護者の皆さんとお話しする時間を少しずつですが持つことができ子どもたちの成長を共有する機会となりました。また乳児クラスの保育参加も始まりましたので是非ご参加ください。こうした機会の中で園での様子を垣間見ていただいたり、お子さんのことをお話しする機会にし、家庭と園とで子どもたちの成長を見守っていきましょう。
夏の間楽しんだ水遊びを終え、やっと戸外遊びが楽しめるようになってきました。お散歩に出かけたり、園庭で過ごしたりと戸外での遊びが活発になってきました。遊歩道やまな広場、愛光園のお庭では小さな草花や虫たちとの出会いもあります。子どもたちは、戸外で里の自然に触れたり、体を沢山動かしたりしながら、好きなことを見つけ夢中になって遊ぶ経験を繰り返しています。私たちこども園が基本としている認定こども園教育保育要領及び保育所保育指針には、「乳幼児期は、生活の中で興味・関心や欲求に基づいて、自ら周囲の環境に関わるという直接的な体験を通して、心身が大きく育っていく時期である。子どもは身近な人やものなどあらゆる環境からの刺激を受け、経験の中で様々なことを感じたり、新たな気づきを得たりする。そして充実感や満足感を味わうことで、好奇心や自分から関わろうとする意欲を持って、より主体的に環境と関わるようになる。」とあります。これらは、決してバーチャルな体験では得られないものであって、自分の体を使った直接的な体験が大切になってきます。子どもが自らの力でやりたいことを見つけ、集中して遊ぶ中で、興味関心が広がり、遊びを工夫しようと考える力が育ちます。また、からだを思い切り動かして遊ぶ事の楽しさを知り体力がついていく事も乳幼児期の発達に大きく関わります。子どもたちの様々な力を育てていくためにも、好きな遊びを夢中になって楽しむことを、園生活の中でも大切にしていきたいと思っています。
今月は乳児クラスの「親子ふれあいひろば」と、幼児クラスの「めぐみっこひろば」が予定されています。乳児クラスでは、子どもたちの今楽しんでいることを保護者の皆さんにも知っていただく機会としていきたいと思っています。そして親子でのふれあいを楽しんでいただきたいと準備しています。幼児クラスではそれぞれの年齢にあった内容を考えていますが、体を思い切り使って楽しんだり、挑戦したりする中で、失敗したり、悔しい思いをしたり、達成感を味わったりと一つひとつの経験が子どもの成長の機会になればと思っています。保護者の皆さんと一緒に子どもたちを応援していきたいと思っていますので、ご協力をお願いいたします。
最後になりますが、能登半島での1月の地震に続く今回の豪雨災害に心が痛みます。被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、私たちにできることとして被災地に思いを寄せお祈りすること、少し先になりますがクリスマスの献金も送りたいと考えています。子どもたちと日々のお祈りの中で思いを寄せていきたいと思っています。
朝夕の風の心地良さ、聴こえてくる虫の音に秋の訪れを感じるようになりました。季節の変わり目で気温差も大きく、また夏の疲れから体調を崩しやすい時期です。生活リズムを整え、健康に過ごせるよう十分注意していきましょう。
さて、先月より園では年長クラスの保護者の皆さんを対象に「就学前面談」を行っています。園での生活も残り半年余りとなる中、園での様子をお伝えしたり、家庭での様子を伺ったりしながら子どもたちの成長の様子を確認し合い、小学校という新しい環境へとつながっていくこれからの大切な時期を出来るだけ充実して過ごしていけるよう色々なお話をする貴重な時間となっています。園と家庭とで共通している姿もあれば、家庭では見られない姿が園で見られたりと新しい発見もあるようです。また、大人が子どものことを思い心配するあまり、できないことやこうなってほしいと思うことに目が向き「学校に行ったら困っちゃうよ」などと言葉をかけがちです。反対にいつの間にかできるようになっていることは当たり前のことと感じてしまう場合が多いように思いますが、子どもの成長を具体的に言葉にして「本当に大きくなったね」などと伝えてあげることがとても大切ですねなどとお話をしています。面談の機会に色々なお話をする中で、ご家庭が子どもたちの心の安定にいかに繋がっているかを改めて感じています。保護者の皆さん、そして園では私たち職員が子どもたちとしっかりと向き合い、子どもたちが自分は大切にされている、愛されていると日々感じ、自己肯定感を育みながら成長していくことができるよう見守っていきたいと思います。心の安定は、新しい世界に一歩踏み出す力になっていきます。様々なことに挑戦できるよう働きかけながら、子どもの成長を喜びあい、自信が積み重なっていくよう今後も子どもたちそして保護者の皆さんとの関わりを大切にしていきたいと思います。ぺんぎん・いるか組でも保育参加に多数参加していただきありがとうございました。保育参加後に保護者の皆さんとお話しする時間を少しずつですが持つことができ子どもたちの成長を共有する機会となりました。また乳児クラスの保育参加も始まりましたので是非ご参加ください。こうした機会の中で園での様子を垣間見ていただいたり、お子さんのことをお話しする機会にし、家庭と園とで子どもたちの成長を見守っていきましょう。
夏の間楽しんだ水遊びを終え、やっと戸外遊びが楽しめるようになってきました。お散歩に出かけたり、園庭で過ごしたりと戸外での遊びが活発になってきました。遊歩道やまな広場、愛光園のお庭では小さな草花や虫たちとの出会いもあります。子どもたちは、戸外で里の自然に触れたり、体を沢山動かしたりしながら、好きなことを見つけ夢中になって遊ぶ経験を繰り返しています。私たちこども園が基本としている認定こども園教育保育要領及び保育所保育指針には、「乳幼児期は、生活の中で興味・関心や欲求に基づいて、自ら周囲の環境に関わるという直接的な体験を通して、心身が大きく育っていく時期である。子どもは身近な人やものなどあらゆる環境からの刺激を受け、経験の中で様々なことを感じたり、新たな気づきを得たりする。そして充実感や満足感を味わうことで、好奇心や自分から関わろうとする意欲を持って、より主体的に環境と関わるようになる。」とあります。これらは、決してバーチャルな体験では得られないものであって、自分の体を使った直接的な体験が大切になってきます。子どもが自らの力でやりたいことを見つけ、集中して遊ぶ中で、興味関心が広がり、遊びを工夫しようと考える力が育ちます。また、からだを思い切り動かして遊ぶ事の楽しさを知り体力がついていく事も乳幼児期の発達に大きく関わります。子どもたちの様々な力を育てていくためにも、好きな遊びを夢中になって楽しむことを、園生活の中でも大切にしていきたいと思っています。
今月は乳児クラスの「親子ふれあいひろば」と、幼児クラスの「めぐみっこひろば」が予定されています。乳児クラスでは、子どもたちの今楽しんでいることを保護者の皆さんにも知っていただく機会としていきたいと思っています。そして親子でのふれあいを楽しんでいただきたいと準備しています。幼児クラスではそれぞれの年齢にあった内容を考えていますが、体を思い切り使って楽しんだり、挑戦したりする中で、失敗したり、悔しい思いをしたり、達成感を味わったりと一つひとつの経験が子どもの成長の機会になればと思っています。保護者の皆さんと一緒に子どもたちを応援していきたいと思っていますので、ご協力をお願いいたします。
最後になりますが、能登半島での1月の地震に続く今回の豪雨災害に心が痛みます。被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、私たちにできることとして被災地に思いを寄せお祈りすること、少し先になりますがクリスマスの献金も送りたいと考えています。子どもたちと日々のお祈りの中で思いを寄せていきたいと思っています。