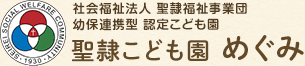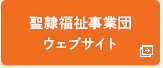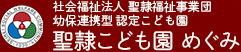園長 冨永 裕美
6月に入り、あじさいの花も色づき始め、梅雨入りが近づいてきています。季節の変わり目、また新しい生活からの疲れも出やすい時期です。生活リズムを整え、体調を崩さないように過ごしていきたいですね。
さて、子どもたちの様子を見ていますと、新しいクラスでの生活にも少しずつ慣れてきているようで笑顔も増えうれしく思います。安心して過ごせるようになってきた子どもたちは毎日、室内や戸外での遊びを楽しんでいます。乳児クラスの子どもたちはといえば、担任の先生が一緒にいることで安心して、探索活動が広がっているようです。好きな玩具や、好きな場所、好きな遊び興味の幅も少しずつ広がっています。幼児クラスになると子どもたちの興味関心の幅はますますぐっと広がっていきます。年齢や発達によっても違ってきますが、自分の好きなことを見つけ集中してじっくり遊ぶ中で、また仲間と一緒に活動する中で「やってみたい」「これは何だろう」という気持ちが生まれてきます。そして、心が動かされた事柄や現象に対して見たり、触れたり、試したり具体的な体験を通して物事の理解を深めていきます。毎日繰り広げられているこうした子どもたちの世界は一つひとつ意味があり、大切にしていかなくてはと思っています。
先日クリストファー大学国際教育学部 教授 鈴木光男氏の「これまでの保育とこれからの保育~今だからこその手間暇保育のススメ~」という興味深いお話を聞く機会があり、こうした思いを強くしました。子どもたちを取り巻く社会は日々大きく変化しています。スマホやユーチューブなどは子どもたちにとって身近なものになっているのかもしれません。さらに生成AI、チャットGPTといったAI社会は確実に進んできています。自分で考えるAIがあらゆるものに組み込まれ、いろいろな分野で活躍していきそうです。子どもたちが成長していく社会の中でこうした状況は切り離せないものになっていくことは間違いありません。しかし便利になる一方で、様々なことをバーチャルの中で経験していくことの影響は危険性も含んでいるのかもしれません。実際に対人関係が苦手な子どもや若者が増えたり、生き物に触れるのも苦手、そのような報告もあります。そんな時代に何が大切であり、何を大切にしたいのか考えていくことが必要であると話されました。お話の中では、自分の身体を動かしてみない限り正常な発達ができないという実験結果も紹介されました。頭で学んだ知識も体・五感を使って初めて意味を形作っていくというのです。身近な自然環境や地域資源、特に多様な人との関りは感性と人生を豊かにする、と話されました。こども園の生活の中でも、実体験を積み重ねられるように、子どもが自ずと「やりたい!」となるような環境を手間暇かけて作り、子どもの挑戦を見守り、豊かな遊びとなるように支援していくこと、プロセスを振り返り手間暇かけて評価することが求められています。こども園めぐみでの毎日の中で子どもたちの豊かな実体験を保証していきたいと思います。「見てみて」と子どもたちの心が思わず動き出す瞬間を大切にし、ワクワクした毎日をすごしていきたいです。保護者の皆さんにもコドモンの活動の様子にて、こうした子どもたちの心の動き、心の育ち等を発信していきたいと思います。子どもってこんなことに興味を示すのだな、こんな風に物事を感じているんだな、子どもの世界って面白いな等感じていただけたら嬉しいなと思っています。園でも家庭でもちょっとした手間暇をかけた保育・育児が子どもたちの心の豊かな育ちにつながっていくのではないのかなと思います。
6月に入り、あじさいの花も色づき始め、梅雨入りが近づいてきています。季節の変わり目、また新しい生活からの疲れも出やすい時期です。生活リズムを整え、体調を崩さないように過ごしていきたいですね。
さて、子どもたちの様子を見ていますと、新しいクラスでの生活にも少しずつ慣れてきているようで笑顔も増えうれしく思います。安心して過ごせるようになってきた子どもたちは毎日、室内や戸外での遊びを楽しんでいます。乳児クラスの子どもたちはといえば、担任の先生が一緒にいることで安心して、探索活動が広がっているようです。好きな玩具や、好きな場所、好きな遊び興味の幅も少しずつ広がっています。幼児クラスになると子どもたちの興味関心の幅はますますぐっと広がっていきます。年齢や発達によっても違ってきますが、自分の好きなことを見つけ集中してじっくり遊ぶ中で、また仲間と一緒に活動する中で「やってみたい」「これは何だろう」という気持ちが生まれてきます。そして、心が動かされた事柄や現象に対して見たり、触れたり、試したり具体的な体験を通して物事の理解を深めていきます。毎日繰り広げられているこうした子どもたちの世界は一つひとつ意味があり、大切にしていかなくてはと思っています。
先日クリストファー大学国際教育学部 教授 鈴木光男氏の「これまでの保育とこれからの保育~今だからこその手間暇保育のススメ~」という興味深いお話を聞く機会があり、こうした思いを強くしました。子どもたちを取り巻く社会は日々大きく変化しています。スマホやユーチューブなどは子どもたちにとって身近なものになっているのかもしれません。さらに生成AI、チャットGPTといったAI社会は確実に進んできています。自分で考えるAIがあらゆるものに組み込まれ、いろいろな分野で活躍していきそうです。子どもたちが成長していく社会の中でこうした状況は切り離せないものになっていくことは間違いありません。しかし便利になる一方で、様々なことをバーチャルの中で経験していくことの影響は危険性も含んでいるのかもしれません。実際に対人関係が苦手な子どもや若者が増えたり、生き物に触れるのも苦手、そのような報告もあります。そんな時代に何が大切であり、何を大切にしたいのか考えていくことが必要であると話されました。お話の中では、自分の身体を動かしてみない限り正常な発達ができないという実験結果も紹介されました。頭で学んだ知識も体・五感を使って初めて意味を形作っていくというのです。身近な自然環境や地域資源、特に多様な人との関りは感性と人生を豊かにする、と話されました。こども園の生活の中でも、実体験を積み重ねられるように、子どもが自ずと「やりたい!」となるような環境を手間暇かけて作り、子どもの挑戦を見守り、豊かな遊びとなるように支援していくこと、プロセスを振り返り手間暇かけて評価することが求められています。こども園めぐみでの毎日の中で子どもたちの豊かな実体験を保証していきたいと思います。「見てみて」と子どもたちの心が思わず動き出す瞬間を大切にし、ワクワクした毎日をすごしていきたいです。保護者の皆さんにもコドモンの活動の様子にて、こうした子どもたちの心の動き、心の育ち等を発信していきたいと思います。子どもってこんなことに興味を示すのだな、こんな風に物事を感じているんだな、子どもの世界って面白いな等感じていただけたら嬉しいなと思っています。園でも家庭でもちょっとした手間暇をかけた保育・育児が子どもたちの心の豊かな育ちにつながっていくのではないのかなと思います。