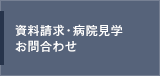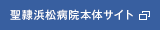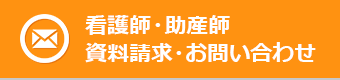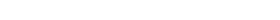ページ内リンク
日本看護協会が定める専門看護師は14分野、認定看護師はA課程21分野とB課程19分野があり、熟練した看護技術の提供や医療に携わるスタッフの教育を担います。当院においても看護ケアの質向上のために認定者の育成に力を入れています。
当院では、日本看護協会認定の専門看護師・認定看護師28名が活躍しています。また、診療看護師(NP)1名、特定行為研修修了者25名が協働し、高い臨床推論力と病態判断力に基づき患者の状態をタイムリーに捉えたケアの提供を行い、チーム医療を推進しています。
※認定看護師A課程:特定行為研修を含まない。認定看護師B課程:特定行為研修を含む。
専門看護師 7名
| 専門領域 | 人数 | 専門領域 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 精神看護 | 1 | 母性看護 | 1 |
| 老人看護 | 1 | 慢性疾患看護 | 1 |
| 小児看護 | 2 | 家族支援 | 1 |
認定看護師 21名
| 認定領域 | 人数 | 認定領域 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 救急看護 | 1 | 脳卒中リハビリテーション看護 | 1 |
| 集中ケア | 1 | 脳卒中看護(B) | 1 |
| クリティカルケア(B) | 3 | 摂食嚥下障害看護(B) | 1 |
| 新生児集中ケア | 1 | 慢性呼吸器疾患看護 | 1 |
| がん化学療法看護 | 2 | 慢性心不全看護 | 1 |
| がん性疼痛看護 | 1 | 感染管理 | 2 |
| がん放射線療法看護 | 1 | 感染管理(B) | 1 |
| 緩和ケア(B) | 1 | 皮膚・排泄ケア(B) | 2 |
診療看護師 1名
| 領域 | 人数 |
|---|---|
| クリティカル | 1 |
特定看護師 25名
| 特定行為修了区分 | 人数 | 特定行為修了区分 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 術中麻酔管理領域パッケージ | 8 | 創傷管理関連 | 2 |
| 在宅慢性期領域パッケージ | 1 | 褥瘡:血流のない壊死組織の除去 | 1 |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 16 | 感染に係る薬剤投与関連 | 2 |
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 1 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | 1 |
| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 2 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 4 |
| ろう孔管理関連 | 1 |
また、がん看護の質の向上のためにがん看護専門教育コースを開設し、がん看護を担う看護師の教育にも力を入れています。
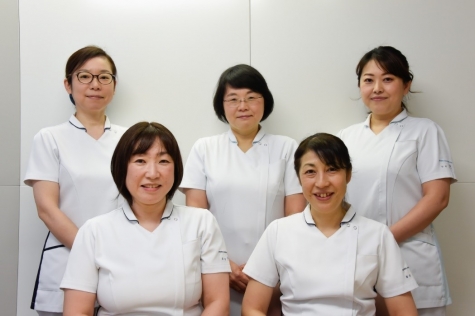
がん化学療法看護認定看護師 齋藤 佳代 柴﨑 幾代

がん化学療法看護認定看護師は、がん化学療法の専門知識をもち、患者さんとそのご家族が安心して治療を受けられるように支援します。がん化学療法の選択の時期、治療中、治療後に渡り、患者さんやご家族への情報提供や相談に応じ、治療を支えていきます。特に治療中の副作用については、患者さんの苦痛を少なくできるように、医師や薬剤師と連携して症状緩和に努めています。
また、がん化学療法に関連する知識の普及のため、看護師への学習会や指導を行っています。がん化学療法に携わるすべての看護師が、安全・確実・安楽な治療を患者さんへ提供できることを目指しています。
がん放射線療法看護認定看護師 杉村 恭子

主な活動としては、放射線治療の正しい情報の提供を行い、不安を軽減できるように努めています。
副作用の出現時期に配慮しながら、症状を低減できるように支援したり、 安全に治療が受けられるような環境を整え、他部門との調整も担います。
その他には、院内外の看護師を対象に学びの場を設け、放射線療法看護の普及に努めています。
緩和ケア認定看護師(特定看護師) 梅田 靖子

また治療中の症状や外見の変化のつらさ、治療費や仕事の悩み、お子さんや高齢のご家族への負担などの気がかりもご相談ください。患者さんやご家族一人ひとりの身体やこころなどのつらさを和らげ、あなたらしく生活を送れるように支えていきます。
お一人で悩まず、お近くの主治医や看護師に、お声がけください。
がん性疼痛看護認定看護師 吉田 恵理

がん性疼痛看護認定看護師は、がんの痛みに使用する薬剤やがんの痛みに関する最新の知識を持ち、患者さんやご家族へ痛みの緩和のためのケアや指導、不安などの相談を受けアドバイスを行います。そして、患者さんやご家族が安心して生活ができ、QOLを維持・向上できることを目指しています。
がんの痛みは身体的な痛みだけではなく、心理面・社会面・スピリチュアル面など、さまざまな要因が複雑に影響していると言われています。それらの要因を総合的に判断し、多職種で協力して適切なケアを提供していきます。また、看護師へ学習会などを行い、がんの痛みに関する知識とケアの普及に努めます。

クリティカルケア認定看護師(特定看護師) 鈴木 美由紀 林 美恵子 別所 輝哉

救急、集中治療に必要な高度な看護を培った知識・技術を生かした看護実践と同時に看護職・多職種への指導、相談にも対応しています。
また、活動の場は院内だけでなく、救急現場、災害現場などの院外に及んでいます。
いのちの最前線である現場から託された「命」と患者さんの尊厳を最優先にした「思い」を繋ぐ看護を実践しています。
救急看護認定看護師 清水 将人

救急看護認定看護師は、少ない情報の中から患者の重症度・緊急度を判断して急激な状態変化に即応した看護援助を行います。また、多種多様な疾患・外傷のある、あらゆるライフステージの患者とその家族を対象として、発症・受傷時から社会復帰するまでの幅広い領域をカバーする分野です。
そのほかの活動としては、応急手当や各分野の救急蘇生法を医療者だけでなく、要請があれば地域の皆様などにも提供しております。
集中ケア認定看護師 尾崎 彩乃


老人看護専門看護師(特定看護師) 宗像 倫子

慢性疾患看護専門看護師 山本 真矢

脳卒中看護認定看護師(特定看護師) 鈴木 千佳代

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師(特定看護師) 藤田 三貴

脳卒中リハビリテーション看護の認定看護師は、発症した時点から退院後の生活を患者さんや家族と一緒に考え、入院中の看護ケア、退院後の患者さんの生活に合わせた血圧自己測定方法や、塩分制限の食事指導などの生活指導を行っています。
脳卒中の症状は患者さんひとりひとり違い、その援助方法は個別性が重視されます。病前と違う姿に、戸惑う患者さんや家族の心に寄り添いながら、生活の再構築に向けた援助をしていきます。
慢性呼吸器疾患看護認定看護師(特定看護師) 中村 麻友美

慢性呼吸器疾患看護認定看護師は、他職種と連携をとりながら患者さんの病状や生活に合わせた支援を行っています。動作の工夫や環境の調整を行う事で息苦しさを伴う生活や、在宅酸素療法を取り入れながらの生活の中でも、患者さんとご家族がその人らしく療養できるように支援していきます。
慢性心不全看護認定看護師 近藤 理子

心不全を抱えた患者さん後家族だけでなく、療養を支援する医療専門職の方からのご相談も受けています。
摂食嚥下障害看護認定看護師(特定看護師) 二橋 美津子

専門・認定看護師が連携し、妊娠前から出産・育児を行なう過程で、女性とその家族が安心して妊娠・出産・育児ができるよう、また疾患や障がいを抱えた子どもがその子らしく成長・発達できるよう継続的に関わり、子どもとその親・家族が健全に育まれるように支援しています。

母性看護専門看護師 爪田 久美子

普段は産科病棟で勤務していますが、必要に応じて産科外来・小児科・NICU等にも出向きます。
小児看護専門看護師 鈴木 さと美 一柳 雄輔

又、多職種と連携しながら子どもと家族中心のケアの質の向上に貢献する役割を担い、子どもと家族にとっての最善の目標を考える看護実践を大切にしています。
主な活動内容は、 入院中、または在宅療養されている子どもと家族を対象とし、子どもと家族の意向を尊重した医療・看護が提供できるよう、多職種と連携し支援を検討しています。又、治療・療養の場面における倫理的課題を把握し、最善の支援をスタッフとともに検討しています。
新生児集中ケア認定看護師(特定看護師) 寺部 宏美

家族支援専門看護師 加藤 智子

普段は、MFICUで患者・家族の意向を尊重した医療・看護が提供できるように、多職種と連携しながら活動しています。そして必要に応じて、病棟や外来の家族支援も行っています。
精神看護専門看護師 高橋 淳子

皮膚・排泄ケア認定看護師(特定看護師) 大杉 純子 太田川 沙織

具体的活動として、褥瘡予防と褥瘡の早期改善を目標に、褥瘡対策チームと協働しながら褥瘡回診やカンファレンス・学習会を行っています。オストミーケアでは、病棟看護師と協働して人工肛門や人工膀胱の管理や、日常生活・社会福祉制度などについて説明を行っています。また、看護スキンケア外来では、退院後もオストメイトが安心して暮らすことができるよう継続支援しています。
2022年から「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去」「創傷に対する陰圧閉鎖療法」の特定行為を開始しています。医師・褥瘡対策チーム・病棟看護師と連携して、タイムリーかつ安全に特定行為を実践することを目標に活動しています。
感染管理認定看護師 眞壁 利枝(特定看護師) 内山 沙紀(特定看護師) 澤木 由紀子

診療看護師 松村 一美

昨今では超高齢社会が到来し、医療・福祉の在り方にも変化がみられており、医療・看護ニーズはますます高度化・多様化・複雑化しています。診療看護師は、患者さんの療養生活をアセスメントする看護の視点を基盤とし、さらに幅広い医学的知識を兼ね備えることで、治療と療養の双方向からアプローチを行います。外来から退院まで継続的に関わり、病状の変化にはタイムリーな医療的介入を行うことで、安心して療養生活を過ごしていただけるよう努めていきます。また、患者さんの生活に合わせた療養指導や意思決定支援、地域とのシームレスな連携の強化などを目指して活動していきます。