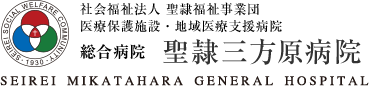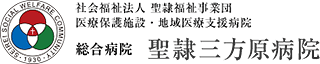このたび、私のこれまでの医師としての歩みや取得した資格、留学での経験、そして日々大切にしている考え方について、病院サイトにまとめて掲載いたしました。医師を目指す学生さんや若い医師の皆さんにとって、進路を考える上での一助となれば幸いです。 どうぞご一読いただければと思います。
院長 山本貴道
ふじのくに地域医療支援センター「静岡県で活躍する医師」に取材記事が掲載されました。こちらも是非ご覧下さい。
「静岡県で活躍する医師」病院長 山本貴道 医師(2025年3月)*外部サイトへ移動します
院長 山本貴道
ふじのくに地域医療支援センター「静岡県で活躍する医師」に取材記事が掲載されました。こちらも是非ご覧下さい。
「静岡県で活躍する医師」病院長 山本貴道 医師(2025年3月)*外部サイトへ移動します
経歴
| 1980年3月 | 静岡県立清水東高校理数科卒業 |
| 1980年4月 | 浜松医科大学医学部入学 |
| 1986年 | 浜松医科大学医学部 卒業・同大学脳神経外科入局 |
| 1987年 | 総合病院 聖隷三方原病院 脳神経外科研修医 |
| 1988年 | 東京厚生年金病院 (現・JCHO東京新宿メディカルセンター) 麻酔科研修医 |
| 1988〜1992年 | 浜松医科大学 脳神経外科関連病院研修医 |
| 1992年 | 脳神経外科専門医取得 |
| 1992〜1998年 | 浜松医科大学 脳神経外科関連病院勤務 |
| 1998年 | 渡米・Department of Neurosurgery, State University of New York, Upstate Medical University, Syracuse, NY |
| 2001年 | Department of Neurosurgery & Comprehensive Epilepsy Center, New York University Langone Medical Center, New York, NY |
| 2003年 | New York University Wagner Graduate School of Public Service, New York, NY |
| 2004年 | ニューヨーク大学ワグナー公共政策大学院 修士課程修了 浜松医科大学 脳神経外科帰局 |
| 2004年 | 総合病院 聖隷浜松病院 脳神経外科 |
| 2008年 | 総合病院 聖隷浜松病院 てんかんセンター・センター長 |
| 2014年 | 総合病院 聖隷浜松病院 副院長 |
| 2023年 | 総合病院 聖隷三方原病院 副院長 |
| 2023年7月~現在 | 総合病院 聖隷三方原病院 院長 及び 社会福祉法人聖隷福祉事業団 理事・専務執行役員就任 |
資格
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
脳神経外科の専攻と修練の日々
浜松医大の臨床講義は臓器別のカリキュラムでしたが、その中でも脳神経系はとても興味深く勉強したのを覚えています。翌年ポリクリでしたが、脳神経外科を回った2週間で見た手術で、その思いをより強くし入局を決意しました。手術室のモニターに映し出された顕微鏡手術の映像は、まるで宝石を見ているような感覚でした。
1986年卒業と同時に脳神経外科学教室に入局。ところが脳神経外科で一人前の技量を身に付けるには年月がかかることを、入局後に身をもって知りました。最初の1〜2年目は脳神経外科救急で多忙な日々を過ごしました。研修医の頃に聖隷三方原病院にいた頃は、数日間病院に居続けることも稀ではありませんでした。その後ローテーションで麻酔科の研修となり当時の東京厚生年金病院に赴任しました。当直の日以外は夕方定時に病院を出て寮に戻るという生活でしたが、脳神経外科とのあまりの違いに、このまま脳神経外科を続けるべきか麻酔をかけながら自問する毎日でした。その時に幸いだったのは、いろいろな手術を目の前で見ることができたことです。年月をかけず身に付けられて、かつ自分に合うものはないかと、麻酔を真剣にかけつつ消化器外科・整形外科・形成外科・耳鼻科・産婦人科など興味深く「見学」させてもらいました。しかしそんなに容易く身に付けられる技術などあろうはずがなく、麻酔科の研修が終わる頃には自分なりに結論が出ました。やはり「脳神経外科」でした。
1986年卒業と同時に脳神経外科学教室に入局。ところが脳神経外科で一人前の技量を身に付けるには年月がかかることを、入局後に身をもって知りました。最初の1〜2年目は脳神経外科救急で多忙な日々を過ごしました。研修医の頃に聖隷三方原病院にいた頃は、数日間病院に居続けることも稀ではありませんでした。その後ローテーションで麻酔科の研修となり当時の東京厚生年金病院に赴任しました。当直の日以外は夕方定時に病院を出て寮に戻るという生活でしたが、脳神経外科とのあまりの違いに、このまま脳神経外科を続けるべきか麻酔をかけながら自問する毎日でした。その時に幸いだったのは、いろいろな手術を目の前で見ることができたことです。年月をかけず身に付けられて、かつ自分に合うものはないかと、麻酔を真剣にかけつつ消化器外科・整形外科・形成外科・耳鼻科・産婦人科など興味深く「見学」させてもらいました。しかしそんなに容易く身に付けられる技術などあろうはずがなく、麻酔科の研修が終わる頃には自分なりに結論が出ました。やはり「脳神経外科」でした。
その後浜松に戻り、元の忙しい生活を再開しましたが、この時にはもう迷いはありませんでした。次に立てた目標はどうやって海外で研修するかでした。中でも最も門戸が広いのは米国です。当時から日本脳神経外科学会総会では、海外から、特に米国からゲストが多数招待され、素晴らしい講演をしていました。どうやったらあのような脳神経外科医になれるのか、どうやったら彼らの下で働いて技術を身に付けられるだろうかと、そんなことばかりを考え悶々としていました。当時も現在も米国で臨床をやるのに最低限必要なのはECFMG Certificateです。入局した脳神経外科では教授以下4名の先生方がこれを取得しており、米国での臨床研修を終え帰国していました。朝の回診の後に院内の喫茶店でモーニングを食べながら、その先輩から「いつアメリカに行くか分からないからECFMGは取っておいた方が良いよ」と言われたのを鮮明に覚えています。学生時代から興味はあったので、少しは洋書を揃え勉強はしていましたが、本格的に勉強し始めたのはこの頃からです。普通に臨床をやりつつ、時間ができるとすぐに図書室に籠りECFMGの問題集を解いていました。週末は当番でなければ、全てその準備に費やしました。休みの日は一日中勉強していた記憶があります。
米国留学
ECFMG Certificateを取得後渡米し、米国でやっと臨床の世界に入った時の緊張感と感激は忘れられません。マンハッタンは常に道路が渋滞している感じで、朝は早く出て6時半には回診。7時半から手術が始まり、午前中に1件目を終了。軽くランチを食べ、昼過ぎから2件目です。てんかん外科では午後に長い手術を入れることが多かったので、夜は21時とか22時になり、そのまま病院内の空いている当直室を見つけて休むことが多々ありました。隔週で週末は呼出しからも解放され全くフリーになれるので、家族とセントラルパークに出かけたり、郊外のアウトレットにショッピングに行ったりと、気分転換ができました。ブロードウェイのミュージカルも偶にですが観に行きました。そんな時は「ああ、ここはニューヨークだ」と感激したものです。
米国では簡単に医療訴訟が起こります。そのため医療安全のシステムは当時の日本とは比較にならないくらい発展していました。また提供される医療の格差や差別が顕著で、一体この国では何が起きているのかと、米国の医療システムを詳しく勉強したくなりました。臨床で区切りがついた所で主任教授と相談し、医療政策・医療管理を学ぶため同じNYUの大学院へ入りました。しかし実際始めてみると、大量の予習と論文にまとめる作業が膨大で、精神的には米国で最も大変な時期を過ごしました。これだけ英語を読み書きした時期はこれが最初で最後だったと思います。米国の大学院に入るのは、言われている通りそれ程難しくはない印象ですが、進級と卒業は予想以上に厳しく周囲の何人かは退学していきました。年末のクリスマスの時期、ニューヨークはとても華やかに彩られます。中でもロックフェラーセンターの巨大なクリスマスツリーは圧巻です。そんな中、担当教授と論文の読み合せを行い、修士課程修了の許可を得た時は安堵で胸が一杯になりました。間もなく家族と共に華やかなニューヨークを後にし帰国の途に着きました。
米国では簡単に医療訴訟が起こります。そのため医療安全のシステムは当時の日本とは比較にならないくらい発展していました。また提供される医療の格差や差別が顕著で、一体この国では何が起きているのかと、米国の医療システムを詳しく勉強したくなりました。臨床で区切りがついた所で主任教授と相談し、医療政策・医療管理を学ぶため同じNYUの大学院へ入りました。しかし実際始めてみると、大量の予習と論文にまとめる作業が膨大で、精神的には米国で最も大変な時期を過ごしました。これだけ英語を読み書きした時期はこれが最初で最後だったと思います。米国の大学院に入るのは、言われている通りそれ程難しくはない印象ですが、進級と卒業は予想以上に厳しく周囲の何人かは退学していきました。年末のクリスマスの時期、ニューヨークはとても華やかに彩られます。中でもロックフェラーセンターの巨大なクリスマスツリーは圧巻です。そんな中、担当教授と論文の読み合せを行い、修士課程修了の許可を得た時は安堵で胸が一杯になりました。間もなく家族と共に華やかなニューヨークを後にし帰国の途に着きました。
現在の仕事内容と現況
院長職ですが現在もまだ臨床は継続しています。外来もやれば手術にも入ります。希望して通ってきてくれる患者さんも多くいらっしゃるので、出来るだけ続けようと考えています。一方で病院経営のマネジメントは材料費の高騰や人件費率の上昇で極めて大変な仕事になっています。病床の稼働率をはじめ様々な病院指標を事務方と検討し、方向性を見極める会議を頻繁にやっています。
それ以外に医療安全など病院機能を改善させることも、院長の重要な仕事の一つです。就任後間もなく院長直下にTQM (Total Quality Management) センターという組織を立ち上げました。このセンターは医療安全管理室・感染管理室・病院機能管理室を包括しており、様々な案件に対し迅速に動くことができています。院内でサーベイを繰り返し、業務の改善点を見つけ出し、現場と相談しながら修正を促しています。経営もそうですが、このような医療の質や安全といった考え方は、ニューヨーク大学ワグナー公共政策大学院で学んだことがとても役立っていると感じます。現在は国内でも医療・病院経営を学ぶことができる大学院があるので、興味のある方は短期間でも行ってみると良いと思います。
聖隷三方原病院の理念は「キリスト教精神に基づく隣人愛」です。本邦で最初にできた独立した病棟としてのホスピスには教会もあり、クリスチャンが設立した「聖隷」が今も息づいていると感じます。病院はハラスメントの生じやすい組織と言われています。そのため全ての職員が気持ち良く働けるような仕組み作りが重要です。「仕事に厳しく、人には優しく」と患者さんには勿論、スタッフ同士でも温かく接することのできる雰囲気になるように気を配っています。


院内サーベイの様子
若手医師や医師を目指す方へのメッセージ
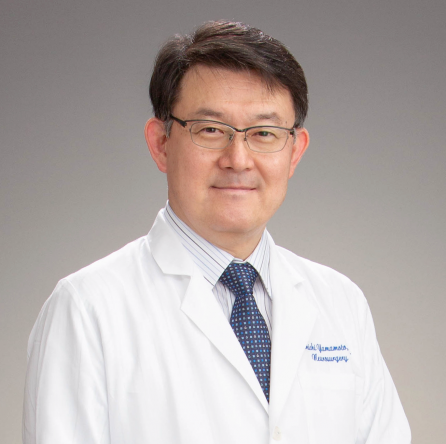
現在では初期研修が2年間あり、その間に専攻を決められます。興味のある診療科を回って、本当に自分に合っているのか確かめることも可能です。ぜひ若手の皆さんには、後悔の無い選択をして欲しいと願っています。医師になって数年間は慣れるのに大変な時期で、気持ちが揺らぐ時が多いと思います。私も前述したように大いに悩みました。しかし現在では自分の選択は正解だったと確信しています。
医学部を目指しておられる高校生の皆さんは勉強が大変だと思います。大学に入学して一時的には解放される感覚はありますが、医師としての一生は結局のところ勉強の連続です。医学部における進級も厳しい場合がありますし、医師国家試験も更にストレスがかかります。医師になってからも、最初はテキストを買って勉強して、そこから先は最新の論文を読み続けることになるでしょう。医学部受験はそのような長いプロセスのほんの一時と思います。集中して頑張って下さい。そしてその後に続く長い医師生活に向けての余力を残しておいてください。これは即ち、医学部合格は最終目標ではなく自らの人生設計を達成するための道程の関所の一つ、或いは手段の一つ程度に捉えることだと思います。医師という職業はその内容が多岐にわたり、何か自分に合った診療科を見つけられるはずです。皆さんの努力が実ることを祈念しております。
医学部を目指しておられる高校生の皆さんは勉強が大変だと思います。大学に入学して一時的には解放される感覚はありますが、医師としての一生は結局のところ勉強の連続です。医学部における進級も厳しい場合がありますし、医師国家試験も更にストレスがかかります。医師になってからも、最初はテキストを買って勉強して、そこから先は最新の論文を読み続けることになるでしょう。医学部受験はそのような長いプロセスのほんの一時と思います。集中して頑張って下さい。そしてその後に続く長い医師生活に向けての余力を残しておいてください。これは即ち、医学部合格は最終目標ではなく自らの人生設計を達成するための道程の関所の一つ、或いは手段の一つ程度に捉えることだと思います。医師という職業はその内容が多岐にわたり、何か自分に合った診療科を見つけられるはずです。皆さんの努力が実ることを祈念しております。