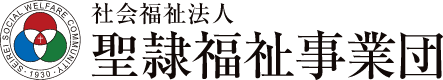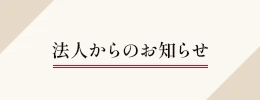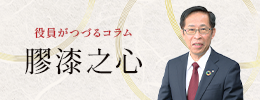聖隷淡路病院の経営移譲
国立病院移譲までの経緯
1.淡路町と国立明石病院岩屋分院
国立明石病院岩屋国立明石病院岩屋分院(以下岩屋分院といいます) は国立病院等の再編成計画により統廃合の対象となり、2000年(平成12年) 年度末までの対処方策決定を迫られていました。これを受けて、1997年(平成9年) 淡路町では「淡路町地域医療に関する検討委員会」を設置し、地域医療体制の整備についての検討し、町議会において地域の中核病院としての体制整備ができる機関への移譲が望ましいという決議がされました。
2.聖隷淡路病院の誕生
聖隷福祉事業団が岩屋分院(淡路)を移譲先候補として選択した主な理由は以下の点があげられます。
①北淡地域の発展
1998年(平成10年)明石海峡大橋の開通で淡路島と本州のアクセスが格段に良くなり、医療が必要な島民は明石市や神戸市に受診していましたが、聖隷福祉事業団としてはこの状況に「医療をきちんと整備し安心して生活できるようにならなければ、この地域の発展はない」と考えました。そこで当時、当法人が開設準備を進めていた特別養護老人ホーム淡路栄光園(1999年4月開設)と共に保健・医療・福祉を総合的に整備し、北淡地域の子どもから高齢者が24時間安心して生活できる地域となるよう支援させていただきたいと考えました。
②特別養護特別養護老人ホーム淡路栄光園の医療支援
当時、当事業団では1999年(平成11年) 年4月に開設する淡路町初の特別養護老人ホーム「淡路栄光園」の準備中であり、高齢者福祉施設にとって医療の確保は重要な問題であり、経営移譲によりその解決が図れると考えました。
③地域の認知度向上
静岡県浜松市の聖隷が淡路島民の信頼を得て、認知されるには相当な努力と時間を要すため、聖隷精神をもって、病院と特養施設の運営により着実な認知度向上を目指したいと考えました。
④淡路地区の効果的な人事交流
特別養護老人ホーム淡路栄光園1施設では組織が膠着するおそれがあり、病院と特養の2施設運営により効果的な人事交流を図ることができると考えました。
①北淡地域の発展
1998年(平成10年)明石海峡大橋の開通で淡路島と本州のアクセスが格段に良くなり、医療が必要な島民は明石市や神戸市に受診していましたが、聖隷福祉事業団としてはこの状況に「医療をきちんと整備し安心して生活できるようにならなければ、この地域の発展はない」と考えました。そこで当時、当法人が開設準備を進めていた特別養護老人ホーム淡路栄光園(1999年4月開設)と共に保健・医療・福祉を総合的に整備し、北淡地域の子どもから高齢者が24時間安心して生活できる地域となるよう支援させていただきたいと考えました。
②特別養護特別養護老人ホーム淡路栄光園の医療支援
当時、当事業団では1999年(平成11年) 年4月に開設する淡路町初の特別養護老人ホーム「淡路栄光園」の準備中であり、高齢者福祉施設にとって医療の確保は重要な問題であり、経営移譲によりその解決が図れると考えました。
③地域の認知度向上
静岡県浜松市の聖隷が淡路島民の信頼を得て、認知されるには相当な努力と時間を要すため、聖隷精神をもって、病院と特養施設の運営により着実な認知度向上を目指したいと考えました。
④淡路地区の効果的な人事交流
特別養護老人ホーム淡路栄光園1施設では組織が膠着するおそれがあり、病院と特養の2施設運営により効果的な人事交流を図ることができると考えました。

(旧)聖隷淡路病院
・1998年(平成10年)7月
厚生省近畿地方医務局より、国立病院・療養所再編計画
に基づき移譲についての申し出
・1998年(平成10年)8月
理事会・評議員会で移譲受入れの承認
・1998年(平成10年)12月
四者会議(厚生省、兵庫県、淡路町、聖隷)
・1999年(平成11年)4月22日
四者会議(厚生省、兵庫県、淡路町、聖隷)にて、正式
に12月1日目途に聖隷に運営移譲することを合意
・1999年6月
聖隷淡路病院開設準備室を開設
・1999年12月1日
国立明石病院岩屋分院から聖隷淡路病院として経営移譲
厚生省近畿地方医務局より、国立病院・療養所再編計画
に基づき移譲についての申し出
・1998年(平成10年)8月
理事会・評議員会で移譲受入れの承認
・1998年(平成10年)12月
四者会議(厚生省、兵庫県、淡路町、聖隷)
・1999年(平成11年)4月22日
四者会議(厚生省、兵庫県、淡路町、聖隷)にて、正式
に12月1日目途に聖隷に運営移譲することを合意
・1999年6月
聖隷淡路病院開設準備室を開設
・1999年12月1日
国立明石病院岩屋分院から聖隷淡路病院として経営移譲
聖隷淡路病院の基本構想
1.基本方針
(1)聖隷福祉事業団は、国立明石病院岩屋分院の経営移譲を受け、同院が担ってきた医療はもとより、保健・医療・福祉の連携を強化した包括的な医療が実践できる「聖隷淡路病院」を設立し、淡路島北部の信頼される中核的医療機関として住民の健康と生命を守るべく、地域の医療要求に対応した運営を行う
(2)開設当初の病院の運営は、国立明石病院岩屋分院の機能を引き継ぎ、更に、初期救急医療体制の充実、診療機能の強化を図る
(3)地域保健医療計画との整合性を図りながら、地域医師会との連携により、施設・設備の共同利用、機能分担を図り、病診・病病連携を行う
(4)予防医学の観点から、自治体、保健所、地域医師会との協力体制のもと、住民検診、企業検診の実施など地域の保健事業の充実に寄与する
(5)将来的には、高齢者等への質の高い医療を提供するため、療養型病床群の整備及びホスピスの設置ならびに在宅介護の支援を行う
2.病床規模
病床数 152床(一般)
但し、引き継ぎ時は102床とし、2001年(平成13年)4月を目途に新病棟(療養型病床群50床)を整備する
(1)聖隷福祉事業団は、国立明石病院岩屋分院の経営移譲を受け、同院が担ってきた医療はもとより、保健・医療・福祉の連携を強化した包括的な医療が実践できる「聖隷淡路病院」を設立し、淡路島北部の信頼される中核的医療機関として住民の健康と生命を守るべく、地域の医療要求に対応した運営を行う
(2)開設当初の病院の運営は、国立明石病院岩屋分院の機能を引き継ぎ、更に、初期救急医療体制の充実、診療機能の強化を図る
(3)地域保健医療計画との整合性を図りながら、地域医師会との連携により、施設・設備の共同利用、機能分担を図り、病診・病病連携を行う
(4)予防医学の観点から、自治体、保健所、地域医師会との協力体制のもと、住民検診、企業検診の実施など地域の保健事業の充実に寄与する
(5)将来的には、高齢者等への質の高い医療を提供するため、療養型病床群の整備及びホスピスの設置ならびに在宅介護の支援を行う
2.病床規模
病床数 152床(一般)
但し、引き継ぎ時は102床とし、2001年(平成13年)4月を目途に新病棟(療養型病床群50床)を整備する

(旧)聖隷淡路病院からみた明石大橋
3.主たる機能
(1)地域の中核的医療機関として必要な診療科を設置する
(2)外科系を中心とした救急患者の受け入れを24時間体制で実施する
(3)自治体、保健所、地域医師会との協力体制のもと、住民及び企業・団体に対して、人間ドック、成人病検診、定期健康診断、基本検診の保健事業を実施する
(4)訪問看護ステーションを開設し、在宅医療の支援を行う
(5)淡路島北部のの中核的医療機関として、包括医療体制(保健・医療・福祉)を実施するため、医療相談室を設置して保健医療福祉関係機関との連携を図る
4.診療科目(3診療科)
内科、外科、整形外科
(1)地域の中核的医療機関として必要な診療科を設置する
(2)外科系を中心とした救急患者の受け入れを24時間体制で実施する
(3)自治体、保健所、地域医師会との協力体制のもと、住民及び企業・団体に対して、人間ドック、成人病検診、定期健康診断、基本検診の保健事業を実施する
(4)訪問看護ステーションを開設し、在宅医療の支援を行う
(5)淡路島北部のの中核的医療機関として、包括医療体制(保健・医療・福祉)を実施するため、医療相談室を設置して保健医療福祉関係機関との連携を図る
4.診療科目(3診療科)
内科、外科、整形外科
淡路開設準備室のメンバーにアンケート聴き取り(2024年8月実施)
・沖原俊宏さん(当時の事務課)
・沖原由美子さん(当時の看護部長)
・神谷知弘さん(当時の事務課長)
・北島隆志さん(当時の事務長)
当時、移譲にあたっての困難や課題、地域・利用者等の受入れ、やりがいなどの聴き取りをした内容のまとめ
<聖隷としての移譲決断>
・当初は移譲受諾の断りを入れるところからのスタートだったとのこと。聖隷の事業として、当時の理事長が国立病院からの経営移譲を決断したということ。
・統廃合する国立病院の移譲を受けるかどうかの判断の際に聖隷理念が大きく作用したと考えられる。この地域から求められる医療提供の灯を消してはいけない、知らない地域ではあるが、国立病院廃止で困っている地域ニーズに手を差しのべることとなった。
<準備室の役割>
・準備室は、聖隷三方原病院を中心に各部署で中心的な役割を担う職員が任命されプロジェクトチームが組織された。移譲の1年以上前から組織され、準備にあたるも国立病院という旧態依然の体制に準備作業がはかどらない面もあったが、各担当が自分たちの役割分担を真面目にこなすことができた。
・準備室における医師・看護・医療技術・事務の連携は短期プロジェクトでは必要であり、混乱なき体制変更に有効であった。それにしても移譲における事務処理や手続き関係で、官民(国立と民間)のスピード感の違いに戸惑いながら移譲手続きを行った。(窓口を飛び越えて、直接、国に働きかけ、手続きが円滑に進むよう訴えることもあった)
<職員の力>
・新病院を混乱なく動かすのに、国立病院からの転籍職員は大きな力となった。また、医師が刷新する中で、神戸大から志ある医師の存在は大きかった。
<運営体制のこと>
・国立時代の封建的な運営体制から聖隷の運営体制(職種間で意見が言い合えるようなこと)に切り替わりが図れた。
・移譲後の経営戦略においては、やや現場任せとなり聖隷本部からのフォローがなくなってしまった。本部と現場の情報の不徹底さが課題としてあった。
<地域の協力、受入れ>
・生活面において2つの大きな地域グループの存在があったが、地域において中立的なスタンスをとり、病院運営することにより、大きな混乱をすることなく、次第に地域に受け入れられていった。
・地域に望まれている病院だからこそ、患者反応については悪い印象を与えたものは少なく、むしろサービス提供や接遇面での評価は高まった
<聖隷職員へのメッセージ>
・時節柄、専門特化した事業展開が主流となっているが、かつての理念実践のため自分の領域以外のことにも、わからなくても真摯に取り組んだ姿勢は大切にしてほしい。地域に優しい聖隷は職員も優しく大切にしてほしい。
・沖原由美子さん(当時の看護部長)
・神谷知弘さん(当時の事務課長)
・北島隆志さん(当時の事務長)
当時、移譲にあたっての困難や課題、地域・利用者等の受入れ、やりがいなどの聴き取りをした内容のまとめ
<聖隷としての移譲決断>
・当初は移譲受諾の断りを入れるところからのスタートだったとのこと。聖隷の事業として、当時の理事長が国立病院からの経営移譲を決断したということ。
・統廃合する国立病院の移譲を受けるかどうかの判断の際に聖隷理念が大きく作用したと考えられる。この地域から求められる医療提供の灯を消してはいけない、知らない地域ではあるが、国立病院廃止で困っている地域ニーズに手を差しのべることとなった。
<準備室の役割>
・準備室は、聖隷三方原病院を中心に各部署で中心的な役割を担う職員が任命されプロジェクトチームが組織された。移譲の1年以上前から組織され、準備にあたるも国立病院という旧態依然の体制に準備作業がはかどらない面もあったが、各担当が自分たちの役割分担を真面目にこなすことができた。
・準備室における医師・看護・医療技術・事務の連携は短期プロジェクトでは必要であり、混乱なき体制変更に有効であった。それにしても移譲における事務処理や手続き関係で、官民(国立と民間)のスピード感の違いに戸惑いながら移譲手続きを行った。(窓口を飛び越えて、直接、国に働きかけ、手続きが円滑に進むよう訴えることもあった)
<職員の力>
・新病院を混乱なく動かすのに、国立病院からの転籍職員は大きな力となった。また、医師が刷新する中で、神戸大から志ある医師の存在は大きかった。
<運営体制のこと>
・国立時代の封建的な運営体制から聖隷の運営体制(職種間で意見が言い合えるようなこと)に切り替わりが図れた。
・移譲後の経営戦略においては、やや現場任せとなり聖隷本部からのフォローがなくなってしまった。本部と現場の情報の不徹底さが課題としてあった。
<地域の協力、受入れ>
・生活面において2つの大きな地域グループの存在があったが、地域において中立的なスタンスをとり、病院運営することにより、大きな混乱をすることなく、次第に地域に受け入れられていった。
・地域に望まれている病院だからこそ、患者反応については悪い印象を与えたものは少なく、むしろサービス提供や接遇面での評価は高まった
<聖隷職員へのメッセージ>
・時節柄、専門特化した事業展開が主流となっているが、かつての理念実践のため自分の領域以外のことにも、わからなくても真摯に取り組んだ姿勢は大切にしてほしい。地域に優しい聖隷は職員も優しく大切にしてほしい。
黒田名誉院長へのインタビュー(2024.10.25実施)

黒田名誉院長
昼夜を問わず、できることはしていくという聖隷職員の働きには転籍の職員は驚いていました。移譲当初は、医師の数も少なく、常勤だけで当直もまわし、皆、必死で診療にあたっていました。2006年(平成18年)に始動した新病院建築移転計画に伴い職員アンケートを実施し、新病院の目指す方向性の共有化を図り、急性期と一般・療養のバランスを取りながら地域密着型の機能を目指してきました。管理者としては、経営的に改善させられなかった責任を感じていますが、聖隷理念に従いながら地域医療に貢献できていると思います。職員に対するメッセージとしては、聖隷精神を継承し利用者中心のサービス提供に努めていただければと思います。また、聖隷淡路病院は経営的にも改善していくことを願っています。