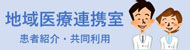聖隷佐倉市民病院は、千葉県佐倉市の地域に根差した中核病院。腎臓病・脊椎脊髄疾患・がん治療における高度な医療技術に対応。
部門別業務内容
このページの目次
病棟業務
医療機器管理業務
医療の進歩に伴い医療機器は複雑高度化しています。院内の医療機器が最良の状態で使用できるよう、使用前・使用中・使用後の日常点検と定期点検を実施しています。また、多様な医療機器を管理するために専用のソフトウェアを使用し、保守点検を適切に実施するとともに業務の効率化を図っています。

医療機器の定期点検

人工呼吸器点検の使用前点検
ペースメーカー関連業務
ペースメーカーとは、徐脈性不整脈により脈拍が低下した患者さんに埋め込みを行い、心臓へ電気刺激を送り脈拍のサポートを行う機器です。
ペースメーカー植え込み後は、定期的にペースメーカーの動作確認や各種点検が必要です。臨床工学技士は、ペースメーカー外来にて専用のプログラマーを用いて各種点検、調整を行っています。
負荷心筋シンチグラフィー検査立ち会い業務
負荷心筋シンチグラフィー検査とは心臓に負荷をかけ、その後にCTを撮影し心臓の動きを評価する検査です。心臓に負荷をかける方法は薬剤負荷と運動負荷があり、負荷をかけている間の生体情報のモニタリングを行っています。
RFA(ラジオ波焼灼術)立ち会い業務
RFAとは肝臓に経皮的に穿刺し、針から発する電流を肝臓がんに流し焼灼する治療法です。臨床工学技士は、医師の指示のもと機器の操作を行っています。
SCS(脊髄刺激療法)業務
SCS(Spine Cord Stimulation)は、脊髄の硬膜外に電極を挿入し体内植え込んだ刺激装置に接続、微弱な電流を流すことで神経障害性疼痛を緩和する治療法です。刺激装置植込みから、外来での刺激装置点検まで幅広く関わっています。
在宅酸素療法(HOT)業務
在宅で酸素を使用する患者さんに対し、導入時の説明や機器の手配を行っています。自宅で安全に過ごせるよう、酸素使用時に注意点やボンベの使用方法について指導を行っています。
LIPUS(超音波骨折治療)業務
LIPUS(Low Intensity Pulsed Ultra Sound)とは、骨折部に断続的に超音波をあて、骨折部の骨癒合を促進する医療機器です。退院後に自宅で使用できるよう使用方法の説明や導入時のサポートを行っています。
手術室業務
手術室は麻酔器、電気メス、内視鏡装置など、様々な医療機器が活躍する部署です。臨床工学技士はこれらの医療機器を管理、操作する役割を担い、常時4名のスタッフを配置し、医師・看護師と連携しながら、安全で質の高い医療に貢献しています。
~ 臨床工学室の関わり ~
整形外科では最新のナビゲーションシステムと脊椎用手術台を3台ずつ配備する他、誘発電位測定装置、自己血回収装置、顕微鏡、手術用ドリルなど、様々な機器を使用します。また、外科・呼吸器外科・泌尿器外科においても、低侵襲手術が発展するにつれて使用される機器は増加傾向にあり、これらの保守管理から術前準備、手術中の操作、トラブル対応まですべてに対応できることが臨床工学技士の強みといえます。

手術室風景

手術室~内視鏡点検~
| 2023年度 立ち会い症例数1,230件 | |
|---|---|
| 整形外科ナビゲーション | 213件 |
| 自己血回収 | 86件 |
| 術中誘発電位モニタリング | 129件 |
| 内視鏡機器対応 (外科、呼吸器外科、泌尿器科、整形外科等) | 450件 |
| 手術用レーザー | 66件 |
心臓カテーテル室業務
心臓カテーテル検査では医師・看護師・診療放射線技師と連携し、検査・治療に当たっています。臨床工学技士は3名体制で業務にあたっており、清潔介助・外回り業務・ポリグラフ業務に分かれています。
| 清潔介助 | 医師の指示のもと、清潔物品の準備やフレーミング操作等、医師のアシスタント業務を行っています。 |
|---|---|
| 外回り業務 | 使用物品の受け渡しや、検査や治療に使用される血管内エコー(IVUS)・補助循環装置の操作を行っています。 |
| ポリグラフ業務 | 検査中の生体情報のモニタリングや、検査の結果から心不全の程度や弁膜症の重症度のなどを解析します。 |

ポリグラフの操作

検査中の様子
内視鏡業務
内視鏡センターには臨床工学技士3名を配置し、検査が安全かつスムーズに進行するように電子スコープや内視鏡システムの保守管理、トラブル対応、機器の取り扱い説明等を実施しています。また医師・看護師と協力の元、医師の処置介助や患者介助を行うと共に、資格取得や学会参加を通して自己研鑽に励み、検査・治療の質向上に努めています。
消化器内視鏡技師の資格取得者 4名在籍(2025年2月)
2023年度 内視鏡対応件数
検査項目 | 件数 | 検査項目 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 上部内視鏡検査 | 1,864件 | 超音波内視鏡検査 | 48件 |
| 下部内視鏡検査 | 1,880件 | ERCP | 12件 |
| 上部EMR・ESD | 20件 | 気管支鏡検査 | 67件 |
| 下部EMR | 469件 | ||

使用前点検

内視鏡室治療風景
血液浄化業務
血液浄化療法とは、血液中から病因関連物質を除去することにより病態の改善を図る治療法の総称です。これには血液透析(HD)、血液濾過透析(HDF)、血漿交換療法(PE)、血漿吸着療法(PA)などがあります。当院では、通院透析患者の95%以上がオンラインHDFを実施しております。
水質管理
オンラインHDFでは無菌化された透析液(超純水透析液)を置換液として使用するため、透析用水の正常化が重要となります。
水質管理は日本臨床工学技士会のガイドラインに準じてエンドトキシン測定と生菌測定を行っています。

検体採取

エンドトキシン検出装置(左)と生菌培養用装置(右)
透析開始前業務

回路取り付け

透析液作成
透析開始業務

透析開始時の穿刺

シャントエコー
点検風景

定時点検

メンテナンス風景
バスキュラーアクセス(VA)管理と治療補助業務
VA異常の早期発見・早期治療を目的として、エコーを用いたVA管理を実施しています。また、VA治療においてエコーを用いた補助業務を行っています。


特殊血液浄化療法

何らかの原因で、体内に過剰に増えた血球・脂質・抗体などの分離・除去を目的とした治療法です。
| 当院で実施している特殊血液浄化療法 | 持続的血液透析濾過法(CHDF) |
|---|---|
| 血漿交換療法(PE) | |
| 二重濾過膜血漿交換(DFPP) | |
| 血液吸着療法(DHP) | |
| 血漿吸着療法(PA) | |
| 顆粒球吸着療法 | |
| 腹水濾過濃縮再静注法(CART) |
その他
持続的血液透析濾過法、腹水濾過濃縮再静注法なども行っています。