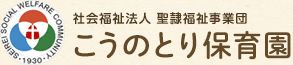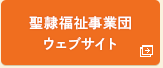- 2025年7月1日
- 共に創る
- 気温がぐんぐん上がり、日本列島の広い範囲で最高気温が35度以上の猛暑日となるなど、真夏のような6月でした。梅雨明け後も平年よりも気温がかなり高く、猛暑が予想されています。こまめな健康観察や水分補給などを心掛け、熱中症対策をはじめ、健康管理には十分気を付けていきたいと思います。
7月初めの週末に年長児のお泊り保育があります。金曜日の朝9時に登園してから、土曜日の9時に保護者の方がお迎えに来るまでの間、友達や先生と何をしてどんな風に過ごすのかを1ヶ月程前から話し合いを重ね、準備を進めています。夕食のデザートは2日がかりで決定しました。様々な遊びを通して、科学への興味関心が広がってきている為、金曜日には、浜松科学館(みらい~ら)に出掛けることになりました。館内ではグループごとの行動になります。先日パンフレットを見ながら探索経路の相談をしました。ケーキグループ(7名)は行きたいゾーンの確認から始まりました。「私は音ゾーンに行きたい」「いいじゃんそうする?」「おれ、力ゾーンがいい」「2階だからいいんじゃない」「そうだね、行ったり来たりはやめよう!」「じゃあ2階だね」と経路を考えながらも時間の意識をしていることがわかりました。科学館に到着してからの時間の流れ、昼食スペースの時間やサイエンスショー、プラネタリウムの時間を子ども達がわかりやすいように絵と文字で表しました。すると館内の探索時間が2回に分かれる事、1回目の時間の方が長いことに気付き、お昼の前(1回目)は「2階だけにしよう」と満場一致で決定し、3つのゾーンを順番に回ることになりました。階をまたぐと時間が掛かる為、2回目に1階の自然ゾーンへ、プラネタリウム見学後に同じ3階の宇宙ゾーンを覗こう!ということでまとまりました。お互いの意見を聴き合い、「それでいい?」と確認をしながら決めていったので、大きな意見の食い違いもなく進みました。私が「1回目の45分間って夢中になって遊ぶとあっという間に過ぎちゃうかもしれないから3つ目の光ゾーンに行けなくなっちゃうかもしれないね」と投げ掛けると「それは嫌だ!」「3つ行きたいよね」「どうすればいい?」とまた話し合いが始まりました。時間管理は難しいですが、3等分するような意見が出てくるのかなと思っていると…Aさんが、「わかった!2回ずつ行けばいいじゃん」と提案をしたのです。えっ?2回ずつ!?どういう事?と私が考えていると、Bさんも「それいいね!そうすれば3つ行けるじゃん」と。するとCさんが「何があるか見て、やりたいのを決めればいいね」、「いいじゃん、いいじゃん」「やりたいのやれるよね」と7人で喜んでいました。1回目は何があるのかをさっと見て回り、やりたい物を決め、2回目にそれをやって次のゾーンに行くという事でした。私が理解する前に、子ども達同士が理解をして同意していった事、私が考えもしなかった方法でまとまり、喜んでいる子ども達の姿に驚きました。当日は計画通りにいかない事も出てくると思いますが、仲間と共に考え、工夫して過ごす事を楽しみにしています。4、5歳児になると子ども達が集まって、様々なテーマについて話し合う場を作っています。子どもたちが主体的に考え、発言し、お互いの意見を聴き合うことで、より良い物や事を創り出すきっかけになっています。自分の考えを表現し、受け入れられる経験を通して、自信に繋げたり、異なる意見を持つ相手を受け入れ、尊重する態度を養ったりしながら、仲間の一員として行動する意欲へと繋がってきています。保育者は、子ども達の話し合いをサポートしたり、必要に応じて助言をしたりしますが、基本的には子ども達自身が主体的に話し合えるように見守っています。今回のように、子どもは大人とは異なる視点や発想で物事を捉えるため、私達保育者も新たな発見をすることができます。自分達で決めた事なので、たとえ失敗しても、あきらめずに最後までやり抜こうとし、子ども達ならではの工夫が生まれています。物事だけなく、共に役割や担当も決めることで、達成感や人との関係性を築くことにも繋がっていくことでしょう。お泊り保育を通して、愛されていること、愛すること、信じること、希望を持つこと等を仲間と共に経験し、心の大きな成長に繋がることを願い、子ども達を見守っていきたいと思います。
園長 梶山 美里
- 2025年6月2日
- 環境を通して学ぶ
- 色鮮やかな紫陽花の花とともに梅雨の時期がやってきました。晴れたり、雨が降ったりと自然の変化に一喜一憂する子ども達。体調を崩しやすい季節なので健康管理に気をつけていきたいと思います。
先日はお忙しい中、懇談会へご参加いただきありがとうございました。短い時間でしたが、保護者の皆様同士が顔を合わせ直接お話ができたことを嬉しく思い、感謝致します。懇談会でもお伝えさせていただいたように、子ども達は、保育園で様々な体験や経験をしています。その中でも生き物の観察は子ども達の大好きな遊びです。園庭でのダンゴムシやアリ、カエルやチョウの観察、季節によって変化する鳥類、夏野菜や稲の生長観察など、身近な生き物を通して、自然との関わりを感じ、生命の大切さを学んでいます。こうのとり保育園には毎年ツバメがやってきます。今年度は3月末の早い時期からウッドデッキに巣を作り始め、5羽のヒナがすくすく成長しています。4,5歳児クラスはA先生を中心にツバメに夢中です。本を購入し、いろいろと調べながら観察を続けています。何度も土やワラを運び、上手に重ねて巣を作っていく様子、母鳥が卵を温めている姿、ヒナが生まれ、ヒナの口に親鳥が餌を運び続ける様子、日に日に成長していくヒナの姿等、ツバメの生きる姿勢や習性、生態系の中での役割などを学んでいます。ツバメとの触れ合いを通して、子ども達は社会性、協調性、そして自然とのつながりを感じる力も身につけているのです。実はウッドデッキだけではなく、玄関、2階のテラス、2歳児のテラス(子どもの靴箱の上)にもツバメが巣を作り始めました。渡り鳥であるツバメは、風通しがよく衛生的な場所、気の流れが自然で心地よい場所、また外敵から巣を守るために人通りの多いにぎやかな場所など本能的に良いと判断した場所を選び巣を作るそうです。実際に巣を作ると、私共も管理が必要になります。一番の問題は「糞」。糞よけガードなど対策が必須になります。また、作る場所によっては園生活に支障をきたす場合があり、糞による健康被害の心配もあります。乳児クラスでは困ったあげく、撤去せざるを得ない…でもそれって本当に大丈夫?縁起物の「ツバメの巣」を壊してしまっていいのか、何よりこんなに必死に時間を掛けて作っているものを壊すだなんてと葛藤しながらも泣く泣く撤去をしました。すると作りかけていた巣が無くなってしまい、ツバメ達がパニックになり、巣があった周りをいつまでも飛び続け確認をしていました。心を痛めながらツバメの姿を見て、子ども達は何を感じていたのでしょうか。「ごめんなさい。でもね…」この気持ちを職員が子ども達にしっかり説明をし、共有をすることがとても大切なことだと思い見ていました。翌日、ツバメはまた巣を作り始めました。悩みながらも撤去。ツバメも今度は諦めたかなと思ったのですが…子どもの少ない土日に急ピッチで巣を完成させたのです。これには子ども達もビックリ!「ツバメ考えたね」「頭いいね~」と感心してしまいました。さすがに今回はツバメに譲るのかなと思いましたが、卵とヒナがいないことを確認して撤去をしました。子ども達の安全の為に決心したとの事でした。今後、ツバメと職員、子ども達の心の動きも含め、生き物達がお互いに助け合って暮らしていることを知り、自分達だけでなく、周りの人や自然環境とも対等に関わりを持てるよう見守っていきたいと思います。保育者は子どもたちがたくさんのことに触れながら、小さなことにも気付き、成長できるよう一緒に遊んだり考えたりしています。A先生のように、時には先頭に立って行動し、物事に興味を持つことも大切なことだと思います。子ども達はそんな保育者の姿を見て、成長していきます。まずはお手本となる私達大人が物事の面白さや楽しさ、美しさを感じることも大切ですね。自然からの学びは、楽しく、興味深く、記憶に残るものとなります。豊かな遊び、経験を実現するためには、子どもの気持ちをくみ取り、適切なタイミングで援助をする職員の関わりと、自由に遊びを深められる時間や空間、道具などの環境が必要です。子どもが心と頭と体をフルに働かせて、夢中で「遊び込む経験」ができるような環境を子ども達と共に創り出していきたいと思います。
園長 梶山 美里
- 2025年5月7日
- 子どもの思いを受け止める
- 磐田駅付近の街路に白とピンクのハナミズキが交互に花開き、4月の街路が色鮮やかになり、毎朝の通勤時間は心が和みました。ハナミズキにはイエス・キリストにまつわるエピソードがあり、花言葉の「永続性」「耐久性」は、キリストの忍耐や復活、変わらぬ愛にちなんでつけられ、「逆境に耐える愛」は、成長速度は他の木に比べてゆるやかですが、着実に大きくなり、美しく花を咲かせることに由来すると言われています。また、さまざまな逆境を乗り越え復活したイエス様が、人々に永遠の愛を説いたことが由来という説もあるそうです。
4月は新入園児だけではなく、在園児のお子さんも(職員も)新しい環境の中で出会い、安心して過ごすことができるように、一人ひとりの思いを受け止め、丁寧に関わる中で心と言葉を掛けながら信頼関係を深めていけるように願い、過ごしてきました。今年度は転園されてきたお子さんが数名いらっしゃいます。前園での様子を伺い、スムーズに移行できるように一人ひとり考慮させていただきながら過ごしております。前園の先生が様子を見に来て下さった時のことです。まだ慣れないお部屋で過ごすには不安があり、大好きな絵本コーナーで絵本を見ていたAさん。絵本に夢中でなかなか先生の存在に気が付きませんでした。ふと顔を上げ、先生に気が付くと、「うわぁ~○○先生」と何とも言えない優しい声で言いながら先生の頬を両手で包み込み、鼻と鼻が触れ合う程顔を近づけ、目と目を合わせて喜んだのです。安心できる大好きな先生が今ここにいることを全身で感じていました。しっかりとした深い信頼関係を感じると共に、こうのとり保育園でも安心して過ごせるように関わっていきたいと強く思いました。新しい環境が不安で泣き叫ぶお子さんの思いを受け止め、その子の思いや願いとは何なのかを理解することは容易なことではありません。その子の思いを心と身体で受け止め、あの手この手で探りながら関わっています。その子の見ている世界を探る中で、少しずつ何が好きなのかが見えてきます。歌や電車等、好きな物がヒットすると涙が止まる瞬間が増え、そこから担当保育者に抱っこされるのが少しずつ心地よく好きになり、その子が落ち着いて遊べる環境を用意すると、保育者から少しずつ離れて遊び始めます。少しずつ信頼関係が生まれ、心の安全基地ができ、そこから世界を広げていくのです。これから思いが受け止められることを重ね、やりたいことが満たされる中で、安心感が生まれ、自分に自信をもって世界を広げ、挑戦にも繋がっていくことを願っております。職員の関わりを見ていると、「おしっこ出たね。おむつ替えてもいい?」「お鼻かんでも(拭いても)いいですか?」「そろそろお部屋に入りませんか?」等「あなたはどうしたい?」を聞いています。丁寧に子ども達一人ひとりの話を聞き、伝えたいことを整理することや、共感して思いに寄り添う言葉掛けを私達保育者は心掛けています。子どもの思いを理解するために、毎日の関わりの中で、いつもの様子を熟知する担任同士が連携をし、共有していくことも大切にしております。職員会議では子ども達の様子をドキュメンテーションを基に共有します。4月は「はじめまして」「だいじょうぶ」「よろしくね」「春の自然に癒されて」「おまめくんたちと一緒に過ごした4月」等と題し、子どもの中に4月の一ヶ月の主題が物語る姿を伝え合いました。子どもも大人も、神さまに愛されていることを覚え、心穏やかに歩み進められることを願い、保護者の皆様と共に子育てをしていきたいと思っております。
園長 梶山 美里
- 2025年4月2日
- ご入園、ご進級、おめでとうございます
- 園庭の桜も咲き始め、一年の始まりをお祝いしているかのようですね。
ご入園、ご進級、おめでとうございます。今年度は17名の新入園児をお迎えして全園児132名でスタートします。新入園の皆様におかれましては、初めての園生活でもあり、不安なこともあるかと思いますが、いつでもご遠慮なくご相談してくださいね。ご家庭と協力し合って、心を通わせ、一緒に子育てをしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
在園児の保護者の皆様には、年度末特別保育にご協力いただきましたことを感謝申し上げます。新年度の準備と共に園内研修、ワークショップ等を行わせていただき、聖隷こども園・保育園職員合同研修会では、中遠教会に磐田4園の職員が集まり、キリスト教保育について考える時を持つ事が出来ました。教会に響く讃美歌、中遠教会の牧師兵藤辰也先生のお話、聖隷こども園こうのとり東園長平野春江先生の聖隷の理念と歴史、グループディスカッションを通して、職員一人ひとり、自身の保育を振り返り、愛に気付き、心に大きく響くものがありました。教会で年度末の合同研修会を行えたことに感謝をし、大きな意味を感じました。子ども達一人ひとりが受け入れられていると感じ、神の愛、愛されている自分を実感出来るように、共に育ち、子どもから学び続けられる保育者でありたいと思います。
「はじめの100ヶ月の育ちのビジョン」(こども家庭庁)をご存知でしょうか。妊娠期から小学校1年生までがだいたい100ヶ月。全ての子どもの「はじめの100ヶ月」をみんなで大切にしていきたいと考え、5つのビジョンとしてまとめています。ビジョン2に『「安心と挑戦の循環」を通して、こどものウェルビーイングを高める』とあります。子どもは、不安な時などに身近な大人が寄り添い、気持ちを受け止めてもらう経験を繰り返すことで、「アタッチメント(愛着)」<安心>を得られ、自分や周りの人を信頼していきます。この安心を土台として、様々な子どもや大人と出会い、モノ、自然、絵本、場所などと関わる「遊びと体験」<挑戦>を通して、子どもは自分の世界を広げていきます。乳幼児期の子どもは、遊びを通して、人との心の繋がりや体の感覚など、豊かで幸せに生きるための力をつけていきます。昨年度から園内研究でも学びを重ねている、遊びを通して、何に気付き、何を試し、何ができるようになったのかをしっかり観察し、「今何が育ちつつあるのか」という過程に気付くことに加え、子どもなりのペースやその子らしさに寄り添い、生活や遊びを通して子どもの育ちに必要な経験が得られるような環境(玩具)つくりが出来るように園内研修を組み立てました。4月からの新しい環境の中で、子ども達がどんな遊びと体験を重ねていくのかとても楽しみです。
子ども達一人ひとりの育ちを的確に捉え、継続して子どもを観察し、最初の一歩を踏み出せるよう、健やかでのびやかな育ちを応援し、こうのとり保育園の園児、保護者、職員皆が心と心が通い合っていけるよう保育をしていく所存でございます。
2025年度もどうぞよろしくお願い致します。
園長 梶山 美里
- 2025年3月5日
- センス・オブ・ワンダー
- 2025年2月4日
- 子どもの姿から学ぶ
- 2025年1月6日
- 心の宝探し
- 2024年12月2日
- クリスマス(神の愛)
- 2024年11月7日
- 彩り
- 2024年10月2日
- 共感
- 2024年9月17日
- 耳を傾ける
- 2024年8月5日
- 愛を知る
- 2024年7月22日
- 生きる力
- 2024年6月5日
- 葉っぱのトランプ
- 2024年5月10日
- 健やかな育ち
- 2024年4月8日
- ご入園、ご進級、おめでとうございます
- 2024年3月9日
- 通い合う心
- 2024年2月2日
- もう1回!
- 2024年1月9日
- 夢
- 2023年12月4日
- 目に見えないもの
- 2023年11月1日
- 模倣遊び
- 日中のぽかぽかとしたお日さまがより暖かく感じられる程の、朝晩の冷え込み。晩秋の気配が深まる頃となりました。子どもたちはますます深まる秋を感じながら、自然との触れ合いを楽しんでいます。
この間3歳児の部屋を覗くと、一角に椅子を並べて数人が何かをしている様子が見えました。バスごっこをしているのかな?と思い部屋に入っていくと…「うわぁ~本物が来た!」と。私(園長)役の子が3名、「礼拝ごっこ中です」と教えてくれました。「じゃあ私も入れて!子ども役になるね。」と椅子に座ると、続きが始まりました。立って讃美歌を歌い、聖句を言い、園長役の3名が司会を進めます。そしてモニャモニャお話をし、「それではお祈りをします」と手を合わせお祈りをしてくれました。最後に子ども役の子達の頭を撫でてくれます。私の頭も撫で、肩を優しく触ってくれたのです。その手から伝わる優しいぬくもりに感動し、そのまま目を閉じていると…「静かに歩いて行って下さい。」と声を掛けられ、「はい」と急ぎその場を立ったのでした。9月より4、5歳児と一緒に礼拝を守るようになり、日々子ども達の模倣遊びが繰り広げられているとのことでした。礼拝の流れが良く分かっていることに驚くと同時に、話し方や仕草等も意識して真似ている姿に思わずクスッと笑ってしまいました。何よりあの優しい手のぬくもりが忘れられません。子ども達がこのように感じているのだということを嬉しく思いました。園庭で体操やダンスをしている姿を見ていても、担任の動きをそのまま一所懸命真似るため、しっかり肘を伸ばし、指先までピンと伸びています。膝も胸に付くほど上げて万遍の笑みで踊っているのです。以前「空に届くくらい手を上に伸ばして!肘曲げないよ。」なんて言っていた自分を恥ずかしく思いました。適切な見本を示せば、子どもは大人の行動を真似るのですね。
子どもは視覚や聴覚を使って大人の動作や声を観察し、真似をしながら自分の行動や表現力を増やしていきます。3歳頃は、想像力がさらに豊かになり言語能力も向上する時期です。この時期の模倣遊びは、複数人で展開するごっこ遊びやロールプレイの割合が増え、さまざまな状況や役割を想定して遊ぶようになります。直接経験したことのない状況をイメージすることで、想像力や創造力、発想力が養われ、また、演じる役割に応じた言葉遣いや表現方法を考えることで、言語能力の向上にも繋がります。友だちとの役割分担や協力も必要になり、協力して物事を進める力やコミュニケーション能力も育ちます。そして4、5歳頃になると、言語能力や想像力が成長し、他者との協力やルールを意識した遊びができるようになり、より複雑なシナリオや役割分担が可能になります。友だちや保育者と一緒に独自のストーリーや世界観を創造して遊ぶ力が高まっていくのです。夢中・没頭する遊びの中で経験していることが子どもの育ちに繋がります。子どもは遊びのプロセスにおいて、今を超えていこうとする力(意欲)が育ち、より複雑なものへと取り組むことで、新たな力を自らのものとして獲得(成長・発達)していきます。
森の動物になりきって木の実を拾い集める3歳児、桃太郎のお話の世界の中で遊ぶ4、5歳児、友達と力を合わせ、協力して頑張る姿等々、11日に予定されているあおぞら広場では、このような子ども達の姿に注目していただき、あたたかい応援をお願い致します。
園長 梶山 美里
- 2023年10月3日
- 絵本が繋ぐ素敵な関係
- 2023年9月4日
- あたたかい心
- 2023年8月4日
- 傾聴
- 2023年7月4日
- 答えはいつも相手(子ども)の中にある
- 2023年6月5日
- 「子どもの"?“」
- 2023年5月8日
- はじめの一歩
- 2023年4月3日
- ご入園、ご進級、おめでとうございます
- 2023年3月1日
- 子どもの育ち
- 2023年2月1日
- お手伝い
- 2023年1月10日
- ハッピー&レジリエント
- 2022年12月1日
- 実りある秋に感謝
- 2022年11月7日
- 体感を育む
- 2022年10月17日
- 安心と快適
- 2022年9月1日
- 「子どものものさし」
- 2022年8月2日
- 平和を考える
- 2022年7月1日
- 子どもたちの“今”
- 2022年6月1日
- 「認める」「認め合う」
- 2022年5月9日
- 共育(きょういく)
- 2022年4月1日
- ご入園 ご進級 おめでとうございます
- 2022年3月1日
- 『 あしあと 』
- 2022年2月1日
- 『 幼児期、学童期に大切なこと 』
- 2021年12月7日
- 『意欲と自己充実の繰り返し』~みんな金メダル~
- 2021年11月1日
- 『祝 創立50周年』
- 2021年10月1日
- 『生きる力を育むアタッチメント』
- 2021年9月1日
- 『相手の気持ちになって考える』
- 2021年8月1日
- 『 子どもを見る 』
- 2021年7月1日
- 『子どもたちの輝ける未来のために』
- 2021年6月1日
- 『隣人愛 ~実習生との関わりの中で~』
- 2021年5月7日
- 『子どもたちの今が未来を創る』
- 2021年4月8日
- 「ご入園 ご進級 おめでとうございます」
- 2021年3月3日
- 『人とつながる力』
- 2021年2月3日
- 『御言葉に導かれて』
- 2021年1月7日
- 「心と心が通い合うコミュニケーション」
- 2020年12月9日
- 「心から感謝し、喜び祝う」
- 2020年11月9日
- 『豊かな感性』
- 2020年10月8日
- 『おさるのジョージ』
- 2020年9月3日
- 『心をはぐくむ』
- 2020年8月7日
- 仲間 ~ 共に育つ経験 ~
- 2020年7月2日
- 新型コロナ時代の食育
- 2020年6月1日
- 小さないのちとの出会い
- 2020年5月11日
- 遊びから学ぶ
- 2020年4月6日
- ご入園 ご進級 おめでとうございます
- 2020年3月5日
- 新しい生活(進級・卒園)を迎える大切なときに
- 2020年2月4日
- 子どもが実体験から得られるもの
- 2020年1月7日
- 新しい年も
- 2019年12月2日
- クリスマスを迎える
- 2019年11月13日
- 子どもの心に寄り添って ~自分って何だろう~
- 2019年10月3日
- 『祈る』
- 2019年9月4日
- 保育料の無償化が始まります
- 2019年8月9日
- 育ちに必要な手間をかけて ~西瓜の“ゆりかご”~
- 2019年7月1日
- 「子ども目線の評価」 ~「氷がとけると○○になる」の答えは?~
- 2019年6月4日
- 「お母さんのどこが好き?」
- 2019年5月12日
- 新しい時代『令和』
- 2019年4月2日
- ヨセフの会(お父さんの会)に支えられて
- 2019年3月7日
- 巣立ちのときを迎えて
- 2019年2月5日
- 自分を生きていく
- 2019年1月16日
- 新しい年を迎えて
- 2018年12月4日
- 神様に愛されて
- 2018年11月2日
- 自然災害から考える
- 2018年10月1日
- 海ガメ放流を通して
- 2018年9月6日
- 子どもの姿を的確に捉える保育者の目
- 2018年8月3日
- リスク回避のために ~周りの大人の丁寧な見守りを~
- 2018年7月3日
- よい子になれないわたしでも
- 2018年6月6日
- 大きな新玉ねぎの収穫
- 2018年5月8日
- こうのとり保育園が大切にしていることは
- 2018年4月2日
- 『生まれてきてくれてありがとう』
- 2018年3月1日
- 大きくなりました
- 2018年2月1日
- 主体的で対話的な深い学び
- 2018年1月11日
- 新しい年に向って
- 2017年12月1日
- 喜びの時を待つ
- 2017年11月1日
- 「こころの3大栄養素」
- 2017年10月3日
- もっと楽しく運動あそびを
- 2017年9月1日
- 子どもたちの命を守るために
- 2017年8月1日
- お泊り保育でのできごと
- 2017年7月3日
- 子どものあそび「表出」の重要性
- 2017年6月14日
- 自然は大きな保育室
- 2017年5月8日
- 愛されて育つ
- 2017年4月6日
- 出会いの中で
- 2017年3月14日
- 家庭生活と園生活がつながり合って
- 2017年2月7日
- 花育 ~五感で感じながら~
- 2017年1月6日
- 小さなことを大きな愛をもって
- 2016年12月2日
- クリスマスを迎えるために
- 2016年11月2日
- 『もったいないばあさん』と一緒に
- 2016年10月8日
- やさしい気持ち
- 2016年9月1日
- 保育環境を考える
- 2016年8月9日
- 家族から離れて友だちの中で育つ子どもたち
- 2016年8月9日
- 聖隷の始まりは
- 2016年6月3日
- 自然の中で「いのち」のつながりを感じて
- 2016年5月19日
- 子どもの持つ力を信じて
- 2016年4月6日
- 大きく豊かな愛に包まれて
- 2016年3月14日
- 成長を共に喜び合って
- 2016年2月5日
- 『共に育ち合う統合保育をめざして』
- 2016年1月5日
- 新しい年に 想いを新たに
- 2015年12月7日
- 感動の“あおぞらひろば
- 2015年11月12日
- 成長する子どもたち
- 2015年10月1日
- 秋には
- 2015年9月1日
- 共に育ち合う保育をめざして
- 2015年8月10日
- 年長組のお泊り保育 ~子どもの命を預かるために~
- 2015年7月1日
- 豊かな自然体験が育むものは
- 2015年6月2日
- 親子散歩
- 2015年5月7日
- 親子で心地よさを味わって~「もっとやりたい」~
- 2015年5月7日
- 新しい年度を迎えて
- 2015年3月4日
- 〝自分らしく〟生きていく
『意欲と自己充実の繰り返し』 ~みんな金メダル~
本格的な寒さに冬の訪れを感じる時期になりました。1年の締めくくりの月だからでしょうか、いつにも増して子どもたちの成長を感じ取っている今日この頃です。
先月は皆様のご理解、ご協力の中、無事に幼児クラスのあおぞら広場を開催できました。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。心から感謝致します。空模様を心配しながらの開催となりましたが、保護者の皆様の温かい見守りと拍手の中、子ども達が笑顔で楽しみ、力を発揮し、誇らしげに金メダルをかける姿に感動しました。アンケートのご協力もありがとうございました。「見ていて楽しかった、面白かったです」「子ども達の遊びや片づけなど生活の中からヒントを得て競技が考えられていて、年齢にも合っているなと思いました」等、お子様のクラス以外のクラスの競技(遊び)に対する感想が多いことに驚くと共に、日常の保育や当日までの過程があおぞら広場から伝わったことを本当に嬉しく思いました。4月から子ども達と楽しんできた遊びや園庭が人工芝になったことで生まれた遊び、オリンピック・パラリンピック競技から刺激、ヒントを得た遊び等々、今の子ども達の姿を大切に、子ども達と担任とで考え、創られたあおぞら広場。誰よりも担任達が楽しんでいる姿がありました。年長児が長縄に挑戦をしている時の事です。担任が絶妙なタイミングで縄を回しながら「すごい!入るタイミングが掴めたね!」「入る位置が良くなったよ」と一人ひとりに声を掛けていました。跳べた、跳べないで表情が変化する子ども達ですが、この言葉掛けで“もう1回やってみよう“と気持ちを切り替え、挑戦し続けるのです。子どもに就いてもらおうと回す役を私が交代すると、案の定タイミングが悪く跳びにくくなりました。それでも担任と一緒であれば私の下手くそな回し方でも跳べるようになっていくのです。保育者は、子どもの成長に合わせた手だてを行うために、子どもの仕草や言葉、行動の観察を大切にしています。「どこまで出来るのか、どこで躓いているのか、何が原因か」という現状把握と原因志向の視点と共に「成功したのは何が良かったのか、躓きを解消するためにどんな関わりが必要か、今後どうなって欲しいのか」という未来志向の視点で保育を考えています。子どもの姿を分析し、手だてを模索する保育力をフル活用している職員達がそこにはいました。意欲と自己充実の繰り返しが子ども達と担任と共に創り出したあおぞら広場に繋がっているのです。
クリスマスのアドベント(待降節)が始まりました。私達保育者は、神さまの愛の中で子どもの成長を育むお手伝いをさせていただいております。クリスマスの本当の意味を理解し、子ども達と共に過ごす中で、日々の生活の中に神さまがいらっしゃることが子ども達に伝わることを願い、喜びと感謝をもってクリスマスを迎えたいと思います。
園長 梶山 美里
本格的な寒さに冬の訪れを感じる時期になりました。1年の締めくくりの月だからでしょうか、いつにも増して子どもたちの成長を感じ取っている今日この頃です。
先月は皆様のご理解、ご協力の中、無事に幼児クラスのあおぞら広場を開催できました。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。心から感謝致します。空模様を心配しながらの開催となりましたが、保護者の皆様の温かい見守りと拍手の中、子ども達が笑顔で楽しみ、力を発揮し、誇らしげに金メダルをかける姿に感動しました。アンケートのご協力もありがとうございました。「見ていて楽しかった、面白かったです」「子ども達の遊びや片づけなど生活の中からヒントを得て競技が考えられていて、年齢にも合っているなと思いました」等、お子様のクラス以外のクラスの競技(遊び)に対する感想が多いことに驚くと共に、日常の保育や当日までの過程があおぞら広場から伝わったことを本当に嬉しく思いました。4月から子ども達と楽しんできた遊びや園庭が人工芝になったことで生まれた遊び、オリンピック・パラリンピック競技から刺激、ヒントを得た遊び等々、今の子ども達の姿を大切に、子ども達と担任とで考え、創られたあおぞら広場。誰よりも担任達が楽しんでいる姿がありました。年長児が長縄に挑戦をしている時の事です。担任が絶妙なタイミングで縄を回しながら「すごい!入るタイミングが掴めたね!」「入る位置が良くなったよ」と一人ひとりに声を掛けていました。跳べた、跳べないで表情が変化する子ども達ですが、この言葉掛けで“もう1回やってみよう“と気持ちを切り替え、挑戦し続けるのです。子どもに就いてもらおうと回す役を私が交代すると、案の定タイミングが悪く跳びにくくなりました。それでも担任と一緒であれば私の下手くそな回し方でも跳べるようになっていくのです。保育者は、子どもの成長に合わせた手だてを行うために、子どもの仕草や言葉、行動の観察を大切にしています。「どこまで出来るのか、どこで躓いているのか、何が原因か」という現状把握と原因志向の視点と共に「成功したのは何が良かったのか、躓きを解消するためにどんな関わりが必要か、今後どうなって欲しいのか」という未来志向の視点で保育を考えています。子どもの姿を分析し、手だてを模索する保育力をフル活用している職員達がそこにはいました。意欲と自己充実の繰り返しが子ども達と担任と共に創り出したあおぞら広場に繋がっているのです。
クリスマスのアドベント(待降節)が始まりました。私達保育者は、神さまの愛の中で子どもの成長を育むお手伝いをさせていただいております。クリスマスの本当の意味を理解し、子ども達と共に過ごす中で、日々の生活の中に神さまがいらっしゃることが子ども達に伝わることを願い、喜びと感謝をもってクリスマスを迎えたいと思います。
園長 梶山 美里