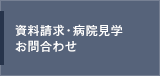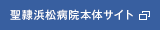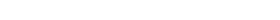指定されたページ(URL)は移動したか、削除された可能性があります。
下記からご覧になりたいページをお探しください。
- 修了生の声 第19期生(2024年3月修了)
- 修了生の声 第18期生(2023年3月修了)
- 修了生の声 第17期生(2022年3月修了)
- 修了生の声 第16期生 (2021年3月修了)
- 修了生の声 第15期生(2020年3月修了)
- 修了生の声 第14期生(2019年3月修了)
- 修了生の声 第13期生(2018年3月修了)
- 修了生の声 第12期生(2017年3月修了)
- 修了生の声 第11期生(2016年3月修了)
- 修了生の声 第10期生(2015年3月修了)
- 修了生の声 第9期生(2014年3月修了)
- 修了生の声 第8期生(2013年3月修了)
- 修了生の声 第7期生(2012年3月修了)
- 修了生の声 第6期生(2011年3月修了)
- 修了生の声 第5期生(2010年3月修了)
- 修了生の声 第4期生(2009年3月修了)
- 修了生の声 第3期生(2008年3月修了)
- 修了生の声 第2期生(2007年3月修了)
- 修了生の声 第1期生(2006年3月修了)